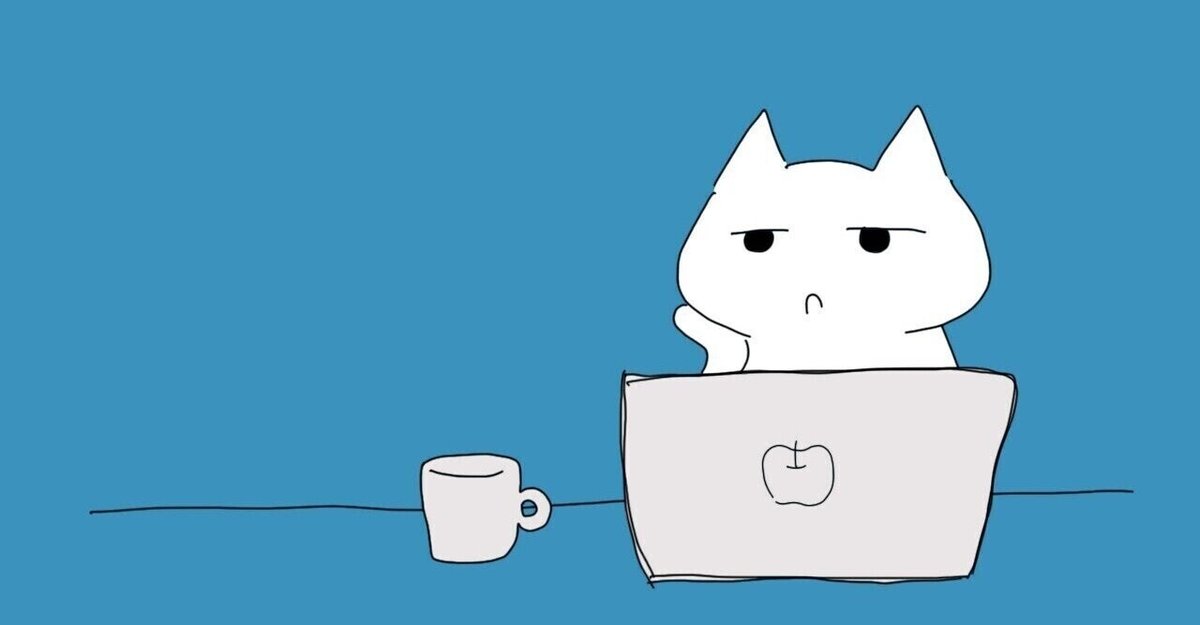
脱「小説家になろう」からはじめる作家生存戦略 実践編(note版)
-「地獄に落ちるにしても、せめて納得だけはしていたい
(佐藤大輔著『皇国の守護者』より)
前回は「『小説家になろう』に依存するのは危険。他のサイトも掛け持ちすることで逃げ道を作ろう」というようなことを書きました。
今回は、「脱なろう」を実践するに当たって知っておくべきことを書いておこうかと思います。
1、他の投稿サイトの特徴は?「ノベリズム」 「ノベルアッププラス」「カクヨム」 のメリット・デメリット
結論を一言で書きましょう。
「ノベリズムで書け」、以上。
さすがに極論過ぎるので補足しますが、ノベリズムのメリットはなんといっても「他サイトを圧倒する縦書きの読みやすさ」が一番のメリットです。
ライトノベルは縦書きで読むべきというのが筆者の持論ですが、ノベリズムの縦書きはフォントも美しく配置も適当で読みやすい。
最近はカクヨムの縦書きも大分改善されましたが、ノベリズムには敵いません。
その上、最近のトレンドである投げ銭システム(ノベポイント)も完備。
いわゆる「チート&ハーレム」な、なろう系では戦いにくい点がデメリットですが、水が合うなら書く側も読む側も居心地の良いサイトです。
次点はノベルアップ+ですね。
文字でコメント書くのは気恥ずかしい人でも、気楽にスタンプで感想を送れるのはかなり良い。
投げ銭システム(ノベラポイント)も完備でけっこう稼いでる人いるのでは。あとは縦書きが読みやすくなれば…あの「枠方式」は正直使いにくい。これがデメリットですかね。
カクヨムのメリットは人口の多さと、洗練されたデザインです。
メリットは広告料還元システム(カクヨムリワード)があること(還元率はやや渋い)。
デメリットは挿絵機能がないこと、そして投げ銭機能が無いこと、ややなろう系にジャンルが偏っていること、大正義カドカワの傲慢さが見えて色々アレ、といったところですかね。
まずは読み専をしてみて、次にアカウント作ってお試しして、居心地よければ続ける、といった感じで良いかと。

2、作家メンタル防衛法の研究
作家にとってのメンタルは、アスリートにとっての筋肉のようなもの。
消耗すれば「選手生命」に関わりかねない、と思ってください。
α―投げ銭、FANBOXでモチベ補給
身銭を切ってまで応援してくれる人がいる。その事実だけで立ち上がれる人がたくさんいます。
かくいう筆者もその一人。
なので、上にも書きましたが「投げ銭が飛んでくる可能性がある場所で戦う」のは重要です。
もちろん、投げ銭もらえるのはごく限られたケースですが…可能性ゼロよりもマシですよね。
高宮も読者としてあちこちに投げ銭しています。
ネット小説への投げ銭文化がYouTubeのスーパーチャットみたいに普及するといいんですが。
ノベリズムだと10円単位から投げられますので、おひねり感覚で投げ銭しよう。
1度「推し」小説に投げるとハマりますよ。
βーコメント欄は閉じるのもアリ
コメント欄はたいてい励ましの言葉ばかりですが、なろう用語で毒者と言われる存在もいるのは確か。
私も過去になろうのコメント欄で、読者同士が設定に関する論争を始めた時は白目になりました(遠い目)。
…設定厨さんはお帰りください。
しんどくなったら、コメントは受け付けない設定にするのもアリですよ。
2-3 息を吐くようにブロック(C・れみさん)せよ!
作者に向かって「この設定はおかしい」、「こんな話の展開は間違ってる」などという人がいたら、「アドバイス罪(C・あきまん先生)」でブロックしましょう。
あなたの小説はあなたのもの。チームで書いている人は、チームメイトの助言を聞く必要があるかもしれません。しかし、見も知らぬ(けして責任だけはとらない)人間のアドバイスに耳を傾ける必要はありません。
感想、意見は時に「参考」にはしても、基本的にスルーするのが一番でしょう。
あなたの物語りの舵を取れる人はあなただけ。「おまえの小説のオールを任せるなー♪」です。
3,好きなように書くのが一番。研究、分析もほどほどに。
世の中色々な研究があり、「この傾向の作品が売れる」という分析は掃いて捨てるほどあります。
しかし、「鬼滅の刃」がとても売れ線とはいえない「大正時代を舞台にした伝奇活劇」というジャンル、「長男だから頑張れるという前時代的価値観」にもかかわらず売れたように、何がヒットするかは、誰にも分かりません。
政策研究学者の高橋洋一氏が「研究なんて数百、数千に一つ当たるものがあるだけ、だから研究投資は数を打つ(筆者の要約)」と動画などで言われています。
発光ダイオードの研究のような社会を変える発明に繋がる研究は、数百数千の研究の中のほんの一握り。
ビジネスの世界でも、たまたまサービスや製品が当たって財をなす人もいますが、その足元には似たようなビジネスを展開して潰れた会社が死屍累々だったりします。
つまるところ、我々がヒット作を飛ばす、プロになるために必要なのは「打席に立ち続ける」ことでしかないのかもしれません。
どうせ打席に立つなら、せせこましく「研究」するのではなく、ホームラン狙って好きにブンブン振り回すしかないのかも。
そもそも「研究」にしたところでそれは「今過去になりつつある現在」の分析に過ぎません。
私の予想では、「アフターコロナでヒットする作品」からは今の「お手軽チートハーレムもの」は消えて居ると思います。
なにしろテレワークで「通勤時間」というものが消滅、死語化すると思うので。スローライフものも、リアルでスローライフがお手軽になるので、
ちょっと厳しいかも。
5(結論)「僕は好きにした。君も好きにしろ(「シン・ゴジラ」より)」
結局のところ、何が正解かなんて分からない、というのが身も蓋もない結論です。
だとしたら、自分が納得できることを出来る範囲でやり続けることが正解。
だからこそ理論編で触れたように勝利条件の設定が必要です。
(古い意味での)プロになることばかりが小説書きの「正解」ではないのですから。
「僕は好きにしたよ。君も好きにしようぜ」とだけ私は述べて、この論考を終えたいと思います。
Twitter版
https://twitter.com/thrud_114514/status/1351545613419102210?s=20
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
