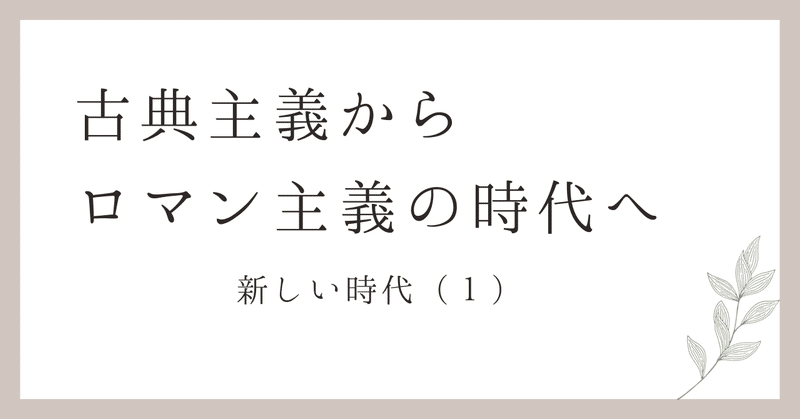
「静かな偉大さ」から、「ダイナミックな激動」の時代へ(19世紀初頭から1830年代まで)
19世紀初頭から1830年代まで、次の順序で3回に分けて述べていく。
一般的傾向
文学の場合
哲学、思想の場合
1、一般的傾向 「古典主義」から「ロマン主義」へ
この時代の一般的傾向としては、18世紀各国を貫いた「古典主義」の時代から19世紀初頭の「ロマン主義」の時代への劇的変遷として語られている。
その契機となったのは、あのフランス革命末期、いわゆるジャコバン独裁期における「最高存在」=「理性の祭典」であった。あれは西洋人の国籍、宗派、趣味嗜好の如何を問わず、すべての人が服さなければならない祭典であった。しかし、あの祭典は見事な失敗作であった。ジャコバン独裁の下では可能であったにせよ、ジャコバン独裁が崩されるやいなや、人々は四分五裂に陥り、それを収拾するナポレオンの登場に期待せざるを得なかった。
ナポレオンは、従来のフランス人の宗教を是認する立場で、時代の収拾をはからざるを得なかった。ただし、彼、ナポレオンは1804年12月2日、フランス皇帝に即位するにあたって、ローマ教皇ピウス7世の捧げる「帝冠」を教皇から奪い取り、自分の手で帝冠をかぶった事件は、これまたあまりにも有名であろう。要するに、ナポレオン皇帝は古い時代の皇帝ではなく、いわゆるナショナリズムとそれに基づく自由の時代を代弁する皇帝であったのである。
これは画家ダビットによるナポレオン戴冠式の下絵である。ナポレオンは帝冠を自分自身の手で被ろうとしている。それを、わざわざローマからやってきた教皇ピウス7世が眺めている姿はあまりにも惨めである。

下の絵画を見ていただきたい。これは画家ダビットによるナポレオン戴冠式の完成絵である。今しも、皇帝ナポレオンが妻ジョゼフィーヌに皇后の地位を約束する皇后冠を自らの手で授けようとしている。この行為も、本来ならローマ教皇の特権に属していたはずである。しかし、皇帝ナポレオンはそれを拒否し、自らの手で皇后冠を妻に与えようとしているのである。それを後の席で、憮然として眺めているだけの教皇ピウス7世曲とその側近たちの姿はこれまた哀れである。

翻って考えてみるに、かつて18世紀を支配したのは、古代ギリシャローマを理想とした「古典主義」の支配の時代であった。これは、イギリス、フランス、ドイツといった各民族を超えた共通の理想でもあった。このことは、あの18世紀末、ジャコバン派によって提示された「最高存在」=「理性の祭典」によってよく示されていた。しかし、ジャコバンの失墜とともに、あの祭典の意義も失われてしまったとすると、後はどうなるであろうか。
かつて古典主義の時代、バウムガルテンは、「美」の本質を「静かな完全性」、ヴィンケルマンは、「ラオコーン」像を見て「高貴な単純と静かな偉大さ」と評したことがある。古典主義の時代はどのような態度をとっても、この「完全性と静かな偉大さ」の枠を超えるものではなかった。カントの哲学も、またこの古典主義時代の枠の中にあると言ってよかった。
だが、次の時代である「ナポレオン時代」は、欧州各国に広がる「戦争の時代」であり、従って、各国の自立を求める時代でもあったとすれば、「完全性」と「静かな偉大さ」の時代から、「ダイナミックな激動の時代」に移っていくことになると考えてよい。「静かな完全性」から「ダイナミックな激動の時代」へ。これが次の時代のテーマとなる。
もう一度要約すると、「普遍的理性」に基づく「合理主義」から個々人の自我を尊重し、これに基づく感性を優位に立てたーー従って、個々の民族の感受性をも尊重する風潮へと転換していくことになり、このような風潮を一言で表すなら「古典主義」から「ロマン主義」の転換と言っていい。
しかも、大ナポレオン戦争が全ヨーロッパに展開された時期でもあったので、全ヨーロッパでの民族主義、民族文化の交流時期でもあった。要するに、「古典主義」の持つ「普遍的理性」から個々の「民族」あるいは、個々の自我の自由な表現を求める「ロマン主義」への移行→これが19世紀初頭の西欧の一般的傾向であったのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
