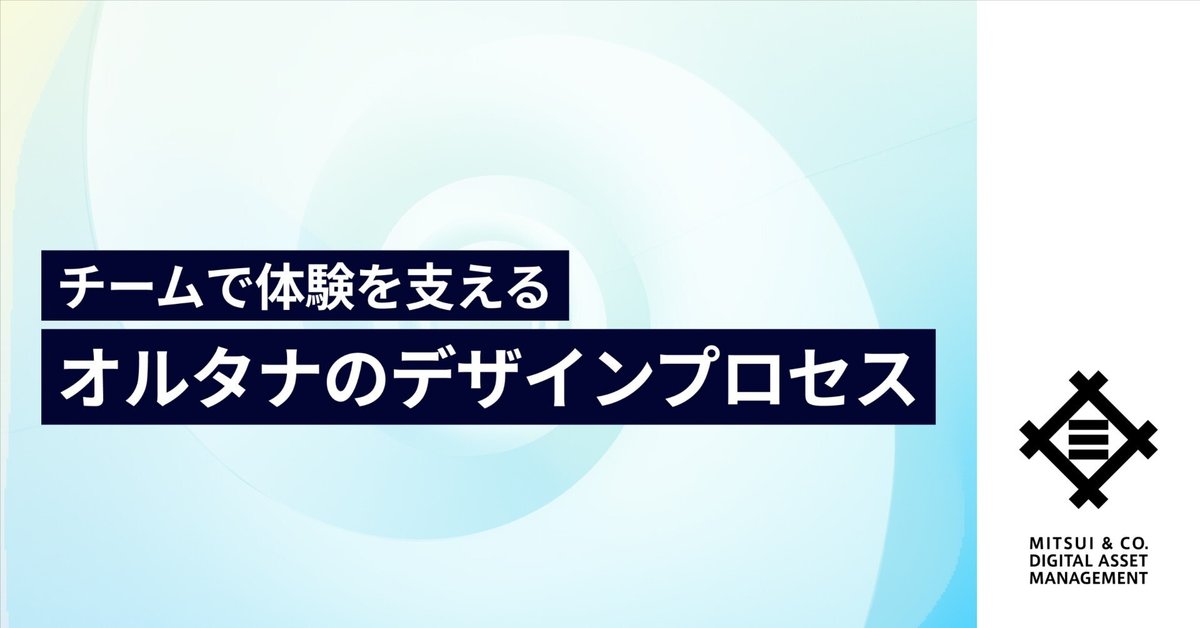
チームで体験を支える、ALTERNA(オルタナ)のデザインプロセス
この記事は、こんな方へおすすめの記事です👀
・金融系サービスのやっていることの実例を知りたい人
・LayerXのFintech事業に興味がある人
LayerXでデザイナーをしているぴーや(@taka_piya)です。
三井物産デジタル・アセットマネジメント(MDM)に出向し、デジタル証券を活用した資産運用サービス「ALTERNA(オルタナ)」のUIデザイン、フロントエンドの部分を担当しています。
転職から1年、オルタナもリリースしてからちょうど1年が経過しました。
そういえば、資産運用系のプロダクトデザインの情報って少ないんですよね。
転職するときになかなか想像しにくいなーと思っていたので、区切りがいいこのタイミングで「オルタナのデザイナーってなにをしているんですか?」を少しご紹介してみたいと思います。Fintech系デザイナー増やしたい。
ちなみに、入社するまで金融系のプロダクトデザインって「なんとなく独特なんでしょう?🧐」と偏見を持っていましたが、いざ入ってみるといい意味で全然違ったと感じています。
個人向け資産運用サービス「ALTERNA(オルタナ)」
「オルタナってtoBサービスでしょ…?」 と思われている方が結構いるのですが、実は違います。
オルタナは個人が資産運用を行うためのtoCサービスです。
デジタル証券という新しい有価証券の仕組みを使って、金額が大きく限られた人しか投資できなかった大型不動産(ホテルやマンション)に、10万円からスマートフォンで投資できるというサービスです。

オルタナのデザインプロセス
このオルタナの機能追加・改善活動は、PdM・エンジニア・デザイナー・QAで構成されるプロダクトチームが中心となって活動しています。ご近所さんにマーケティングチームやオペレーションを担当するチームがいます。

機能追加であればPdM、UI改善であればデザイナー、実装であればエンジニアなど、各々のメンバーが企画を行います。
この段階では、仮説構築のためのユーザーインタビューなども織り交ぜつつ、提供すべき価値をさぐっていきます。

プロトタイピング
仕様概要が決まってくると、デザイナーが入り体験設計・情報設計を行っていきます。
Fixされた仕様を書き起こすというよりも、アウトプットベースで仕様とUIを行き来しながら検討を詰めていくイメージです。
このフェーズで、サービス内外で起きる体験の構造や、既存のデザインのとの整合性(=デザインシステムとの連携)、実装上の困難なポイントはどこかなど、デザイナーを中心に具体化していきます。
金融や不動産の概念が入ってくるため、どう伝える?表現する?というのが難しくも面白い領域です。

フィードバック・体験会
プロトタイプをもとに、チーム全体にフィードバックをもらいます。
チームにSlackでプロトタイプを触ってもらうお願いをしたり、関係者を集めて1時間程度の「体験会」を設定しその場でフィードバックをもらう機会を設けています。

特に新しい案件を公開する前は10〜20人程度が集まり、多いときは100以上のフィードバックが集まります。
もらったフィードバックをもとに、更に改善を進めます。

広告審査・コンプライアンスチェック
審査というと「重そうな響きだなぁ」という印象ですが、要するにリリース前チェックです。
MDMは日本証券業協会に加入しているため、なにか対外的に出す際(ex. 広告、LP、UIなどなど)には広告審査が必要になります。
(※協会の自主規制規則として定められています)
見た人に誤解を与えないよう、明確な表記をしているか、誇大広告になっていないかなどの観点をコンプライアンスチームに確認してもらい、その履歴を記録します。(ダークパターンは許されません!)
建付けが規則に基づくものなので確実に担保する必要がありますので、デザインシステムのようなプロダクトのガイドラインに基づくものに比べちょっと重たいのは事実です。
もちろん効率化は図られており、審査してくれるコンプライアンス部長がSlackやFigmaでコメントしてくださるので「とてもデジタルぅ😎」と思いながら審査を出しています。
弊社、コンプラ部長を無邪気にFigma招待したら、Figma上で表現チェックしてくれる環境なのでとてもおすすめです
— takahiro hayashi/ぴーや (@taka_piya) January 25, 2024
分析リポジトリ
リリースした後は、もちろん利用状況を分析し、当初の目的が達成されているのかを確認します。
分析した結果は、実データ、サマリ、データに対する解釈を分析リポジトリにまとめ、チームに展開します。これがMDMのFact baseを支える要です。

そして、自分も実際に投資して体験する(※これは任意です)
ちなみにですが、オルタナは中の人も案件へ投資することもできます。
もちろん任意です。(※情報公開前に申込しない、償還まで持ち切るなどの一定の制限があります)
自分が実際に使うことで「自分が買うときはここが気になったのに、この情報ないな〜」や「ここは数が増えてくると見づらくなるなぁ」といった設計時には見えてこなかった点が、解像度高く見えてきます。

あれ、意外と普通…?でも
さて、ここまでオルタナのプロダクトデザインのプロセスをまとめてきましたが。オルタナのデザインは企画〜リリースまで、みんなが越境しながらチームで行っています。
「あれ?普通のサービスデザインと同じプロセスじゃない?」と思われた方。そうです。金融系だろうとプロセスはよくあるものなのです。
金融系だからどうこうっていうのは、ドメインの複雑さにあるのではないかと思います。
しかし、金融のドメインは法律や、開発された概念が多いので、「解があるので、読み込めば理解できること」が多く、チームで協力することで乗り越えられるものだとも思っています。(それにしたって、難しいしキャッチアップすることが多いのですが)
デザイナーの責任
すこし話はそれますが、今から20年前に出版された「戦争広告 代理店」という本があります。
政府から依頼を受けたPR会社が、情報提供の形やライティングを駆使して人々の関心を集め世論を操作していくノンフィクション…内容という内容なのですが、情報を持っている側が取捨選択し、ストーリーにして届けるという構造はデザインにも似ていると、今でも印象に残っている一冊です。
ALTERNAは資産運用サービスなので、小さくない資金をお預かりすることになるので、この点は他のサービスとの違いを感じながらやっています。
最後に
この1年のALTERNAは0→1のフェーズで、みんながみんな何でもやるというバタバタ状態でしたが、ユーザー数の増加、徐々に体制整備が進み1 →10の段階に変わってきました。
それに伴ってデザイナーの役割も、1人が領域横断して担当する「幅」から1つ1つのクオリティを高める「深さ」に変わっていきます。
ALTERNAは現在プロダクトデザイナーを募集しています。「触っていて気持ちのいいUIを突き詰めたい」「視覚表現にこだわりたい」「難しい概念を分解するのが好き!!」という方にいいフェーズだと思います。
ぜひお気軽にお話しましょう!
▼1周年ケーキパーティをしました
オルタナ(ALTERNA)は1周年を迎えました💐
— ALTERNA オルタナ (@ALTERNA_mdm) May 10, 2024
この1年の累計案件数は7件。続々と新しい商品の企画も進めています。
これからもデジタル証券を活用した #あたらしくておもしろい投資のカタチ をお届けできるよう邁進してまいります! pic.twitter.com/UKXJND154P
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
