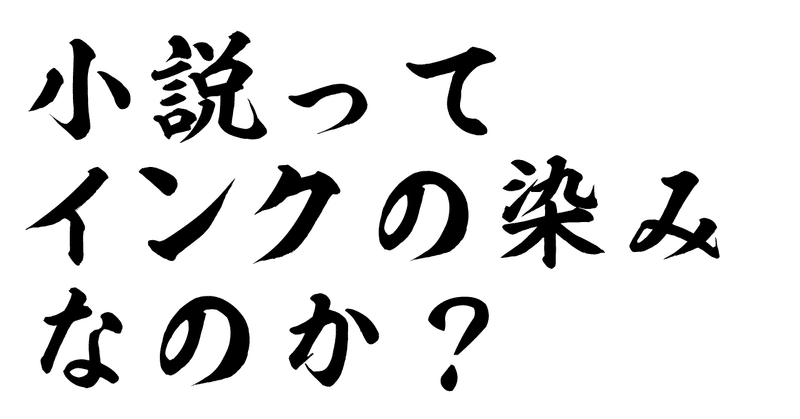
小説ってインクの染みなのか? ※約5分
こんな言葉があります。
小説はインクの染みである
文学を学んでいた大学時代、恩師から聞いた言葉です。
一瞬、小説という文芸を蔑視する言葉のようにも思えますが、そんな簡単な話ではありません。
紙があり、そこにインクが載っている。
そのインクは一定のルールに基づき、形を作っている。
それが日本語だとすれば、日本人には理解ができる。
日本語を知らない外国人には、文書であることはわかるが、小説かどうか判断がつかない。
そして言葉を知らない動物たちにはもちろん読めない。
つまり小説が小説として存在するためには、その記号(文字)を「読める人」が必要、ということです。
これが、小説が根源的にはインクの染みである、という論拠です。
たとえ書いた本人が「これは小説だ」と言ったところで、そう認識できる人がいなければ、小説ではない。
これはまあ、たしかにその通りです。
しかし話はそれで終わりません。
更に考えを進めるとすれば、それが「推理小説なのか」「恋愛小説なのか」「ホラー小説なのか」も同様に、それを読む人がいて初めて決まる、と言えるのではないでしょうか。
書いた本人がなんと言おうと、ということです。
小説はインクの染みである
これは、書く人間にとってはいつでも戒めになりうる言葉です。
そして同時に、読み手の権利を約束する言葉でもあります。
大学を卒業してもう20年近く経っていますが、未だに私の中にはこの言葉が残り続けています。
実は、私がこんなにもこの言葉を大切にしている理由は、もう一つあります。それは、大学を卒業して数年経った頃に発見したこと。
皆さんは
ロールシャッハテスト
というものをご存じでしょうか。
心理学で用いられる別名「インクの染みテスト」です。
インクの染みのような、曖昧な図形を被験者に見せ、何に見えるかを
答えてもらう。
それぞれが異なる答えを出す。
その答えで、その人の心理状態を診断する。
我々が「小説」と読んでいるインクの染みも「まさにこれではないか」とふと思ったのです。
たとえば、私とあなたが同じ物語を読んだとしても、感じることが違う。
なぜ違うのか。
それは、私が私で、あなたがあなただから。
その小説がどう心に響いたか。それは、そこに何が書かれていたかのみによって決まるものではありません。
「そこに何が書かれ、それをどう読んだか」によって成立するものです。
この点において、目の前にある小説は、私やあなたが「どんな人なのか」を測る試験紙である、とも言うことができるのではないでしょうか。
さて数年前、恩師に再会する機会がありました。
「大学時代に聞いた『インクの染み』には、このロールシャッハテストの意味合いも含まれていたのではないか」
私はそう訊ねようと一瞬だけ思って、やめました。
きっと訊ねることにあまり意味はない、と考えたのです。
教壇から発せられた恩師のその発言自体も、それはある種の「インクの染み」であるのでしょうから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
