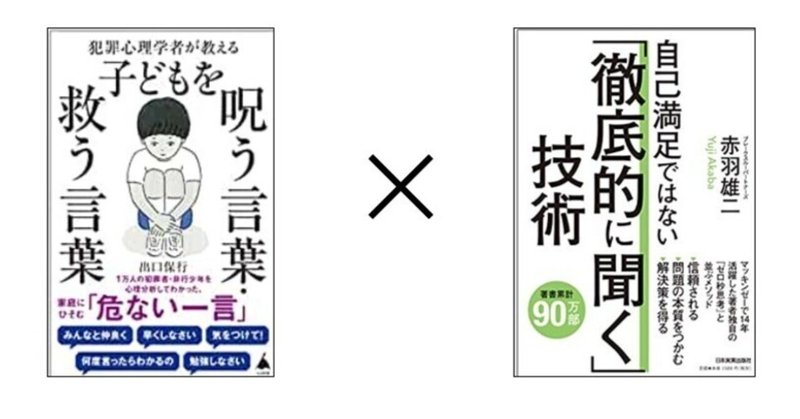
「呪いの言葉」は、家庭の中にあふれていました
赤羽雄二さん『自己満足でない徹底的に聞く技術』で書かれている
アクティブリスニングを実践中の畑中です。
今回は、赤羽雄二さんがご紹介されていた『犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉 救う言葉』を読んだ気づきをシェアします。
あらすじ
1万人の犯罪者・非行少年を心理分析してわかったこと。それは、虐待や育児放棄、貧困といったわかりやすい問題だけが、犯罪や非行につながっているのではない、ということ。実は、親がよかれと思って投げかけた言葉が「呪い」となって子どもを思わぬ方向に導いてしまう。子どもの可能性を潰さずに伸ばす子育ては、どのように実現できるのか。犯罪心理学者が解説する新・子育て論。犯罪者・非行少年の事例とともに紹介する。
書籍で紹介されていた下のグラフをご覧ください。

法務教官が感じる保護者の問題は、子育てでやっていはいけないと言われていることばかりです。
特に青枠内は、子育てでやってはいけないと知ってはいるもののも、ついつい「子どものため」という免罪符をふりかざし、この状況では仕方がないとか、たまにはそんなときもあるなどと自分に都合の良い言い訳をし、私がアクティブリスニングを知って実践する前まで、我が家でありふれていた問題行動です。
そのような育児への問題提起は、赤羽雄二さんが『どうして毒親と呼ばれないといけないのか』(Voicy・Instagram)などでも配信されています。
家庭にひそむ「危ない一言」
「よかれと思って」
「みんなと仲良く」
「早くしなさい」
「頑張りなさい」
「何度言ったらわかるの」
「勉強しなさい」
「気をつけて!」
これは、各章のタイトルに書かれいてる子どもを呪う言葉です。
いかがですか?
子育て家庭では、日常にあふれている言葉ではないでしょうか?(*'▽')
そういった声かけや関わりを断ち切れるのが、『自己満足でない徹底的に聞く技術』で書かれているアクティブリスニングです。

幸い、私の父親は子どもをよく観察する人でした。口癖のように言っていたのは、「子どもは思っていることの1%も口に出せない。だから保護者や教師は常に子どもを観察して、何か異常が起きていないか確認するいことが大切」ということでした。「子どもが助けてと言ったときは、すでに事態の深刻さは回復が難しいところまで来ている」とも言っていました。
(中略)
私の様子がおかしいと感じる「どうかしたか」と声かけてくれる父親でした。実際に悩み相談をして解決してもらったわけではないですが、常に「話を聞くよ」という姿勢でいてくれたのが良かったと思っています。そのときちょっとモヤモヤしていることを話すだけで気がラクになるのです。何かあったときは相談できるという安心感もありました。
普段、あまり会話がなく、急に「最近ちょっと様子が変だぞ。話してみろ」と呼び出されたら話しにくかっただろうと思います。いつものお風呂で何気なく声をかけてくれるのがとても助かりました。
聞いてもらえると「大丈夫」と思える
私は中学1年生のとき、上靴を捨てられたことがあります。
朝、登校して下駄箱を見ると上靴がないのです。
困っている私に気づいた周りの子や友だちが、上靴を探してくれて、なんと、ゴミ箱から私の上靴が見つかったのです。
見つけてくれた友だちにもお礼をいって、励ましてくれる友だちにも心配をかけないように、元気に振る舞っていたけれど、とっても悲しかったです。
帰宅して、よっぽど暗い顔をしていたのでしょうね。
母親がすぐに気づいて声をかけてくれました。
でも、親に心配をかけてはいけないという気持ちがあって、学校であったことを話さずにいました。
「いつもと変わらないよ。大丈夫」と。
なぜかその日は、父親も家にいて、一緒に川に行こうというのです。
気分転換もいいかなと思って、一緒に付いていくことにしました。
一緒に川を見ながら、「川って良いよな~」とか、「自然に身をおくといろんなことが大したことじゃないと思えるよな~」とか、そんな話をきいているうちに、私は大泣きして、今日、上靴が捨てられていたことを話していました。
嫌がらせを受けた自分のことを親に話すのも嫌だったし、心配かけちゃって申し訳ない気持ちもあったけれど、耐えきれなくて話をしてました。
自分の悲しかったことや原因として考えられることなどを話をしているうちに、自分には絶対的な味方がいるような気持ちになって、「大丈夫!」と思えたことを覚えています。
で、翌日は大丈夫だろうと登校すると、また下駄箱に上靴がないのです。
でも、この日は、友だちが私の上靴をゴミ箱に捨てたのを目撃して、拾っておいてくれた私の上靴を自分の下駄箱にしまっておいてくれたというのです。
さらに、その子は、一緒に言いに行こう!というのです。そして、また次もやるかもしれないから、私の上靴はしばらく友だちの下駄箱にいれておこうと提案してくれました。
静かにこの事件を終わらせたい気持ちと、ずっとやられっぱなしなのは悲しいし、やめてもらいたいという思いもあり、友だちに連れられて震える気持ちで、彼女に話しをしにいきました。
すると、彼女は「好きな男の子に、私(筆者)のことを好きだと言われて、嫌な思いをさせたかった」「嫌なことされても、友だちに靴も探してもらえるし、いいでしょ」と。
「そう思って、やったんだー」「私が靴がなくて困っているところもみていたんだ」ということがわかり、可哀そうな子だと感じました。
アクティブリスニングを知った今、彼女に「話を聞いてもらえる人」がいたら、彼女はこんなことをしなくてよかっただろうし、悲しい思いをする人も、いなくなかったと思います。
コントロールする育児から信頼の育児へ
「呪いの言葉」は、すべて「子どもをコントロールする言葉」です。
これまで私は、『犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉 救う言葉』に書かれている「呪いの言葉」をさんざん子どもに言ってきました。いけないことは知っていたけど。
なぜ、いけないと知っているのに、言ってしまうのか?
アクティブリスニングをするようになってその原因は、「子どもを信頼していない」からだと気づきました。
言わないとわからない、言ってもわからないから、さらにガミガミ言う。
親が言うことで、子どもが受け取るメッセージは、「言われないとできない僕」。繰り返し言われると、「さんざん言われてもできない僕」です。
これでは、自己肯定感の高い子が育つわけありませんよね。
では、子どもを信頼するためには、どうしたらいいか?
それは、「子どもの話を徹底的に聞くこと」です。
子どもの話を聞くと「子どもってほんとによくわかっているし、色んなことを考えているな」ということに気づかせてもらえます。
その気づきがティッシュを一枚一枚積み重ねるように少しずつ増えていくと、徐々に子どもを人として尊重できるようになってきます。
そうやって私の子どもに対する「在り方」が変化する中で、あーだ、こーだと子どもをコントロールする言葉をいってしまうことが激減しました。まだそういった言葉が出てしまうこともありますが、ほんとうに言わないようになりたいです。
子どもに呪いの言葉を言わないためにできることは、子どもの話を徹底的に聞くこと。
これが、私が毎日、子どもたちにできる副作用なしの育児法だと改めて感じます。
苦しくつらい子育てから抜け出し、家庭を安全基地にしたい方へ、情報を更新しています。
よろしければ、フォローしていただけると嬉しいです。
他の投稿も参考にしてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
