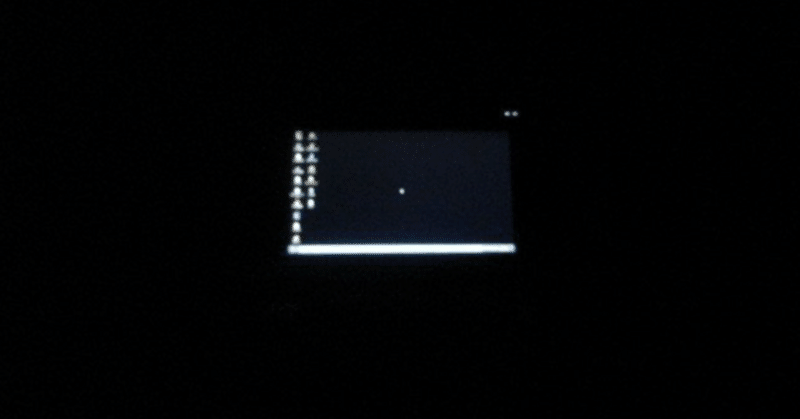
2024/6/5
今日もお疲れ様。1日が終わった。疲れた。
・死について
死という問題ほど人間にとって共通的で、なお主観的なものはないだろう。私たちはいずれ死ぬ。存在論が哲学における究極的な問いであるとしたら、その終局である死についても同様に論考される必要がある。
しかし、死ほど見ぬふりをされるものもない。なぜだろう。死をただ生の区切りとして認識するから、あまり日常において重要性を見出されないのか。それとも死の破滅性を恐れるあまり、日常から死への不安ごと排除されるのか。そのどちらもかもしれない。
私が何故急に死について考えるのかというと、バタイユの非―知について興味があるからである。バタイユは非―知を知に非ざるものとしてではなく、むしろ知を押し拡げるものとして考えている。どういうことか。
私たちはそれまで経験したことのない対象について初めて知覚したとき、経験的に獲得した領野から何か関連性のあるものを持ち出し、推測する。例えば、オオサンショウウオについて何の情報も持ち合わせない人が初めてオオサンショウウオを見たとき、「水中にいるな。魚類なのかな。でも手足が生えていてカエルみたいだ。両生類かもしれないな。」みたく推測することが可能である。(余談だがオオサンショウウオは両生類)
知りえないものを「非―知」、知っているものを「概念知」、経験的に推測することを「推論的=言説的思考」とバタイユは述べるが、ある意味で閉鎖的な空間である概念知の領野を非—知は切り開く。非―知の衝撃によって知的生産の活動、意味化の運動は停止し(その意味でバタイユは非―知が概念知を「裸にする」と述べているが)、そのような意味の破局の危機も一時的なものにすぎず、結局は概念知の領野に回収されてしまう。(「非―知」→「非―意味」)
言うまでもなく、死とは非―知の領野にある。死は存在そのものを揺るがすという意味で、私たちは(いくら日常において忘却されているにしろ)死に密接に関係しており、死について問う必要がある。しかし、それは必ずしも否定的なものではなく、むしろ概念知を押し拡げるポジティブなものであって、決して忘却されなければならないタブーではない。
孤独と死は良く結び付けられるが(何となく心霊現象に遭遇するのは希死観念の強い孤独な人というイメージがある)、死の持つ究極の主観性と「非―知」性が〈私〉に強く一体感・完全性を感じさせ、そこで全体性が生まれるというか、安定感をもたらしてくれる。その意味で表象=再現前化された営みから逃れさせてくれるのかもしれない。現実が如何に非情でも、死は居場所を与えてくれるのかもしれない。
多動な社会で私たちは接続過剰になっている。内的監視の圧や能力の可視化、繋がりの増大、情報の過剰などによって「あれもこれも」という焦燥感のインフレが発生しうる。そこである意味、死は安らぎをもたらしてくれよう。繋がりを切断することなくとも、繋がりを休止して明日に備えられる。私たちはみずから孤独になる時間が必要であるかもしれないと思う夜。おやすみ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
