
TEDxAnjo に参加して、一つの気づきを得ました。
”障害者とは。もしかしたら社会が作り出しているだけかもしれない。”
つまり、教える立場の人がついやってしまいがちなのが以下の3点です。この3点は障害者に対しても行われているそうです。
1.相手の興味に理解を示さない
人によって興味を持つものは様々です。ただひたすら絵を描くことが好き、魚が好きすぎて魚の話ばかりしてしまう人がいるかもしれません。自分と違う世界や考え方に少し寄り道して理解を示すことが、相手にとって心理的安全に繋がると思います。
もちろん私も物心ついた頃から絵を描く、本を読む、コンピューターが大好きで、小学校の図書室にあった本を全部読み漁ったり、部屋に篭ってゲームを開発していて、変わり者だったと思いますが、今があるのは良き理解者がいたお陰だったと思います。
2.出来ないことにフォーカスをする
人と比べて出来ないことや苦手な分野は誰でもあると思います、そうした弱みを指摘して自信を失わせると自己効力感が損なわれ「自分にできるはずがない」、「きっと失敗する」といった気持ちが大きくなり、行動する意欲が減退してしまいます。
しかも出来ないことを繰り返し指摘されると、何をしていいのか分からなくなります。それよりは少しでも出来たことを教えてあげてください。一歩前に踏み出すためには足の置き場が必要なのです。
3.答えを示すが解き方は教えない
「これは当たり前だから」、「こんなの常識だよ」という捨て台詞だけで答えを示されても、出来ない自分に対して不安で押しつぶされそうになるだけで前に一歩も進めないと感じます。
当たり前と思えるほど理解しているのですから、相手の理解度に応じて解き方を教えてあげることも出来るのではないでしょうか。
健常者であっても、こんな環境であれば自信を無くして病んでしまうのではないでしょうか。
得てして競争社会では、人間らしい心や優しさを簡単に見失ってしまうものです。もちろん自分だけが生き残る為に必要な行為かもしれません。ですが組織が生き残るために「共創」が必要です。
例えば、魚が大好きな事に理解を示したら、魚を通して絵を描くことが上手になり、魚の知識とイラストの才能を開花させ、東京海洋大学名誉博士・客員准教授となった「さかなクン」のように、人の能力とは、誰かが作った「ものさし」だけで全てが測れるものではないと感じました。
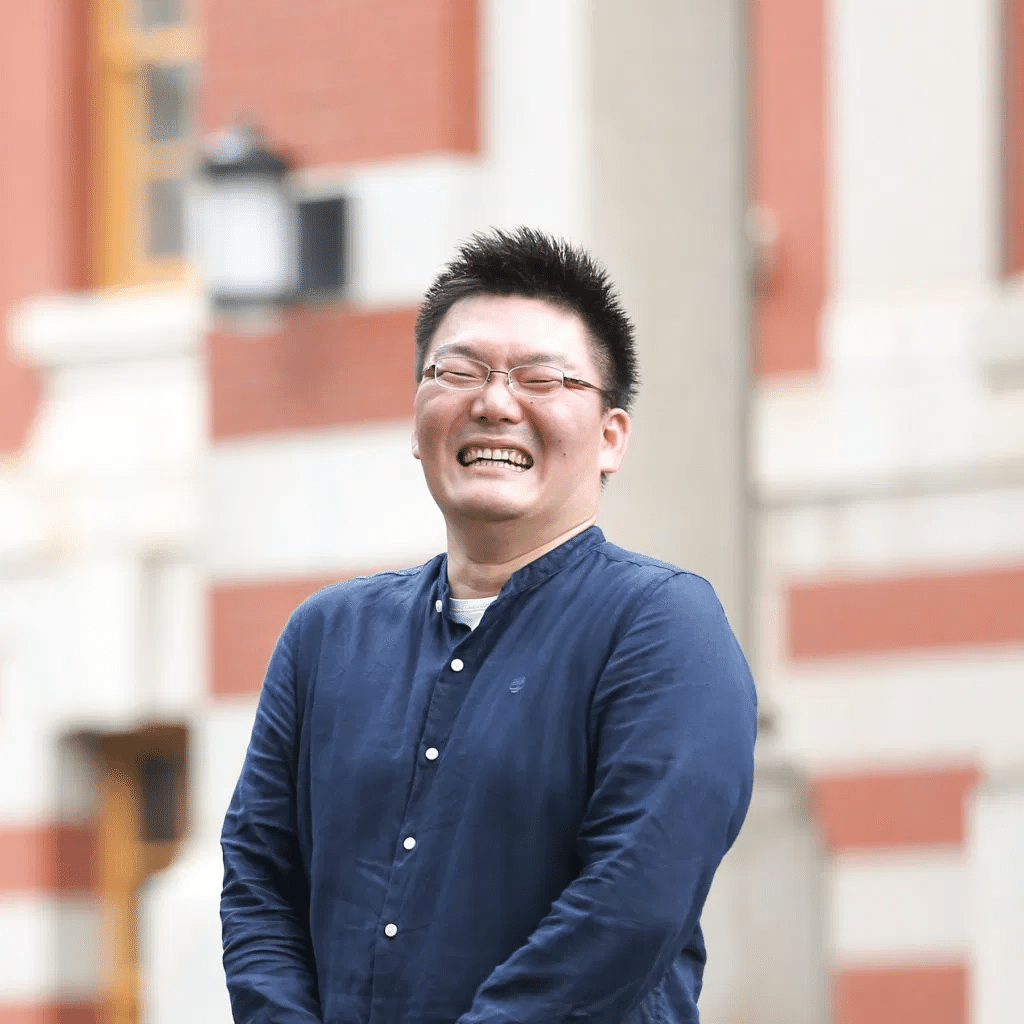
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
