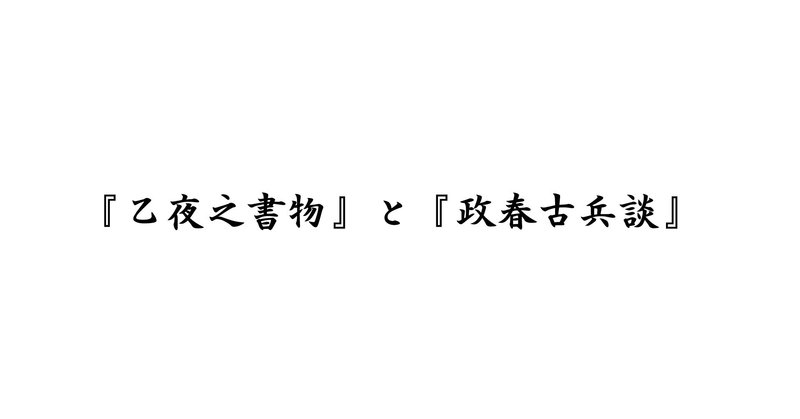
『乙夜之書物(いつやのかきもの)』にみる「本能寺の変」
「私が住む富山市には江戸時代に宥照寺という寺があり、光秀を祀る塚と墓が築かれていた。寺は明治時代に廃絶し、いまは跡形もないが、光秀重臣の明智左馬助の兄弟が住職だったため、光秀の塚を築いて供養したと伝わる。私がこの光秀塚について調べていた矢先に出くわしたのが、「乙夜之書物」の記述だった」(萩原大輔氏談)
※宥照寺(富山市辰巳町)の光秀塚:当時の住職が明智光秀の兄だという。(出典『越中奇談集』)
1.概要
『乙夜之書物(いつやのかきもの)』:加賀藩の兵学者・関屋政春(せきやまさはる)が、古兵らから約500件の「武辺噺」を聞き集めて箇条書きに書き著した本。全3巻で、自筆本が現存する。
1669年に成立したと考えられている上巻の「本能寺の変」に関わる部分は、斎藤利三の三男・利宗(「本能寺の変」当時数えで16歳。1647没。享年81)が加賀藩士・井上清左衛門(斎藤佐渡守利宗の甥)に語った話の伝聞が中心になる。(古兵の語りということは、先日(2月5日)に発売された『明智物語』の類か。)
■『乙夜之書物』
斎藤佐渡守殿物語の由、井上清左衛門語る。斎藤佐渡守、之は内蔵助子息。清左衛門は内蔵助孫佐渡守殿をいなり。
斎藤利三┬長男(1565-1582):利康(虎松)
├次男(1568?-1650):利成(明智平三郎。伊豆守)
├三男(1567-1647):利宗(利光。佐渡守)─利重─利昭
├四男(?-1582):七兵衛
├五男(1580?-1625?):三存(津戸右衛門、与三右衛門)─三友
├長女:柴田勝全前室
├次女:柴田勝全継室
└三女(1579-1643):福(稲葉重通養女、稲葉正成継室。春日局)
關屋政春:通稱新兵衞。前田利常、光高、綱紀に歴仕す。兵法に達し、傍ら學を好み、嘗て君道臣道師道を論じ、又儒佛神三教一致の理を講じ、以て子弟を誘掖せり。著す所、乙夜之書物三卷、政春古兵談あり。古兵談には、木下順庵、平岩仙桂、澤田宗堅等の言説を録すること多し。寛永十年初めて來仕し、貞享二年歿す。(『石川県史』)
書名の由来:「「乙夜」とは午後9時から午後11時ごろを指すので、日中の勤めを終えた後の夜に執筆していたのだろう」(萩原大輔氏談)。
【補足】「乙夜之覧(いつやのらん)」(略して「乙覧」)という故事成語がある。出典は『杜陽雑編(とようざっぺん)』である。
唐の文宗皇帝は、政務が忙しく、側近に「若(も)し甲夜(19時~21時)に事を視、乙夜(22時~24時)に書を観ずんば、何を以て人君たらんや」と言って乙夜(1夜を2時間ごとに5区分した2番目の時間帯)に読書した。『乙夜之書物』とは、「中国の文宗皇帝は乙夜に本を読んだと言うが、私は乙夜にこの本を書いた」「天子は「乙夜之読書」。私は「乙夜之執筆」」という意味であろう。最後は「寛文9年閏10月11日の夜、筆を留畢」と締めて、筆を置いている。(天子も乙夜に書くことはあるようだ。霊元天皇は『乙夜随筆』を書いている。)
■『杜陽雑編』(上)
文宗皇帝毎視朝後、即閲群書。謂左右曰、「若不甲夜視事、乙夜観書、何以為人君邪」。
2.『乙夜之書物』の内容
加賀藩士には、元明智光秀家臣がなぜか多い。
・加賀藩士・井上清左衛門談:明智光秀は「本能寺の変」の時は鳥羽。
・加賀藩士・恒川斎仁談:天野源右衛門が織田信長に槍傷を負わせた。
(注)安田作兵衛国継(初名)=天野源右衛門=平野源右衛門(晩年)
・?談:明智光秀は、鳥羽から2里を駆け、二条新御所へ攻め込んだ。
■『乙夜之書物』(井上清左衛門談)
一、天正拾年の春より、中国毛利家為退治、羽柴筑前守秀吉、備中の国ゑ発向して、同国高松の城をかこむ。(中略)硯箱に料紙と熊野の牛玉を出す。各、血判すみて、亀山の城を朔日の暮前に立て、大井の山を打越て、夜中に掛桂川に至り、諸軍を川原に座備て「兵粮つかゑ」と云、各心得ぬ事哉。「亀山を出て、やうやうて三里計来りて何事ぞ」と思いながら、竹葉つかいける所に、物頭ども乗廻し、「本能寺え取かくるぞ。各其心得可仕」と云ふ。諸軍ふるいたるとなり。扨、本能寺えは明知弥平次、斎藤内蔵、人数弐千余き指むけ、光秀は鳥羽にひかゑたり。
一、明知弥平次、斎藤内蔵助、弐千余騎にて本能寺ゑ押寄たれば、早、夜は、ほのぼのと明にけり。内より水汲の下郎、水桶をにない出けるが、敵の押寄たる体を見て、内ゑにげこみ、門を立る。「あの門たてさするな」とて押詰、門を打やぶり乱入る。当番の衆、「是は何事ぞ」とをきふためき、はしり出て見ければ、敵、早、門内ゑ込入たり。各、鑓を取て縁の上下にて攻合。信長公、白き御帷子をめし、みだれがみにて出させたまい、御弓にて庭の敵をさし取引つめ射たまう。御弓のつるきれたりと見ゑて、御弓をなげすてたまい、十文字の鑓を取て、せり合たまう。然所に御手を負はれたりと見ゑて、白き御帷子に血かかって見ゆる。御鑓、御すて、奥ゑ御入、ほどなく奥の方より焼出たり。
一、御番衆、ずいぶん働といゑども、をもいよらぬ事なれば、何(いずれ)もすはだびて、わづかの人数、敵は具足、甲を着、弓、鑓、鉄炮備て大勢攻め込む。終に縁の上ゑ追い上げ、突き伏せ、切り伏せ、首をとる。(中略)
右三ケ条、斎藤佐渡守殿物語の由、井上清左衛門語る。斎藤佐渡守、之は内蔵助子息、清左衛門は、内蔵助孫佐渡守殿をいなり。
【大意】 天正10年の春から、中国地方の毛利家の退治と称して羽柴筑前守秀吉が備中国に向けて出陣し、同国の高松城を取り囲んだ。(中略)硯(すずり)箱と熊野牛玉神符(熊野三山で配布される神札)が出され、熊野牛玉神符の裏に、各自、名前を書き、血判を捺した。血判状の作成が済んだ6月1日の日暮れ前に亀山城から出陣し、大江山を越え、夜中にかけて桂川に至り、諸軍を川原に陣取らせ、「兵粮を使え」と言うので、皆、不審に思った。「亀山城を出て、ようやく約3里(12km)進軍したばかりなのに、早くも腹ごしらえをさせるとはどういうことだ?」と思いながら、竹葉(酒の異称)を飲んでいると、物頭(武頭、足軽大将)たちが馬に乗って、「本能寺に攻め入るぞ。各自、心構えをせよ」と触れて回った。皆、「すぐに戦だ」と奮い立った。
さて、本能寺へは明智弥平次、斎藤内蔵助利三が、軍勢2000余騎を指し向け、明智光秀は、鳥羽(山城国紀伊郡鳥羽郷、現在の京都府京都市伏見区鳥羽町)に控え(織田信忠の居場所を探らせ)た。
一、明智弥平次と斎藤利三が2000余騎で本能寺に押し寄せると、早くも、夜は、仄仄と明けた。本能寺の境内から水汲みの下郎が、(常の日課で、「天下の三名水」の「柳の水」を汲もうと)水桶を持って出てきて、敵が押し寄せている様子を見て、境内へ逃げ込み、門を閉じようとした。「あの門を閉じさせるな」と言って押し詰め、門を破って乱入した。寝ずの当番衆(当直の警備兵)は、「是(こ)れは何事ぞ」と叫び、慌てふためいて、走り出て見れば、敵は早くも門内に入り込んでいた。各々、手に鑓を取って、縁側の上や下で戦った。織田信長は、白い帷子を着て、乱れ髪のまま出てきて、弓で庭の敵を指し取り、引き詰めて矢を射た。弓の弦が切れたようで、弓を投げ捨て、十文字鑓を手に取って戦った。こうした時に怪我をしたようで、白い帷子に血がかかったように見えた。鑓を捨て、奥へ入り、程なく奥の方から出火した。
一、番衆(宿直の警備兵)はよく戦ったが、不意打ち(奇襲)であったので、皆、武装しておらず、数も少なかった。これに対し、敵(明智軍)は具足を身に纏、兜を被り、弓、槍、鉄砲を持って大勢で本能寺へ攻め込んだ。最初は庭で戦っていたが、やがて縁側の上に登り、敵(御番衆)を突き伏せ、切り伏せ、首をとった。(中略)
以上の3ヶ条は、16歳の時に「本能寺の変」に参陣した斎藤利三の三男・利宗が、加賀藩士・井上清左衛門(斎藤佐渡守利宗の甥)に語った話である。
3.『乙夜之書物』と他の古文書との比較
(1)本能寺を攻めた明智軍の兵数
この『乙夜之書物』は、「光秀は鳥羽にひかゑたり」とあること、つまり、明智光秀が「本能寺の変」の時に本能寺にいなかったという記述ばかりが注目されていますが、私が注目するのは「明知弥平次、斎藤内蔵助、弐千余騎」です。本能寺を攻めた人数は、諸書に
・3万人(『イエズス会日本年報(1582年追加)』)
・2万人(『惟任退治記』)
・13000人(『川角太閤記』『綿考輯録』)
・3500人(『明智軍記』)
・2000人(『乙夜之書物』)
とありますが、本能寺は、発掘調査により、1町(約109m)四方の寺だと判明しています。13000人も必要ありません。13000人は明智軍の総数であり、本能寺は2000~3000人で攻め、残りは「京の七口」と呼ばれる京の出入口を塞いだのでしょう。
現在の通説は、
・本能寺を13000人で攻めた。
・七口は封鎖されていなかったが、織田信忠は、なぜか逃げなかった。
ですが、『乙夜之書物』に端を発する議論を通して、将来の通説が、
・軍勢を複数に分け、本能寺は2000~3000人で攻めた。
・七口が封鎖されていたので、織田信忠は京から脱出不可能であった。
に変わるかもしれません。(七口の全てを封鎖する必要はありませんけどね。たとえば、明智光秀領の西の丹波国へ通じる丹波口や、明智光秀領を通って安土城に入る東の粟田口は封鎖されていなくていいでしょう。)
★「京の七口」
・東へ:粟田口
・西へ:丹波口
・南へ:伏見口、鳥羽口
・北へ:大原口、鞍馬口、鷹峰口
南(織田信孝がいる堺)へ織田信長が逃げると考えて鳥羽に本陣を置くか、北(柴田勝家がいる北陸)へ織田信長が逃げると考えて大原口に通じる三条堀川に本陣を置くか。
■『明智軍記』
二日の曙に、明智左馬助光春を武将として、其勢三千五百余騎、本能寺の館を百重、千重に取り巻けり。又、明智治右衛門光忠を頭にて、軍兵四千余騎、二条城、同妙覚寺を取り囲めり。総大将・日向守光秀は、諸軍の命を司りて、二千余騎を随へ、三条堀川に扣へたり。
(2)亀山城を出た時間
亀山城を出た時刻については、
・「申の刻(16時の前後2時間)」説(『明智軍記』)
・「酉の刻(18時の前後2時間)」説(『川角太閤記』)
・「戌の刻(20時の前後2時間)」説(『綿考輯録』)
・「亥の刻(22時の前後2時間)」説(『名将言行録』)
・「子の刻(24時の前後2時間)」説(『惟任退治記』)
があり、『乙夜之書物』では「朔日の暮前(6月1日の日暮れ前)」としています。
実際に甲冑を身に着けて歩いて時間を測り、本能寺に夜明け(午前5時)に着く(本能寺では、夜明けに総門の扉を開ける習慣があったので、そこを襲う)には、「遅くとも午後9時に出れば良い」そうで、少なくとも「亥の刻」説と「子の刻」説は「無理だ」と否定されました。(こういう計算は、あてにはなりません。なぜなら1人でさっさと歩いて着く時間と、13000人でだらだら歩いて全員が着くまでの時間では異なるからです。明智軍が何人で行軍したのか分からない限り、「目安にはなるが、あてにはならないデータ」と言わざるを得ません。)
「夜半に出陣」とする史料が多いのですが、何が起こるかわからない(6月2日は新月で暗闇である。桂川には橋はなく前日の雨で増水しているとも)ので、明るい内に亀山城に軍勢を集めて分け、暗くなったら各隊が出発し、本能寺に夜明けの開門と同時に着くよう、桂川の川岸で食事をとりながら、時間の調整をしたのでしょう。『川角太閤記』にも、『乙夜之書物』同様、桂川の川岸で休ませ、その時に向かう先が本能寺であることを知らせたとあります。
■『明智軍記』
六月朔日、「中国へ発向する勢揃」と号して、申の刻に及びて、日向守は、能条畑に打ち出で、水色の幡を立て、軍勢の手組有りて、三手に分つ。一手は、明智左馬助、四王天但馬守、村上和泉守、妻木主計、三宅式部。一手は、明智治右衛門、藤田伝五、並河掃部助、伊勢与三郎、松田太郎左衛門。自身は、明智十郎左衛門、荒木山城守、諏訪飛騨守、奥田宮内、御牧三左衛門を先として、酉の下刻ばかり、保津の宿より山中に懸り、水尾の陵を徐になし、内々作らせ置きたる尾伝ひの道を凌ぎ、嵯峨野の辺に打ち出で、衣笠山の麓なる地蔵院迄著陣す。左馬助は、本道を歴へて大江坂を過ぎ、桂の里の打ち越ゆる。治右衛門は、王子村より唐櫃越の嶮難をへて、松尾の山田村を通り、本陣近くぞ寄合ける。
諸軍勢、此の形勢を見て、「中国への出陣は、播磨路に可趣処に、只今の上洛は不審多き事也」とて、武頭等に向に、其の様を尋ねしかば、士大将、是を聞き、謀叛の儀を隠密して偽云ひけるは、「織田殿の仰せには、路次の程廻りなれども、当手武者押しの次第、京都に於て御見物可有に付、如此と聞き及ぶ処なり」と答へければ、諸人、「実(げ)にも」と思ひつつ、何心もなく、終夜、駒を早めて、都近くぞ上りける。爰にて光秀、諸勢に触られけるは、「各、兵粮を仕ひ、武具を固めよ。敵は四条本能寺、二条城にあり。可攻討」と下知しければ、「偖は野心ぞ」と心得て、何れも小荷駄を招き、支度の体、不穏便と云へども、曽て外へは知らざりける。
【概略】
・申の刻、能条畑で9500人を3隊に分けて進軍開始
↓・明智左馬助隊:山陰道を往き、大江山を越えて桂へ。
↓・明智光忠隊:唐櫃越え
↓・明智光秀隊:酉の下刻、保津宿から山中へ入り、地蔵院へ。
・京の近く(桂川の川岸?)で明智光秀が次のように下知。
「各自、兵粮を使い(食べ)、武具を固めよ(準備せよ)。敵は四条本能寺と二条城にあり。攻め討つべし」(この時点では織田信忠は妙覚寺にいて、二条新御所にはいなかった。)
・明智左馬助隊3500人:本能寺へ
・明智光忠隊4000人:妙覚寺→二条新御所へ
・明智光秀隊2000人:三条堀川(本陣)へ
■『本城惣右衛門覚書』
山さきのかたへとこゝろざし候へバ、 おもひのほか、京へと申し候。 我等ハ、其折ふし、いへやすさま御じやうらくにて候まゝ、 いゑやすさまとばかり存候。 ほんのふ寺といふところもしり不申候。人じゅの中より、馬のり二人いで申候。 たれぞと存候へバ、さいたうくら介殿しそく、 こしやう共ニ二人、ほんのぢのかたへのり被申候あいだ、 我等其あとニつき、かたはらまちへ入申候。それ二人ハきたのかたへこし申候。 我等ハミなみほりぎわへ、ひがしむきニ参候。
【現代語訳】山崎の方へ向かうと思っていたが、意外にも「京へ」と言われた。我らは、ちょうど家康様が御上洛中なので、家康様を討つのだとばかり思っていた。本能寺がどこにあるのかも知らなかった。軍勢の中から馬に乗った2人が出てきた。誰かと思えば、斎藤内蔵助利三の子と小姓の2人であった。本能寺へ行く間、我らは彼らの後につき、片原町へ入った。2人は北の方へ行ったが、我らは皆、堀際へ東向きに行った。
(注)斎藤利三の長男・利康、次男・利成、三男・利宗の3人が参戦しており、ここに登場した斎藤利三の子が誰なのかは特定できない。なお、長男・利康は、山崎合戦で討死している。
(3)「本能寺の変」の様子
『乙夜之書物』では、
①番衆と戦う。
②寝起きの織田信長が白帷子(寝間着)を着て登場。遠くから弓を射る。
③弓の弦が切れたので、弓を投げ捨て、十文字鑓を手にして接近戦。
④負傷したようで、十文字鑓を捨てて、奥へ入り、放火した。
であって、他の古文書(『信長公記』等)の記載内容と一致します。
■『信長公記』
さる程に、不慮の題目出来候て、六月朔日、夜に入り、丹波国亀山にて、惟任日向守光秀、逆心を企て、明智佐間助、明智次右衛門、藤田伝五、斎藤内蔵佐、是れ等として、談合を相究め、信長公を討ち果たし、天下の主となるべき調儀を究め、亀山より中国へは三草越えを仕り候。爰を引き返し、東向きに馬を並べ、老の山へ上り、山崎より摂津国の地を出勢すべきの旨、諸卒に申し触れ、談合の者どもに先手を申しつく。
六月朔日、夜に入り、老の山へ上り、右へ行く道は山崎天神馬場、摂津国の皆道なり。左へ下れば、京へ出づる道なり。爰を左へ下り、桂川打ち越し、漸く夜も明け方に罷りなり候。
既に、信長公御座所、本能寺取り巻き、勢衆、四方より乱れ入るなり。
信長公も、御小姓衆も、当座の喧嘩を下々の者ども仕出し候と、おぼしめされ候のところ、一向さはなく、ときの声を上げ、御殿へ鉄炮を打ち入れ候。
「是れは謀叛か、如何なる者の企てぞ」
と、御諚のところに、森乱申す様に、
「明智が者と見え申し候」
と、言上候へば、
「是非に及ばず」
と、上意候。
透をあらせず、御殿へ乗り入れ、面御堂の御番衆も御殿へ一手になられ候。御厩より、矢代勝介、伴太郎左衛門、伴正林、村田吉五、切って出で、討死。此の外、御中間衆、藤九郎、藤八、岩、新六、彦一、弥六、熊、小駒若、虎若、息小虎若を初めとして廿四人、御厩にて討死。
御殿の内にて討死の衆、森乱、森刀、森坊、兄弟三人。小河愛平、高橋虎松、金森義入、菅屋角蔵、魚住勝七、武田喜太郎、大塚又一郎、狩野又九郎、薄田与五郎、今川孫二郎、落合小八郎、伊藤彦作、久々利亀、種田亀、山口弥太郎、飯河宮松、祖父江孫、柏原鍋兄弟、針阿弥、平尾久助、大塚孫三、湯浅甚介、小倉松寿。
御小姓衆懸かり合ひかかりあひ、討死候なり。湯浅甚介、小倉松寿、此の両人は、町の宿にて、此の由を承り、敵の中に交り入り、本能寺へ懸け込み、討死。御台所の口にては、高橋虎松、暫く支へ合ひ、比類なき働きなり。
信長公、初めには、御弓を取り合ひ、二、三つ遊ばし候へば、何れも時刻到来候て、御弓の絃切れ、其の後、御鎗にて御戦ひなされ、御肘に鎗疵を被り、引き退き、是れまで御そばに女どもつきそひて居り申し候を、
「女はくるしからず、急ぎ罷り出でよ」
と、仰せられ、追ひ出させられ、既に御殿に火を懸け、焼け来たり候。
お姿をお見せあるまじきとおぼしめし候か、殿中奥深く入り給ひ、内よりも御南戸の口を引き立て、無情に御腹めされ、
(4)「本能寺の変」の時に明智光秀がいた場所
①本能寺(通説)
②三条堀川の本陣(『明智軍記』)
③鳥羽(『乙夜之書物』)
記者「「本能寺の変」の時、明智光秀は鳥羽にいたと思うか?」
学者「鳥羽にいたとは思えない」
実に明瞭な質問に、明瞭な回答である。ただ、私としては、記者に、
記者「では、「本能寺の変」の時、明智光秀はどこにいたと思うか?」
と突っ込んでいただきたかった。というのも、
『乙夜之書物』が投げかけた問題は、
「明智光秀が鳥羽にいたかどうか」
ではなく、
「明智光秀が本能寺にいたかどうか」
だと思うからである。
「本能寺の変」が「2000人で本能寺の織田信長を討った政変」であれば、大将の明智光秀は本能寺にいて指揮していたはずで、「鳥羽にいたとは思えない」と笑い飛ばせばいいのですが、「本能寺の変」が通説のように「13000人で本能寺で織田信長を討ち、次にこの13000人が二条新御所へ移動して織田信忠を討つという行き当たりばったりの政変」ではなく、「進軍前から軍隊を複数に分け、本能寺を含む複数箇所を占拠するという綿密に計画された政変」であれば、実際に軍隊を指揮するのは各軍隊の大将であり、総大将の明智光秀は本陣にいたはずです。その本陣が三条堀川であれば、「本能寺の変」は「洛中規模」の政変、 鳥羽であれば、「洛中洛外規模」の政変になります。
・洛中規模の政変:三条堀川に本陣を置き、七口を固めて京から出さない。
・洛中洛外規模の政変:織田信長や織田信忠が、明智領の丹波国に逃げ込むとか、近江国の明智領を通って安土城へ逃げることはない。逃げるとすれば南(堺=織田信孝率いる四国攻めの軍隊)なので、鳥羽にいて、京の南側に網を張れば、取り逃がすことはない。
なお、明智光秀が本陣を飛び出して、二条新御所へ急行したのは、誠仁親王に自害されては困るからでしょう。
従来説の、
「13000人で本能寺の織田信長を討った」
では、
「13000人も必要だろうか?(そんな無駄を明智光秀がするだろうか?)」
「なぜ織田信忠は安土なり堺へ逃げなかったのか?」
という疑問が湧きます。今回の『乙夜之書物』の記述の公表は、単に「本能寺の変の時に明智光秀が鳥羽にいたかいないか」の問題に留まらず、「本能寺の変の実際」を再考するいいきっかけとなる「研究・議論の序章」なのです。
※情報1:『乙夜之書物』の詳細は来月(2021年3月)発行の越中史壇会機関誌『富山史壇』(第194号)に掲載とのこと。
・論文:「『乙夜之書物』に記された本能寺の変―宥照寺の光秀塚と明智左馬助―」
https://shidankai.web.fc2.com/
https://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I031356376-00
※情報2:『乙夜之書物』の「本能寺の変」の記述部分の書籍化が進行中とのこと。個人的には解説は後でいいので、まずは『乙夜之書物』と『政春古兵談』の翻刻を早く出版して頂きたい。
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
