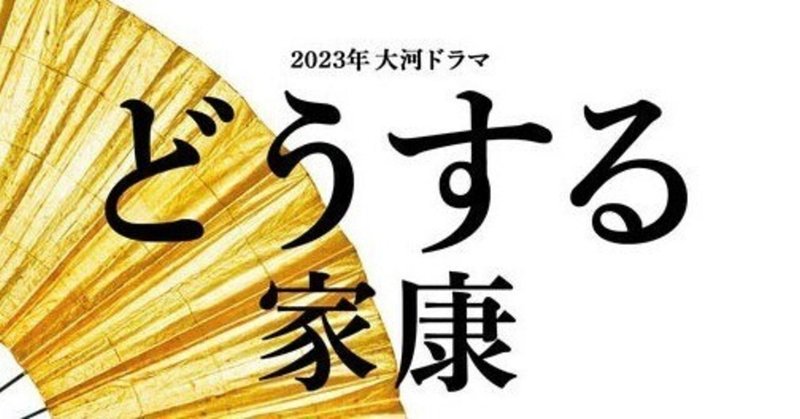
第17回「三方ヶ原合戦」(復習)
【徳川家康略年表】
天文11年(1542年)12月26日 徳川家康誕生
天文24年(1555年)3月 徳川家康、元服
永禄3年(1560年)5月19日 「桶狭間の戦い」(岡崎城へ帰還)
永禄4年(1561年)4月11日 「牛久保城攻め」(今川氏から独立)
永禄5年(1562年)1月15日 「清須同盟」(織田信長と和睦)
永禄5年(1562年)2月4日 「上ノ郷城攻め」(人質交換)
永禄6年(1563年)7月6日 「元康」から「家康」に改名
永禄6年(1563年)10月 「三河一向一揆」勃発
永禄7年(1564年)2月28日 「三河一向一揆」終結
永禄8年(1565年)11月11日 二女・督姫(母:西郡局)誕生(旧説)
永禄9年(1566年)5月 松平家康、三河国を平定。
永禄9年(1566年)12月29日「松平」から「徳川」に改姓。「三河守」に。
永禄11年(1568年)10月 織田信長、足利義昭と共に上洛
永禄11年(1568年)10月18日 足利義昭、征夷大将軍に任官
永禄11年(1568年)12月6日 武田信玄、駿河国へ侵攻開始(第1次侵攻)
永禄11年(1568年)12月13日 徳川家康、遠江国へ侵攻開始
永禄11年(1568年)12月18日 徳川家康、引間城を奪取
永禄12年(1569年)5月15日 掛川城、開城(遠江国平定)
永禄13年(1570年)3月 徳川家康、上洛。
元亀元年(1570年)4月30日 「金ヶ崎の退き口」
元亀元年(1570年)6月28日 「姉川の戦い」
元亀元年(1570年)9月12日 徳川家康、浜松城に移る。
元亀元年(1570年)10月 徳川家康が、武田信玄との同盟を破棄。
→上杉謙信と「三越同盟」を締結。
元亀元年(1570年)11月 松平勝俊、下山を脱出して浜松へ至る。
元亀3年(1572年)10月3日 武田信玄、「西上作戦」を開始。
元亀3年(1573年)12月22日 「三方ヶ原の戦い」
・・・(今回ここまで)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
元亀4年(1574年)4月12日 武田信玄、死没。享年51。
元和2年(1616年)4月17日 徳川家康、死没。享年75。
1.遠江国の領主は、徳川家康と武田信玄のどっちがいい?
前回、井伊虎松は、「武田信玄は金をくれるいい人で、徳川家康は、旧領主・今川氏を追い出した侵略者だ」と評していたが、どうなんだろう?
──遠江人にしたら、徳川家康も、武田信玄も侵略者では?
国衆は、勝ち組について領地を確保したいと思うもの。遠江国の国衆にしたら、徳川家康と武田信玄の戦力を比較し、武田信玄につきたいと考えるのは当然のことであろう。金をくれるなら尚更であろう。
民衆にしたらどうか? 確かに大量虐殺が行われた気賀(浜松市北区)の住民は徳川家康を恨んでいるが、そこ以外の住民は「武田信玄は今川氏真を殺そうとして駿府を焼き払ったが、徳川家康は今川氏真を逃がした人物」と思っているのではないだろうか。
今回、武田信玄が攻めてくると知った引馬宿の人々は逃げていた。(実際、浜松城内に逃げ込んだという。)武田信玄が、侵攻ルート上の村々で乱取りしている(食料(兵糧米)を奪い取っている)という噂が伝わって来たのであろう。そうでなければ、「今川氏を追い出した侵略者・徳川家康を追い出すために、名君・武田信玄が来て下さる」と歓迎する準備をするはずである。
2.武田信玄の侵攻ルート
武田信玄は、侵攻ルート上の寺社に金銭や食料を要求した。それに応じた寺社には安堵状を発行したが、応じない寺社は焼き払った。どの寺社にいつ安堵状を発行したか調べることにより、武田信玄の侵攻ルートが判明した。
武田信玄の侵攻ルートは、南下ではなく、西進である。
天竜川の東の「一言坂」で、本多忠勝は、武田軍本隊と戦った。『どうする家康』の
①武田軍は、全員、赤備えであった。
②本多忠勝は、黒尽くめで、負傷していた。
①武田軍の中で、赤い甲冑を身に纏っているのは山県隊だけである。この時、山県隊は別働隊として、東三河にいた。(後に二俣城で武田本隊と合流した。)本多忠勝が戦ったのは、武田本隊の馬場隊である。
②本多忠勝の兜には、伊賀八幡宮の御符を貼り合わせて作った鹿の角があった。また、名槍「蜻蛉切」の柄は青貝の螺鈿細工が施されており、青白かったという。また、本多忠勝は、戦場で負傷したことはなかった。あの血は、本人が言うように返り血か?(返り血であれば、甲冑にもついているであろう。)
3.「三方ヶ原の戦い」
さて、「三方ヶ原の戦い」であるが、主戦場がどこであるか分からない。
①小豆餅説:旧説(参謀本部『日本戦史』)
②祝田の旧坂説(丸山南麓説):有力説(歴史学者・高柳光寿)
③大谷説:新説(郷土史家・鈴木千代松)
が有名である。
「祝田の旧坂説」は、歴史学者・高柳光寿氏の説で、今年(2023年)3月31日、椿地蔵の横に解説板が設置された。
いくさばの果てのしづけさ藪椿 (鈴木良枝)
『どうする家康』では、武田信玄は、欠下で三方原に上り、信玄街道を通って横切り、祝田の坂で三方原を下ろうとしたという「祝田の旧坂説」が採用された。
「なぜ徳川家康は篭城しなかったのか? 出陣したのか?」の回答には諸説あるが、「勝てる」と思わなければ出陣しないはずで、「祝田の坂を下っている時に上から攻めれば勝てる」(実際「一言坂の戦い」では上下から挟まれて負けたが、直前の「三箇野台の戦い」では台地の上から攻めて勝っている)と思ったからであろう。(しかし、徳川軍が祝田の旧坂へ行くのが早すぎて、武田軍は坂を下る前で、隊形を整えて待っていたという。ドラマでは、徳川軍が有利なのは「地の利」(地形が頭に入っていること)だとしていたが、武田信玄が戦い前に地形を徹底的に調べさせることは有名であるし、武田方に寝返った天野氏が地形を教えていた。
──「勝兵先勝而後求戦、敗兵先戦而後求勝。」(『孫子』)
地形の把握など、事前の準備をしっかりとしておけば、勝ったも同然。
※浜松の2人の高柳氏:1人目は、歴史学者・高柳光寿氏(1892-1969)。静岡県敷知郡浜松町(現・浜松市中区肴町)で生れた。彼の研究方法は、「歴史研究は良質な史料に基づかなければならない」という「実証史学」で、参謀本部『日本戦史』によって通説化していた説の再検討を行った。
もう1人の有名な高柳氏は、「日本のテレビの父」高柳健次郎氏(1899-1990)である。静岡県浜名郡和田村(現・静岡県浜松市東区安新町)に生まれた。近くの浜松橋羽郵便局(浜松市東区天龍川町)の風景印は「イロハのイの字」である。(「てんりゅうがわ町」(地名)の正しい表記は「天竜川町」ではなく「天龍川町」であるが、JRの駅名は「天竜川駅」である。知念侑李さんの母校は、浜松市東区龍光町の浜松市立天竜中学校(芸能活動に専念するため、東京都杉並区立宮前中学校へ転校)である。)
4.Reco説
ここから先は
¥ 500
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
