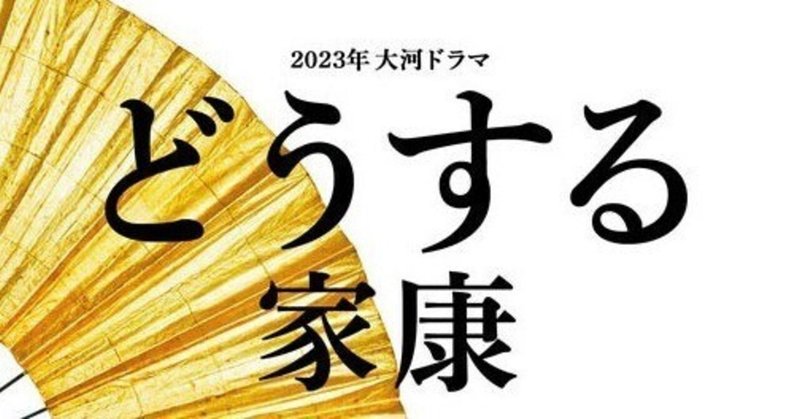
第17回「三方ヶ原合戦」(予習)
【徳川家康略年表】
天文11年(1542年)12月26日 徳川家康誕生
天文24年(1555年)3月 徳川家康、元服
永禄3年(1560年)5月19日 「桶狭間の戦い」(岡崎城へ帰還)
永禄4年(1561年)4月11日 「牛久保城攻め」(今川氏から独立)
永禄5年(1562年)1月15日 「清須同盟」(織田信長と和睦)
永禄5年(1562年)2月4日 「上ノ郷城攻め」(人質交換)
永禄6年(1563年)7月6日 「元康」から「家康」に改名
永禄6年(1563年)10月 「三河一向一揆」勃発
永禄7年(1564年)2月28日 「三河一向一揆」終結
永禄8年(1565年)11月11日 二女・督姫(母:西郡局)誕生(旧説)
永禄9年(1566年)5月 松平家康、三河国を平定。
永禄9年(1566年)12月29日「松平」から「徳川」に改姓。「三河守」に。
永禄11年(1568年)10月 織田信長、足利義昭と共に上洛
永禄11年(1568年)10月18日 足利義昭、征夷大将軍に任官
永禄11年(1568年)12月6日 武田信玄、駿河国へ侵攻開始(第1次侵攻)
永禄11年(1568年)12月13日 徳川家康、遠江国へ侵攻開始
永禄11年(1568年)12月18日 徳川家康、引間城を奪取
永禄12年(1569年)5月15日 掛川城、開城(遠江国平定)
永禄13年(1570年)3月 徳川家康、上洛。
元亀元年(1570年)4月30日 「金ヶ崎の退き口」
元亀元年(1570年)6月28日 「姉川の戦い」
元亀元年(1570年)9月12日 徳川家康、浜松城に移る。
元亀元年(1570年)10月 徳川家康が、武田信玄との同盟を破棄。
→上杉謙信と「三越同盟」を締結。
元亀元年(1570年)11月 松平勝俊、下山を脱出して浜松へ至る。
元亀3年(1572年)10月3日 武田信玄、「西上作戦」を開始。
元亀3年(1572年)12月22日 「三方ヶ原の戦い」
・・・(今回ここまで)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
元亀4年(1573年)4月12日 武田信玄、死没。享年51。
元和2年(1616年)4月17日 徳川家康、死没。享年75。
南遠(遠江国南部の平野部)の古社、古寺を回ると、由緒書に「古文書は武田と徳川の戦火によって失われた」とあることが少なくない。たとえば、遠江国一宮・事任八幡宮もその1社である。
現在の刷新された公式ホームページには、
戦国の世では、この一帯も戦いの渦の中でした。「己等乃麻知比売命」様をお守りしようと社家の者は、比売神様の分霊をあちらこちらにお祀りいたしました。
戦国の時代を経て、徳川家康が大檀那として本殿を造営した棟札があります。造営しなくてはならない痛手を当社も受けていたのでしょう。
とあるが、以前の公式ホームページには「武田と徳川の戦禍を避けるため、事任神社、小国神社、砥鹿神社に比売神様の分霊をお祀りいたしました。その後、社殿は武田と徳川の戦火で焼失したので、現在地に造営しました」と書いてあった気がする。
事任八幡宮での武田と徳川の戦いがあったなんて聞いたことがないが。
他の焼失した古社、古寺でも、武田と徳川の戦いがあったなんて聞いたことがないが。
調べてみると、「武田信玄は、遠江侵攻ルート上の古社、古寺にお金や食料を要求し、差し出せば安堵状を発給し、拒否すれば焼いた」ということらしいことが分かった。
──あれ? 武田信玄って青崩峠から南下したんじゃないの?

最近の学会では、北遠の青崩峠から浜松のある南遠へ南下した「南下説」という従来説は否定され、駿府から浜松への南遠「西進説」が主流らしい。
『当代記』にも「十月、武田信玄、遠州に発向。高天神表を通り、見付国府に打ち出さる」とある。
■白羽神社(10月14日)

定
白羽神主並二之禰宜被成御赦免之間、早々令還住、神役等、如前々無相違可懃仕之旨、所被仰出也。仍如件。
市河宮内助奉之
元亀三年
十月十四日(竜朱印)
土屋豊前守殿
永禄年間、今川義元まで武将代々の朱黒印の寄進もあったが、元亀年間、武田信玄がこの地に出兵乱入の際、所伝の古文書類はもとより社殿等兵火に罹り、全て焼失したが、御神体のみ島田市中川根白羽山に疎開、戦乱平定後、武田氏は神威を畏れ社殿を再建し、元亀3年10月14日御神体を還幸した。
白羽神社は徳川方についており、武田と徳川の戦禍を避けるため、山間部に避難した(「白羽山之神社」)。社殿が武田軍によって焼かれると、白羽神社は武田方についたようで、これは領主宛の「安堵するので、白羽山(静岡県榛原郡川根本町水川)から降りて来て、今まで通りに営め」という書状のようだ。
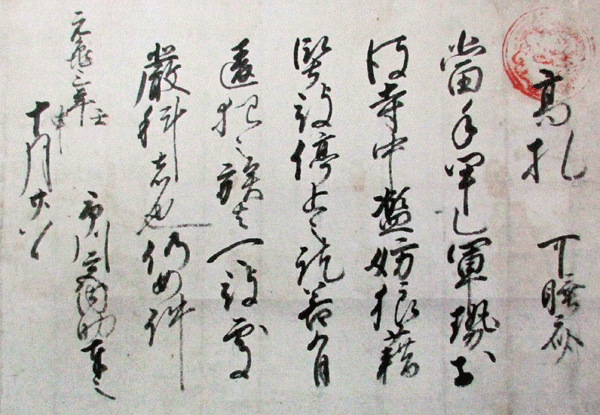
(竜朱印)高札 可睡斎
当手甲乙軍勢、於彼寺中濫妨狼藉、堅被停止之訖。若有違犯之族者、可被処厳科者也。仍如件。
元亀三年壬申 市川宮内助奉之
十月廿八日
武田軍の寺内での乱暴、狼藉を禁止している。

なお、可睡斎の近くに久野城があるが、武田信玄は落せなかったという。(武田信玄が落せなかった遠江国の城は、高天神城、久野城、堀江城の3城だけだとされる。)
また、可睡斎には、武田軍に追われた徳川家康が逃げ込んだ「出世六の字穴」がある。
【武田信玄の遠江侵攻ルート論争史】 -南下(従来説)か西進(新説)か-
新説(西進説)発表:柴裕之『戦国・織豊期大名徳川氏の領国支配』2014
↓ 反論(旧説=南下説支持)
鴨川達夫「元亀年間の武田信玄」2012
https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/kiyo/22/kiyo0022-05.pdf
↓ 反論(新説=西進説支持)
・本多隆成「武田信玄の遠江侵攻経路 -鴨川説をめぐって-」2013
↓ 反論(旧説=南下説支持)
・鴨川達夫「武田信玄の「西上作戦」を研究する」2015
https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/kiyo/25/kiyo0025-01.pdf
↓ 反論(新説=西進説支持)
・本多隆成「徳川・武田両氏の攻防と二俣城」
↓ 反論(旧説=南下説支持)
・柴辻俊六「武田信玄の上洛路は青崩峠越えか駿河路か」2020
↓ 反論(新説=西進説支持)
・本多隆成「信玄の遠江侵攻経路 -柴辻俊六説批判-」2022
★今後の『どうする家康』
・第17回「三方ヶ原合戦」(5/7)
・第18回「真・三方ヶ原合戦」(5/14)
・第19回「お手付きしてどうする!」(5/21)
・第20回「岡崎クーデター」(5/28)
・第21回「長篠を救え!」(6/4)
・第22回「設楽原の戦い」(6/11)
・第23回「瀬名、覚醒」(6/18)
・第24回「築山へ集え!」(6/25)
※ノベライズ3巻は6月、4巻は9月発行予定です。
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
