
上ノ郷城攻め
■鵜殿氏
鵜殿長善【上ノ郷】┬長将┬長持─長照(「桶狭間の戦い」時の大高城主)
│ ├長祐【柏原】…西郡局(徳川家康の側室)
│ └長成【不相】
└長存【下ノ郷】
■上ノ郷城
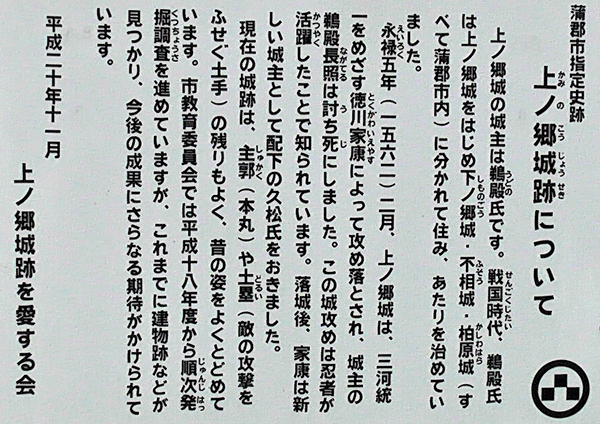
■甲賀忍者の上ノ郷城攻め「鵜殿藤太郎御退治」
「上ノ郷城攻め」では甲賀忍者が活躍したという。
後掲の「甲賀古士訴願状」によれば、仲介者は戸田三郎四郎と牧野伝蔵。2人は甲賀へ向かい、伴与七郎ら80人、鵜飼孫六ら200人、合計280人の忍者を連れて帰ったという。(牧野伝蔵は今川方では?)
一方、松井忠次の親友・石川昌隆(正西)が著した『石川正西聞見集』によれば、松井忠次が一緒に食事をするほど仲の良い伴中書兄弟に頼んで忍者を集めさせたとある。
津の平近所さしむかひに、東条と申す昔よりの城へ、宗輝様(忠次。のち康親)御移り、御用心よく、御心安おぼし召し、伊賀、甲賀より覚えある者御呼び下し、其の内、物頭(ものがしら)・中書兄弟、此の人とは、朝夕相伴にて、御膳の内の物をも分けて下さるるやうに、御懇に成られ、御かゝへ置き、其の上、御談合有りて、東三河の内、西郡の城を雨の夜に忍び取りになされ候。
※「宗輝様」は松井忠次、「物頭・中書」は忍者頭(組頭、棟梁)・伴中書、「西郡(にしのこほり)の城」は上ノ郷城である。
「上ノ郷城攻め」の出陣は2月4日で、上ノ郷城夜襲で活躍したのは、松井忠治の要請でやって来た「甲賀五十三家」伴家(伴家、望月家、山中家で「柏木三家」)の伴中書&伴太郎左衛門資家親子等182人と、「甲賀五十三家」多良尾家の多良尾四郎左衛門光俊(「神君伊賀越え」で活躍)の郎党18人、合計200名だと思われる。彼らは雨の日の夜、上ノ郷城内に潜入して、上ノ郷城の櫓に火をつけて城内を混乱させ、鵜殿藤太郎長照を伴与七郎資定が討ち取った。松平蔵人元康が伴与七郎資定に送った2月6日付の感状が残る。

今度鵜殿藤太郎其方被討取、近比御高名無比類候。我等別而彼者年来無沙汰候。散心霧弥祝着申候。委細、左近、雅楽助可申候。恐々謹言。
二月六日 松蔵元康(花押)
伴与七郎 参
※泰巖(たいがん)歴史美術館:東京都町田市中町1丁目に3年前(2020年3月22日)に開館した歴史美術館。町田市の不動産「太陽グループ」の山中泰久氏が蒐集した「太陽コレクション」を管理、展示する。
この「上ノ郷城攻め」は、「鵜殿藤太郎御退治」「鵜殿合戦」とも呼ばれ、甲賀忍者の功績として語られることが多い。(一方、伊賀忍者の功績として語られることが多いのは「神君伊賀越え」である。)
権現様へ甲賀古士共ご奉公申上げ候由来は、権現様未だ三州に御住国の刻、御敵御同国の住人・鵜殿藤太郎御退治の儀を、永禄五年二月、戸田三郎四郎殿と牧野傳蔵殿との御両使を以って甲賀二十一家の者共に御頼み成され候に付、早速御請申し上げ、甲賀の者二百人、三州へ罷り越し、同二十六日の夜、鵜殿の城へ夜討に入る。即ち、鵜殿の首を捕り、子供二人を生捕り候て差し上げ、其の外にも名の有る家来二百余人を焼き討ちに仕り、其のついでに土呂張崎の御堂まで踏み落とし候得ば、斜めならず御感悦成され、御前へ甲賀の者を召し出だされ御盃を下され、自今以後は甲賀廿一家の者共を余所には御覧成され間敷候間、廿一家の者共も、御家の儀粗略に存じ奉り間敷の旨仰せ出でられ、その以後よりは数度御密通の御用仰せ付けられ候御事。
また、活躍したのは甲賀衆(甲賀21家)ではなく、伊賀衆(服部半蔵)だと『寛政重修諸家譜』「服部正成」にあり、それは服部正成(1542-1597)が16歳の初陣の時の話だという。とすると「西郡宇土城」=鵜殿城=上ノ郷城夜襲は、「桶狭間の戦い」以前の弘治3年(1557年)の出来事になってしまう。(上ノ郷城夜襲は5年後の1562年の出来事である。)さらに言えば、この時、徳川家康は服部正成に盃と槍を贈ったとするが、当時、徳川家康は今川家で人質生活を送っており、贈るのであれば徳川家康ではなく今川義元のはずであるし、今川義元が鵜殿氏を攻めさせるはずがない。
父に継で東照宮に仕へ奉り、三河国西郡宇土城夜討の時、正成十六歳にして伊賀の忍びの者六、七十人を率ゐて城内に忍び入り、戦功をはげます。これを賞せられて御持鎗(長七寸八分両鎬)を拝賜す。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1082721/1/53
■鵜殿坂
安楽寺(愛知県蒲郡市清田町門前)の横の坂で木の根に躓いて転倒し、その場で伴与七郎に討ち取られた。この坂を「鵜殿坂」と呼び、鵜殿長照の無念がこもったこの坂で転ぶと一生怪我が治らないとか、病気で死んでしまうとかいわれる。
鵜殿長照の供養塔は、上ノ郷鵜殿家の菩提寺「長応寺」(上ノ郷城からの飛び火で焼失し、廃寺となったが、後に復興された。現・正行院)にある。
■仙家道全
一、西尾郡鵜殿を、永録五年、家康公御攻めの時、鵜殿の家人に仙家道全迚(とて)、国中無隠大力の弓捕りありて、家康公、御陳射ける矢、御覧候へば「仙家道全」と有り、「此勘六矢先にては戦を先ず引くべし」迚御引成られ、後、山綱、羽栗通り、山忍に両村案内仕り、堀切りて山に御陳取り、夜討に北の裏門より御攻め、落城の由、古老・七兵衛咄にて候。
■『烈祖成績』
五年壬戌春、西参河粗(あらあら)平らぐ。神祖(注:徳川家康)、東参河を経略せんと欲す。
氏眞の将・鵜殿長持、西郡城に拠る。松井忠次をして之を図らしむ。忠次、従士・石原三郎左衛門、及び、伊賀諜(ちょう)伴中務、伴太郎左衛門と謀り、甲賀諜十八人を招く。三月十五日夜、中務と西郡城に潜入し長持を刺殺す。長子・藤太郎長照、次子・藤三郎を擒(とら)へて城を火(や)く。神祖、兵を進め、之に応ず。守兵、潰走し、城陥つ。
久松俊勝をして之を守らしむ。西郡要害の地たり。氏真、数(しばしば)出兵し、之を争ふ。俊勝、城に拠り、之を拒ぐ。既にして、俊勝、岡崎に還る。神祖の出師する毎に留守を為す。長子・康元をして西郡城を守らしむ。
是に先んじ、氏真、神祖の任子を殺さんと欲す。然れども、其の外祖・関口親永、豪族たるを以て止む。石川数正以為(おもえら)く、「郎君の駿府に在る勢、甚だ危殆(きたい)なり。一朝殺されて一(ひとり)として士人の殉死する無からん。是れ邦の辱なり。之を告ぐるも、神祖、必ず聴かれず」と。乃ち書に留め、家に已(お)く。竊(ひそ)かに駿河に往き、公子を保護す。氏眞の長照兄弟、執(と)らはるゝを憂ふるを聞き、親永に就きて之を謀る。質を易ふるを議す。氏眞之を許す。数正、岡崎に帰り、其の状を言ふ。神祖、大いに悦び、長照兄弟を駿河に還し、氏眞、夫人、公子を
岡崎に還す。数正、意気揚揚として、公子を雍樹(だきかゝえる)して帰る。時の人、之を壮とす。譜第の将士、皆、念子原に往き、之を迎ふ。持子、公子に換ふ。我が福にして彼が禍なり。其の識無きこと知るべきなり。〔徳川代々記、家忠日記、徳川記、徳川歴代、東照宮年譜附尾、松栄紀事〕
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
