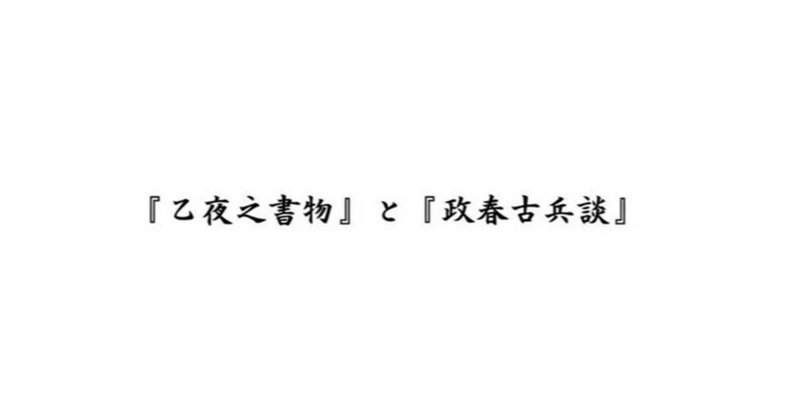
萩原大輔『異聞 本能寺の変』
『乙夜之書物』も、『政春古兵談』も、学者は存在を知っていたが、翻刻が無いため、検討が後回しにされてきた。萩原大輔氏が読んだところ、「本能寺の変」の時、明智光秀は本能寺にいなかった、鳥羽にいたと書いてあることが分かった。これが史実であれば、今まで書かれた歴史小説や、制作されたドラマは史実ではないことになる。
ちなみに、学説は、「明智光秀は、13000人の兵で本能寺を取り囲み、織田信長を討った」であり、「本能寺の変の凄いのは、13000人の兵で本能寺で織田信長を討ち、次に1万人の兵が二条御新造(二条城)へ移動して織田信忠を討ったこと」である。
織田信忠については、「信用できる」という『信長公記』に「か様之謀叛によものがし候はじ、雑兵之手にかゝり候ては、後難無念也」(これほどの謀反だから、しかも敵は、あの明智光秀であるから、万が一にも我々を逃さないよう「京都七口」は固めているだろう。妙覚寺を出て、雑兵の手にかかって死ぬのは、後々までの不名誉であり、無念である)と言ったとある。また、「ある程度は信用できる」という『当代記』には「惟任深く陰密しける間、路次へその擬ならざる間、安土へお移りにおいては別条あるべからずとこと、ご運の末と覚えたり」(明智光秀は、このクーデターをひた隠しにしていたので、(前々から細かな作戦(兵の分散配置等)を指示せず、全員で本能寺に向うという、打ち合わせなくして実行できる単純な作戦をとったのであって)街道には兵はおらず、織田信忠は、問題なく安土へ行けたのに、行かなかったのは、織田信忠の運が尽きたということであろう)とある。
これらの書物から、学者は、
・本能寺を取り囲むには3000人で十分。残り1万人を妙覚寺や「京都七口」に向わせるべきであった。愚策である。しかし、結果は大成功だった。
・織田信忠は、「京都七口」から安土なり、堺に逃げれば助かっていた。
と、明智光秀も織田信忠も馬鹿だと評価している。
今回の、「明智光秀は本能寺にはおらず鳥羽にいた」という指摘は、明智光秀が13000人の兵を分散配置していたことを意味し、明智光秀は馬鹿ではないし、織田信忠の「明智光秀は馬鹿ではないから、京都から逃げ出せなくしているであろう」という状況判断も正しかったことになる。
実は「明智光秀は兵を分散した」「明智光秀は本能寺にいなかった」ということは、江戸時代のベストセラー『明智軍記』に書かれている。『明智軍記』の明智光秀は、「敵は本能寺にあり」ではなく、「敵は四条本能寺、二条城にあり」と言っている。つまり、明智光秀は、最初から「織田信長を討つつもり」ではなく、「織田信長と織田信忠を討つつもり」であり、兵を分散し、自らは本陣にいたと書いてある。ところが学者は、「織田信忠は妙覚寺にいたので、『敵は四条本能寺、妙覚寺にあり』でなければならない。『明智軍記』は信用できない小説である」と無視してきた。
--------------------------------------------------------------------------------------
萩原大輔『【史料で読む戦国史④】異聞 本能寺の変―『乙夜之書物』が記す光秀の乱―』(八木書店)
本体2,800円+税
初版発行:2022年3月22日
A5判・上製・カバー装・290頁
ISBN 978-4-8406-2246-2 C3021
【目次】
はじめに
本書の主眼
本書の構成
第一章 『乙夜之書物』とその著者
加賀藩内有数の知識人
政春の曾祖父・祖父・父母・姉妹
五二四条に及ぶエピソード集
息子たちに他見を禁じる
関屋家秘蔵の書はいつ流出したのか
書名の名づけ親と由来
もう一つの著作『政春古兵談』
小括―『乙夜之書物』の性格と伝来―
第二章 『乙夜之書物』が記す織田信長攻め
第一節 謀議と挙兵
斎藤利三の到着を待つ
数寄屋での誓詞血判状
日暮れ前の亀山出発
桂川まで夜間の行軍
二〇〇〇余騎の先鋒隊
光秀は鳥羽に控えたり
第二節 本能寺攻め
明け方の乱れ髪
可児才蔵吉長の参戦
最前線にいた斎藤利宗
利宗姪の子 井上重成
第三節 信長の最期
畳を立て侍女を逃がす
何も出よ、何も出よ
第四節 謀反の遠因
信州諏訪での折檻
小姓衆にも殴られた金柑頭
堀に膳を捨てさせられる
怨恨と不安の複合説
第三章 『乙夜之書物』が記す織田信忠攻め
第一節 妙覚寺・二条御所へ
急ぎ足で鳥羽を発つ
道中で出会った女房
京の町屋にいた信長家臣
第二節 二条御所の攻防
証言者は進士作左衛門か
門前に迫る光秀
負傷でその後を知らず
第三節 脱出した織田有楽斎
狭間くぐりの悪名
信忠は自害した
第四章 『乙夜之書物』が記す乱の終焉
第一節 安土城の接収と山崎の戦い
安土城の財宝を分け与える
本陣「ヲンボウガ塚」
天王山の小競り合い
途方に暮れる大敗
第二節 明智左馬助と明智弥平次
新座家老と越前衆
光秀「ヲイ」と光秀「御モツ立」
第三節 安土退去と坂本落城
安土を捨て大津へ
波打ち際を駆け抜ける
不動国行の太刀
城に火を放つ
第四節 信長に鑓を浴びせた天野源右衛門
左の肩先を突く
顔に黒いアザ
第五章 『乙夜之書物』が記す戦国エピソード
第一節 惟任光秀の乱直後の前田利長
京都見物の上洛命令
日野から松ヶ島へ
安土は信雄が放火した
第二節 徳川家康の「神君伊賀越え」
木津川で殺された穴山梅雪
本多忠勝の諫言
大和国経由伊賀越え説をめぐって
第三節 佐々成政の「さらさら越え」
十八歳で供した者の証言
商人の道「ザラザラ越え」
第四節 伊達政宗の「小田原参陣」
御次の間で聞いた前田直玄
懐に小さな脇指
おわりに
「山鹿流の秘書」との関係
信長との軋轢と天下取りへの野心
付録
『乙夜之書物』内容一覧
主要史料解題
主要参考文献
索引
あとがき
【コラム】
桂川で「敵は本能寺にあり」と言ったのか
白小袖の信長イメージはいつからか
挙兵した光秀は何歳だったのか
山崎庄兵衛その後
高野山に光秀供養墓を築かせた津田重久
明智左馬助の兄弟が築いた光秀墓
前田利長の誕生日
https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/2237
【試し読み】
https://catalogue.books-yagi.co.jp/files/pdf/d9784840622462.pdf
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
