
瀧山寺の日吉神社と東照宮

1.日吉神社(日吉山王社)
最澄は、比叡(ひえい)山に入るとすぐに「七仏薬師」を刻み、本堂が出来ると安置し、比叡山の神を祀る「日吉(日枝、ひえ)大社」を守護社としたという。それで天台宗の寺には「本尊:薬師如来、守護社:日吉神社」というケースが多い。この滝山寺も「本尊:薬師如来、守護社:日吉神社」である。
2.滝山東照宮(常磐神社)
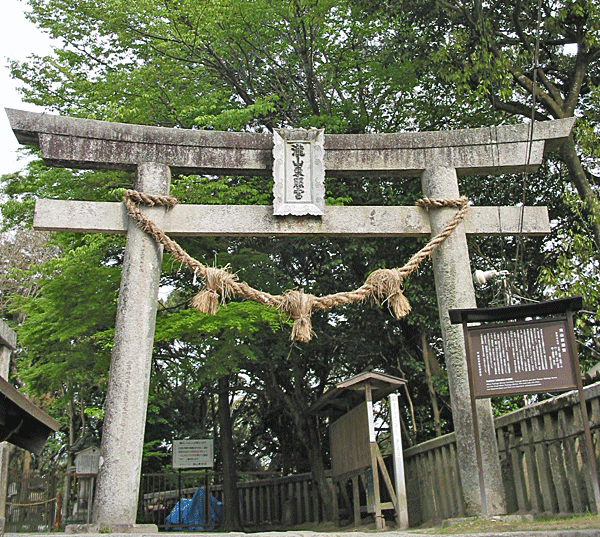
案内板が多いのは助かるが、写真を撮るには美しくない。

滝山東照宮
重要文化財 本殿・拝殿・幣殿・中門・鳥居
水屋(付石柵・銅燈籠・棟札)
昭和28年指定
滝山寺に伝える由緒書によれば、徳川三代将軍家光が、酒井忠勝、松平右衛門大夫及び龍山寺の青竜院亮盛の三人を召して、「三河の国は徳川家の本国、岡崎城は家康誕生の地で、また、在世の本城であるから、岡崎附近に権現さまを勧請したい。」「幸いにも、滝山寺は古跡で岡崎の要害の地にも当たり、家康が岡崎在城の節、信仰も厚かった霊地であるから、この地に東照宮を勧請するように…」と命じて神社が創建された。
社地は、滝山寺本堂の東、やや小高い場所を整地し、正保二年(一六四五)五月に着工し、同三年九月に竣工したと伝えられる。
江戸時代全期を通じて、日光東照宮、久能山東照宮と共に三宮の一つとして崇敬され、権勢を誇っていた。
社殿は、東照宮風のけん爛華麗な漆塗り及び極彩色が施され、蟇股、手挟みなど江戸時代初期の特徴がみられる。創建以来、江戸時代に七回、近年では昭和四四年から四六年にと度々修理がなされている。
拝殿の中に、狩野探幽一門の筆になる板地著色三十六歌仙扁額(市指定文化財)が掲げられている。


*滝山東照宮の狩野派一門による『三十六歌仙扁額』より「人丸」

*狩野探幽『三十六歌仙額』より「人丸」
・保乃\/戸明石能浦農朝霧尓 島かく連行舟を志所於毛婦
・帆能\/戸明石乃うら農朝霧尓 島閑具礼行舟を志所お毛ふ
ほのぼのと明石の浦の朝霧に
島がくれ行く舟をしぞ思ふ
(注)この歌は『万葉集』に載っておらず、万葉仮名ではなく、変体仮名が使われている。柿本人麿の歌ではなく、小野篁が隠岐島へ流刑に処せられた時に詠んだ歌だとする説もある。
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
