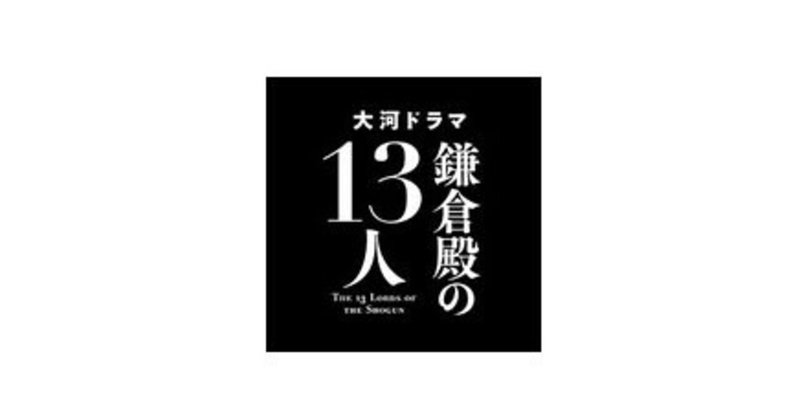
2022年NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(第2回)「佐殿の腹」の復習「八重姫と江間次郎」
1.入水自殺した八重姫
━━八重姫(ガッキー)を偲んで伊東市へ行く人が増えていると聞いた。
(1)源頼朝と八重姫
・音無しの森:源頼朝が八重姫と会っていた森。音無神社が建つ。
・日暮八幡神社:人目を忍ぶが源頼朝と八重姫は夜にしか会えない。源頼朝は、この神社で日暮れ(夜)になるのを待ったと伝えられている。
(2)千鶴丸
・稚児ヶ淵(伊東市八代田/鎌田):千鶴丸を沈めた川の淵。蜘蛛ヶ(くもが)淵、思ヶ(おもが)淵、稚児ヶ淵、轟ヶ淵、松枝が淵。鎌田山と雨降り山(今は無い)に挟まれた谷間にあったと伝えられている。
千鶴丸を沈める時、近くの鎌田神社の境内にあった橘の枝を2本折って、千鶴丸の両手に握らせて手向けとしたという。
■歌碑&現地案内板「柱状節理そびえる渓谷の悲しい物語」
■頼朝の愛児千鶴丸と稚児ヶ淵
伊豆に流された源頼朝と、伊東の領主 祐親の娘 八重姫との間に恋が芽生え、やがて二人のもとに生まれた愛児は千鶴丸と名づけられた。しかし、平家への恐れを抱く祐親の手によって、千鶴丸は伊東大川の上流の淵へ沈められてしまった(曽我物語による)。
淵の名は、くもが淵、とどろきが淵、松枝が淵などいろいろに呼ばれてきたが、今では稚児ヶ淵の名が一般的で、このあたりがその雰囲気を一番よく伝えている。
・轟の橘と産衣石(伊東市富戸):千鶴丸の水遺体は、宇根海岸に流着し、漁師・甚之右衛門が葬った。墓の目印がこの「産衣石」である。千鶴丸が握っていた橘の小枝は、根付いたが、昭和時代に枯死したという。(鎌田区の鎌田神社の橘と共に「轟の橘」という。)後に源頼朝は、甚之右衛門を呼び出し、恩賞や「生川(うぶかわ)」の姓(現在の屋号「生川屋(なまかわや)」)を与えたという。なお、富戸(ふこ)は、伊東荘や宇佐美荘が置かれた伊東氏の領地である。
・三島神社(伊東市富戸):富戸三島神社。式内・許志伎命神社の論社。流人・源頼朝の「祈願十七社」の1社。賀茂郡白浜村(河津町白浜)にあった伊豆国一宮・三嶋大社が、現在地(田方郡三島)に遷座した時が創始という。相殿の若宮社に千鶴丸が祀られている。
・最誓寺(伊東市音無町):江間小四郎と八重姫の発願により創建された千鶴丸の菩提寺・西成寺の後身寺。本堂には、八重姫が奉納したという千鶴丸地蔵菩薩像が安置されている。(慶長元年(1596年)、宗銀によって曹洞宗に改宗され、寺号も最誓寺に改められた。)
ここから先は
¥ 500
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
