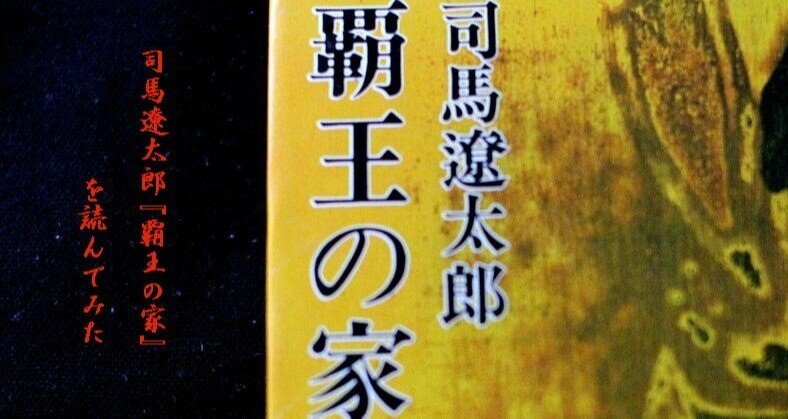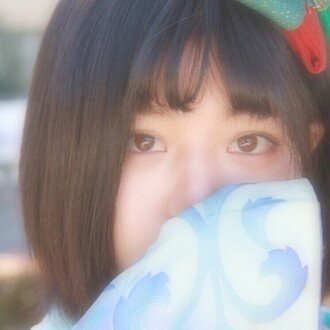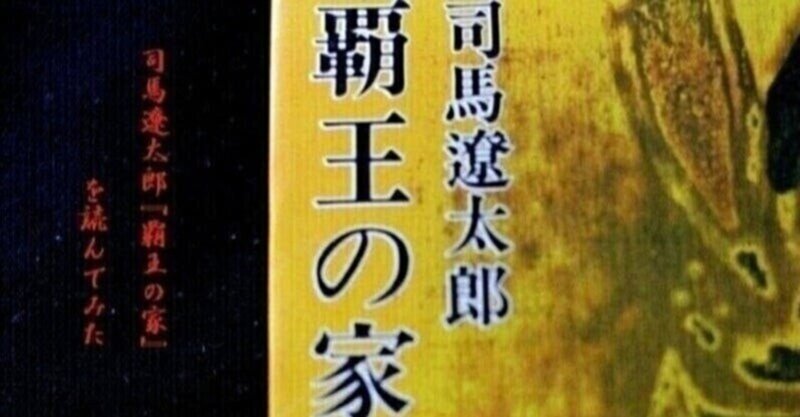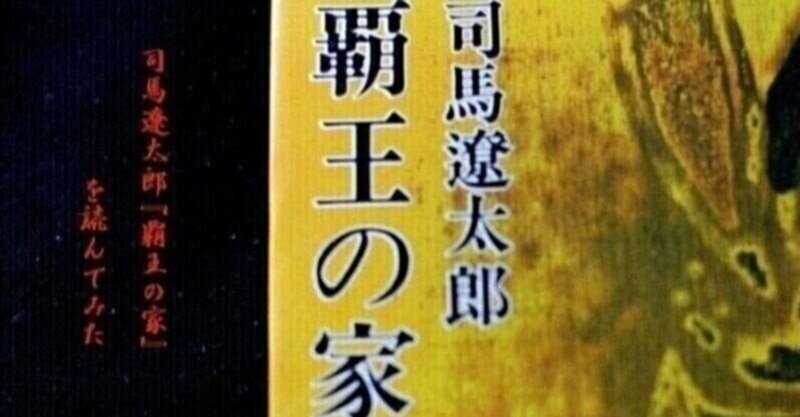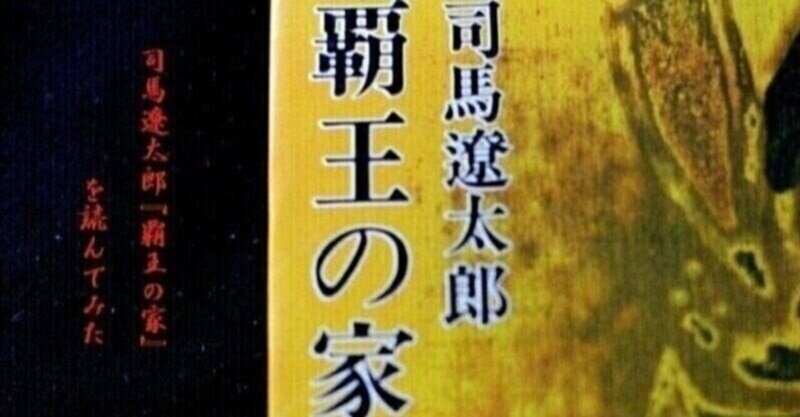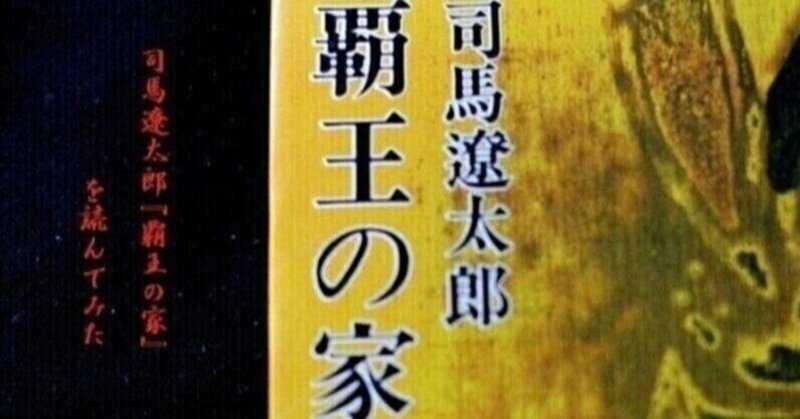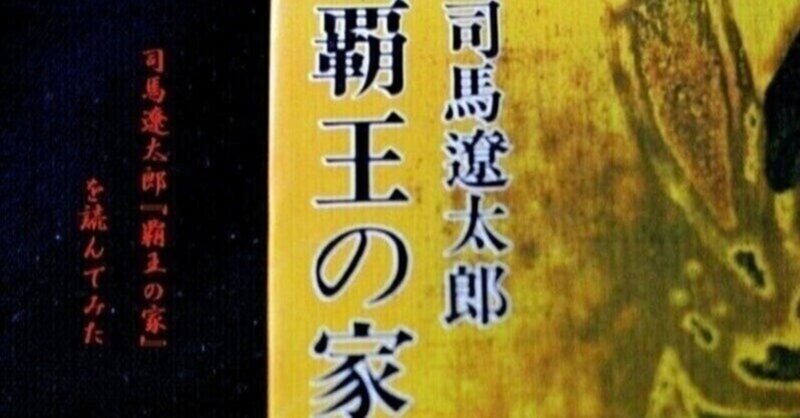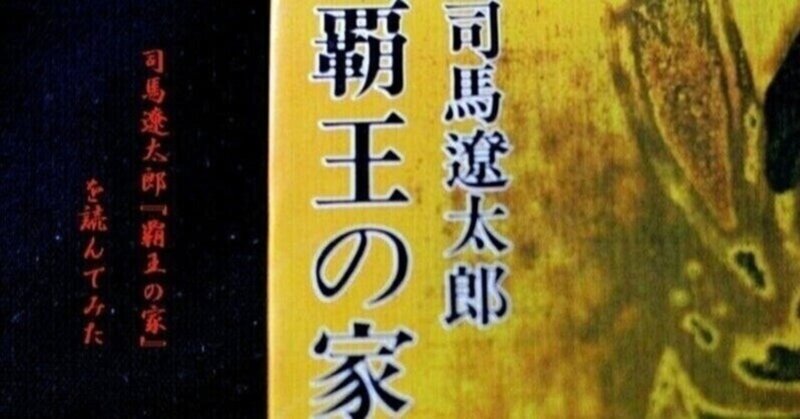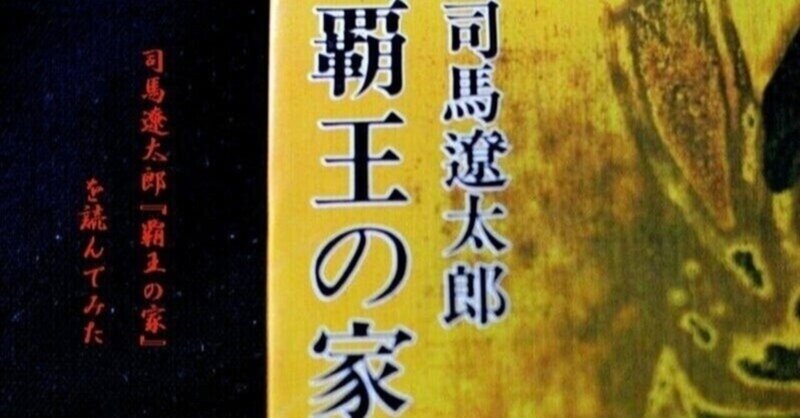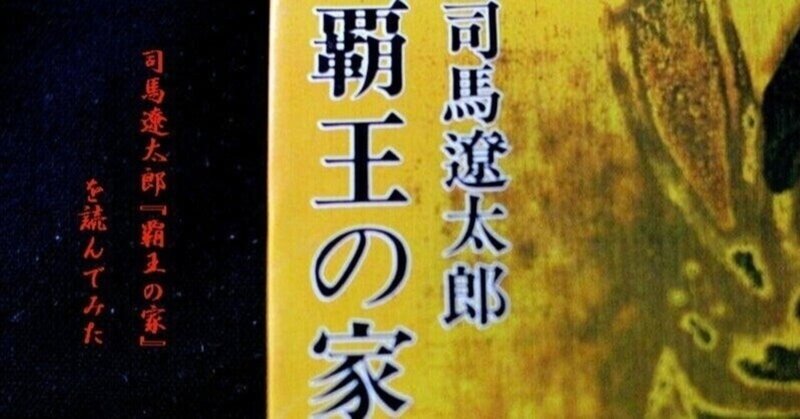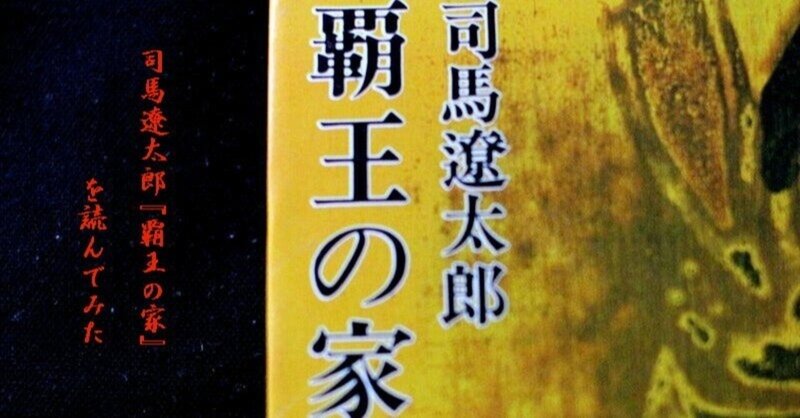記事一覧
司馬遼太郎『覇王の家』を読む⑤
以後、家康の代までこの家系はときにさかえたり、ときに衰えたりしたが、ともかくも三河国で3割ほどの面積を領分にし、岡崎城の城主であるほどの分限になっていた。しかし新興は新興でも、大名といえるほどの存在ではない。三河でのいくつかの大土豪のうちの代表的な存在というべきもので、ひとつ油断をし、働きがにぶると、戦乱のなかで消滅するかもしれない存在だった。
──司馬
司馬遼太郎『覇王の家』を読む
三河かたぎ
奥三河の山のなかの坂をのぼって、松平郷という、これ以上は山径(やまみち)もないという行きどまりの小天地に行ったときの夏の陽ざかりの印象は、筆者にとってわすれがたい思い出になっている。
(ここがあの徳川家の発祥の地か)
とおもえば、草木まで意味ありげにおもえてはくるのだが、なににしても山が深く地がせまく、しかも気づいてまわりを見まわしてみると、みぞほどの流れもない。水がないとい