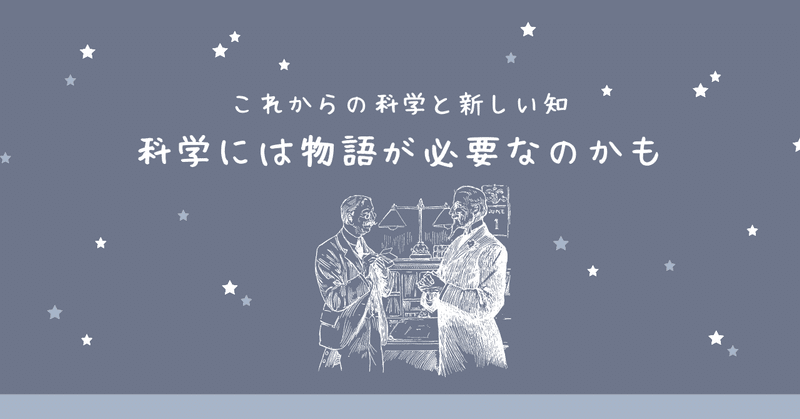
科学は物語をつくれるか。曖昧さを抱えること。
科学は多くの人を救ってきた。
科学は事実を取り出し、公平に思考することを許してくれる。
わからないことを、少しずつわからせてくれる。
でも、科学はつまらない。
ちがう、今の科学はつまらない。
このnoteのために論文を読み、原稿を準備しているうちに、私はそう思いはじめていた。
科学はおもしろい! という科学者たち
私は、科学の恩恵に与りながら、科学というものをあまり信用せずに大人になった。
誰かの発見を「事実」として教わり、それ以上にもそれ以下にも余白のない感じが窮屈だった。
そのくせ、あっちの科学とこっちの科学は矛盾するのだ。そして、本当に必要なことは教えてくれない。
ちょうど一年と少し前、私は延長された育休のまっただ中にいた。
毎日かわいい娘と遊んでいると、脳みそがヒマだった。
そんなときに、図書館で中村桂子さんの『知の発見』という本をなんとなく借りて、科学という学問に対するイメージが変わった。
科学って、想像していいんだ。
ひとことでいうと、そんな感じだった。
想像は、私が好きな小説の世界では許されても、科学では許されないと思っていた。
わくわくした。
科学は、自分の想像力の幅を広げてくれる気がした。
復職の際、それまでの肩書きを捨てて研究職を希望した。
科学はおもしろい、という科学者たちがいる。
彼らは、自分で仮説を立て(おそらくそこには想像力のための場所がある)、それを実験で証明できたときにおもしろさを感じるのかもしれない。
でも、それを教わる私たち一般庶民に「伝わらない」のだ。
それは、発見されたあとの科学には物語の入り込む余地がないから。
物語のない科学、曖昧さを排除する科学
上述の中村桂子さんが、30年前に「生命誌研究館」という場所をつくった。
科学のコンサートホールとして、芸術と同じように科学を楽しんでもらいたいという願いも込められている。
ここが年に4回出している季刊誌を私は楽しみにしているのだけれど、今回の季刊誌に掲載されていた鼎談はまさしく今の私にとても刺さる内容だった。
霊長類学者の山極壽一さん、小説家の小川洋子さん、そして生命誌研究館現館長の永田和宏さん。
詳細はぜひ読んでいただきたいのだけれど、ここで山極さんが「科学には原因と結果が大事で、物語にすることを避ける。だから伝わりにくくなってしまう」と仰っていたのが印象的だった。
それに対して、永田館長は「生命誌では、生命の辿った時間の累積を物語るナラティブを大事にしている」と答えておられ、
この回答に私はものすごくものすごく慰められた。
誰かが科学者を批判してそう言っているんじゃない。
一部の科学者たち自身がそういった意識で取り組んでいる。
デジタルに依存し始める生命科学。
アナログに生きる自然の中の人間。
厳密さが求められる中で、科学はどこまで曖昧さを抱えられるのか。
そんな言葉が飛び交う今回の鼎談は、再現性、画一性、科学的であるということ、そんなすべてを考え直すことを許し、求めさえしていた。
鼎談の内容はこちらから見られます。
これまでの科学は、こうしたやり方でよかった。
でもこれからの科学は、そのやり方を変えていかなくてはいけない。
中村桂子さんは、10年前も同じことを言っておられた。おそらく、30年前からそうした考えのもとに活動しておられるのだろう。
下手をすれば、エセ科学だと否定されかねない難しい試みだ。
でも、科学界の第一線で活躍する人、そして芸術界や料理界など異分野の第一線で活躍する多くの人が集まる生命誌研究館には、たぶん人間としての私たちが揺さぶられ、惹きつけられる何かがあるのだろう。
それは学問の統合といった大げさなものではなく、お隣さんと毎日挨拶をすることを当たり前にしようといったような試みなのかもしれない。
私は、目の前にある、自分の五感で知覚できる事実以上のことを想像する余地のある科学を信じていたい。
目に見えない微生物は、きっとそのわくわくする余白に思いを巡らせる機会をくれると思うから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
