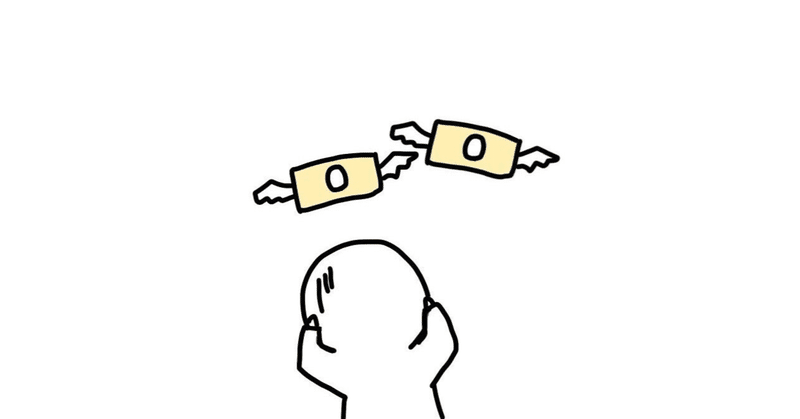
2年間積み立てた学資保険を解約しました【後悔はしていない】
学資保険への加入は失敗でした
2020年2月、待望の長男が誕生。
そして2ヶ月後の4月に教育費の貯蓄のために学資保険に加入しました。
子供が生まれたら学資保険。
特に深く考えることをせず、営業マンに言われるがまま支払いを開始しました。
「深く考えることなく」
今思えばここが私の大失敗。
昨今、学資保険は満期まで積み立てたとしても返礼率が低いことは分かっていました。
ならば他の貯め方があるのではないか?
本当にこれがベストな選択なのか?
全くリサーチせずに契約してしまったのです。
この記事では、
✔︎ 何故学資保険を解約しようと思ったのか
✔︎ 解約を躊躇した理由
✔︎ それでも解約した経緯
について簡単にまとめています。
現在学資保険を検討されている方や学資保険解約について悩んでいる方はぜひお読みください。
そもそも学資保険とは?
学資保険は、子どもの教育資金を準備するための保険です。
また、両親に万が一のことがあった場合、それ以降の支払いが免除され、その後満期を迎えた際に予定されていた教育資金を受け取ることもできます。
私たち夫婦が加入した学資保険は、
14歳までに合計300万円を年払いで積み立て、その後18歳から5年間に分割して計320万円がもらえるプランでした。(細かい数字は割愛しています)
返礼率は約106.6%。
保険料払込よりも、多く保険金がもらえるのがメリットです。
「定期預金と比べるとそれでも18年後には多少増えるからいいね」と夫婦で話し合い加入をしました。
学資保険を解約しようと考えた理由
月日は流れ、2022年1月。
第二子を妊娠し、安定期に入った私は流行りのマネーリテラシーをつけたい!と考え、お金の勉強を始めました。
そこで度々目にするようになったのが、
「学資保険は必要ない」
「学資保険加入の検討は慎重に」
そんな文言でした。
学資保険にばっちり加入していた私は、恐る恐るその理由が解説されたある動画を見ることにしました。
それがこちら↓
この動画から学んだ学資保険のデメリットは3つ
①元本割れのリスク
②インフレリスクに対応できない
③資金が長期固定される割に利回りが低い
詳しくは是非動画またはリベラルアーツ大学のブログを見てみてください。
そして同時に、2年前の私には全くなかった定期預金でも学資保険でもない新たな教育資金の準備の方法があることも知りました。
それがインデックス投資です。
(新たに教育資金をどのように貯めることにしたのかもまた後日書きたいなと思います。)
学資保険は、
リスクの割にメリットが薄い。
お金の勉強をしていく中で、そのことを強く感じるようになりました。
解約を躊躇した理由
しかし、いざ途中解約するとなると気になったのが「元本割れ」。
私たちの場合、42万円の支払いに対して解約返戻金は35万円。
つまり、7万円の損切りが必要でした。
これから2人目が生まれ、出費がかさむ中での7万円はとても大きく感じ、正直怯みました。
それでも解約しようと決意
7万円の損切りをしてでも解約を決意した理由は1つ。
時間とお金がもったいないからです。
15歳までに300万円貯めようと思うと、年間約21万円、月々17,500円の積み立てになります。
これを学資保険で貯めるとなると年利はたった0.6%。
しかもこのお金は18年間しっかりと固定されてしまいます。
もしも、同じ金額を同じ期間インデックス投資で年利4%で運用することができれば、運用益が100万円以上になります。
もちろん投資にはリスクがあり、学資保険と全く同じように積み立てればいいという話にはなりません。
しかし、年間21万円の貯金を全て学資保険にあてるのはあまりにももったいない。
そう考えると、今のうちにあっさり損切りをして今後の貯め方を今一度考え直したいと思いました。
私たちが加入していた学資保険は電話一本では解約できず、店舗まで行って手続きをしました。
手続きの時点で保障は終了、解約返戻金は10日後には入金されました。
返戻金は息子の2年分積み立てた教育資金になるのでどのように活用しようか現在検討中です。
学資保険への加入は慎重に検討を
学資保険は強制的に教育資金を貯めることができるメリットがあります。
しかし、デメリットは超低金利で長期間に渡ってお金が固定されてしまうことです。
多くの場合、途中解約をしてしまうと大きく元本割れしてしまいます。
学資保険を定期預金と比較するだけでなく、インデックス投資などの選択肢も考慮して十分に検討することをおすすめします。
また、保険など馴染みのある金融商品を入り口にお金についての知識を広げることはとても重要です。
私も「知らない」ことに目を背けず、大切な子供たちの将来に向けてしっかりと準備をしていきたいと思います。
それではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
