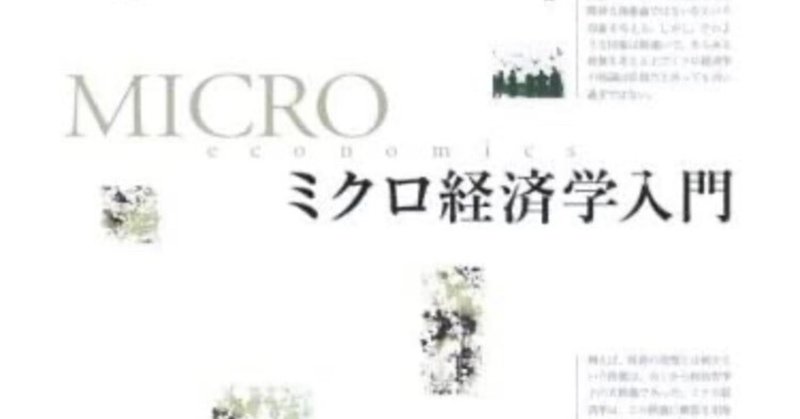
書記の読書記録#795『ミクロ経済学入門』(麻生)
麻生良文『ミクロ経済学入門』のレビュー
レビュー
レベル感としては奥野『ミクロ経済学』と同程度で,モデルを用いた説明に一貫性がある。
もくじ
はしがき
第Ⅰ部 ミクロ経済学入門
第1章 経済学入門
1.1 経済学とは何か
1.2 市場の機能
第2章 消費者余剰と生産者余剰
2.1 消費者の利益と生産者の利益
2.2 需要曲線と消費者余剰
2.3 限界便益と総便益
2.4 供給曲線と生産者余剰
2.5 限界費用と供給曲線
2.6 社会的余剰
2.7 社会的余剰の最大化
2.8 市場の機能とその限界
第3章 需要曲線と供給曲線
3.1 需要曲線
3.2 供給曲線
3.3 価格弾力性
3.4 需要曲線と供給曲線
第4章 部分均衡分析の応用
4.1 価格規制
4.2 数量規制
4.3 租税の効果
4.4 補助金の効果
4.5 国際貿易
第Ⅱ部 消費者行動の理論
第5章 効用関数と予算制約
5.1 効用関数(1財のケース)
5.2 効用関数(2財のケース)
5.3 予算制約
第6章 消費者行動の理論
6.1 消費者行動の理論
6.2 所得効果と代替効果
6.3 コーナー解
6.4 2財モデルの解釈
6.5 n財モデル
第7章 需要関数の性質
7.1 0次同次性
7.2 需要曲線のシフト
7.3 補償需要関数
7.4 スルツキー方程式
7.5 代替の程度
7.6 効用最大化問題の解き方
7.7 補償変分・等価変分
第8章 貯蓄と労働供給
8.1 貯蓄の決定
8.2 労働供給の決
第Ⅲ部 生産者行動の理論
第9章 生産関数と費用関数
9.1 生産関数
9.2 規模に関する収穫
9.3 平均生産物・限界生産物
9.4 等量曲線
9.5 生産要素の代替の程度
9.6 費用関数
9.7 平均費用と限界費用の関係
第10章 生産物の供給
10.1 利潤最大化
10.2 供給曲線
10.3 生産者余剰
第11章 費用関数と生産要素の需要
11.1 全ての生産要素が可変的な場合
11.2 可変的な生産要素が1種類の場合
11.3 短期費用曲線と長期費用曲線
11.4 生産要素の需要
第Ⅳ部 市場メカニズムの機能とその限界
第12章 市場均衡の効率性
12.1 厚生経済学の基本定理
12.2 パレート効率性とは何か
12.3 パレート効率性の条件
12.4 市場における資源配分
第13章 独占と不完全競争
13.1 競争条件の分類
13.2 独占の原因
13.3 独占
13.4 価格差別
13.5 買手独占
13.6 費用逓減産業
13.7 寡占
13.8 独占的競争
第14章 不確実性
14.1 不確実性下の選択
14.2 期待効用理論
14.3 リスクに対する態度
14.4 危険回避度
14.5 平均・分散アプローチ
14.6 保険の利益
14.7 確率
第15章 市場の失敗
15.1 市場の失敗
15.2 公共財
15.3 外部性
15.4 情報上の失敗
15.5 政府の役割
第16章 所得分配
16.1 生産要素価格の決定
16.2 生産要素市場における独占
16.3 人的資本投資
16.4 調整過程
16.5 補償格差
16.6 限界生産力説と労働価値説
16.7 資産価格
第17章 再分配政策
17.1 再分配についての政治哲学
17.2 格差の原因
17.3 再分配政策
17.4 所得格差の指標
付録A 数学付録
A.1 微分法
A.2 初等関数の微分
A.3 指数関数・対数関数の応用
A.4 微分法の経済理論への応用
A.5 制約条件付き最適化問題
A.6 不等式制約
A.7 テイラー展開
A.8 無限等比級数の和
A.9 ギリシャ文字
付録B 学習ガイド
参考文献
索 引
本記事のもくじはこちら:
学習に必要な本を買います。一覧→ https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/1XI8RCAQIKR94?ref_=wl_share
