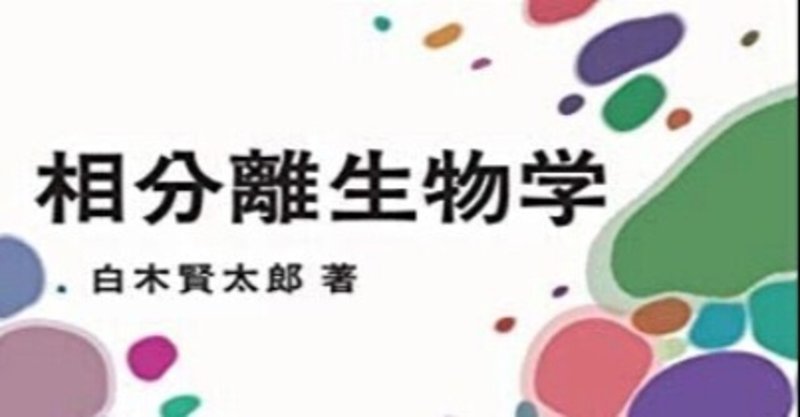
書記の読書記録#332『相分離生物学』
白木 賢太郎『相分離生物学』のレビュー
レビュー
自身の関心から見ると,様々な病態を引き起こすプリオンに+面があることが興味深かった。細胞生物学および分子生物学の発展的分野,また生物物理学の分野として目を通しておくべき。
もくじ
1.は じ め に
1・1 膜のないオルガネラと液-液相分離
1・2 相分離生物学
2.情報伝達と液-液相分離
2・1 セントラルドグマとアンフィンセンドグマ
2・2 染色体はどのようにして凝縮した構造を形成するのか?
2・3 エピジェネティックな修飾は溶解度を変えている?
2・4 転写因子がDNAの周りにたくさん集まるのはなぜなのか?
2・5 シグナル伝達は矢印で描くように情報の伝達をしているのか?
2・6 キナーゼはタンパク質の溶解性を変化させている?
2・7 シグナル伝達のハブとなるタンパク質は何をしているのか?
2・8 多様な翻訳後修飾は溶解性を制御している?
3.タンパク質パラダイムの転換
3・1 タンパク質の構造機能相関
3・2 タンパク質フォールディング
3・3 レビンタールのパラドックス
3・4 タンパク質の結晶構造
3・5 天然変性タンパク質の発見へ
3・6 天然変性タンパク質は液-液相分離する
4.RNAパラダイムの転換
4・1 多様なRNAの姿
4・2 局在するRNA
4・3 ストレス顆粒
4・4 RNAの足場
4・5 lncRNA
4・6 相分離以降のRNAワールド
5.細胞内オーガナイザーと場の構築
5・1 生化学の代謝
5・2 代謝の物理学
5・3 RubisCO
5・4 ピレノイドは膜のないオルガネラ
5・5 試験管内でのRubisCOの相分離
5・6 酵素反応をオーガナイズする
5・7 酵素超活性と反応場
6.アミロイドと低分子コントロール
6・1 アミロイドとは
6・2 タンパク質はアミロイドになる
6・3 FUSと液-液相分離
6・4 相分離シャペロン
6・5 ATPには別の顔が?
6・6 生物学的相分離の低分子コントロール
7.プリオンはなぜ保存されてきたのか?
7・1 プリオンとは
7・2 酵母プリオンSup35
7・3 ゲル化するプリオン
7・4 シャペロン
7・5 普遍的な五次構造
8.細胞内にある物理学
8・1 非対称性と溶液物性
8・2 細胞内の空間記憶
8・3 ドロプレットと染色体高次構造
8・4 オーバークラウディング
8・5 アクティブマター
9.タンパク質溶液の理論とテクノロジー
9・1 アミノ酸
9・2 タンパク質の高次構造
9・3 アミノ酸側鎖間の相互作用
9・4 タンパク質の凝集
9・5 タンパク質の共凝集
9・6 タンパク質凝集抑制剤
9・7 タンパク質高分子電解質複合体
9・8 液-液相分離の安定化原理
9・9 クラウディングと排除体積
10.新しいタンパク質研究
10・1 タンパク質の進化
10・2 進化のアルゴリズム
10・3 進化のゆりかご
10・4 de novoデザイン
10・5 状態機能相関
10・6 相分離メガネをかけて
本記事のもくじはこちら:
学習に必要な本を買います。一覧→ https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/1XI8RCAQIKR94?ref_=wl_share
