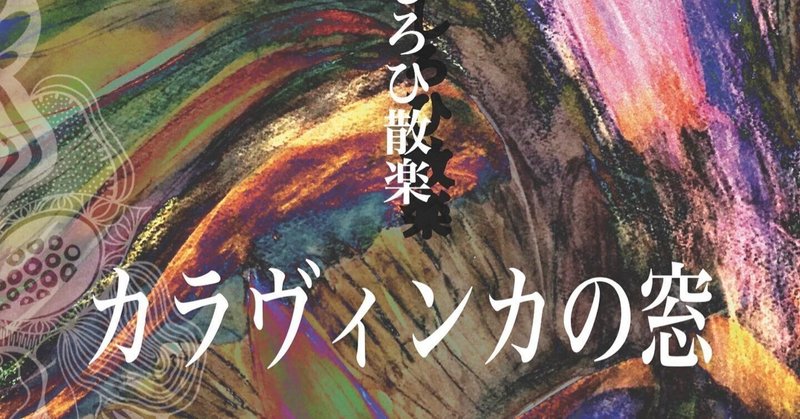
迦陵頻伽
先週、新聞の訃報を見て驚きました。
食わず嫌いだった私にわかりやすく現代音楽を教えてくれたのはこの番組でした。前回から追悼の特集になっています。
毎週日曜のこちらを録音して、その週に聞くのがここ何年かの習慣でしたが、西村氏のことは解説者メインと誤解しており、氏の作品が他の番組や場面で何度か演奏されるのを聞いて、大変失礼なことをしていたと反省。
昨年見に行った演劇、広島アビエルト芝居小組公演第三番「ましろひ散楽 カラヴィンカの窓」というものがありました。
極楽に住み、妙声で鳴くとされる人面の鳥「迦陵頻伽(カラヴィンカ)」というインド神話の鳥のことはその演劇で初めて知りましたが、後日西村朗氏作曲の「カラヴィンカの歌」をたまたま聞くことがあり、その舞台の場面を思い出してハッとしました。
「現代音楽」を英語で言えば「Contemporary Music」「Modern Music」「20th century classical music」ということらしいですが、「Contemporary」は同時代、今起こっていること
「Modern」は近代的、今日的
「20th century classical music」は20世紀の古典的な音楽
ということであれば、既に21世紀ですから「20th century」の意では使えない。
「Contemporary」や「Modern」も今現在でなく、時間的には作られた時から既に過ぎ去って今になっているわけですから、これもあまりピンとこないです。
ただ「現代の音楽」の番組は「の」が入っている所で、随分自由度が上がっていたような気がします。
「現代の音楽100年のレガシー」「20世紀・現代音楽の系譜」と名前の聞いたことのある作曲家の特集をされ、わたしみたいな素人にもわかりやすいものでしたし、「日本の作曲家」も継続して紹介され日本の現代音楽の豊富で多様な人々も知ることができました。
聞かなかったら「All Time Classical Music」としては、昔学校の音楽室の壁にかかっていた著名音楽家の肖像画のお歴々しか存在を知らなかったかもしれないでしょうし、「Classical Music」の世界でどう拡がっていったかも知らなかったかもしれません。せいぜい、ストラヴィンスキー、ラヴェル、サティ止まりだったのではないでしょうか。
今の中高の音楽はどういうものを教えてもらっているのかとググると、広島県の中学一年の音楽鑑賞の教材は「魔王」シューベルト。
目当ては「詩の内容と音楽が一体となった歌曲のよさを味わおう」
なんだ全然昔と変わらない。
優れた音楽とは思いますが、今の社会とは全然違うから、言ってみれば「万葉集」「源氏物語」を当時のバックグラウンドを知らないまま読ませているような感じではないでしょうか。
現代音楽は教えないのかな?と更にググると面白いものを発見しました。
食べ物もグルメサイトで点数が高い店が美味しいわけじゃなくて、美味しいと思う人がそれなりに多いだけ(金貰ってるかもしれないけれど)。
実際には自分の口に入れないと、自分では美味しいかどうか判断できません。自分の好みの味や感触がありますからね。とにかく自分で色々食べて舌と胃袋に判断してもらうこと。点数が高い店が必ずしも自分に合うかどうかわかりません。頭で食べるんじゃなくて、口と胃袋で食べるんですから。
音楽、特に現代音楽もこれだったと思います。私は西村氏の番組に出会うまでは、敬遠していたダメ親父でしたが、今はおかげさまで「聞いてみないと、自分の中まで落ちるかどうかなんてわからない。本物もあるし、自分に合わないものも当然ながら合う。あってものから広げていけばいい」と思えるようになりました。
ご冥福をお祈りします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
