
#145 読書日記22 学校教育で多元的知能を隠す壁をどう壊そうか
以前にも取り上げたハワード・ガードナー教授。
20代の頃にガードナーの『認知革命』を読んで衝撃を受け、あれから30年以上がたった。
戦後最大の教育改革といわれている現在、機は熟したのか、熟しすぎたのかわからないが、ようやくそちらへ舵を切ったのかという思いもある。
今回はガードナーの『多元的知能の世界』
人間の「知能」を測定しようとする試みは古くからあり、IQがその代表だろう。
こうした一元的な指標で人間の知能を測ることにどれほど妥当性があるのかということに関する疑問は常に語られてきた。
ハーバード大学のハワード・ガードナー教授は多重知能(Multiple Intelligences)の理論を打ち出し数十年にわたって自身の講義や著書、講演で語ってきた。
日本の有名な事例でいえば、IQ180というとんでもない数値を叩き出した大阪の天才少年の筒井くんは、当時、天才教育を行う特別科学学級で学んだが、理系の道には進まず、筒井康隆としてSF作品や戯曲、脚本等で異才・鬼才を放ってきた。
同じく天才少年だった伊丹くんも特別科学学級出身で、後に伊丹十三として俳優、作家、映画監督としてマルチなタレント性を発揮した。

彼らは複数の潜在能力を上手く組み合わせながら大成したのだろう。
私には突出した才能はない。
得意なこと、好きなこと、持続的に取り組めることはある。
多くのことは後天的な努力で磨いてきたものだと思っている。
仕事やプライベートの諸活動において、立てた目標をひとつずつ達成して目的へ辿り着こうとしても、パレートの法則みたいに、8割は余計な努力や時間を費やしてきたのだろと後になって気付いたりもした。
そのすべてが無駄だったとは思わない。
違う場面で直接・間接に生かされているのだろうから、やはり何かに集中して努力することは尊いと思うのである。
とはいえ、自分の努力の仕方をいかに洗練されたものにするかということが常に課題になる。
日頃、考えていることや、やりたいことがあれこれとあって、それがどうにもこうにも複雑に絡み合って、とっ散らかっている状態だ。
ガードナーは、学校は生徒の各方面の知性を発達させると同時に、各生徒は誰もがある方面に特別突出した知能を持っていることに留意しなければならないとしている。
そしてその生徒が他の方面で追いつかない場合は、それで生徒を罰するのではなく、生徒が長所から学ぶよう指導すべきであるとしている。
秀でた特徴-8分類
◆言語
Verbal/Linguistic
◆数理・論理
Logical/Mathematical
◆空間
Visual/Spatial
◆身体運動感覚
Bodily/Kinesthetic
◆音楽
Musical/Rhythmic
◆人間関係
Inter-personal/Social
◆內省
Intra-personal/Introspective
◆自然
Naturalist
現実に目を向けると、学問や文学、哲学、数学、科学であったり、トップアスリート、アーティストなどが各分野において高いレベルで活躍している人がいる。
実際のところ個人個人がどの分野に特異な才能があるのかを見極めるのに、私たち国民が受けている学校教育では測れないことが多い。
ギフテッドや天賦の才の一言で片付けてしまうと、大多数の人は浮かぶ瀬がない。
少なくとも、子どもたちは「潜在的な能力+後天的に獲得した能力」で飯が食える大人にならなければならないのだ。

「多元的知能の世界」に書かれている多重知能理論を読めば、IQだけが知能じゃないことは理解できる。
カードナーが述べているとおり、私たちの知能・能力は単一のものではなく多元的なものだから、スキルの量や組み合わせのパターンを一人ひとりの個性に合わせながら学び取っていくべきなのだろう。
認知能力を示すIQという指標は不幸にして知能の多元性が隠れてしまう壁のようでもある。
学校教育の場面で、特に現行の学習指導要領では『総合的な学習の時間(義務教育)』『総合的な探究の時間(高等学校)』を通じて、教科横断型で、なおかつ個別最適な学びと協働的な学びを統合させながら、問題を解決する態度を養い、将来の職業や日常生活、趣味などを通じてパフォーマンスを発揮できることを標榜しているわけである。
仕事をするうえで、やはり「性格・人柄」は重要だなとは思う。
EQ (emotional intelligence quotient:心の知能指数)なるものもあるが、これは、向き合う人や所属する集団・組織によって可変的であるという不安定要素がある。
ある部署では「ダメな人」扱いを受けていた人が、部署替えや転職した途端に「デキル人」になるという話はいくらでもある。
「非認知能力」については、自然科学、社会科学、人文科学の各分野で研究が進められているが、未解明なことも多い。

Webや自己啓発セミナーではバスワードとなり、言葉が一人歩きし、「非認知能力を伸ばせ!」となっている。
しかし、方法論ということになると
「で?その方法は確かなんですか?」
「エビデンスは?」
「成果は?」
「いや、随分とお高い料金を取るんですね」
ビジネスとして成立しているものもある。
といったように、頭の上に「?」マークがいっぱい並ぶなようなことも起きているわけである。
学校教育でエビデンスを蓄積し結果を出さなければならない。
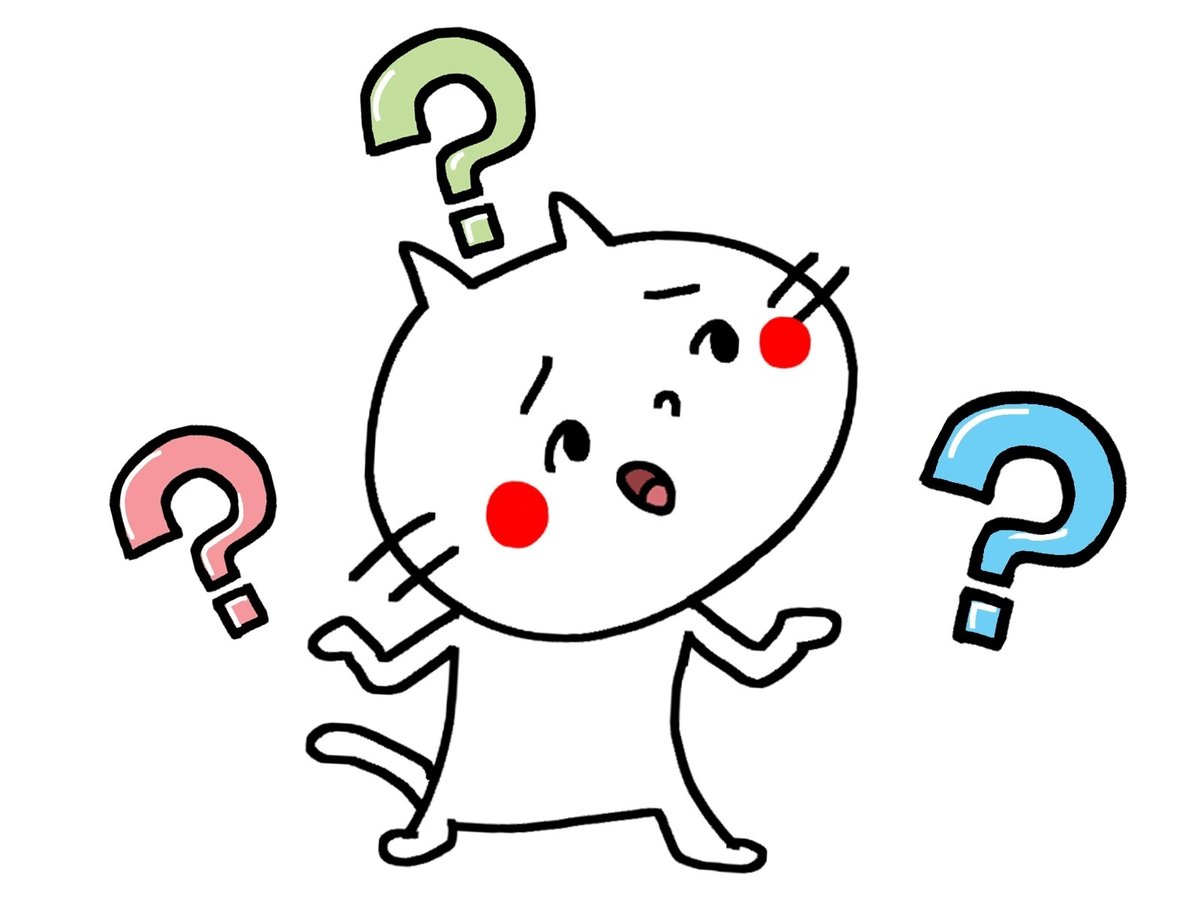
説明できないことはスピリチュアルなこととして精神性や霊性で訴えようというのも違うだろう。
「信じるか信じないかはあなた次第です」「実現できていないのは信心が足りないからです」では困る。
ガードナーは、あくまでも科学的なアプローチに基づいて教育の在り方を問いかけている。
自分の長短を受け止めながら今一度よく読み込む必要があると思った次第。
