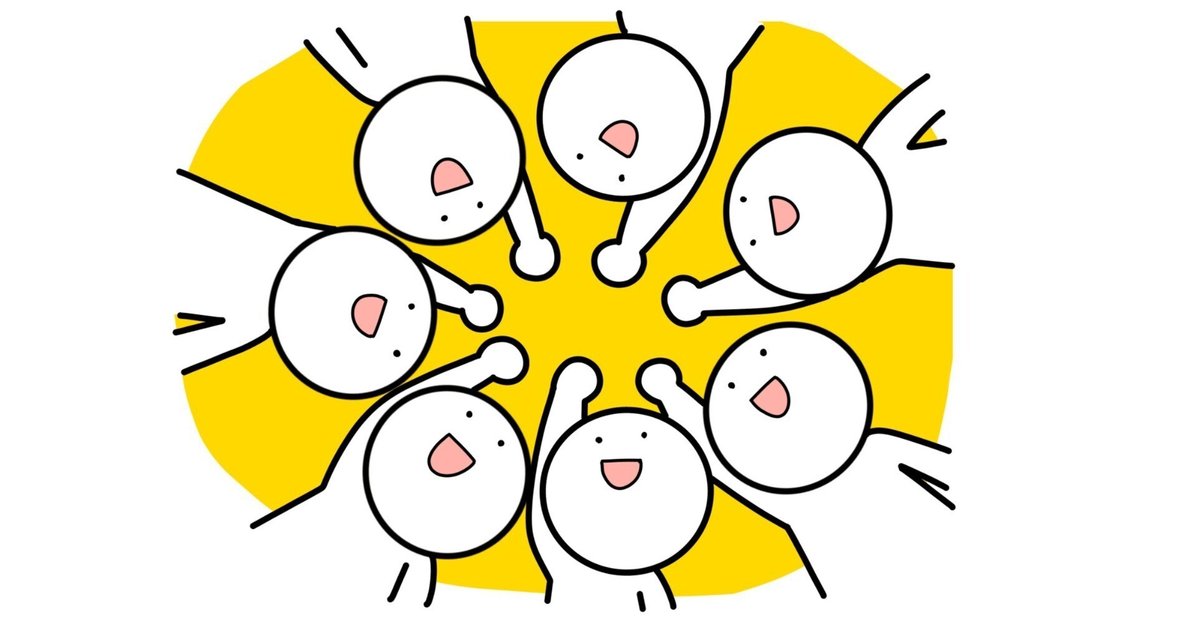
#76 学校教育で育む「能力」ってなんだ? 後編
ひとりの人間の中に備わっている能力にはデコボコがある。
誰かと比較して、自分の凹の部分が際立って見えて嫌になることもある。
私も発達過程でさざまな偏り、凸凹があり、いろんな誤解や差別を受け、悲しい思いもしてきた。
鈴と、小鳥と、それから私、みんなちがって、みんないい
(金子みすゞ)
時々、金子みすゞの詩集を読み返して心を落ち着かせるようにしている。

■例えば「コミュニケーション」
コミュニケーション能力は定量化できない。
あるプロジェクトで、私とAさん、Bさんの3人で協力しながら仕事を進めるとする。
私は日頃からAさんと円滑なコミュニケーションによって関係性をうまく構築している。
Aさんとの協働はバッチリだ。
一方のBさんは頭脳明晰で仕事もテキパキやる人だけど、時々めんどくさい人だなと感じるところがあり、アプローチの仕方で苦労する。
自ずとギクシャクした関係になり、Bさんとは没交渉的になり、Aさんに頼ろうとする。
多くの組織では特定の人に仕事が偏り、結果として、プロジェクトは歪んだ形で進みパフォーマンスが低下する。
かくして、仕事は属人化する。
複数の人と協働して同じ方向を向くのが仕事なのだが、その調整は難しいといつも感じている。
おそらく、Bさんとのコミュニケーションには、もっと別な技術やアプローチの仕方があるのだろう。
Aさんとのコミュニケーションで用いる手法・力量がBさんには通用しない。
■コミュニケーション能力の危うさ
ある先生は、A君のことを「コミュニケーションに難がある子だ」と評価する。
でも、私はA君を「朗らかで素直に話す子だ」と評価している。
コミュニケーション能力は相手によって変わり得るという典型的な例だ。
「人を選ぶ」と言ってもよい。
つまり、「能力」というものは前編で触れた言い方をすれば、
「固有性がない」「絶対化できない」「可変的」ということだろう。
他者との比較や場面、環境によって能力は刻々と変化する。
現在、まだ内定をもらっていない学生は就活真っ只中。
たった一度の面接試験で、「コミュニケーション能力」にスポットを当てて合否が決められるとしたら、こんな不幸なことはない。
大学生の面接の場合、1次、2次、3次・・・と複数のチャンスはあるのだが、上手く対応できないと学生のメンタルは低下する。
コミュニケーションは自己責任なのか?
本田由紀教授(東大・教育社会学)は数々の著書や講演で次のようなことを述べている。
就職活動において「コミュニケーション能力」は、" 人間性 “ を評価する概念として、とりわけ採用選考で重要な選抜基準とみなされてきた。
「●●力」に関する一連の語句は、面接担当者の好みにより応募者を選別するための道具になっている。
「経営者が望ましいと考える事柄が、安易に「●●力」として表現され、増殖し続ける状況は危うい。
「意識高め」「意識高い系」な言葉が持つ負の側面に切りこんでいる論だ。
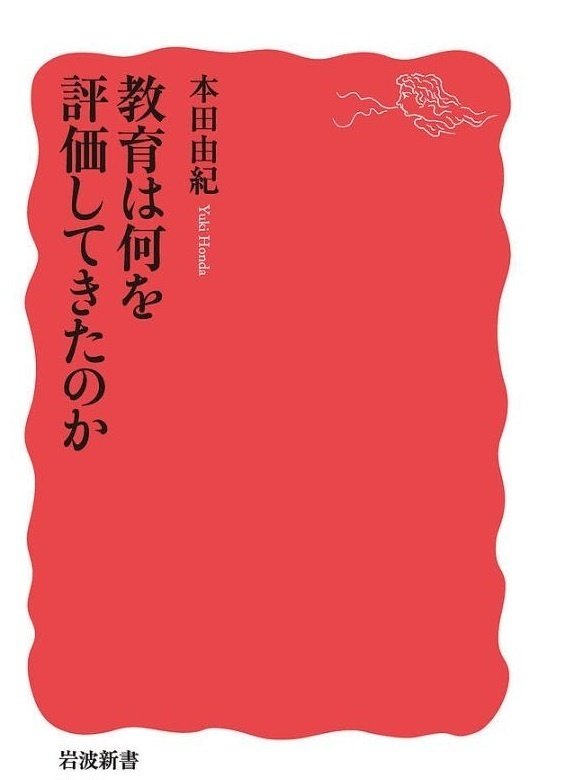
私たちは、無意識のうちに「●●力」という言葉によって、理想の人物像を絶対化しているのかもしれない。
確かに、コミュ力が上手く発揮されないと、わずかな隙間に「わかりあえなさ」が入り込み、自分と相手との間に壁ができる。
「コミュニケーション能力が高い」と評されても、その能力に絶対値があるわけではない。
私は「コミュ障」という言葉が嫌いだ。
学生には「自分のことをコミュ障なんて卑下するんじゃない。君には君の伝え方があるんだよ」と言う。
実際には、かなり繊細な気遣いが必要になる。
異質な他者と交わる際、人間の脳は、そう簡単に柔軟に対応できるわけではない。
真面目にやっていれば、大人になった頃に、みんな平等に身に付く能力というものでもない。
実際には、
観察力や洞察力を働かせる。
自分と相手との距離の取り方を模索する。
両者間にある問題や考えの違いを認識する。
ステレオタイプの先入観を排除する。
感情をコントロールする。
他にもいろいろな要素が必要だろう。
私たちは日頃、こうしたことを瞬時にやっている。
もしくは、「やらない」「やれない」といった要因が何かの形で潜んでいる。
学校や企業では、いろいろな能力の育成・向上を目標にして教育プログラムを編成し人材育成に努めている。
一定割合で何かに優れた人材は育つけれど、全方位的に優れた人材が育成されることはない。
■放置プレイはやめて!
「それはあなた次第です」
「最後は自己責任です」
というキメ台詞がある。
あれこれ美辞麗句を並び立て、最後は「自己責任論」で片付けようとする場面は結構ある。
アリバイづくりか?
少なくとも学校教育においては、自主性や自己責任という名の「突き放し」「放置・放任」「あきらめ」があってはならない。
自主性や主体性は放っておいて育つものではない。
どんな学校にも、生徒が動き出すきっかけとなる有形・無形の教育的仕掛けがある。
発達に応じた仕掛けも考えている。
川下へ流れて姿が見えなくなる前に引っかける “ フック ” だ。
フックに引っかからない無気力、無軌道な生徒をどうするかということが学校現場の悩みの種のひとつになっている。
私はそれで37年間格闘してきた。
概念や言葉の理解だけでなく、身の内側に刻み込まれる経験がないと体は反応しない。
「流汗悟道」
理屈は後回しにして、身体技法で汗を流し悟ることもある。
そうした意図的・教育的な仕掛けづくりをするのが学校なのだと私は考えている。
しかも、教師だけでは限界がある。
学校教育だけで成長を完結させるとか、人格の完成を実現できるわけではない。
いろんなアウトリーチに繋げる努力もしなければならない。
そのさじ加減は、それぞれの学校にどのような層の生徒・学生が集まっているかで異なる。
私たちにできることは、子どもたちが社会へ出てから勝負するための地力や持久力を身に付けさせることだ。
ひどく簡単に書いてしまったが、それが大変なのだ。
日々努力されている先生方に敬意を表したい。
