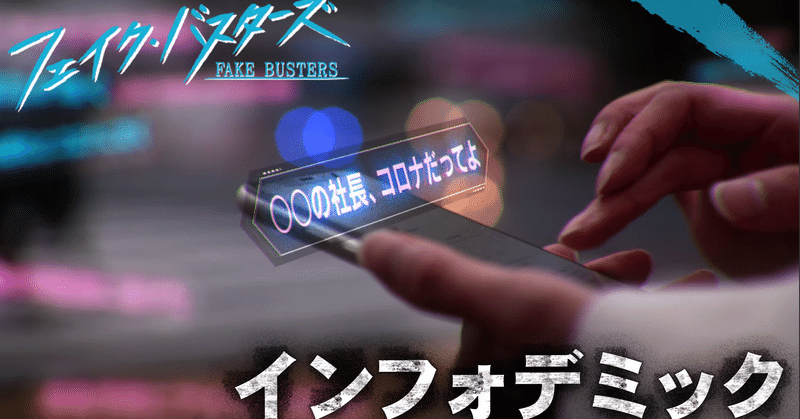
2つのNHK番組を観て、改めてフェイクニュースを考えてみると、、木曜2限③
5月2日木曜2限の「スタディ・スキルズ講座」の第3回、前回のフェイクニュースの議論の流れから、2020年5月放送のNHK番組「フェイクバスターズ」と、行動経済学のセイラ―教授がノーベル経済学賞を受賞した2017年の11月放送の「クローズアップ現代」を視聴して、改めてフェイクニュースを考えました。(ふりかえりをそのまま転載しました)
<第3回の授業の振り返りをお願いします。
今回は、NHKの番組①「フェイク・バスターズ」(2020年5月5日放送)、②「クローズアップ現代」(2017年11月20日放送)を見ました。
① エピソード - フェイク・バスターズ - NHK
フェイク・バスターズ - NHK
② 家でも会社でも使えるノーベル賞理論! 最新経済学の魔法 - NHK クローズアップ現代 全記録
番組から学んだことや発見したこと、気になったことなど、なんでもかまいませんので、自身の視点で自由に意見を書いてください。
また、前回視聴した解説動画などがアップされている日本ファクトチェックセンター(JFC)の③ウェブページを再度見たうえで、どう受け止め、どのように評価しているのかを、前回のふりかえりとは別の視点で記してみてください。
③ 日本ファクトチェックセンター (JFC) (factcheckcenter.jp) >
◆①コロナウイルスは専門家でさえ未知なものであり、毎日感染者や死者が増えていき、不安が募っていった結果が医療従事者やコロナ患者への誹謗中傷に繋がっていったのだと思いました。また、緊急事態宣言で普通の学校生活を送れなかったり遊びに行くこともできなくなり、ストレスのはけ口がSNSになったことも考えられます。私はコロナ禍で、SNSでコロナ関連の情報を得たりデマ情報を見たりしたことはなかったのですが、テレビのニュースで、SNSで話題になっているツイートがとりあげられてそこから知るということは多々ありました。その時に、コロナ禍で情報発信源がツイッターに変化していっているのを身をもって感じました。また、ショート動画が流行ってから、コメント欄を見ることが増えました。コメント欄ではアンチコメントも多いですが、いろいろな角度からのコメントを見ることができるし、切り抜き動画ではこうなるまでの過程を書いてくれている方もいて、客観的思想まで考えることができます。私がひとつ懸念することとして、SNSに慣れ親しんでいる若者世代より、50代以上のSNSにあまり慣れていない親世代やそれ以上の世代の人々のSNSリテラシーがまだ追いついていないのではないかと思います。
②私は高校生の時に行動経済学という学問があることを知り、関連したテーマで卒業レポートを書きました。しかし、セイラー教授が相田みつをさんのファンということを今回の授業で初めて知って驚きました。「人間だもの」という言葉は何度か聞いたことはありましたが、それが行動経済学に繋がっているとは思いもしなかったので驚きましたが、よく考えてみるとそうだなと納得しました。政府の政策でも行動経済学を利用すれば、国民も行動しやすくなるのにと高校生の頃から考えているのですが、大学で実際に経済を学んでみるとなかなか難しいことだなと感じています。
③法律などを使って規制することは簡単ですが、それをしてしまうと言論の自由が奪われてしまうので規制するのはあまり現実的ではないのだなと思いました。するとやはり個人個人がきちんとリテラシーを身につけることが重要で、現代のように赤ちゃんもタブレットで動画を見るなど、物心がつく前から利用する時代なので、幼稚園、小学校ぐらいからSNSとの上手な付き合い方を教えていく必要があるのではないかと考えました。(3年)
◆ネットのデマ情報をすぐにデマ情報と指摘するのではなく、ただただ勘違いしているだけというケースが非常に多いので叩いたりするのはダメだということを番組で言っていて、確かにそうだなと思った。新型コロナにはお湯が効く、ヨーグルトで感染を防げるなど今思うとすごいデマだなと思うけど、その頃を思い出すと確かに自分もクラスの子が少し休むだけで「コロナだ」など決めつけていたので、そういった混乱の中では冷静な判断を下すことがむずかしいんだなと再確認できた。
ネット上でデマをなくしていくためには、まずはネットリンチをなくさなければいけないと言っていたのを見て、確かにそうだなと思った。ただ勘違いして情報を拡散してしまっただけなのにそれで誹謗中傷にあったら、デマを流すことがだめだからと言って誹謗中傷をしている人が、「誹謗中傷をしてはいけない」という当たり前のことをできていないので、矛盾を感じた。ダメなことにダメなことで返していたら本末転倒だなと思った。
リチャード・セイラー教授が唱えたナッジ理論(人々の意思決定を強制や指示ではなく、選択環境を設計することによって、より良い方向に導く)を聞いて、普段からこのような手法は身の回りで使われていて見事に導かれているなと思った。
ファクトチェックセンターを見たところ、岸田首相に対してトランプ氏が「どこがいいの?」というようなニュアンスに書き換えられている記事があった。今まではこのようにデマの記事を見たとき普通はデマを流した方にヘイトが向きがちだが、別の視点から見て考えたときに受け手の判断力にも問題があるなと感じた。このような発言をトランプ氏が堂々とするわけがないのにそれを信じる人々がいると思うと、少し心配になった。そこで、教育機関やメディア、政府などの組織も、情報リテラシーを促進するための取り組みを強化する必要があると感じた。(1年)
◆フェイクバスターズの動画では新型コロナウイルスが流行り始めた時にヨーグルトが予防策になるであるとかアルコール消毒は意味ないのようなフェイクニュースが度々流れていたのを改めて思い出しました。特に花崗岩が感染対策として効くという情報は今思うと明らかに怪しく思いますが、当時は新型コロナウイルスの恐怖に陥っていて、あらゆる情報に敏感になっていたので信じてしまう人がたくさんいたのかなと思いました。動画を見て,日本ファクトチェックセンターの存在が改めて大事だと思いました。Twitter(X)上で見ず知らずの人が情報を呟いても信憑性がないので、動画内でも話されていましたが、そもそもTwitter自体を見なければ良いのではないかというのには確かになと思いました。新型コロナウイルスが蔓延している時期にもっと存在が知られていれば、国民の不安も抑えられたのではないかと思いました。(3年)
◆行動心理学の内容が面白かった。
フェイクニュースは日常に多く存在しており、社会的な混乱が起きると多発してしまうため、混乱してる時こそパニックにならずに冷静に判断するべきだと思った。(3年)
◆個人のフェイクニュースが拡散されそれが企業に発展してしまうと会社の経営にも関わる問題になってしまうと思った。仮に自分がフェイクニュースの拡散の加害者になってしまったら責任が大きいためニュースを鵜呑みにしないことが大切だと思った。(2年)
◆フェイクニュースを見抜く方法を学んだ中でフェイクニュースを出した人間は悪意を持って出したのか、勘違いの部分などがあって悪意を持たずに出したものなのかがとても気になった。この部分は対策する上でとても大切だと思う (2年)
◆フェイクバスターズの動画では主にネットで個人によって流されるデマについて見ていきました。ネットの普及により多くの情報に触れることができるようになったが情報の正確性に関し個人でしっかりと判断することの大切さを感じました。また、ネットの利用量が多すぎるので少し距離を置くことも必要だと思います。行動経済学の話では実際に自分も商品を選ぶ時の判断が人間の行動原理として誘導されていると感じ、上手く活用することで経済や社会に役立つものだと感じました。日本ファクトチェックセンターでは記事にある画像や情報の事実関係を明らかにするための検証が行われていて事実に関してどこがどのように違うのか証拠をもとに判断している。判断の元になっているのは公的機関の情報などが使われていることからもしっかりと正しい情報をもとに判断することの重要性が分かりました。(3年)
◆授業冒頭で見たNHKのフェイクバスターズと言う番組では各分野の専門家4人が出演していて現代のフェイクニュースに関する問題や、これから起こるであろう問題について話し合いをしていた。その4人のうち1人は外科医の方で情報の恐ろしさを医療の視点から説いていた。それは親が医療従事者という情報だけで子供が学校や幼稚園でイジメ、差別を受けている事。医療従事者と言うだけでコロナに感染しているというレッテルを貼られたりしている事だった。誤った情報は差別やイジメにまで発展し人を傷つけてしまうことに気付かされた。クローズアップ現代ではフェイクニュースが会社の業績を大幅に下げたことも取り上げられていた。会社の社長がコロナに感染したというフェイクニュースから客が配達サービスのキャンセルをし、業績が下がったという。根拠もないのにその情報を信じてしまうのは現代人がいかに情報リテラシー能力が低いか物語っていると感じた。ファクトチェックで改めて岸田総理のディープフェイク画像を検索にかけてみたが、やはり嘘の画像だった。自分では判断が下せないような情報はファクトチェックを用いる事で少しでも安心して生きていける気がする。(1年)
◆フェイク・バスターズのコロナウイルスのワクチンや医療法のデマなど間違った噂などは一度広まってしまうと収束するのに時間がかかるので、まずはそういったデマを鵜呑みにはせず改めて自分が間違った情報を拡散しないことが、いわゆるインフォデミックの状態では一番大切な行動になると感じた。SNS上にある誰が書いたのかも分からない記事を無闇に広めるのではなく、政府などの公的機関の情報などといった正しいものを拡散していくことが重要であると改めて認識させられた。また、ファクトチェックセンターに関しては生成AIの進歩によってありもしない発言があたかも本当のように扱われてしまっていて混乱を引き起こすものであり、されてしまった側にも不信感を抱いてしまうので絶対にしてはいけない行為だと思う。こういったことが無くならないのであれば今後、生成AIなどの使用に制限や規則を設けて対策していく必要があると考えられる。(2年)
◆新型コロナウイルス関連のフェイクニュースが広まってしまったことは、人々が情報リテラシーについて考えるきっかけになったと思う。(3年)
◆私の友人に家族が陰謀論といった根拠の乏しい情報を信じ込んでしまい、苦しんでいる人がいるため、身近に感じる講義内容であった。
私はフェイクニュースを信じることはないだろうと今まで考えていた。しかし、ファイターバブルやエコーチェンバーといった身の回りに潜むバイアスを生じさせる概念を知り、今での考えは非常に安易なものであったと気づいた。今後はGoogleの画像検索といったファクトチェックを行いフェイクニュースに引っかからないための習慣をつけようと思った。(3年)
◆SNSで広まったデマ情報により、様々な被害が出ていることが分かった。また、デマ情報の拡散を抑制しようとしての行動もかえって拡散させてしまう事があることがわかった(3年)
◆① フェイクバスターズがいることでフェイクニュースに騙されずに行動できたり、ファクトチェックの意識を人々に広めることができる。しかし、行き過ぎたフェイクバスターズは近年問題となっているSNS上での誹謗中傷に相当する危険性もあるのではと考えた。取材を受けていたフェイクバスターズの方が、「過度に相手を責めることはしない」「気づかせることが大事」という発言をしていたが、確かに相手の間違いを指摘する際に、どうしても自分の普段の言い回しや口調を出してしまいがちだが、それは対面ではないため、表情などの細かいニュアンスなしに言葉のみで相手に伝わってしまう。ゆえに、文章のみで伝えたときに、過度に相手を批判していないか慎重になる必要があるなと感じた。
② リチャード・セイラー氏が今までの経済学に疑問を持ち、行動経済学を生み出したというエピソードに驚いた。私自身、経済学部であるが、「人間はいついかなる場面においても合理的に行動する」という前提自体を全く疑ったことがなかった。既にある理論に対して異なる理論を唱えることは地動説くらいの時代の話だと思っていたが、現代においてもセイラー氏のように新しい考え方をもとにした理論を作り上げているというのは非常に興味深く、さらに共感もした。よく考えたら本来の人間は経済学に登場する人間よりも怠惰で感情的であり、その点に着目した行動経済学は実際の経済動向を知る上ではこれからより重要視されるだろう。
③ フェイクバスターズの動画では「フェイクニュースによってトイレットペーパーが無くなる」事例とそれに付随して「フェイクニュースだと知っていたが心配でトイレットペーパーを購入してしまった」事例が紹介されていた。そして、リチャード・セイラー氏の行動経済学の動画では、人々の行動を自発的に変えるために人々が意思決定する環境をデザインする「ナッジ」というワードが登場した。ここから、フェイクニュースが広まったときに人々が焦って行動することを防ぎ、安心して経済活動を行うためのナッジを考えることが重要なのではと考えた。(3年)
◆今回の講義で出てきたコロナ禍におけるSNSでのデマ情報の過多は自分自身も見てきたことである。
トイレットペーパーの件については自分も被害を被った側なので当時はどうしてこう言うことになるのであろうと憤りを感じたこともあった。
デマ情報に完全に流されないために「だしまきたまご」のようなフェイクチェックの方法を学んだが実践して自分自身で正しい情報を見極められなければいけないと再認識した (3年)
◆フェイク・バスターズにてゲーム理論の話が出ていたが、コロナ当時の家庭内での混乱をよく覚えている。フェイクニュースであることは全員わかっていて、最初は慌ててトイレットペーパーを買おうとはしなかった。しかし、フェイクニュース自体には騙されないものの、そのフェイクニュースに踊らされた人たちが実際に買い占め、本当に供給不足になってしまったらどうしよう、という危機感が出てきた。その結果、トイレットペーパーを買ってしまった。ゲーム理論で言うと、相手が得して自分だけが損することを避けた結果だと思われる。これをクローズアップ現代にて出てきた経済学の話に繋げると、人は思ったよりも「見たもの」が大事だと言うことがわかる。契約書を読むことが億劫なら、逆に拒否する時だけ契約書を書かせる。女性の進出問題を人数比という形ではっきり可視化すれば格差は減る。このように「人が物事をどう見るか、見てるか」を意識すれば、人は簡単に操作することができる。それはつまり、フェイクニュースの効力の大きさを示しているということだ。人は「自分に都合よく分かりやすく極端な情報」を簡単に信じてしまう。そこにどう向き合っていくかがフェイクニュースへの対抗に重要だと感じた。日本ファクトチェックセンターにて出てくるニュースも、今までは騙された人々の規模や反響を意識してきたが、こう見ると「人間の性質」を突いた技巧さが見えてくる。(4年)
◆本日の授業で一番気になったのはナッジです。人間の特徴を逆手に取っていて、非常に面白い仕掛けだと思いました。私も利用していきたいと思いました。 日本ファクトチェックセンターのウェブページを再度見たところこの世の中にフェイクニュースが非常にたくさんあることを再認識させてくれました。私自身自分が持っている情報が正しいかどうかがわからないのでこういったサイトはどんどん活用していきたいと思いました。(2年)
◆今回の授業の中で私はフェイクニュースは悪意のみで広まるのでは無いことを知った。
例えば、コロナ禍においてトイレットペーパーが売り切れるというツイートは少なく、逆にデマだというツイートが多く出回った。多くの人がそれを知りながらも買い占めの被害に遭わないように最低限買うようにした人が多かったがそのタイミングが同時に起きたために売り切れになってしまった。フェイクニュースはわかっていても防ぐのが難しいとわかる内容だった。(3年)
◆デマ情報がいかに危険かを学んだ。デマ情報を発信することだけじゃなく、信じることも、周りに危害を加える可能性があることを理解した。(1年)
◆①インターネットで得る情報は間違ったものも多いため情報を吟味しながら利用しなければならないということは多くの人が理解しているが、やはりたくさんのいいねがあると信じてしまう。いいねの機能はまさに塵も積もれば山となるなシステムなので、デマ情報にはいいねを押さない、むやみやたらにリツイートをしない、など個人個人の配慮や情報リテラシーが大切だと感じた。また、今はデマの報告機能や通報の機能もあるので、必要に応じて活用するべきだと思った。
②動画に登場したナッジの例は昼間のテレビショッピングでよく登場する宣伝方法だった。つい最近、テレビショッピングでクルーズツアーの紹介を父とみたので、ナッジの効果をより実感できた。売り手はその商品をより売り出せるし、買い手も気分よく買うことができるので、経済をより活発化させるためにはとても有効的だと感じた。
③政治に関するフェイクニュースは、フェイクの素材の対象への不満や批判のために作られることが多く、その人の評価を下げようとしてデマの動画などが作られているように感じた。しかし、その不満対象の人物の言動を捏造することはフェアではない。そのため、選挙などのより社会的に自分の意見を反映させられる機会を活用するべきだと考えた。(2年)
◆フェイクニュースにはデマを流し、デマを信じて拡散してしまうということ以外にも、危険性があることを知った。それは、フェイクニュースをデマと分かっていてもしらないうちに拡散する側、加害者側に回ることだった。トイレットペーパーの品切れなどもデマと分かっていても、デマによってなくなる可能性が高いもしくはすでになくなっていれば事実になってしまうので、その人も買おうとする。合理的な行動であっても、デマが拡散することに気づいた。
ファクトチェックセンターのページを見て、政治・災害関係のニュースが多いと思った。嘘でも面白いで済むニュースとそうでないニュースの差があることを実感した。また、一般の人が政治的なニュースを見極めたい時、テレビや新聞の正しいニュースでも切り取られ方などで全く意味が異なるフェイクニュースになりうる。このサイトはそのニュースが拡散される危険性を軽減しているように思う。(3年)
◆最近ではフェイクな話などがネットで広まりその人への誹謗中傷で人権を否定させてしまっているという問題がある。例として3年前のコロナ禍になりコロナに感染しただけで「かかった本人が悪い」などと言われてしまっていた時期があったりした。ただ今では感染対策していたとしても感染することもあったし普通の風邪のように扱われているが、コロナ禍になってすぐはそんな時期が続いた。
他には、芸能人に対しての間違った情報などがインターネットで広まり、その芸能人に対する誹謗中傷によって精神的に病ませてしまうことがある。本人以外真実は誰も知らないのに噂をたてて、たくさんの人にフェイクニュースとして広まる世界、怖いなと思います。
世界的なフェイクニュースではそのニュースを間に受けてしまう人数が多く経済的な問題に影響してしまうこともあるが、身近な狭いコミュニティの中でもフェイクニュースもあり身内の環境が変わるかもしれない。私たちはどの情報が正しいのか?誤っているのか?考えるべきなのかもしれない。(3年)
◆①の動画で、コロナの時のデマの出回り方を見て、未曾有のウイルスが流行っているといったように人々が大きな不安を持っている時は冷静に情報を受け止め発信することができない、誰かにすがりたい気持ちが大きくなってしまうのかなと思った。しかし、今後こういうことを起こさないために、個人もマスメディアも、みんなが正しい情報事実、人々の焦りや不安を駆らないものだったり、受け取り方を考えたりした伝え方をすることが大事。けど、こうなってしまっているのは情報氾濫に対する知恵が足りていない。だから自分の頭で考える、そのための知識考え方を取り入れる場が必要だと思った。その情報知識として、だしいりたまごや、伝え方として真実のサンドイッチを取り入れることが大事だと思った。
②の動画では、商品の機能を吟味するのではなく、分かりやすい情報で買うか判断するという利用可能性ヒューリスティックを聞いて、私自身もTikTokやインスタでインフルエンサーや信頼できる人がおすすめしていると買ってみたいという気持ちが湧くというのが良くあるなと思いました。
また、Webサイトを改めて見て、そもそもフェイクニュースは拡散されてしまうのは見た人がリツイートしていって起きてしまうことだと思った。今回の授業の①の動画でも言っていたようにそのようなリツイート見た時にスルーをするというのもフェイクニュースを拡散させないために大事なことだと気づいた。(3年)
◆日常的に衝動買いしてしまう癖がある。最後の動画で人間の消費行動における習性を知ることが出来たので、浪費をしてしまいそうになったら自分に当てはめてよく考えてから消費をしようと思う。(3年)
◆映像を通して、フェイクニュースとの向き合い方の難しさを改めて感じた。フェイクニュースの発信者を罰することは言論の自由に触れるが、だからといって明確な対処法や判断基準が設けられている訳でもない、自分自身の考えと情報リテラシーがその後の行動を左右する重い問題だと思った。そして、デマを否定する発言の拡散がかえってデマの内容そのものを拡散してしまう可能性があるという皮肉な実情には驚いた。一人一人の悪気ない行動が大きな事態を招く可能性から、情報リテラシーへの意識や、考えてから行動する大切さを身に染みて感じた。これは、個人だけではなくマスメディアにも同様のことが言えるだろう。ただ単に出来事を報道するのではなく、フェイクニュースの内容への理解を正しく深めてから報道することや、報道後の社会の未来を想定することがより必要だと思い、マスメディアも、報道の在り方を見直すべきだと思った。その点において、今後更なる技術の発展により情報も多様化していくだろうと予想できる今、セイラー教授の心理学と経済学を合わせるという考え方は、今まで以上に求められる時代になるだろうと予測できる。
日本ファクトチェックセンターのウェブページでは、ファクトチェックと一般的な報道では手法が異なるということが印象的だった。確かに、事実検証と結果の公表を行うことと、事実に基づいて意見することではやり方が違うので、ファクトチェックと報道それぞれの目的や役割を明確にするべきだと感じた。(4年)
◆コロナが流行りだした当時の差別や混乱は、今から振り返っても尋常ではないと思った。コロナ関連で差別することも、SNSで拡散された情報を鵜呑みにするのも、嘘の情報を広めるのも変だと思った。気になった記事をリツイートしただけの人でも、知らず知らずのうちにフェイクニュースの拡散に加担してしまう場合があるというのが怖いと思った。個人がネットで広めているニュースなどは特に信じる前に、自分で考えた方がいいと思った。 ナッジ理論は、とても自分に当てはまると思った。インフルエンサーの持っているものを買ったりしたことがあるからだ。また、テレビの広告などで、今から電話をするとこの商品を値下げするなどという広告もよく目にする。また、わざわざ提出して変更を求めるものなどがあると、提出しない方が大多数なのかな、めんどくさいな、などと思ってしまい、結局変更をしなくなることが多い。その理論を選挙などに応用することは出来るのか疑問に思った。 ファクトチェックセンターのサイトをもう一度見てみると、メディアにはフェイクニュースとそれに騙されている人々が多すぎると思った。このように真偽を確かめてまとめてくれているサイトはとてもありがたいと思った。また、フェイクニュースには誰かを攻撃する内容のものが多いと思い、製麺会社の社長に関する誤ったニュースと似ていると思った。(1年)
◆①情報の真偽を見抜くことは大切なことなんだなと思いました。
②前々から行動経済学について興味を持っていたので今回の授業で触れてくださって、とても嬉しかったです。
今後も日常生活をしていくうえで、デマには惑わされずにしっかりと自分自身で考えながら行動していきたいと思いました。
③sns上で出回ってしまっているデマを様々なデータから検証して否定をし、正しい情報を世の中に伝えていく機関は必要不可欠な存在だと思いました。(3年)
◆アンカリング効果は単語こそ知らなかったものの日常的によく見る効果でした。たとえこの効果を期待してのものだとわかっても、買い手は原価がわからないためこの効果に乗っかてしまう、単純ながら強力な効果であるといえます。
ほぼ毎日嘘が暴かれていますが、裏返せば毎日のように我々は嘘に踊らされているということです。こうしたチェックが行われていなければ、本当の情報は簡単に埋もれてしまいます。このような機関は今後より一層重要なってくると思います。(3年)
◆真実ではないことが拡散されることによって、人々の心だけでなく企業の将来も危ういものにしてしまう現実にとても恐ろしいと感じた。
フェイクニュースや嘘の情報は次世代の戦争や紛争にも使われる武器になっているので、情報の取り扱いには注意するべきだと思った。(3年)
◆映像を見て、やはり個人の立場から発信するSNSなどの情報は全て信用するべきでは無いなと感じた。自分自身のことを信じて、何でもかんでも情報を手に入れようとしないことも大切だと思った。これからはだしいりたまごを守り、SNSを利用していこうと思った。
ファクトチェックセンターでは問題に対して多様な面からうけとめて、色々な媒体の情報を通じて、ひとつの問題を処理していると感じた。公式など必ず信じられる情報も欠かさずチェックしているなとも感じた。私達もひとつのことを信じるのではなく、様々なことを比較することが大切だと改めて感じた。(1年)
◆前回に引き続きフェイクニュースの話題だったが、SNSで広がってしまっているフェイクニュースへの向き合い方を見ることができた。解説の中では昨年学んだゲーム理論も登場していて、繋がらなさそうな分野でも経済学の理論が役に立つのがわかった。
ファクトチェックセンターのサイトに関しては、よりSNSで間違った情報が拡散されやすい現代において非常に役立つサイトだと改めて思えた。また、自分が目にした情報が正しいのか否か確認する材料にもなり、情報をどのように受け取るかを考えさせられるサイトだと感じた。(3年)
◆今回の授業では動画をいくつか見ましたが、特に印象に残ったのは最初の動画です。コロナが流行り始めた最初の頃はコロナ患者を特定や責める状況がありました。今回の動画ではそのことを思い出させる内容でした。ある企業の社長さんがダイヤモンドプリンセス号に乗っていたというフェイクニュースは企業の業績も落ちてしまっていたし、本当によくないことしかなかったと思います。専門家の方たちも言っていましたが、不安な時こそ冷静に情報を理解すること、そして発信することができない。不安と付き合っていく技術がなく、そのため安心するために何でも情報が欲しいというのも事実だと思います。そういう真理からフェイクニュースが拡散するのを防ぐためにその情報が役に立つのか、今回の例だとコロナの感染予防に役に立つのか?という合理的な判断基準を持って情報を判断できると良いなと動画を視聴して思いました。(3年)
◆フェイクニュースはネット社会になった現代には、当たり前のように存在しています。フェイクニュースを見て、嘘だとわかっていて、個人的に楽しむ分には程度によりますが、構わないと思います、しかし、度を越したフェイクを作ったり、それをフェイクと知りながら、もしくは、フェイクなのかどうかを調べずに、拡散してしまうことは、悪だと私は考えます。嘘を嘘だと見抜く力が重要な世界になってきているなと感じました。フェイクニュースを見抜くことが大事と一口に言っても、結局何すればいいのってことになってしまうので、日本ファクトチェックセンターのように、教材としても使えるように、わかりやすく解説してくれるものがあるとすごく楽になるなと感じました。(3年)
◆行動経済学は学習院の科目には無いけれどずっと興味があった分野だったのでとても面白かった。現在バイブスは自分にも心当たりがありすぎて深く納得してしまった。改めて日本ファクトチェックセンターのウェブページを見ると、能登半島地震の際の偽情報の記事が目に止まった。多くは、授業でもやったように、3.11の東日本大震災の映像を使って、まるで能登半島地震の被害のように投稿する例だった。実際のポストを見て思ったことは、そのような偽情報を流しているアカウントはほとんどが日本のものではないような外国のものばかりだった。解決法のひとつとして、直前のポストや過去の投稿を確認することが挙げられると思う。また何故このような偽情報を流すのかの意図については、故意犯確信犯愉快犯の3パターンが主にいることが分かった。特に愉快犯が1番タチが悪いと私は思った。(3年)
◆今回の授業では Twitter / X という多くの人の意見や投稿が飛び交う場面について話しました。そこでは匿名性があるため、ある程度自由に発言ができます。
そのため、デマの情報や誹謗中傷との上手な付き合いが必要だと感じました。
最近はデマ情報の存在に慣れ、「自分は大丈夫だ」と考える人が多いように思います。
しかし、無意識的に、または実質的にそのデマに惑わされていたり、そのデマの拡散などに加担してしまったりしてしまうケースがあることを知りました。これは情報の真偽よりも自分が安心することに重点がおかれてしまっていることが原因だと思います。個々人の「念のため、とりあえず」という気持ちが大きな混乱を招いてしまうのだと思いました。
インフォデミックで溢れているネット社会でうまくデマ情報と付き合っていくのはかなり厳しいと思います。一人ひとりがフェイクニュースやデマ情報を意識して、被害者や加害者にならないよう、ネットを利用するといっても、実際はそのように気を張りてめてネットを使うことはないと思います。このような状況下では、すべてを自己責任で受け入れるしかないと感じました。そう考えると「にんげんだもの」という言葉はとても深いなと思いました。
また、人々の心理について分析して、それを経済の分野に取り入れるのはとても興味深かったです。アンカリング効果など身近に潜む心理学に目を向けるのも面白そうです。
日本ファクトチェックセンターはすぐに真偽を確かめることができるので、とてもいいサイトだと思います。(1年)
◆今回の授業の動画を見て、自分は本当に日頃からニュースをフェイクかどうか見分けようという意識が薄いなと実感しました。それと同時にそんな自堕落さは人は持っていると語ったノーベル賞を取った経済学者に勇気づけられました。番組の動画内で語られた通り、人は面白ければフェイクでもいいという心情があると思います。しかし面白くても傷つく人がいるかもしれなくて、ちょっとしたリツイートでその傷が広がっていくので、これからは
ただ何も考えずSNSを眺めるのではなく慎重になりたいです。
さもなくば我々社会の人々がSNSをなくそうとしてしまうかもしれません。(3年)
◆今回の講義を受けて日本のニュース媒体であるNHKですら情報を意図的に切り取ることで印象を操作できてしまい、その事で世論を動かすことが出来てしまう事を再確認しました。普段今回の取り組みのようにファクトチェックなどしないでそのまま情報を読み取ってしまっている為間違えた情報であることを疑わずに信じ込んでしまう事が多く感じました。今後は少しでも気になるものや、特になんでもないものを選んで自分で調べてニュースの裏を取る事をしてみたらなにか新しい発見があるのではとも思いました。(4年)
◆TwitterなどのSNSなどで自分の身分が特定されにくいというのが原因で多くの人が自分と何の利害関係もない人のことを平気で批判する時代であるということに改めて気付かされました。自分も責められる立場になったり万が一にも責めてしまう立場にもならないようにネットリテラシーをしっかりと身につけて、今の時代を生き抜く上で大切な判断力を備えて生きていこうと思いました。フェイクニュースと言っても一概にそうとは言いきれず発信者の誤解によって生じてしまうケースを学びフェイクニュースに対しての自分の受け止め方が変わりました。インドネシアなど法律でフェイクニュースを書いた人を犯罪者にするというものがあったが、自分はそれには反対です。事実かどうかを恐れて、表現の自由が大幅に制限されてしまうことがあると思ったからです。(1年)
◆①意識的にやっているかは分からないけれど、自分の解釈で情報を発信することで、いじめや誹謗中傷などにより無関係な第三者が被害を被ることが多々あることを改めて理解し、自分の投稿が瞬く間に世界中に影響を与える可能性があるということに恐怖を感じた。
②アメリカの実証実験結果を見て、人間の行動には心理があり、また経済学と密接に関係していることに興味を抱いたため、行動経済学だけでなく心理についても学んでみたいと感じた。
③フェイクニュースの多くはSNSの投稿で、冷静になってみればフェイクであると分かるものや簡単に調べられるものもあるため、SNSだけを信用せず、多くの媒体を通じて情報の正誤を判断すべきだと感じた。(3年)
◆今回の講義ではナッジ効果というワードが印象に残りました。例えばコンビニのトイレなどで見られる「いつもきれいに利用してくれてありがとうございますという」という張り紙は、低コストで低コストでめざましい効果を得られるナッジ効果であり、強制することなく人々に働きかけるため、反発を招くことなく行動変容を促進できます。しかし、ナッジには人を誘導する倫理的によくない部分があるという批判も見られます。奨学金という言葉をかざす学生の借金などが例に挙げられます。こういった懸念点も含め、心理学と密接にかかわる経済学についてさらに興味をもちました。
ファクトチェックセンターのウェブページを改めて読んで、人を貶めるフェイクニュースやデマがとても多いと感じました。人々はマイナスな事象や発言に目を引かれ、間違いを犯したと思われるものや人を攻撃したい性質を持っているので、いいニュースより拡散力が強いのだと考えました。月並みですが、インターネットは簡単に他人に悪意を向けられるので心の状態が安定しているときに利用すべきだと思いました。(3年)
◆今回の講義で、NHKの「フェイク・バスターズ」という番組を視聴した。番組内では「インフォデミック」という言葉が再三出てきた。それは、SNSなどを通じて不確かな情報と正確な情報が急激に拡散される現象のことだ。「デマか。それとも真実か」を見抜く力が今のネット社会で生きるうえでは大切だという内容は、前回のグループワークでもよく出てきた。また番組内では「皮肉」という言葉も出てきた。それは、デマの注意喚起をすることが結果としてそのデマを広めてしまうという意味での「皮肉」だ。確かにその通りだ。実際にデマを投稿している人に別の人が事実の情報を返信・拡散することで、結果としてそのデマが我々の目の届く場所にまで来てしまうのだ。ただ、そのデマを信じることが悪いわけではない。ゲーム理論の観点から、デマを基に「合理的」な行動を取る人がいるのにも納得した。今回の講義を通じて、ネットに蔓延る情報をただ受け取るのではなく、その情報の根拠はあるのかなど自分で一瞬立ち止まって考える姿勢が大切だと感じた。また、日本ファクトチェックセンターのウェブページを見て、毎日こんなにも多くのデマがあるのかと驚いた。例えば「ゼレンスキー大統領、辞職」というデマも信じてしまう人が一定数はいただろう。ただこういったデマも氷山の一角にすぎない。だからこそ、ネットに蔓延る情報をただ受け取るのではなく、その情報の根拠はあるのかなど自分で一瞬立ち止まって考える姿勢もこの先のネット時代を生き抜くうえでは大切だと感じる。(4年)
◆前回の授業でのグループワークを通じて、様々なフェイクニュースを知りました。今回の授業でフェイクニュースに理解を深めました。インフォデミックはインフォメーションとパンデミックを合わせた造語です。新型コロナによりのパンデミック時に、大量の情報と誤情報が同時に広がって、公衆の混乱や誤った判断を引き起こしました。1つの例としては新型コロナに関する医療デマです。5GモバイルネットワークがCOVID-19の流行と関連があるとするデマが広まりました。実際にこの主張は科学的な根拠に欠け、5G技術とウイルスの伝播との間に直接的な関連はありません。ウイルスは無生物であり、無線波やネットワーク技術によって拡散されることはありません。このようなデマは公衆衛生の取り組みを妨げるだけではなく、完全に捏造された情報であるため、しばしば特定の集団や個人を誹謗中傷する目的で用いられます。そのため、フェイクニュースへの対応は不可欠だと考えています。だしいりたまごはネット情報を見極める7つのポイントの頭文字をとって作り上げられたフレーズです。確かにネット情報を見極めることでフェイクニュースの流布を抑えることができますが、特定の集団や個人を目指す誹謗中傷を抑止することは難しいと思います。
人々が直感や感情によってどのような判断をし、その結果、市場や人々の幸福にどのような影響を及ぼすのかを研究する行動経済学の知恵を生かして、差別と中傷を解決することができるかもしれないです。1つの解決策としては差別を明確にするというアプローチです。差別の形態や発生している具体的な状況を特定し、認識を高めることを目指しています。差別を明確にすることは、教育プログラムや意識向上キャンペーンを通じて、社会全体の認識を高めます。それによって、人々は差別的な行動やその背景にある偏見を自覚し、それに対抗することができます。(大学院)
◆日本ファクトチェッカーのサイトで取り上げられている記事に、自分が見たことのある記事が載っていたので驚いた。内容は「大阪府の中学生のうち8%は高校進学せず、学歴は中卒である」というものである。この情報は誤りで、実際は98%程の中学生は高校に進学することが正しい情報であった。このことがあったので、日常のニュースを見聞きするときは事実がどうかを判別できるようによく調べなければいけないと感じた。授業で動画を見た際に、日常的にフェイクニュースが流れていると聞いたが、改めてそのことを実感した。(3年)
◆ 昨今のフェイクニュースやネット上の偽情報などに関して、かなり勉強になりました。
自分たちのネットリテラシー能力をもっと高めたいと思いました。(1年)
◆デマですと注意喚起することがそのデマを広げることにつながっていることが新たな学びでした。善意や正義の気持ちも意図せずその間違いを広めることに加担しているのだと気づきました。
ナッジ理論の話がとても興味深かったです。臓器提供の意思の決定付け方の違いでこんなにも結果が変わるのだと驚きました。
自分がそうなんだとあっさり受け流していた記事でフェイクニュースだったものがいくつかあり、全ての記事を疑ってみることがフェイクニュースを本当にしないためには必要だと感じました。しかし、多種多様にSNSが広がる今、たくさんの情報がある中で一つひとつを疑うのは極めて困難だと思います。そんな時、たまにファクトチェックセンターを覗いてみるなどして、フェイクニュースは自分たちが思っているよりたくさんあることを日々認識し、情報の受け止め方を軽くすることが大事だと感じました。(3年)
(以上、46人)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
