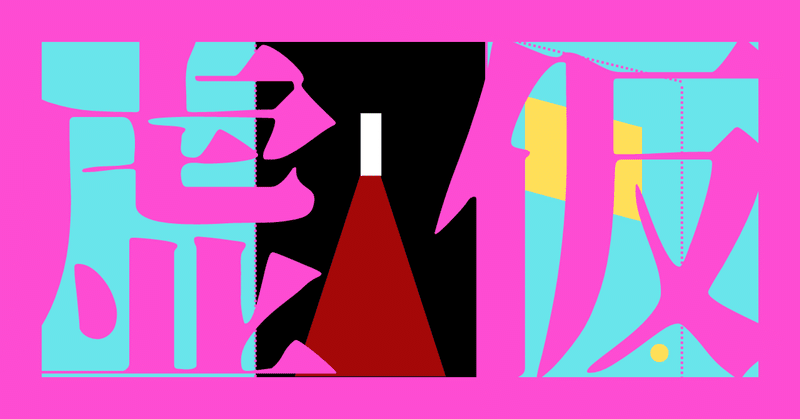
虚仮
先立つ想い
カーテンから差し込む日差し、窓の隙間から聞こえるセミの声は、彼を笑っている様に聞こえ、強く窓を閉めた。花瓶に刺した一輪の花は、名前を知ることも無かった。涙は一滴も出なかった。
家に戻り、喪服を探す。5,6年前に着たきりで、少し埃を被っていた。身支度を終え、玄関へ向かいながら、いつもの名残が口から出た。
「クーラー切ってる、、電気消して、、Switchは、、」
その名残が、まだ残る温度が、いつもあったはずの風景が、抑えていた感情を一気に溢れさせた。
「やっぱり、やっぱりやんか。」
そんな夢を私は毎日見る。顔にかかった白い布の下は未だ覗けずにいた。
「おい岡!」
私を呼ぶ声がした。
「噓つき!」
咄嗟に口に出た言葉の先は、上司だった。
「嘘つきはお前や、コピーしに行ったんじゃなかった?」
ここは向こうの死後の世界。それでいうと私たちは全員死んでいる。人は死ぬと2つの道がある、一つは天国、もう一つは地獄。これを決めるのは神様でも、閻魔様でもない、生前の私たち自身だ。私の仕事はそれをサポートすること。誰がいつどのようにして死んで、これからどの道に進ませるか。その情報管理、伝達、全て私たちが一人一人自分の手で処理する。死んでまで働きゃくちゃいけないのは、必要であるから。必要であるから働く。苦悩の無いこの世界で、労働は特段しんどいことでは無い。面倒だけど。
呼吸
今日は一件登録があり、私は事務室へ向かう。ここにはそれぞれ部署があり、現世さまよう魂を導く特別支援課、私がいる実際に死者の管理を行う管理事務、その他取次や連絡を行う総務課。他にも最近では10を超える部署があり、上司いわくエンジニア部なんかもできたらしい。エンジニアと名づくくらいであればパソコン1台ぐらい使えるようにして欲しい。元々管理事務は総務の内容だったためか総務の人間は全員態度がデカい。あと話が長い。
この日も、そんな態度に苛立ちながら、準備する間もなく連れてこられた死者の登録が始まった。
「わかりました、じゃあ連れてきてもらって。」
その瞬間だった。
「エリカ!?エリカ!!愛してるエリカ!!」
「ちょっと一旦出して下さい。」
その男は私を見るやいなや、すごい勢いで私の名前を呼んだ。どうして私の名前を知っているのか、パニックになりながらも、もう一度中に呼び出し、生前の情報が書かれた書類に目を通す。
「エリカ!ごめんよ!ごめんねずっと」
「あぁ、なるほど。」
書類を見て、大方の予想はついた。彼が死んだのは3年前、その間ずっと現世を彷徨っていたらしい。その理由がこの当時の交際相手である岡エリカだそう。あいにく私と同姓同名の。
「いやあの、残念ですが、ここは死後の世界で、あなたはもう、死んでいます。だから、生前の思い人だったエリカさんはここにはいません。ごめんなさい。」
はっきりと伝えた方が本人のためだ。それに仕事も円滑に進められる。こういったケースはよくある。そして、そのほとんどが自分が死んだことにも気づいていない。
「いや、僕が死んでるのは知ってて」
彼はそう言った。私は疑問に思った。自分がもう死んだと気づいていながら、まだ誰かに会いたいと思うものだろうか。私は私が死んだ時のことはほとんど覚えていないが、ラッキ~と思った。これでやっと、私を苦しめるものがなくなったと。やっと。
だからここにいる。
「ずっと謝りたくて、嘘ついちゃったから。」
彼はそう続けた。名前は土岐利之。見た目に反して古風な名前だなぁなどと考え出したのは、もうこの人とまともに話す気が無かったからだ。
「まあとりあえずそういうのは追い追い聞いていくとして、まず確認と記憶処理、及び映像の方確認していきますね。お名前は土岐利之さんでお間違い無いですね?」
「…はい」
「で、死因は他殺ですね、映像確認に移ります」
「映像っていうのは?」
映像とは、走馬灯のことだ。本来その人が生きてきた人生を全て見て、死因やその時の心情に間違いが無いか確認を行うのだが、うちの部署の上司の惰性によって、死んだ近辺の情報しか確認しないという悪しき伝統が始まりつつあり、私もその後継者の一人だ。
「困ります。」
「え?」
意表を突かれたその男の一言に私は思わず聞き返す。
「本当に覚えてないんでしょうけど、、でも絶対にあなたはエリカなので、困ります。」
まったくもって私の話を聞いてないじゃないかとまた苛立ちを隠せなかった。私はこの男と話すと無性に腹の脇が痒くなる。本当に苦手な人種なのだろう。語気を強め私は言った。
「違いますけど、あなたのいうとおり本当にあなたの探しているエリカさんと私が同じ人だったとして、じゃあこの走馬灯で私が映ってたら証明になるじゃないですか!」
「でも駄目なんです。見せられない、その前にどうしても、僕の口から謝りたい事が」
「あのね、生前色んな事があったのはわかります。でもあなたはやっとその苦悩から解放されたんですよ。この世界の真理を教えてあげます。」
苛立ちからか気づけば私は口に出していた。向こうの世界の人間が一向に気づかない、世界の真実を。
「さっきの職員も、私も、私の上司も、この世界の人間は全て、生前自殺をしています。」
「え?」
「そうやって、誰かにどうだとか、もっとこうなりたいだとか、人間が生きる上で、日々抱える苦悩だったり、欲望だったり、そんな本来必要無いもののために、苦しむこと自体がおかしいと思いませんでした?こっちにはそんなものは一切無い、誰もがみんなただただ平穏ななんにもない日常を生きていける。その真理に気づいた人、つまり、自ら死を選んだ人のみが、この世界で生きていけるんです。」
「じゃあ自殺じゃなかったら?」
「残念ながら生まれ変わります。その真理に気づくまで。何度も何度も。」
わからせてやりたかった。この男に。どうせ全て忘れ、生まれ変わるしかないこの男に、せめてここにいる間は悔やんで欲しいとなんとなく思った。
「よくわからないな、だって、苦しむ事があったから死のうとしたんじゃ」
「まず、そう考えてる事自体が、こっちからしたらおこがましいんですよ!」
声を荒げた。気づけばこの男に会ってから、なぜか凄く感情的になっている。苛立つ。苦しい。辛い。
「なんでそっちの世界の人はみんな、自分勝手にそうやって…そうやって、そうやって…」
私に声をかけるその男を視界の端に、だんだんと意識が遠のいていった。
1輪の花
彼はめずらしく静かだ。私たちは夜行バスに乗って東京に来ていた。色々周りたい場所もあったのに、と口を尖らせる私には目もくれず、彼はずんずんと先を歩く。着いていくのでせいいっぱいだった。
「しんどい疲れた」
「もうちょっとやから」
「東京まで来て見たいものって何?」
彼は立ち止まり、
「別にしょうもないもんやねんけどさ、どうしてるかなあって」
「人?」
「人じゃないよ、気持ち?」
よくわからなかった。信号が青に変わる。その横断歩道の真ん中で、彼は突然しゃがみ込んだ。その視線の先には、一輪の花が。
「どうしたん?」
私はどこか寂し気な彼の背中に尋ねる。
「これ」
その花を指さして答える。
「それ何?」
「花」
「それはわかってるよ」
「こんな東京の交差点の真ん中に、1輪だけで咲いてるねん。昔友達に教えてもらってんけど、ずっとこうして1輪で強く咲いてるってすごいよなぁ」
「なんていう花?」
私がそう聞こうとすると、信号は点滅し、彼は私を置いて先に走って行った。
まってよ。彼はいつだってそう。すぐに私をひとりにする。
あの日も、私はずっと待ってたんだ。彼の言葉を信じて待ってたんだ。トシの、トシの言葉を、帰りを、信じてずっと、ずっと待ってたのに。
8月20日、朝のことだ。私は3度目の電話でやっと目を覚ました。しかし、私の目を覚ましたのは、着信音では無く、耳に飛び込んだ言葉だった。
「利之が…」
いつもはゆったりと話すトシのお母さんの声が、か細く震えるようで、私の心臓をギュッと掴まれたみたいだった。
病院までは、電車で約5分、駅までの道のりを合わせても電車の方が15分早く着くのはわかっていた。しかし、気付いた時には走り出していた。早く嘘だと知りたかった。私の目に映るまで、私は信じない。だから、嘘だと知りたかった。一度も立ち止まりたくなかった。自分の今の感情にすら、目を向けたくなかった。
病院につく。雨に濡れた冷たい手で触れると、まだすこし暖かい。彼の目が少し開いた気がした。
「トシ!?」
それでも、帰ってくる言葉は無いままだった。
病室には1輪の花が飾られていた。あの時の花だ。東京で見た。あの花。私は看護師に尋ねた。
「この花は?」
「昨夜ご親友の方が夜遅くに」
この時からこうなることは決まっていた。私は人を殺した。
10月9日、東京、やはりしめっぽい空気の中、横断歩道を渡る。信号は赤。
1秒、2秒、3秒。クラクションが鳴り続ける。私は構わず歩く。4人、視線を背ける。
名前も知らない、1輪の花と目が合った。
思い出
目を覚ますと、私を心配そうに見つめる彼とおぼろげなトシの顔がぼんやりと重なって見えた。
「ごめんなさい私」
「大丈夫ですか?」
私は震えた声で確かめる
「あの、ごめんなさい、変な質問かもしれないんですけど」
「どうしました?」
「好きな花はありますか?」
「好きな花?」
「そう、例えば東京の真ん中に咲く、」
ただの夢であって欲しかった。それも、彼の顔を見るとすぐ覚めた。
「ああ、」
「やっぱり」
頭の中がぐるぐると回りだす。ずっと、こっちに来てからずっと、そんなことは無かったのに。私は全てを思い出してしまった。
「ありますよ、好きな花、東京の真ん中に咲く」
暖かく話すトシの顔が、より私を苦しめた。
「やっぱり」
やっぱりやんか。だから私は嫌やったのに。勝手に期待して、裏切られる。それがどれだけ怖いか。裏切られた時には一人。だから私は、言葉にしたく無かった。素直になりたくなかった。
「それがどうしました?」
さっきまでぼやけていた顔がはっきりと目の前にある。
私の口から出た言葉は、皮肉にも、素直な今の心の声だった。
「最低」
戸惑うトシを視界に入れず、ただこの心が口から溢れ出す。
「なんで、なんで、、
なんで、私はなんにも無くなりたかったのに
なんでまた思い出させたりなんかするの?
なんで死んでまで私は苦しまなくちゃいけないの?
なんで、なんで、、トシは、、帰って来なかったの」
「ごめんね」
その言葉すら私の記憶に鮮明に焼き付いて離れない地獄を思い出させる。
「謝るくらいなら、、思い出させないでよ。
その方が、よっぽど幸せやった」
戸惑いながらも彼は言う。
「会いたかった。会いたかっただけなんやけど」
いつだってそう。トシは、トシは、、
「ずっと自分勝手やん」
少し黙り込んで、トシはごめんとだけ呟いた。
暫く続く沈黙の中、色んな記憶、色んな感情、トシは今どう思ってるんだろうか、私はどうすればいいんだろうか、そんなことを振り払うために私は仕事を続けることにした。
「このまま、このまま進めたら、もう、私の事は忘れられる。
このまま、最後この映像を流し終えたら。もう。」
もう、会えない。もう、会わなくていい。それでいいのだと自分にも言い聞かせる。
「そうする。ごめん。俺のせいで。」
「ううん。」
私が再生ボタンを押した時だった。
「あの花の名前、、」
「え?」
「あの花の名前やねんけど」
「ごめん、もうボタン押しちゃった、、」
「あ、、」
気まずい空気の中、2人の話も聞かず、走馬灯は流れ始める。
走馬灯
映ったのはトシ最後の日、昼間からゲームをする私に珍しく苛立った様子のトシに連れられ、近くの喫茶店でデートをしている。
いつもどうりのたわいもない会話、でも心無しか今見ると、毅然とふるまうトシに反して私はやっぱり素っ気ない。
その日はトシが夜に予定があると聞いていた私から、最後の会話を切り出していた。
「あ、いいの時間、予定あるんじゃ」
「そうね、、」
「今日はすぐ帰ってくる?」
「あー、うん、すぐ帰る」
「はーい、じゃあここでいいよー」
立ち上がり、店を出ようとする私を彼は呼び止める。
「…エリカ!」
「ん?」
「大好き」
「ありがとう」
これでトシと会えなくなるとも知らず、私はまた。
しばらくして、トシは誰かに電話をかける。
「もしもし、ああ、もうつく?ああ、じゃあ、あの喫茶店おるわ」
店の扉が開く。入ってきた男がトシの前に座る。
私はこの男を知っている。
相当久しぶりなのか、お互いぎこちない。
「ごめんな、急に呼び出して」
トシが話始める。
「その、もう終わりにしたくて。俺の中で。
っていうのは、その、、やっぱり自首しようと思う。
別にお前の名前出すとかそんなことするつもりじゃない、お前にはお前の事情があるし、それはもちろん。だから俺の中でだけ。」
あの日、手紙に書いてあったことだ。なんでもっと早く私はこの手紙を見なかったのか、ずっと悔やんでいた。ただ、その続きは、手紙に書いていなかった。
「俺、好きな人ができて、この人とずっと一緒にいたいって、ほんまに思うねん。だから、いつかどっかで、終わってしまうくらいなら、俺は、今、全部終わらせて、それでちゃんと、胸張ってその人のそばに居続けたいって思う。だから、ごめん。」
そんなトシの気持ちを遮ってその男は口を開いた。
「いや、今更。穏便にしとけばいいやん。」
「穏便にって、いやだから、別にお前を売るわけじゃ」
「これはお前だけの問題じゃないねんぞ、そんな綺麗事だけでお前を信じれるわけないやろ」
「信じろって、今までだってこうして」
「どうせお前は自分は悪くないと思ってんねんやろ?だからそんな簡単に」
「いい加減にしろよ!
あの日だってそう、あの日はまだ俺らも若かったから、焦って、こうなってしまったけど、でも、それは間違いやったって、お前もホンマはわかってるんやろ?」
男は黙る。
「俺、こないだあいつの墓参り行ったよ。もう5年ぶりくらいかな。
あいつの両親はもう他界してるし、兄弟もいないから、掃除でもしてやろうかなって思ってたけど、なんでかすっごい綺麗だった。お前やろ?
供えてた花。あいつが俺らに教えてくれた。東京の真ん中で咲くあの花と同じ、あの!」
「じゃあどうしろっていうねん、毎日毎日、あいつ殺してしまったあの日から、ずっと苦しみ続けた俺の日々を無駄にするんか!」
「そうか、、ごめん俺行くわ。」
そう言うと、トシはお代を置いて、店を出た。
店を出て数歩。それがトシの最期だった。
意識も遠のく中、最期までトシは、ただ私に謝っていた。
素直
映像が終わる。私は蓋をしていた思い出にもう一度目を向ける。トシが死んで、その心臓が止まって、怒りに身を任せ、全てを失って、私は。
「じゃあ、これで」
先に口を開いたのはトシの方だった。
「あ、うん。この部屋を出て、右の突き当りの扉、を開いたら」
もう、と続けそうになる自分の口を紡ぐ。
「わかった、じゃあね」
そう言って席を立つトシの背中を、私は手を伸ばし掴むように呼び止めてしまった。
「トシ!」
「ん?」
でも、やっぱり私は言えない。そんなこと。
「ううん。じゃあね。」
「うん」
そういってトシは部屋を出た。また最期までトシは優しい声で。
ああ。まただ。さっき見た走馬灯が今度は私の視点で流れ出す。
「エリカ!」
「ん?」
「大好き」
「 」
やっぱり。やっぱりやんか。やっぱりいつだって。
いつだって、私のせいやんか。私がすぐ手紙を読んでたら。私が全部わかってたら。私がトシと出会わなかったら。私がおらんかったら。トシは、もっと幸せやった。
やのに、私は、なんで。なんで素直になれんかった。勝手に怖がって。自分を守って。最期まで、ここにきてまで、言われへんかった。
ホントは、ホントは私も、ずっと、一緒にいたかった。
ホントはずっと、ずっと、
忘れもの
愛した方が負け。でも、時に人は負けなきゃいけない時もある。情けないことよりも、それは自分を愛するために。俺は自分が好きだ。あと、漫画と、タバコと、あとなんだっけなぁ。
こっちの世界はすごいよくできてんなぁ、それが死んでから一番に思ったことだ。なんにも考えなくていい、それでいて、別に私利私欲や野望も無い、ただ与えられた仕事をこなす。暇になれば漫画を読む。寝る。それだけが毎日続く。こんなに幸せな事は無い。いや、幸せすらもあるだけ不幸だ。ここにはなんにもない、だからここが本当の世界だったんだ。
そんな中だった。彼女は突然あらわれて、俺の日々に不幸を連れてきた。
それからしばらく時が経ち、部下ができた。なんでか放っておけない、薄々そんな気はしていた。俺も、地獄に行っとけばよかったなぁ。
ヒューヒューだよ
やっぱり嫌や。トシとずっと一緒にいたい。
どんなに苦しくても、それでもずっと、一緒にいたい。
愛してるから、それだけが私の救いやったから。
気付けば、涙が止まらなくなっていた。
「おいまたサボってんのか」
こんな時に限って、上司の声が聞こえる。
「居眠りするは、仕事できひんは、すぐ泣くは、どうしようもないな」
いつも通りの口うるさい上司の言葉が、今日はすごく刺さった。
「なんでそんなこというんですか」
「俺もしんどいねんから、これ以上仕事増やすなよ」
「私だって、」
私の言葉を遮り、上司は続けた。
「処理は俺がやっといたるから、お前は居眠りするなり、人追いかけるなりして油売ってこい。」
私は言葉の意味を理解できなかった。
「それって?」
「しんどいから、手元狂ってまうかもなぁ」
「先輩?」
上司の顔はいつもとどこか違う、気だるげながらも、少し寂しそうだった。そして、珍しく優しく呟いた。
「お前はどうしたい?」
「どうしたらいいんでしょ?」
「俺に聞くなよ、お前の選択肢は2つ、このまま処理を進めて、この利之?は記憶を完全に失って、いつか生まれ変わってしまう。お前はお前で、自分の中で整理して、ゆっくりゆっくり忘れていく。」
「そんなことできるんですかね?」
「もう一つは、俺の手違いでこいつを生き返らせる」
「なんでそんなこと」
「ずっと一緒にいたいんやろ。でこいつもお前を愛してるんやったら。それに賭けてみるのもアリやろ」
やっとその意味を理解した。私たちは死者の登録を書類に手書きで一人一人が行っている。その書類には、死者が今まで生きてきたざっくりとした情報、そして推定される死因が書かれていて、それを私たちが再度、映像と本人の聴取によって確認し、その死者のその後を決める。だから、意図して書き変えることもできる。この人が死んだ事は間違いであったと。それでもそんな前例が無いのは、それをするメリットが無いからだ。だって、トシは、生き返らせたとして、
「でもトシは、どう思うんでしょうか?」
「お前はもっと自分のこと大事にしろ。」
初めて見る真剣な顔の上司の言葉に、私は驚く。
「ただ、これは俺の昔話やけど、俺も昔、死んでも忘れられへんくらい好きな人がおった。でも長いことこっちにいてるうちに、だんだんと全部忘れていった」
「じゃあ」
「でもそんな時に、その子は死んで、こっちに来て、俺が処理をすることになった。俺もその子も、はじめ気付かんかったけど、でもその子は、ずっとずっと、忘れられへん思い人の話を長々としてて、そんな中、二人ともお互いに気づいた。」
「それで、どうなったんですか?」
「いや、なんにも」
「なんにも?」
「だって仕事やし」
「薄情者」
私がそういうと、ようやく上司は少し笑い、続けた。
「まあ、あと、そんな勇気が無かった。白きって生き返らせたとして、その子にとって、俺のエゴを通す、勇気が無かった。
きっと今頃、その子は俺のことも忘れて、またどっかで生まれ変わって、
もしかしたら、また死んでるかもしれん。けど、俺の中では、あの時、勇気を出せなかった自分を、ずっと恨み続けてる。心の底で、深い苦しみが取れへん。もう地獄でもないのに。」
私のエゴ。それでも、私は本当に。何度も自分の中で繰り返し問いかける。本当に私が望んでるのは何か。私はどうしたいのか。
いや、私は私を愛してる。だから、私は、トシを。
トシもそうだとしたら、きっと。
「決めました。」
「そうか。」
「行ってきます。」
「はよせーよー」
私は部屋を飛び出した。それを確かめたくて。
飛び出す部下の背中を見守り、タバコに火をつける。これで良かったんだ。あいつは負けなくていい。上を向く。
「ヒューヒューだよ~」
そう呟いて俺は、ペンを取る。
また逢う日を楽しみに
扉を開き、歩くトシを見つける。
「トシ!」
「エリカ?」
「どうしたの?」
不思議そうに見つめる彼に、感情が溢れ出す。
「ごめんなさい、ごめんなさい、私」
「エリカが謝ることなんてなんにもないよ。ごめんね」
彼はまた優しくそう言った。
「トシ、」
「どうした?」
「死んで」
戸惑っている。
「考えたんやけど、死んでほしいの」
「どういうこと?」
一度深呼吸をする。
「私、ずっとずっとちゃんと言えなくて、素直じゃないから、好きとか、なんか恥ずかしくって、でも、今になってすごい後悔してる」
「エリカ、」
「あたりまえに、ずっと傍におるって思ってたから。ずっと一緒におるって思ってたから。」
「ごめん。」
「だから死んで欲しい」
「ちょっとまだ言葉の因果が見えないな」
「自分勝手やんな」
でも、これでいいんだ。やっと、今なら全部、素直になれる。トシには伝わらなくても、自分の思いを全部。だから、これで良い。
「こんな自分勝手な私、嫌いやんな」
トシの言葉を待つ。
「でも、それがどんな意味やとしても、俺は、エリカが好き。
このまま記憶を無くして、生まれ変わったとしても、ずっと。」
ありがとう。
「嬉しい。
私ね、トシを生き返らせることにした。」
「どういうこと?」
「トシが死んだのは間違いやったことにして、
トシが死んだあの日に戻して、生き返らせる」
「じゃあエリカは」
「それはできない。」
「え?」
「私が死んだという事実は変えられない。けどトシはまだ間に合うから」 「それじゃ意味無いよ、たとえ生き返ったとしても、エリカがおらんかったら」
「それでいいの。トシがそう思ってくれてるなら、それが嬉しいの。」
良かった。
「ごめんね。」
「エリカ?」
少しづつ、遠くなるトシの声に、私は最後に続ける。ずっと言えなかった。本当の気持ち。
「ありがとう。」
「エリカ!」
「また見たいな」
「待って、なんでそんなこと」
「私ゲームばっかりしてたら寂しそうにするのも」
「エリカ」
「可愛くない私の会話も楽しそうに聞いてくれるのも」
「エリカ!」
「いっつも、私のことばっかり考えてるとこも」
「ねえ待ってよ」
「全部 - 大好き - だよ」
「待ってって!」
「また、ずっと一緒にいたいなぁ。」
「 」
死んでね。
上司の元へ戻りながら私は思い出していた。もうすっかり忘れていた。あの花の名前。私がこっちに来た時、握りしめていた、あの花の花びら。何も覚えて居なかったけど、何か大事なことだった気がして。こっちにある図書館で植物図鑑を借りた。花びらしか無かったので、探すのは苦労した。でも、その花のページを開いたとき、心に何かが突き刺さるような感じがした。気づけば涙が出ていた。同じ夢を見るのも、この日からだ。
部屋に戻ると、上司はもう仕事を終えていた。
「これで良かったん?」
「はい、本当にありがとうございました。」
「かわいそうな事しちゃったなぁ」
遠くを見つめながら、そう意地悪に言う。
「今更そんなこと言わないでくださいよ。」
「怒られたく無いなぁ」
「これはでも先輩のミスなので。」
私も意地悪に返した。
「お前なぁ」
花びらを手に取る。
「私、思い出したんです。」
「ん?」
「私が死んだ時、持ってきた。
その意味も忘れちゃってたけど、でもなんとなくずっと持ってたんです。」
「花びら?」
「そう、-ネリネ-です。調べたんです。図書館で。たまたまだと思うけど、花言葉が忘れられなくて。」
「花言葉ねえ」
「この言葉を思い出して、待っておこうと思って。」
「どんなん?」
「-また逢う日を楽しみに。- 地獄からの帰りを。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
