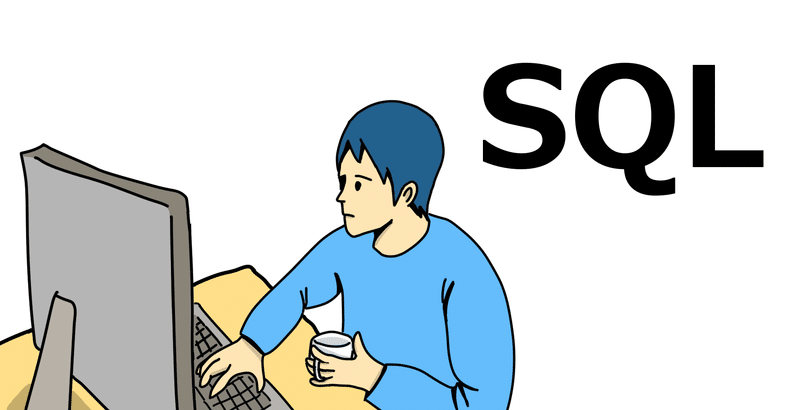
大学で学んだ情報系科目の話 Part5 基礎知識その3
こんにちは、これが289本目の記事となったすうじょうです。今日はこのシリーズの続編です。ここでは、私が大学で学んだ専門の情報系の内容について簡単に説明します。今後、この内容についてさらに深堀りして、感想シリーズを書いたり、解説記事を書くかもしれません。本シリーズの範囲からは数学系の科目は除いています。前回の内容は以下の記事です。
情報系の基礎知識科目その3
今回は前回に話していない基礎?科目について、紹介していきます。
データベースの理論と演習
コンパイラ
信号処理の理論
計算理論
上におおまかにタイトルのみ書きましたが、まったく知らない方が見れば意味不明な部分が多いと思うので、軽く説明をしていきます。といっても一部専門用語の羅列で意味不明になると思います。詳しく知りたい方は、ネットや書籍で調べてください。
まず、データベースの理論と演習では、データベースに関する理論や設計方法について学んだ後、SQLを用いてデータベースの演習を行い利用方法を学びました。
コンパイラでは、コンパイラの字句解析、意味解析、コード生成などについて理論を学びました。関連用語として、flex、bison、LL(1)構文解析、LR構文解析など(ここは分かる人向けです)があります。
信号処理の理論では、アナログ信号処理とデジタル信号処理について、使う数学の道具やフィルタの理論的な設計方法について学びました。関連用語として、フーリエ解析、ラプラス変換、DTFT、DFT、z変換、伝達関数、周波数特性など(ここは分かる人向けです)があります。
最後に、計算理論では、アルゴリズムの評価に用いられる計算理論として、チューリングマシンによる計算可能性理論と計算クラスによる計算量理論を学びました。関連用語として、万能チューリングマシン、停止性判定問題、帰着による非可解性の証明、オーダー記法、P、NP、NP完全、PSPACE、L
、NLなど(ここは分かる人向けです)があります。
今回はシリーズの5回目として、情報系の基礎知識科目の一部について書きました。今回は、少し専門よりな科目や理論系の科目が多いと思います。次回は、しばらく後になると思いますが、基礎知識科目?その4について書いていくつもりです。では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
