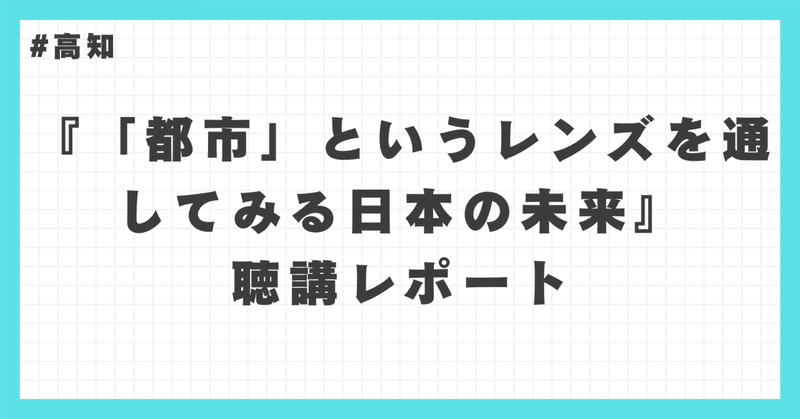
『「都市」というレンズを通してみる日本の未来』 聴講レポート
日本、特に高知県は、人口が減少し続ける中でどのような100年後を迎えるのでしょうか?本記事では、京都大学の森知也教授の人口予測モデルに基づき、100年後の高知県の姿を探り、私たちにできる行動について考えます。
■背景と目的
2024年5月11日、京都大学経済研究所 森知也教授による『「都市」というレンズを通してみる日本の未来〜100年後の日本の都市と地域のすがた 急激な人口減少がもたらす淘汰と希望の未来〜』という講演を聴講しました。この講演では、人口予測モデルに基づく100年後の日本のすがた、そして高知県のすがたが考察されました。講演内容と気づきをまとめます。
日時:2024/05/11(月)
会場:高知工科大学・永国寺キャンパス1階、A104講義室
主催:高知工科大学・データ&イノベーション学群
講演者:
京都大学経済研究所教授・RIETIファカルティフェロー・森知也
高知工科大学・名誉教授・永野正展
高知工科大学・データ&イノベーション学群・教授・金広文
野中兼山研究者(元社会科教員、オーテピア高知図書館高知資料デスク勤務)・横山有弐
高知工科大学・データ&イノベーション学群・客員教授・高嶋成豪
■人口予測モデルをざっくりと
森教授から、人口集積としての「都市」を単位として地域を捉えることがポイントである、と説明がありました。ここでは「都市」を、人口密度が1000人/km²以上で、総人口が1万人以上の連続的な地域と定義します。下図をご覧ください。

出典元:第1話 「都市」というレンズを通してみる地域経済
この図は、地域の人口順位と地域の人口の関係を対数グラフで示しています。青色のプロットは、きれいな直線になっています。一方、緑の都道府県やオレンジの市区町村内の人口等は直線になっていません。よって、都市単位で人口を考えることで、予測モデルを構築しやすくなります。確かに、行政区という人が決めたエリアで考えるよりも、結果として人口が集まったエリアで捉えたほうが自然だと感じます。
もう一つ考慮すべきは、テクノロジーの進歩による、輸送・通信費用の減少です。大きい流れをで考えると、人は大都市に集まります。一方、輸送・通信費用の減少によって、都市の中心に済むメリットよりも、郊外に済むメリットが大きくなり、郊外化が進みます。高知県で考えると、高知駅周辺の人口が、北環状線北部、南国市、香美市のあけぼの街道沿いに広がるイメージでしょうか。
以上の前提条件をもとに、100年後の日本のすがたを考えると、
・都市の人口順位と都市の人口は、対数グラフにおいて直線で表現される
・直線(=べき乗則)のまま、人口が減少する
・大都市に人口が集中する(大都市はより大きく、小都市はより小さく)
・都市において郊外化が進む
という動きとなります。
この動きを人口予測モデルとし、高知県の100年後の人口を予測します。

■人口予測モデルに基づく100年後の高知のすがた
予測モデルに基づいて計算した場合、「都市」の人口は、どのように変化するでしょうか?下図をご覧ください。

1970年は、「都市」が高知、長浜、香美、須崎、安芸、室戸、四万十の7都市あります。これが、2020年には5都市、2070年は3都市、そして2120年には高知市の1都市のみになっています。ここまで人口と都市が減っていくのですね。
さらに、地域の「拠点都市」として、10万人以上と50万人以上の都市の分布を見てみます。下図は、2120年の低位推計における分布図です。

2120年の低位推計における高知市の人口は71,300人であり、10万人都市ではなくなります。10万人都市を拠点都市と捉えた場合、高知は、松山圏と高松圏に取り込まれています。また、50万人都市を拠点都市と捉えた場合、高知は、大阪県内に取り込まれています。
講演の中で、人口減少自体が問題なのではなく、人口減少急速であり、この急速な変化に適応できないことが問題、とありました。私たちの世代、私たちの子どもの世代は、この人口減少社会を生き抜くことになります。このような人口減少社会において、私たちに何ができるでしょうか。
■人口減少社会において、地方に何ができるのか?
勝ち目のある地方創生として、森教授から4つの提言がありました。
ご紹介します。
①人口維持・増加を目指さない
②地域特有の自然資源に注目(特に1次産業):発想の転換で高利益化
③社会による子育て(国を当てにしない人口再生)
④地域資源を活かすための拠点都市・インフラの選択と集中
①は、都市に人口が集まるという力が働くので、地方がこの力に逆らって人口を増やすには、よっぽどの魅力が必要なのでしょう。人口を増やす取り組みよりも、②③④を実行することが重要なのかもしれません。
②は、特に高知で着目したい内容です。質疑応答の中で、聴講者から「他の都道府県と比べた場合の高知県の特徴は?」という問いがありました。これに対する森教授のご回答は、「自然資源、特に山林資源」というものでした。高知の山林資源を生かした林業、温暖で雨の多い気候を生かした農業、太平洋での水産業、そしてこれらに組み合わさせるイマドキなテクノロジー。高知で暮らし、高知で働く中で、深堀りしていきたい内容です。
③は、具体的にどうすればいいのでしょうか。以前、インドの地方の村に訪問したことがありますが、社会による子育てがなされているように見えました。お金という面では豊かな村ではないように見えましたが、子どもの人数が非常に多く、子どもたちは最高の笑顔で無邪気に遊んでいました。ここにヒントがある気がしています。
④が、実際にうまくいっている地方はあるのでしょうか。実際問題、推し進める中で、地元住民からの反発があることが想定されるため、強烈なリーダーシップと、ユニークなアイデアが必要になるのでしょう。
■まとめと今後の課題
森教授の講演を通じて、高知県が直面する人口減少に関する課題を考えるキッカケとなりました。
・人口減少社会の中でいかに生きるか?
・高知特有の自然資源に注目した産業をいかに生むか?
・家族による子育てではなく、社会による子育てをいかに推進するか?
・地域資源を活かすための拠点都市はどうあるべきか?
・インフラをいかに選択と集中するか?
など、引き続き考えていきたいテーマです。
■参考
森教授の理論は、下記コラムにまとまっています。
非常に読みやすい記事です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
