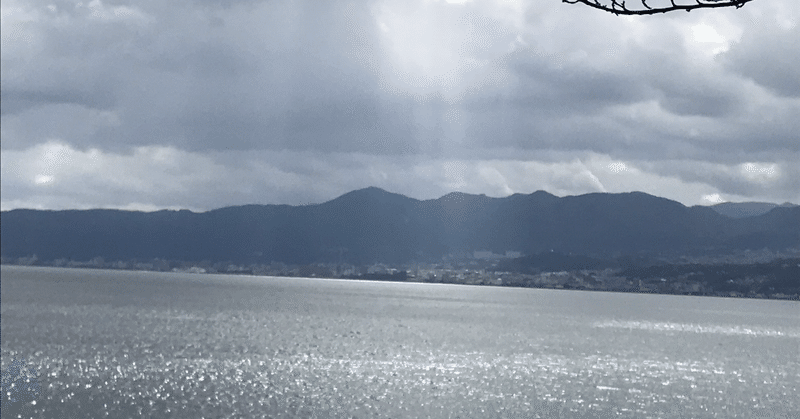
その台詞は、どこから来たの? のつづき
俳優、声優を志す人を応援したく、話させていただいています。
前回のその台詞は、どこから来たの、のつづきです。
どう読むかの声から入らず、何を思ってこの台詞になったのか、
最初の心の動きを、まずは掘りあててほしいのです。
何にも頭に浮かばないのに、何かを話そうとする人はいません。
頭にないことを言葉にすることは不可能です。
ちょっと試してみてください。
ね、できないでしょう?
ところが、台本を読んで自分の役の台詞を言う時には、
これをやってしまうのです。
平気でね。
こんな感じ、こういうつもり、なんてね、器用にやってしまうわけですよ。
それは一見、いい感じにみえるかもしれませんが、違うんです。
上手く言えてるだけで、平べったいんです。
そこにその人物はいないのです。いるようにみえて、いない。
意味がわかるだけ。
たとえば、朗読でも同じことが言えます。
字だけを追って、滑舌良く、間違えずに読むだけだと、綺麗に聞こえてはいますが、
あらすじがわかるだけなんです。解説を聞いているようになってしまいます。
この台詞を言わざる負えなかった気持ちをつかむ。
これが大事。
でも、その前に何より、その人物をつかむことが絶対に必要。
どんな性格のどんな人間かを具体的に。
この人間だったら、こう言うであろう、
こう考えたから、この台詞になったのだと決めることです。
役を生きる。
書けば簡単ですが、とってもむつかしい。
どうしたら、役になりきれるか、役を生きられるかについては、また機会を見てゆっくり語りたいと思います。
山ほどあるので。
ここでは、まず前回の「あたまよみ」についての私なりの考察を。
頭だけで解釈して読むと、聴いている人の頭にしかいかないのです。
えっ?
と思うでしょ。
これが面白いんだな。本当にそうなの。
と、言うところで、またにします。
次回をお楽しみに。
何から何まで、どんどん解き明かしていきますぞ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
