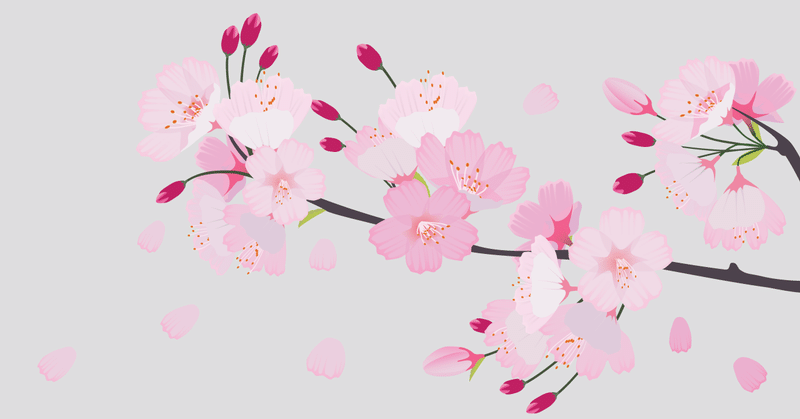
花あかりの小径 ( 終章 ) 明日への素描
コップの底に、過飽和の甘い砂糖の結晶を見るような——はしゃぎ過ぎた後に味わう気だるい虚脱感をいつも残したまま——季節は変わろうしている。
卒業式までの休みの間、カイはコンビニで夜間のアルバイトをしながら、日中はアトリエに通った。
時折、美野川の岸をルイと一緒に散歩する楽しみもあった。
そんな時、ルイは決まって美野川の景色をひとつひとつ摘み取る様に言葉を紡ぐ。
——大自然の息吹と生命の感覚を詠うように、ひとり言のように語る言葉は、どんな「配剤」よりもカイの思考に意味のある揺さぶりをかけてくる。かつてそうであったように、今もなお——
そしてたった今
「ほら見て。たんぽぽ」と、連れ立って歩いている足もとの草地を指差した。
ギザギザの葉が地面に這いつくばる様に円形に広がっている。
「ひろげた葉の表面からは太陽の光を取り込んで、地面に接する裏側の葉からは地熱を取り込んでるの。寒い冬を越して花を付けるための戦略なんだって。賢いよね」
カイは短く相槌を打った後、足もとに目を落とすルイの横顔を振り向いた。
大自然の営みに示唆されたルイの言葉の数々………。
「僕は——そう言うルイの言葉に触れるたびに、大切なことに気づかされたて来た様な気がする」
首元に巻いた紺色のマフラーを顎に押し上げ、はにかむように肩をすぼめた。
「ううん、違う」
顔を上げ、ルイはキッパリと否定した。
「私の言葉じゃなくて全部両親の受け売り。でも、本当に素晴らしい贈り物をもらってきたんだなあって思ってる」
小さい頃からボランティアとして活動する両親と一緒に、環境への取り組みを実践していく中で、見て、聞いて、受け止めてきた言葉なのだと言う。
「だから、私が立ってる大地は両親が耕してくれた様なもの。その土の下には未だ手入れが届かない(心土)があって、それは私自身が掘り起こして耕していかなければならないの。私が私自身である為には、私が感じ取ったことを、自分の言葉で語れる様にならないと。でもね——」
ルイはいったん言葉を切ってから、引き結んだ口もとに笑みを湛えて
「私に決断を与えたのはカイ君なんだよ。一人で悩みながら、内に秘めたものを求め続ける姿を目の当たりにして、(表現)することに惹かれる自分に気が付いたの。同時に私はやっぱり大沢東吾の娘なんだなぁって思い知ったんだ」
肩をすくめ、作陶は未経験だけれど絵付もあるから楽しみだと言う。
祖父の工房を手伝いながら陶工の道を目指す事になったルイ。
表現を通して二人の間に共感が生まれ、改めて励み合う、かけがえのない存在としての重みに気付かされた。
( 探求 )から( 探究 )へ——ひと連なりの道を進みながら、これからの自分は、足りないものを極めていかなければならない。
「頑張ってな。ずっと応援してるよ」
「ありがとう。私も応援してるよ」
頭上を滑翔してゆく鳥を目で追い、空の一隅を仰ぎ見る。
自分の青春は、自然への憧憬を掻き立てるこの美野川無くして語れない。
今、カイはひとり、自然のしつらえの中でスケッチを兼ねて散策している。
踏みしだく足もとの草地には、枯れた根元に新しい緑が立ち上がっている。
楚々とした細い枝を垂れる一本立ちの柳は浅緑の花穂をつけ始めた。
川岸の向こう、崖下の雑木林のほねばった枝にも芽吹は始まっているにちがいない。
冬は冷たく長い沈黙のあと、耐え忍んだ「生命」すべてに暖かな大気を呼び寄せ報いてくれる。
カイは春の兆しを目で追いながら、探し、求めることに明け暮れた日々を想う。
こだわり続けた父との関係はどうにか小康を保った程度に過ぎない。
権威的な態度で服従をさせられる事のない代わりに、相変わらず目に見えない軋轢が近づくことを拒んでいる。
美幸は、敵対してるわけでもない父との関係を、なんと呼べば良いのだろうと言ったことがある。
親の愛情を必要とする子供にとって、意識の外に置かれることは拒絶に他ならない。そんなはずは無いと否定し続ける子供の心は不安を囲い、安定を失っているのだとも。
美幸がよく言う「期待をしない」と言う言葉が、心の安定のを保つための諦念だとしたら悲しい現実だ。
その現実を乗り越え、美幸の様に「達観」の域に到達できた時、はたして一人の同性としての父を理解することができるのだろうか。
先週末、その美幸から便りが届いた。
母とカイ、それぞれに当てた便箋に、フィヨルドの写真が添えられていた。
——すべてカイの思いどうり⁈
美大に進学するつもりなんだって? 希望が叶って良かったね。先ずは来年の受験に向けて頑張りなね。
私といえば………
たった3ヶ月で会話をものに出来るわけはなく、ワーキングホリデーを楽しむための脱出であったと述懐しています。
それでも、異国にあって自分の生活を賄っていることの自信は、誇りと達成感につながっているかな。
でも一方、登山ガイドをしながら大自然に圧倒され続ける、ちっぽけな存在の自分に気が付いて、ただただ無力をかこち、最近は士気がさがりぎみ。( ホームシックかも?)
ハミテージホテルのアルバイトも冬に入る迄。そのあと、帰国するまで観光を楽しむつもり————
親しくなったガイド仲間と一緒に、旅行の計画は練ってあるのだと言う。
どんな環境にあっても友だち作りができる姉の向日性を羨ましく思いながら、帰国後
どんな体験談を語ってくれるのか、朝のひと時の、賑やかなお喋りの再開が待ちく思われた。
久しぶりにパステルロードへ徒歩で出かけた。
三年間、満身創痍で走り続けた愛車を処分した後、憧れのロードを買う決心をしたのだ。
「中古のマシンじゃ、嫌かい?」
親父さんは銀色の愛車を磨き上げながら言った。
「中古って? 中古のロードも置いてるんですか?」
事情が飲み込めず聞き返すと
「いいや、これだよ」
しゃがみこ込んでいた腰を上げ、磨いていた自分の愛車を指差した。
「僕のお古だけど良かったら乗ってくれる?」
親父さんは卒業祝いのつもりだと言った。
「僕の新しい相棒は、ほら、あそこ」
作業台の奥に、お気に入りのパーツで組み立てたのだという、ブルーのロードが置かれていた。
「充分乗り慣れたら新しいのを買うといい。これだって僕が組み立てたやつだ。まだまだいい走りをするぞ」
親父さんは、口髭の奥に真っ白い歯を覗かせて笑った。
いくら使い古しと言っても特注と同じだ。自分には手が届かない高価なものに違いない。
カイは、信じられない気持ち半分でお礼を言った。
貯金箱を全部さらい、祖父母や、叔父叔母に貰った卒業祝いを合わせて用意したお金は、思いがけない申し出によって手もとに残ることになった。
親父さんに見送られ、銀色のロードのハンドルを握った時、何かわからない熱い波動の様なものが手に、身体に、伝わった。
——こいつに乗って描きたい風景を探しに行くんだ。ルイや吉見のところにだって——
卒業式の数日後、哲と一緒に吉身を見送ることになった。
待ち合わせの新幹線のホームで、吉見はバックパッカーの様なゴツいリックを背負って立っていた。
両親には最寄駅まで車で送って貰ったのだと言う。
「上手く親の監視を逃れても、結局何処かしらに属して、手取り足取り手引きしてもらわなければ合格は達成出来ないんだ。」
当然、寮生活は厳しい制約があって家庭の比ではない。
今さら気付いたわけでは無いだろうけど、吉見はしきりとぼやいた。
「つべこべ言わずにこれを持ってけ」
合格祈願だからと、哲が吉見にお守り袋を手渡した。
「これはカイの分。そして——これは俺の分」と、残りのひとつを自分のポケットに押し込んだ。
哲は合格を果たしたものの、安全圏を狙ってレベルを下げすぎたと後悔していた。
大学に在籍しながら高みを目指すつもりらしい。
吉見は手の中のお守りをじっと見つめ
「俺たち何処まで連れ合う仲間なんだろう。揃いも揃って再チャレンジとはね」
そう皮肉った言葉は、偏頗な教育制度を揶揄しているかのようだった。
「たまには手紙くれよ。訪ねてきたっていいんだぞ。外出許可もらえるから」
別れ際、吉見は駄々っ子のような口調で、ニンマリと、あの独特の笑顔を向けた。
「あいつ、あい変わらず辛気臭いやつだなあ」
遠ざかる白い車体を見送りながら哲がつぶやく。
「彼らしくていいさ。受験生の代弁者だ」
カイは、墓地の広場で見せた吉見の葛藤を知っている。
その葛藤を知っているからこそ、自分が多くの人に支えられたように彼を支えたいと思うのだ。
桜は、ほぼ満開を迎えた。
美野川公園の桜や、国道を隔てた墓地の桜は、大勢の花見客で賑わっていた。
此処は、ときおり、自転車や近隣に住む人が通り抜けてゆくだけだ。
公園との間を仕切る高木の林が、小さな桜並木にほの暗い陰影を落としている。
日差しは枝を編んだアーチの上からこぼれ、万朶(ばんだ)の桜は淡く霞んで、仄かな光を放っていた。
ルイは、花陰に身を寄せ、夢中でカメラのシャッターを押し続けている。
「ここ、花明かりの小径って言うんだよ。僕たちがそう呼んでるんだけどね。ほら、薄桃色の灯りが灯っているみたいでしょ」
ルイと一緒に連れ立って来た末の弟の律が、したり顔で説明する。
野球帽の下に覗く顔は十一歳のヤンチャ盛りだ。
「本当だ。ぼんぼりの灯りみたいだね」
花あかりの小径と名付けた理由が良くわかるよと言うと
「でしよ?——それとぉ、桜はどうやって咲くのか知ってる?」
律はまた質問をたたみ掛ける。
( 知ってる知ってる。君のお姉ちゃんにおしえてもらったから)
カイは知らないふりをして首を振った。
「じゃあ、教えてあげる。桜はね…………………」
律の話を聞きながら上空をふり仰いで目を閉じた。
薄いまぶたの皮膚を通して光が溜まる——
風は無いかのようにみえて、薄い花びらを微かに震わせているはず。
花はその芳しいかおりを風に託して、わたしは此処よ——とばかりに匂い立つ。
————目に入るものを描くだけじゃだめよ
目を閉じて 自然の中にいる自分を感じてね
見えないけれどあるはずよ
太陽の光や 風のそよぎ
草いきれや 花の香り
自分を取り巻くすべての自然————
律の声に被るように、麻亜さんの懐かしい言葉が語りかけていた。
ふと気がつくとカイの横に、律がぴたりと並んでいた。
「桜のトンネルを入れて一緒に写すからねー」
ルイが並木のはずれでカメラをこちらに向けている。
「お姉ちゃん、明日おじいちゃんのところに行っちゃうんだよ」
口もとをぷっと膨らませ、寂しさを滲ませた律の瞳に、カイは昔の自分を見たような気がした。
予定は承知だけどまた知らないふりをして訊ねる。
「明日、行っちゃうんだ」
「うん、明日」
「一緒に見送ってもいい?」
「うん、いいよ。だって——二人は恋人なんでしょ?」
「恋人?」カイは思わず笑った。でも否定はしなかった。
なぜか律の方がはにかんで「あはっ」と大声で笑った。
「何してるのー。」
並木のはずれからまた声が響いた。
「もう一枚撮るから。ちゃんとポーズ、き・め・てー」
————完————
☆ 読んでくださった皆さんへ
拙い作品を読んで頂き有難うございました。
年頭 、[ Note ]編集部から一周年記念のメッセージを頂きました。遅延ながら御礼申し上げます。
ここ数ヶ月、愛犬の老いが目立ち始めて、まるで老老介護のような状態になつてしまいました。
目一杯の忙しさが続くと、ストレスから思考と行動が遅滞するのはいつもの事なのですが——終章を大幅に改稿する予定だったので仲々着手出来ませんでした。
漸く、と言うところですがもうひとつの作品が未完成です。頑張って仕上げたいとおもいます。
引きこもり中、皆さんの作品を楽しく、感慨深く読ませて頂きました。繋がりを感じます。
自分の作品を始めから読み返してみると、ところどころおかしな表記があったり、手直ししたい部分もあったり。修正したいのですが後ほどゆっくりと……。
それと——
へ〜〜〜〜〜〜い、ここまで来れたのはあなたのおかげ。ありがとねー!
そして、「Note 」さん、発表の場を有難う!
再開したらエッセイを書きます。どうぞまた宜しく。
SNS初心者どころか、にぶ〜い、ゆすら梅でした!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
