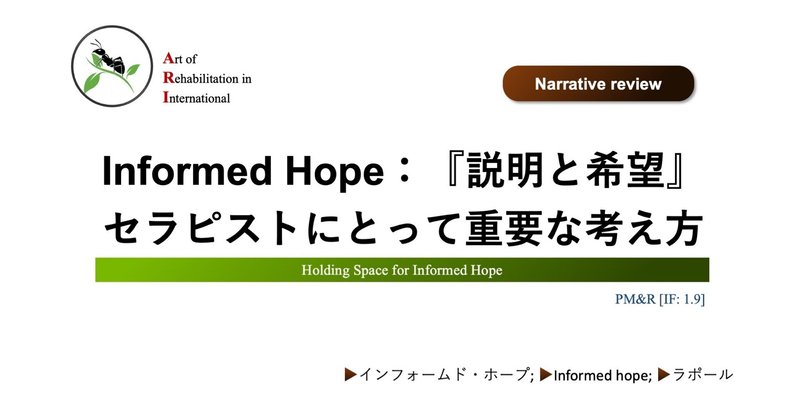
Informed Hope:『説明と希望』-セラピストにとって重要な考え方
▼ 文献情報 と 抄録和訳
インフォームド・ホープのためのスペースの確保
Benjaminy, S, Stein, J, Jansen, L, Mukherjee, D. Holding Space for Informed Hope. PM&R. 2021; 13( 8): 915– 921.
[ハイパーリンク] DOI
[レビュー概要] 文献の中では、インフォームド・ホープとは、『最先端の研究に期待し、同時に現在の臨床の現実を理解した上での楽観主義を意味する』とされている。このレビューでは、インフォームド・ホープの概念が当てはまるケースプレゼンテーションが示されたあと、複数名の権威がテーマについてのナラティブレビューをするという構成の論文である。面白い。ケースプレゼンテーションの概要は、以下の通りだ。
・マールブルグ型多発性硬化症と診断された女性
・この疾患は急速な変性をもたらし、発症から1-2年以内に死に至ることが多い
・彼女は科学と医学を信じており、治療法を待ち望んでいた
・幹細胞治療を受ければ、病状が回復し、自分の人生を取り戻すことができると
・科学の進歩が少しずつしか進まず、希望が持てないことがよくある
・このような場合、どのようにしてリハビリテーションの場で希望を伝えますか?
これに対する各権威の回答のエッセンス
・リハビリテーション医学は、治療法が確立されていない障害を持つ多くの人々(脳卒中、外傷性脳損傷、脊髄損傷など)に治療を提供してきた
・永久的な障害を受け入れるように患者を「押しつける」ことは、治療同盟を壊し、患者に過度の心理的苦痛を与える危険性がある。
・時間が必要であり、患者が自分の状況を受け入れるように徐々に働きかけることが重要である
・希望を与えようとすると治療的誤認のリスクがある。治療的誤認とは,研究参加に伴う利益を過大評価し,リスクを過小評価することである。
・知識に基づく謙虚さ(Epistemic humility)をもって臨むのがよい。知識に基づく謙虚さとは、臨床知識の限界と医学的意思決定の不確実性を認める姿勢
▼ So What?:何が面白いと感じたか?
まず、定義。
Informed Consent『説明と同意』→Informed hope『説明と希望』
われわれの説明が、患者さんの希望に与える影響、とざっくり捉えたらいいと思う。
いろいろ調べてみたが、この用語の定義をはっきりつかむことができなかった、草創期の言葉なのだろう。
「俺って、歩けるようになるんかい?」
「私、また歩いて買い物に行けるようになるかしら?」
「どのくらい、よくなれる?」
リハビリテーションの現場には、超難問が溢れている。
その何気ない1つ1つに、患者さんの重心がのしかかっているのがわかる。
ネガティブな答えは、治療同盟を壊し、患者に心理的な苦痛を与える。
逆に根拠に乏しいポジティブ(楽観)は、治療的誤認のリスクを高める。
そもそも、希望とは、何だろう?
1つの漢字をずっと見ているとその形態に疑問を持ち始めるように、
だんだん、希望というものが分からなくなってくる。
その闇中の光となり得ると感じたのが、『知識に基づく謙虚さ(Epistemic humility)』の活用である。
上記の質問への回答が難しいのは、「完全には実証されていないから」「未来は過去(エビデンス)を塗りかえる可能性があるから」である。
『知識に基づく謙虚さ』の活用は、この不完全性・不確実性・未知を認めた上で、患者とコミュニケーションを取ることだ。
たとえば、同じ60歳代の脳卒中患者様であったとしても、歩けるようになる人もいれば、歩けない人もいる。それに対する歩行練習の効果はある、それはエビデンスが確立されていて、胸張っていえる。
だが、どこまでよくなれるかは、確率論で語ることはできても、絶対論ではないし、何よりそれらのデータは先人たちの積み重ねによるもので、その歴史を塗り替える可能性は、いつだって、ある。
そんなとき、『知識に基づく謙虚さ』を活用すると、以下のようなコミュニケーションになると思う。
「俺って、歩けるようになるんかい?」
「〇〇さんのお病気に対する歩行練習には効果があると思います。ただし、絶対に歩行が自立できるかどうかという点は分かりません。確率論になってしまいますが、過去のデータや我々の経験からは、××頃までにT字杖歩行の自立を目指したいと思っています。どこまでよくなれるかという部分は、確定できない部分がありますが、だからこそ○○さんと一緒に、最善を尽くして自立を目指したいと思っています!!!」
希望とは、何だろう?
それは、「信じることのできる可能性が明らかにあること」ではないか?
未知や不確実性を認め、提示することは、「可能性を提示すること」といえないか?
大事なことは、明らかな未知や不確実性を提示することなんだと感じた。
科学者というのは全てを知っている者のことではない
現在、何が分かっていて、何が分かっていないかを
最もわかっている者のことだ
~池内了~
ほんとうの希望を与えようと思ったら、
真剣な勉強が必要だ
ほんとうの科学者になって、
都度、前進し続ける既知と未知の境界線を捉え続けよう
そこには、ネガティブ?、ポジティブ?、いや、どんな色もいらない
装飾的なことはぜんぶ廃して、ただ、現実と向かい合う覚悟を持て
そこには、必ず可能性のスペースがあって、それが希望となる
-----------------------------------------------------------
良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』
こちらから♪
↓↓↓
-----------------------------------------------------------
