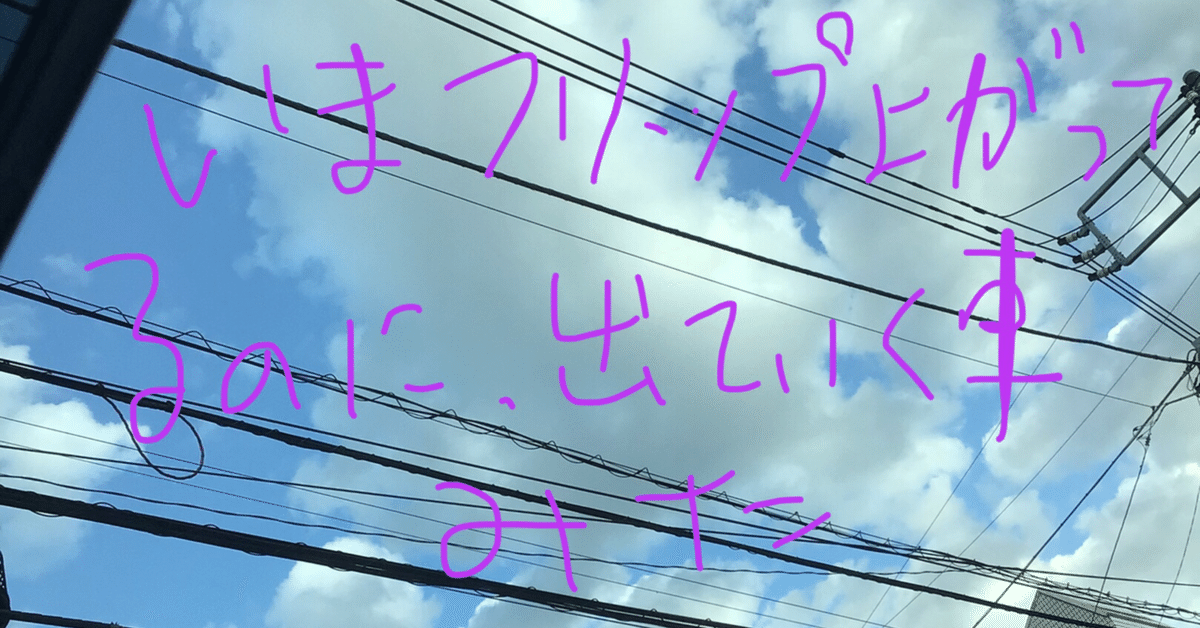
遺品・忍耐・鼠の匂い
『遺品整理屋は見た!』という本がある。
先日、ボロボロになったかつての我が家に立ち寄った時に、積み上げられた段ボールの中から発見した一冊。『ビルマの竪琴』と同じ感じで見つけたやつ。
表紙は、ほこりが粘り着いて、ガサガサしていたので、アルコール入りのウェットティッシュで拭いて、ピカピカにしてみた。
昨今、葬儀屋の開業が増えているというが、たぶんに「遺品整理屋」業も増えているに違いない。
この方のブログを発見したのは、確か、酷道関連のHPや、廃スキー場について集めている方のHPを好んで観ていたときだった。
最近では、住みたくない街について書かれていた方のHP(というかnoteに投稿された有料コンテンツだった)も、面白かった。
保育園児だったとき、食べるのが遅くて、保育士のおばさんに叩かれていた。
その光景を今でも思い出すのだから、トラウマになっているというやつかもしれない。
食べ終わると、すでに、ブロックのめぼしいものは、奪い取られていた。
残るのは、使いようがないブロックばかり。
私はそれら打ち捨てられたブロックに愛着を覚えて、その残りで何か美しい建築物が造れないかと工夫を重ねたものである。
使い勝手のいいブロックを巡って争いが起こる中央を尻目に、独りでブロック遊びに興じた。
*
星新一の短編に「殉教」というものがあった。
死者と交信出来る機械が発明され、死者の声が聞こえるようになると、死後の世界の良さばかりが聞こえてくる。
なので、みんな死後の世界に行こうとして、自殺するようになる。
その列は、ひたすら長く続いて留まることをしらない。
その死体が余りに長く続いて、野山を埋め尽くせんとするころ、死体を片付ける二人の男女が、会話をする。
その会話の趣旨は、
何故あんたは死なないの?
片付ける人がいないと困るだろ!
というようなさりげない内容だったと思われる。
はっきりは覚えていない。
*
それはともかく、あとに残されたものを片付けること、の大変さは、作業だけに留まるものではない。
その場に残された思念やら痕跡やらについて引き受け、その声を最後まで聞いてあげることが、もっとも重要な作業であるように思われた。
だから、本書の著者の吉田さんは、その声なき声を痕跡として未来に送るために、こうしたブログや本を出版したんだろうと思われた。
そのような不要とされる遺品の中でも、百パーセントの人が欲しがらないのが、故人の遺体が残していった痕跡です。
この本が出版されたのは2006年。
私が吉田さんのブログを読み始めたのはいつだっただろうか忘れてしまったが、その時に受けた孤独死以後の問題は、あれから10年以上たって明瞭に現実のものとなってきている。
もちろん、孤独死などのような事象を増やさないための社会インフラも必要だし、孤独な状態を作らないようなネットワークの構築も必要なのだが、すぐさまそうした活動に自分が身を挺せるとは思えない。
そんなとき、自分にちょっとでも出来ることといえば、死について一石を投じる本を紹介するだけだ。
私のような役立たずにできるのはその程度である。
それで、この『遺品整理屋は見た!』を取り上げた。
*
死は小さい頃から端的に怖かった。
中島義道氏がしばしば著作の中で「死への恐怖」について言及しているのだが、そこで示される自分の意識が無いという状態へ到ることの怖さ、はよくわかる。
死よりも辛い生があるというのもわかるが、自分の意識が無になる、ということを天秤にかけたら、やはり現実にワンパンかましてケツをまくる方が性に合っていると思うのだ。
この辺の裁量はなかなか難しいのだが、死=自分の意識が無になる、ことの方がやっぱり怖い。
中島さんの『どうせ死んでしまうのに、なぜいま死んではいけないのか?』は、興味深い。
それ以上に、痕跡が残り、誰かにそれが操作される可能性がある、ということを自分が今意識できる、ということが怖い。
ネットにおいて、過去の痕跡がいつまでも残ることの怖さに、近いのではないか。
ただ、その痕跡を誰かが未来へ適切に受け渡してくれるという保証があると、その怖さも軽減されるのかもしれない。
怖いというか、身につまされて泣きたくなるのは、以下のような記述である。
目の前に立ちはだかるゴミの山をかきわけながら、ようやく部屋の中程まで入っていったところで、私は思わず足を止めました。トイレのドアの下半分に直径五十センチほどの大きな穴が開いていたからです。それはノコギリなどを使って開けたものではなく、何度も何度も足で激しく蹴って、まさしく蹴破ったという感じの穴でした。しかも驚いたことに、その横にあった冷蔵庫にはマジックで大きく黒々と書かれた「忍耐」の二文字。
「忍耐」と蹴破った穴には、因果関係は全くないのかもしれないし、忍耐の代償として、扉に穴があいたのかもしれない。
ただ、外に対して「忍耐」をし、内側で激しく憤懣を燃やさざるをえない、この心理的状態はよくわかる。
私も、浪人時代に書いて貼っていた「謙虚になれ」は、今でも父親がなぜか記念碑として持っているようだ。
弟も「これは兄貴の書いた最高傑作だ」と今でも言っている。
そんなに俺は謙虚じゃなかったか?と自分では思うが、なかなか自分を客観的に見られない。
私が、過去の小説を読んで、何かを書くのは、たぶん、この遺品整理屋さんの作業に近いのではないかと思っている。
実際、自分語りをしながらも意識しているのは、作品が直接伝えきれなかった部分を形にすることである。
*
この本を読んで、はっきりと私の行動が変わったことが一つある。
それは、ゴミ出しをキチンとするようになったことだ。
若いときは、私は、ゴミに関してはやはりというべきか無頓着だった。
しかし、この本を読んで、それが変わった。
足を一歩中に踏み入れた瞬間、猛烈な悪臭が全身に襲いかかってきました。そのすさまじさは今までにもちょっと経験がないものでした。まるで毛穴から侵入してくるように息を止めていても臭ってきそうなほどでした。
なぜそれほど臭く感じたかというと、その臭いが単なる死臭ではなかったからです。
死臭に、犬猫の糞と腐ったゴミの臭いがミックスされた、いわばトリプルパンチで襲ってくる臭いだったのです。
これを読んで、大江健三郎の「死者の奢り」や大沢啓治の『はだしのゲン』の臭描写を思い出した。
この流れで、提示する譬えとしては不適切だが、ワインを好んで飲むようになって、味だけではなく、喉ごしや、香りを楽しむことを覚えた。
ワインのテイスティングは、手前勝手に言葉を並べるのではなくて、香りを表現するいくつかのワードがあって、そのワードの組み合わせと順序によって表現されるという、立派な記号システムを持っているのだった。そのため、果物や草、土、金属などの香りをひたすら嗅ぐことを覚えたし、それを覚えた上で、いわゆる腐敗臭や雑菌臭を覚えると、香りの色見本のようなものが出来る。
ところが、そうしたシステマティックな香りの記号を実体験で覚えようとすればするほど、臭いに関する感度が逆に高まっていった。
ある臭いがすると、何か不穏なことが起こったのではないか、と不安になってしまうのである。
かつてのボロボロになった実家の洗面所で、嗅いだ香りだ。
たぶん、人ではなく、小動物がどこか手の届かないところで腐っている臭い、なのではないかと思う。
自信がないのは、その根拠を目にしていないからである。それは幸せだった。
臭いが、状況を構成するということを初めて経験したとたん、見えない部分に関する想像力がリアリティを持って迫って来てしまった。
それ以来、ゴミはキチンと捨てるようになった。そして、ゴミに対する愛情を持つようになった。
これも、不適切な関連付けかもしれないが、ゴミの扱いと死の扱いは、どこか関連しているのではなかろうか。
ゴミが、適当に扱われ、そして、散乱している社会において、死もまた適当に扱われるのではなかろうか。
残ったブロックを不要なものとして目もくれない保育園児の傲慢をかんじさせる。
というわけで、死を考えるのであれば、まずは廃棄物のことを考えないといけないな、と思った。
怖いだけで済ませてはいけないし、イヤだで済ますわけにはいかない。
私はだから廃棄されるに忍びない古い言論の痕跡を集めて磨いているのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
