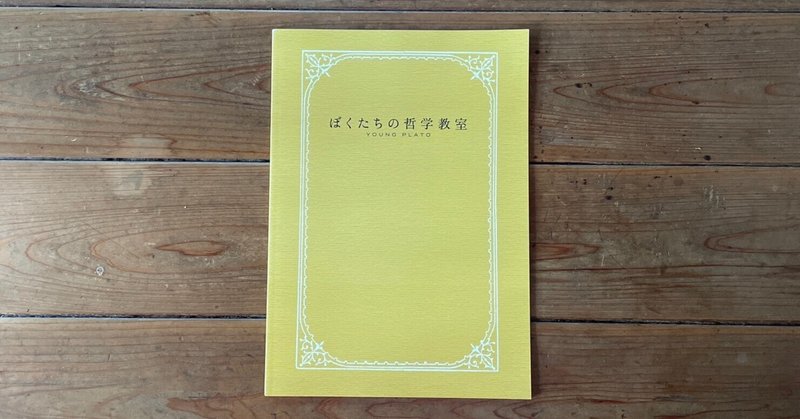
目を閉じて、心のなかで自分の大好きな場所に行くんだ|『モモ』の目で観る哲学の話#4
"ストレスを感じたら、目を閉じて、心のなかで自分の大好きな場所に行くんだ"
映画「ぼくたちの哲学教室」で、校長先生が子どもたちにかけていた言葉。一言一句合っているがどうかは定かではないが。その問いかけにあわせて、思わず一緒に目をつぶった。過去のバカンスで訪れた街をあげる人もいれば、「マック」をあげる人もいた。微笑ましくて、印象的なシーンだった。あなたなら一体どこを思い浮かべるだろうか。
有刺鉄線、乱雑な落書き、道端に散らばるゴミ、どの家も似た建物。北アイルランドの治安が悪そうな街並みが映る。少し前の時代に撮影された映画かと思いきや、撮影は意外にもここ数年だという。
ああ、平和ボケしているのだと自分に対して思った。平和という言葉が無縁に感じる世界がまだまだたくさんある。同時刻の同じ地球上に。戦争が起こっている今、本当にあたりまえのことだけど。
平和が無縁である環境が「ふつう」な世界で生きるってどんな感覚なのだろうと思いながら、ぬくぬくとした世界で生きるわたしは、複雑な気持ちでこの映画を見ていた。
学校でけたたましくサイレンが鳴り響く。避難のために。そんなことは、避難訓練か誰かが間違って押しちゃったか、そのどちらかしかなかったなと過去の自分の小中学生の頃を思い返した。

「やられたらやりかえす」。そのカルチャーが骨の髄まで染み込んでいる社会。それがこの映画の舞台、北アイルランドのベルファストだ。自殺率も薬物使用率も高く、紛争が繰り返されてきた土地である。
暴力で争いを解決しようとしてきたその連鎖を断ち切るには、自分でその感情をコントロールすることが重要だという。そのための訓練として「哲学すること」が用いられていた。
一度立ち止まること。
本当にそうかなあ、どうしてだろうと自分にも相手にも問い直すこと。
暴力で仕返しをするのではなく対話に切り替えること。
違う意見があってあたりまえだと寛容な自分になること。
子どもたちはそれらを徹底して体得させられていた。どうか死なずに生きてほしい。そんな願いとともに哲学の時間があった。日々の生活に重なる、あるいはかぎりなく近いところにある(あってほしい)のが哲学なのだと改めて思わされた。生きるために、生き延びるために彼らは哲学している。

さてさて。これは北アイルランドに限った話ではない。人にやさしくあるために、立ち止まること、そして自分のあたまで考える訓練をすることは、とても大事なのだと思う。いつの時代、どこにいても、だれにとっても。ひいては「哲学する」行為は、平和をつくる可能性すらある。
いつのまにか、人に合わせること、流れに乗ることがうまくなってしまう。私自身は調和性が高い人間である。ストレングス・ファインダーや強み診断をすると必ず上位に調和性が入る。だからこそ、自分の意思を伝え、他人の考えをただ受け入れる、その練習の時間が大事だ。
少しずつ日本の学校教育にも哲学の時間が増えてきているという。それはとても希望だ。大人にもそういう時間が必要。色んな「ふつう」が社会にはある。そのスタンダードを受け入れるだけではなく疑ってみること。
そしてやられたらやりかえす、ではない方法をわたしたちも習得していくべきではなかろうかと改めて思う。「倍返しだ!」という、あの名ゼリフがふと頭をよぎった。
それにしても哲学の時間を牽引する校長先生、ユーモアに溢れた人だったな。人を惹きつけるのはユーモアなのかもしれないと思った。楽しそうな人のまわりには人が集まる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
