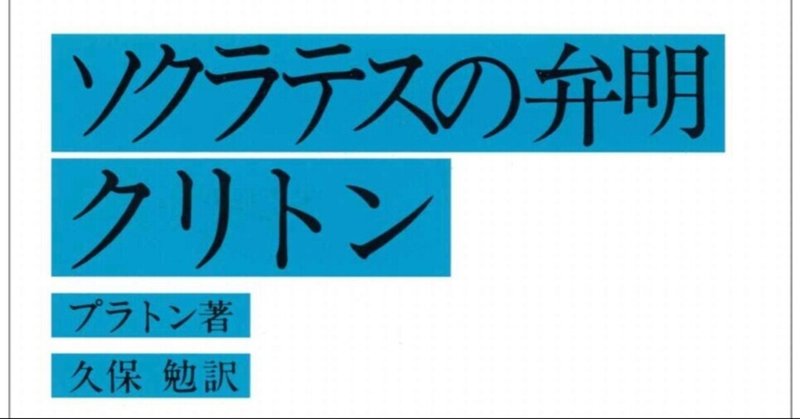
『ソクラテスの弁明』を読んだ感想
まず、『ソクラテスの弁明』の内容に触れる前に理解しておくべきなのは、この著者がソクラテスではなくプラトンだということだろう。書物は当時の考えや出来事について過去の人物が記録したことを時代、場所問わず伝えることができる優れものであるが、そもそも出来事をそのまま記述するのは不可能である。現実の世界を言葉に変換した瞬間、それは嘘になる。もちろん、多かれ少なかれ演出や脚色も加えられる。『ソクラテスの弁明』では、ソクラテスが弁舌をふるうのを記録しており、ソクラテスの問いに対してメレトスが短い返答をするほかには、ソクラテス以外の人物の科白は無いに等しい。しかも、繰り返しになるが、この書物の著者はソクラテス本人ではなく、プラトンである。したがって、ソクラテスの言葉について議論するときは、同様にそれはプラトンの言葉でもあるということを念頭に置くべきだろう。以下、『ソクラテスの弁明』の内容について述べる。
ページを捲りながら最初に考えたことは、ソクラテスの言葉がとても挑戦的に感じられる、ということだったが、読み進めるうちにソクラテスは決して裁判官や他のアテナイ人に「挑戦」しているわけでないとわかった。私は「弁明」と聞くと、「弁解」すなわち「言い訳」のようなイメージを持つが、ソクラテスは自分を正当化するというより、むしろ相手の間違いを正そうとしているように感じた。高校時代の倫理の資料集では、ソクラテスが自らの「無知の知」を自覚したきっかけとして「ソクラテス以上の知者はいない」というデルフォイの神託があったと紹介されており、私はそれに対して少なからずソクラテスの純粋ゆえの傲慢さのようなものを感じていた。しかし、『ソクラテスの弁明』でソクラテスは「神託の真意はソクラテスに名を借りてすべての人間の無知を悟らせることにあると考えるに至った」と言っており、「例えばソクラテスのように」と理解すべきだと見解を述べている。そこには自分のみが正しくあろうとする傲慢さではなく、神託に従ってすべての人間達を「無知の知」の自覚に至らせるという、神への奉仕精神が表れている。この部分を読んだときが、これまで私がソクラテスに対して抱いていた認識が変わった瞬間だった。また、告発者のメレトスに対する弁明では、青年を腐敗させたという罪状に関して、「腐敗させていない」と一言否定すればいいものを、回りくどく様々な喩えなどを用いて論理的に聴衆を納得させようとしていると思った。これには、教育者の姿勢に通ずるものを感じた。後の場面でソクラテスは弁明するのは自分にとっての禍を避けるためではない、とはっきり言っている。むしろ、アテナイ人諸君のためであるとまで言うのだ。「無知の知」を相手に自覚させようとするという意味でソクラテスは啓蒙化であり、教育者でもあった、と私には感じられるし、ソクラテスは法廷でも教育者だったのだと思った。
「ソクラテスの言葉は理屈では正しいが、綺麗事すぎるし相手を丸め込もうとしているようで好きになれない」と反発する人も多いだろう。「世に害を受けることを欲するものは誰もいない」から、「害を加えられるという危険があることをわかっていて故意に青年を腐敗させたわけがない」、という理屈でメレトスの主張を崩す場面では、私も「害を受けるとわかっていても愚かな行いをする人間は沢山いるでしょう」と、ついツッコミを入れたくなってしまった。出来高払い制が導入されて劣等生を追放した19世紀イギリスの学校も、その方法では本質的な解決にはならないこと、露呈したら非難されることを承知していたはずである。それがリアルである。それでも私はリアルよりいわゆる綺麗事が好きなので、メレトスに対して理詰めで弁明するところまでを読んでも、ソクラテスにそれほど反感を覚えなかった。しかし、後半に進むにつれて、「さすがに煽りすぎ、死にたすぎでは?」と思ってしまうような場面が増えてきた。まず、ソクラテスは死刑を求刑されているけれども、同情を惹くために家族を法廷に連れ出すことはしないし、哀願によって罪を赦されようとするのは名誉と正しさに反する、と述べている。有罪、つまり死刑が確定した後もソクラテスは動揺せず、(有罪になるのは)予期に反していなかったし、もっと有罪の評が多くなると思っていたからむしろそちらに驚いている、というようなことを丁寧に語るのである。これでは、ふてぶてしい態度だと取られて心象が悪くなるのではないか。さらに、死刑よりはマシだと考えられる追放刑に対しても、私の解釈で大意にはなるが、「同市民すら私の行動を煩わしく思い、私を排除したいとまで思ったのに、他国人がそれに堪えられると思うほど馬鹿じゃない」と言及している。死刑を免れる代わりに、人に議論を持ちかけるのをやめて静かな生活を送ることも、同様に拒否する。まるで自ら死刑になることを望んでいるかのようである。「生」に拘るよりも優先したい精神があったことはわかるが、そうであってもここまで口に出してしまう人はそういないだろう。そして、ソクラテスは自分が有罪になったのは言葉の不足ではなく、諸君ら(有罪・無罪を決する人々)を喜ばせる言葉を用いて諸君を動かそうとする意志が無かったためである、とも言う。つまり「諸君」は被告が泣いたりわめいたりするのを見れば容易に心を動かされて、その信念に関わらず嬉々として無罪評を投じる愚か者だ、と言外に皮肉っているようなものではないか。それとも、そう感じてしまう自分が捻くれ者なのだろうか。ソクラテスの言葉に触れていると、「正しい言葉」の受け取り方について考えさせられる。また、ここで「煽りすぎ」「普通、そういうことは相手の心情に配慮して言わないでしょう」と多少の反感を抱いた私だったが、思い返してみれば、ソクラテスは「弁明は諸君のため」であり、「正義に反した譲歩はしない」という姿勢を最初から崩していないのだ。ソクラテスが配慮するのは相手の都合や自分の利益に対してではなく、魂に対してなのだ。その考えに至って、私はやはり純粋に正しさを求めるソクラテスの綺麗事が好きだ、と手のひらを返してしまうのである。
さて、ソクラテスに関して最も知られているのは「無知の知」というワードだろう。最後にこれについて述べて、感想を終わりとする。『ソクラテスの弁明』において、ソクラテスは「自ら知らぬことを知っているとは思っていないかぎりにおいて(中略)智慧の上で少しばかり優っているらしく思われる」と言っている。私はそれを読んで、自分が知っていること以外にも事柄があることをわかっている、したがって自ら知を深めることができる可能性を持っている、という解釈に発展させた。「無知の知」を自覚しなければ自分は世のすべてを知っているのだ、という思い込みに陥り、そもそも知を深めようという発想に至らないため、その知は現状維持にしかならないというわけである。つまり、「無知の知」は、学ぼうという意志の根底にある最も基礎的な「気づき」なのだと私は考えた。さらに、ソクラテスは、熟練した分野があるために、他の最も重大な事柄に関しても最大の識者であると信じ込む過誤も指摘している。では、なぜ我々はそのような過誤に陥ってしまうのだろうか。
ここからは、教育分野に関して考えてみようと思う。知を深めることは学習の基本であり、学校は子ども達が卒業した後も、生涯学べるように導くのが理想である。子ども達に「無知の知」を自覚させるためにはどうすればいいのだろうか。まず、過誤に陥るのは小さい世界に自分を閉じ込めてしまうからではないかと思う。子ども達の小さな世界を打破して広い世界を見せるために、社会教育施設を利用した教育は大きな役割を果たすだろう。近年重要視されているインクルーシブ教育のもとで多様な人間と交わるのも、「無知の知」を自覚する機会になると思う。現に、私はこれまであまり障害のある人と関わったことが無かったが、大学で障害児教育について関り、初めて自分が障害者についてほとんど何も知らなかったこと、重い障害から反射的に目をそらしていたことなどを自覚した。学校で障害のある生徒と生活していれば、また違っていただろう。また、講義で扱われた理系が重視されて文系の学生が戦争に駆り出された戦時期などは、ソクラテスの考えに明確に反していたと思う。その時代によって重視される教育が変わってきたことも講義でよくわかった。今日も大学への研究予算の削減や教育課程の変更に伴ってそれぞれの学習分野の必要性について度々議論されるが、そのたびにソクラテスの「無知の知」の考えに立ち返り、「私たちは何を学ぶべきなのか」ではなく、「私たちはどのような姿勢で学ぶべきなのか」と考えたいと思う。そして、私は『ソクラテスの弁明』を読み終えて、偏差値教育の問題点についてさらに考えを巡らせるようになった。偏差値は確かに便利なものである。大学進学を目指すのなら、気にするべき数値だろう。その便利な偏差値に対する批判の多くは、子どもを偏差値という基準で画一的に評価し、子ども達の個性を無視してしまうことに対してであると理解している。それとは別に私が偏差値教育に危惧することは、子ども達が偏差値を上げようと努力するあまり、偏差値に無関係のことに価値を見出さなくなることである。こうなっては子ども達の世界は狭まるばかりになるし、「無知の知」を自覚する機会を奪うことになりかねない。
以上のように、『ソクラテスの弁明』を読んで、ソクラテスは哲学者であると同時に教育者であったこと、プラトンの目を通して、ソクラテスから多くのことを学べること、「無知の知」をはじめとしたソクラテスの考えは、教育学にも大いに役立つということがわかった。私には高校生の時にもこの本を読もうとし、挫折したという経験がある。しかし、今一度このような機会に読み返してみると、想像以上にスムーズに読み終えることができた。このレポートを書くにあたり、『ソクラテスの弁明』と「教育学」の間には果たしてどれほどの関連性があるのだろうか、と少し不安に思っていたが、読み終えて、むしろ「関連性」を自分から見出していこうとする姿勢を持つことが大切ではないかと思った。
2021.8.27
教育史の授業 最終レポート(大1)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
