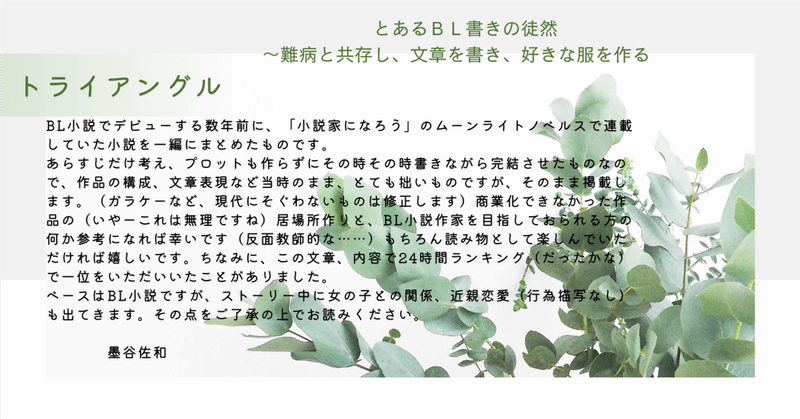
トライアングル21
第十一章 十日間 1 <side カオル>
注:BL的触れ合い描写があります。
僕は、その短いLINEを凝視した。
「たすけて」の後には、○○町三丁目 コーポエイト201 と記してある。
何かが桜子の身に起こって、ここに迎えに来て欲しいということなのか?……僕はスマホを握り締めた。
「どうした?」
トモが声をかけた。僕がスマホを持ったまま立ちつくしているので、変に思ったのだろう。
「カオル?」
呼びかけても返事をしないので、トモは僕の手からスマホを取り上げた。あっと思った時には遅かった。
「なに、これ」
トモはLINEの画面を見て、それから僕を見た。
「桜子と連絡取ってたんだ?」
「違う!」
僕は、弾かれたみたいに言った。
「あのコとは、あれから会ってない。これは突然で、なんのことだか……」
僕は必死に言い訳したけれど、トモの返事はすごくあっけなかった。
「うん」
「うん、って……」
「あれから、カオルにそんなヒマも余裕もなかったのは、俺が一番知ってる」
信じてくれるんだ……そう思ったら力が抜けた。
「でも、あっちの方はカオルに用があるみたいだな」
「何かあったんだ」
「そうだろうな」
トモは、のらりくらりと返事を返す。
僕は、とたんに桜子が心配になってきた。彼女は不安定だった。立っている位置も、帰るべき場所も心もとない彼女は、身を切るような寂しさを誰かの体温で紛らわすような女の子だった。
「行くよ」
「狂言かもよ」
「でも、本当に何かあったのかもしれない」
「もし、これが桜子じゃなくて坂崎や高木でも、カオルはやっぱり行くんだろうな」
言い争いになるかと思ったのに、トモは一歩引いた感じでため息をついた。
「本当は関わってほしくないけど、でも俺も努力するって言ったから」
「ごめん」
「お前一人桜子のところへ行かせるくらいなら、俺も一緒に行く」
トモは崩れなかった。
コーポエイトは、○○駅裏の繁華街にほど近い場所にあった。地図アプリで検索したら、あっけないほど簡単に見つかった。
201号室の前には、ペットボトルや缶ビール、コンビニ弁当の空き容器が詰め込まれたゴミ袋が積んである。あれから何度か電話をかけたが繋がらない。嫌な予感と逸る心を抱え、いざインターホンを押そうとしたが、一瞬とまどった。
中で何がどうなっているのか? 桜子は本当にここに居るのか? いきなり中へ入って、それでーー。
「何してんの。押せば?」
トモが僕の肩越しにインターホンを押した。がたがたと音がして、誰かが玄関の方へやってくる音がする。
「はーい」
ガチャリという音とともに、女の子がドアの隙間から顔をのぞかせた。僕たちと同じ年くらい。キャミソールから胸の谷間が丸見えだった。
「あんたたち、桜子の知り合い?」
僕が言うより先に、女の子の方が僕をじろじろ見ながら言った。うなずくと、彼女は部屋の方へ振り向いて大きな声で言った。
「お客さん来ちゃったよ。カズキの負けー!」
「うっせーな」
不機嫌な声がして、今度はボクサーショーツ一枚の男が現われた。
「入んなよ」
男の声で僕たちは部屋へ迎え入れられた。男といってもやっぱり僕たちと同じくらい。歓迎とは言いがたい状況だったが、とりあえず僕は部屋の中へ入った。
玄関を上がってすぐ、狭いキッチン。その奥に六畳くらいの部屋があって、男が二人と女の子が一人……桜子は窓際のベッドの上にいた。もう一人の、さっき出てきた女の子と同じようにキャミソール姿で、僕の顔を見るとさっと身を縮め、隠すように両腕を交差させて上半身を覆った。
煙草と酒の臭いが充満した室内は、それだけでも気分が悪くなりそうだったが、何日も締め切ったままなのか空気そのものが淀み、異様な雰囲気だった。部屋のあちこちにティッシュや使用済みのコンドームが散らばっている。桜子がこの部屋で何をしていたかは一目瞭然だった。だが目は怯え、憔悴しきっている。顔には殴られたようなあともあった。
カオルくん、と唇が弱々しく動く。
「帰ろう」
僕はそう言って部屋にずかずかと入り込み、ベッドの上の桜子の手を乱暴に握った。
「そいつが行く所がないって言うから拾ってやったんだぜ? タダで泊められるワケないだろ。そんなことはそいつも合意さ」
さっきの男が僕の開いた方の手を掴んで言った。
僕は黙ってその手をふりほどく。一瞬だって、こんな所にいたくなかった。
「どーでもいいけど、カズキ、賭け金払えよ」
桜子の横にいたもう一人の男が、タトゥーの入った手をひらひらさせた。カズキと呼ばれた男は舌打ちして、落ちた財布から札を何枚か出している。
「このコにねえ、ほんとに三時間以内に迎えが来るかどうか賭けてたのよ。で、カズキが負けちゃったのよね。ごめんね、機嫌悪くて」
さっきの女の子が、説明らしきことを言った。
「迎えに来てくれるやつが居んなら、行くとこないなんて言うなよ。さっさと出てけ」
カズキは床に落ちていたバッグを蹴った。桜子は僕に背を向けて衣服をかき集め、身に付け始めた。肩が小刻みに震えている。
「あんた、西校のカズキだろ?」
いつの間に入ってきたのか、玄関にいたはずのトモが僕の後ろから男に声をかけた。とたんに、男の顔が嫌なものでも見たように歪んだ。
「お前……」
知り合い? と言うふうにトモに目線を送る。
「前にちょっとな。カズキくんの彼女が俺のこと好きだって言ってさ」
「こいつの知り合いかよ」
カズキはトモの方を見て、顎で桜子を指した。
ソレは俺の連れの知り合い。俺にはなんの関係もない」
桜子はトモを凝視していた。血の気のない顔に戦慄が走り、それでいて視線を外せない。凍りついた表情だった。僕はなす術もなく立ち尽くし、トモと桜子を交互に見た。最悪の再会だった。
「相変わらず悪いことしてるみたいじゃん?」
トモは床に落ちていた銀色の包みを指でつまんで言った。
「酒と煙草、ドラッグ、レイプ?」
「合意だと言ったろうが!」
カズキはいきり立ったが、トモは冷たい流し目を送っただけだった。
「俺は世界で一番お前に会いたくねーんだ。失せろ。その女連れてとっとと失せろ!」
「言われなくても」
トモは先に立って部屋を出た。僕は桜子の手を掴み、後に続いた。
「ごめんなさい……」
アパートの外階段を降りきったところで、桜子は泣きながら言った。
「あとでゆっくり聞くよ」
僕は労わるように言って、桜子のバッグを持った。
「取り合えず、ここから離れよう」
僕たちより少し先を歩いていたトモが立ち止まり、こちらを振り返った。その目線は鋭く桜子を刺している。
「久しぶり。十年ぶりくらい?」
心の底まで切られるような、冷たい声でトモは言った。
「あの……」
桜子は怯えた目で唇を震わせている。動揺して、声にならない様子が痛々しかった。
「トモ、今は……」
僕はトモを制した。だが、トモは僕を無視して言った。
「どうでもいいけど、カオルにこんな迷惑かけるのやめてくれる?」
トモは振り向いて、先を歩き出した。
どうしようもなかった。桜子は心身ともに憔悴しきっていて、彼女を一人放り出すことはできなかった。無駄だとわかっていたけれど「送ろうか?」と聞くと、彼女はやはり首を振った。
「帰れない」
取り合えず、僕たちの家に連れて行くしかなかった。僕が桜子を伴って電車に乗っても、トモは何も言わなかった。
僕たちはシートに並んで座り、トモは少し離れたところでドアに向かって立った。
「……お母さんとケンカして、家を出たの」
桜子はぽつりぽつりと語り始めた。家を出たと言いながら、彼女は軽装のうえに、小さいバッグ一つだけ。衝動的だったことを物語っていた。
「それで、行くところなくて、あの人たちに声かけられて」
「……これで最後にするって言ったのに?」
僕は桜子を責めた。言っちゃいけないってわかっていたけれど言わずにいられなかった。相手の気持ちを労るよりも、僕は自分の辛さを先に何とかしたいほど子どもだった。
あれから、全てを打ち明けあって、それで終わったと思っていた。でも自己完結したのは僕だけで、桜子の苦しみは続いていた。僕がトモに溺れて、無責任な幸せに浸っていた間も、桜子は居場所を求め、嘘だらけのぬくもりをまた求めてしまったのだ。
「クスリとか……飲まされたの?」
「抵抗したから殴られたの」
桜子は目の下のアザに触れた。しだいに青黒く変化しようとしている。
「自業自得……カオルくんと約束したのに。でも、カオルくんにしか助けてって言えなかった……」
トモには僕たちの会話が聞こえていたはずだ。でも、トモはこちらを振り向きさえしなかった。
「その……トモがいて、驚いただろ」
僕は声を潜めて言った。こんな姿、見られなくなかっただろうにーー桜子は、こくんと頷いた。
駅に着き、量販店で桜子は着替えを買った。僕とトモは店の前で待っていた。「取り合えず、家に連れて行くよ」
「取り合えず?」
「あのまま放っておけない」
「……帰せよ」
「帰れないんだよ」
会話はかみ合いそうになかった。無茶を言っているのは僕の方だが、折れたのはトモの方だった。
「勝手にしろ」
トモは吐き捨てるように言った。
家に帰って、桜子にシャワーをすすめ、開いていた父さんたちの部屋に彼女を通した。
「とにかく、今日はゆっくり休むといいよ」
「こんなにしてもらって、どうしたらいいかわからない」
そう言って、桜子はまた泣きだした。首筋に、殴られたのとは違うアザがある。僕は思わず目を背けた。
「僕も帰りたくなかった時、君に助けられたから」
そう言うと、桜子は僕を見た。
「智行と、仲直りしたんだよね。あたしがここにいると智行が嫌がるよ」
「今は気にしないで。あとで食事を持ってくる。もう休みなよ、な?」
子どもをなだめるようにして部屋を出ると、ドアの横にトモが立っていた。
「優しいことで」
トモは、あからさまに不快な顔をしていた。だが、一方で努めて冷静でいようとしているのもわかる。
「お前に嫌な思いさせて、僕は最低だと思ってるよ」
僕はトモに対して非を認めた。トモに対しては非でも、桜子に対しては何とかしてやりたい気持ちだった。僕はいびつな三角形の真ん中で、ぐらぐらと揺れていた。
「トモ、彼女は……」
「あいつの身の上なんか聞きたくない!」
トモは声を荒げて、リビングに向かって歩き出した。僕は後を追う。
「お前は俺のことが好きなんじゃなかったのかよ。なんで他のやつに……よりにもよって桜子にそんなに優しくすんだよ!」
トモは追いついた僕を壁に押し付けると、乱暴に唇を押し付けてきた。激しく舌が入ってきて呼吸を奪われる。こんなに激しくキスされたのは初めてだった。甘さも何もない、ただ責めるだけのキス。さんざん口の中を荒らして僕を解放すると、トモはそれっきり部屋に閉じこもってしまった。
僕は簡単な食事を三食分、まずはトモの部屋の前に置き、自分の分と桜子の分を持って、桜子のいる部屋に入った。
「一緒に食べよう」
僕の言葉に驚いて、桜子は目を大きく見開いた。驚くと目を見開くのは、彼女の癖のようだった。そういえば、トモもそうだ。
「智行は?」
「ちょっと、いや、かなり怒らせちゃって、部屋に篭ってるよ」
「あたしのせいだよね……」
僕は否定しなかった。ここまで来て言い訳をしても仕方がなかった。
「何があったの?」
食べながら、僕は聞いた。食べながら聞くくらいがちょうどいい。そうでなければ、どんどん底に沈んでいきそうな雰囲気だった。
「終業式の日に、学校が親を呼び出したの。あたしに援交の噂があったから」
「援交?」
「単なる噂。でも信じてくれなかった。体面をものすごく気にする人たちだから。あたしも好き勝手なことしてたから信じてもらえないのは仕方ないけど、でも、あたしは身体を売ることだけは、したことなかったのに」
食べながら話すには、ヘビーな話だった。
「それでケンカになったんだ」
「ケンカになるだけ今回はよかったの。おかしな話だけど。いつもは言い合いにすらならないもの。今回は出てけって怒鳴られた」
彼女は笑って、手を合わせた。
「ごちそうさま。すごく美味しかった」
ミックスベジタブルが入っただけのオムライスを彼女は賞賛した。こんなに美味しいものを食べたのは久しぶりだと。
「ウリだけはしないって思ってたのに、結局、同じようなことしちゃったんだなあ……」
僕が渡した麦茶のグラスを手の中で転がして、桜子はぽつりと言った。
「どうしよっかなあ……これから……」
ここに居れば? 喉元まで出かかった言葉を僕は飲み込んだ。そんなことできるわけない。トモに対してそんなことはできるはずがない。桜子だって、トモの側にいるのは辛いはずなのだ。
でも、ものすごく甘い見解だけれど、僕は一瞬、夢を描いた。桜子の思いが整理され、トモもまた、彼女と居ることで朝比奈の呪縛から一つ楽になる。いびつな三角形は、バランスの取れたトライアングルとなって共鳴し、よい音を響かせるようになる……。
ありえない。僕は頭を振った。そんなこと、ありえない。
トモの部屋の前には、食べ終わった食器がトレーの上に置かれていた。僕はほっとして、そうっとドアを開けた。
「トモ」
呼びかけたけれど、イヤホンをしているせいか反応がない。僕は背中からトモに抱きついた。
「食べてくれたんだ」
イヤホンを外し、トモは僕の方を向く。怒った顔ではなかった。
「ウマかったよ」
唇に軽いキス。
「さっきはゴメンな」
「謝るのは僕の方だよ。トモの気持ちも考えないで」
そう言ったら、もう何も言えなくなった。トモと話したいと思って来たはずなのに。何が言いたかったんだっけ……。
「もういいよ。好きなようにしろよ」
トモは言った。
「あいつを家に帰したくないんだろ?」
「でも」
「事情を知りたいとは思わないし、関わるのはゴメンだけど、あっちがどうしても関わってくるなら、シアトル行くまでにケリつけろよ」
「……いいのか?」
「努力するって言っただろ」
トモはベッドに背中から倒れ込んだ。僕もその隣に横たわる。説明したいことがたくさんあった。でも、二人を守るために、それは絶対にできないことだった。「ちょっと、毒気を抜かれたってのもあるんだ」
「毒気?」
「十年ぶりくらいに会って、なんていうのか、あいつは俺の嫌な思い出の一部に属してるってだけで、確かに俺に何かをしたわけじゃない。生身のあいつを見たら、妙に納得したんだよ。俺のトラウマに勝手に組み込んでただけで」
トモは僕の髪を指先でいじりながら言った。
「けど、やっぱり気分のいいモンじゃないけどな。朝比奈は俺の天敵には変わりない。それに」
僕はトモに両手首を押さえつけられ、上からのしかかられた。色素の薄い瞳が、僕を見下ろしている。
「カオル、あいつとやった?」
「やった、って……」
「今さら純情ぶるなよ。怒ってるんじゃないんだ。知りたいだけ」
「……やったよ」
仕方なく僕が答えると、意外なことに、トモの顔が一気にほころんだ。
「ほらな、やっぱり」
「何?」
「今の俺は、あいつに嫉妬してて、面白くないんだってこと」
「しっと?」
聞き間違い? 僕は耳を疑った。
「俺はな、お前が俺以外のやつに優しくすることが気に入らないんだよ、きっと……」
トモの顔が降りてきて、優しく僕の顔に重なった。
「トモ、好きだよ。好きすぎてどうしていいかわからないくらい」
トモの肩越しに呼びかける。僕が腕を動かしてトモを抱きしめると、密着した身体が震えた。
「俺は……」
トモは少し戸惑ったような口調だった。
「俺は、さっきあんなこと言ったけど……まだ、カオルのことをそういう風に好きなのか、わからない」
「うん」
トモのすまなさそうな口調がせつなくて、僕はもう一度腕に力を込めて、愛しいものをぎゅっと抱きしめる。
「ごめん」
「あやまんなよ」
僕が言うと、トモは顔を上げて僕を見た。
「でも、俺はカオルと一緒に居たいんだ」
「うん」
言葉と一緒に唇に小さなキスを落としたら、トモの方からも唇を押し当ててきた。しばらくお互いの唇を啄ばんでから顔を離すと、トモは甘えるように僕の胸に顔を埋めた。
「だから、カオルがこんな風に近くにいてくれると嬉しい。こうやってカオルに抱かれてると安心する」
抱く、と言う言葉に僕はやっぱり慣れない。僕がトモを抱く……トモが僕に……言葉に置き換えると、顔から火を噴きそうだった。
「僕に抱か……僕とするの、嫌じゃないんだ?」
言葉を変えて、僕は言った。すごく恥ずかしかった。
「抱かれるってことがこんなに安心するなんて知らなかったよ」
答えるトモは、すごくキレイだった。頭がクラクラする。
「それに……キモチイイし」
「もう痛くない?」
僕は、今日はまだ触れていないそこに指を這わせた。人差し指の関節を曲げて、少し中にめり込ませる。
「痛キモチイイ」
トモにつられて、僕は笑った。
「けど、絶対セフレとかそういうんじゃないからな」
「セフレ?」
「俺はその、カオルに恋してるのかどうかわからないけど、でも、いい加減な気持ちでお前とこうなったんじゃないから」
何度か繰り返された台詞を、トモはまた僕に告げる。それは、トモの痛いほどの誠実だった。
僕は、トモに沈み込んで行く。欲しくて、欲しくて、何も考えられなくなって、その刹那、ひとつ屋根の下にいる桜子のことを、僕は完全に忘れた。
トモと、僕と、桜子の奇妙な同居生活が始まった。期間は約十日間。僕とトモがシアトルの両親のところへ行くまでの中途半端な時間。
家出して、行くあてのない桜子に部屋を提供する。そして、僕は桜子との関係になんらかの決着をつける。それがトモから出された条件だったが、僕にできることは、桜子がトモへの思いを整理する手助けをしてやること……くらいだろうか。
トモへの思い。桜子が、実は双子の兄であるトモを好きだという思い。大きな秘密を孕んで、同居生活は幕を開けた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

