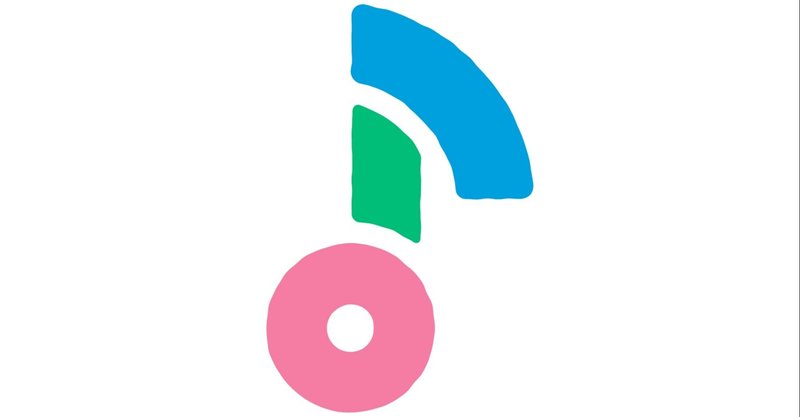
音声配信は現代版ソノシート、になる?
昭和40年代生まれの私にとって、ソノシートは身近な存在でした。
若い皆さんは、単語を聞いたことすらないかもしれませんね。
塩化ビニールなどを素材とした、ぴらっぴらに薄くて赤くてやわらかいレコード盤です。調べてみたところ、1958年(昭和33年)にフランスの出版社が雑誌に付けて「ソノラマ(音の出る雑誌という意味の造語)」として販売したのが始まりのようです。
当時は、レコードで音楽を聴く時代でしたから、同じプレーヤーを使えば、そのまま音が聞こえるソノシートは子ども向け雑誌の付録についていることもしばしばでした。なんなら、紙でつくる簡易プレーヤーも一緒についてきた号もあった気がします。
そして、自営の仕事に忙しい&教育熱心だった母は、2種類ほどのソノラマ(童話を朗読するタイプの)を定期購入して私にあたがってくれました。1社はひかりのくに・・・だったかな。もうひとつが思い出せません。ちょっとおしゃれな感じの装丁で、そっちのほうが好きだったのです。カソリック系の幼稚園ですすめられたものだったかも?
絵本を「読む」と同時に「聴く」も楽しめるのにワクワクし、暗誦できるくらいリピートしたものもありました。いつのまにか、カセットテープにとってかわり、CDになり・・・で、いまは音声配信 ですよね。
形あるもののほうがコレクター魂をくすぐるし、針を落とす瞬間になんかちょっと興奮する感じもよき!と思うのですが、親がかまってくれなくても、好きな話を好きなときに好きなだけ聴ける🎵という快楽は、音声配信でも提供できるよなぁ、と。
よく、国語ができない(とくに読解力がないという意味で)子の成績アップのために、本を読ませようとする保護者さんが多いのですが(私が勤めていた作文塾でも、どうしたら本を読むようになるかとか、どんな本を読ませたらいいかという相談は多かったのですが)、英語などの外国語がいきなり読めないのと同じで、聴いたことがなければ話せないし、話せないことを書けるわけがないし、そのプロセスを踏まずに楽しく読むなんて無理 と確信しています。つまり
聴く→話す→書く→読む
の順番が、スムーズではないかということです。
というわけで、これからAIと競争していくお子さんたちには、
音声配信を活用して、たくさんの本を聴いたり、いろんな大人の言い回しに触れたりして、読解力のベースとなる語彙を獲得してほしいなぁと願っております。
そういう番組、つくりたいんです。
よろしければ、サポートをお願いします! 記事の作成に必要な情報収集、noteのクリエイター支援プログラムにエントリーしている企画の活動などに充てさせていただきます。
