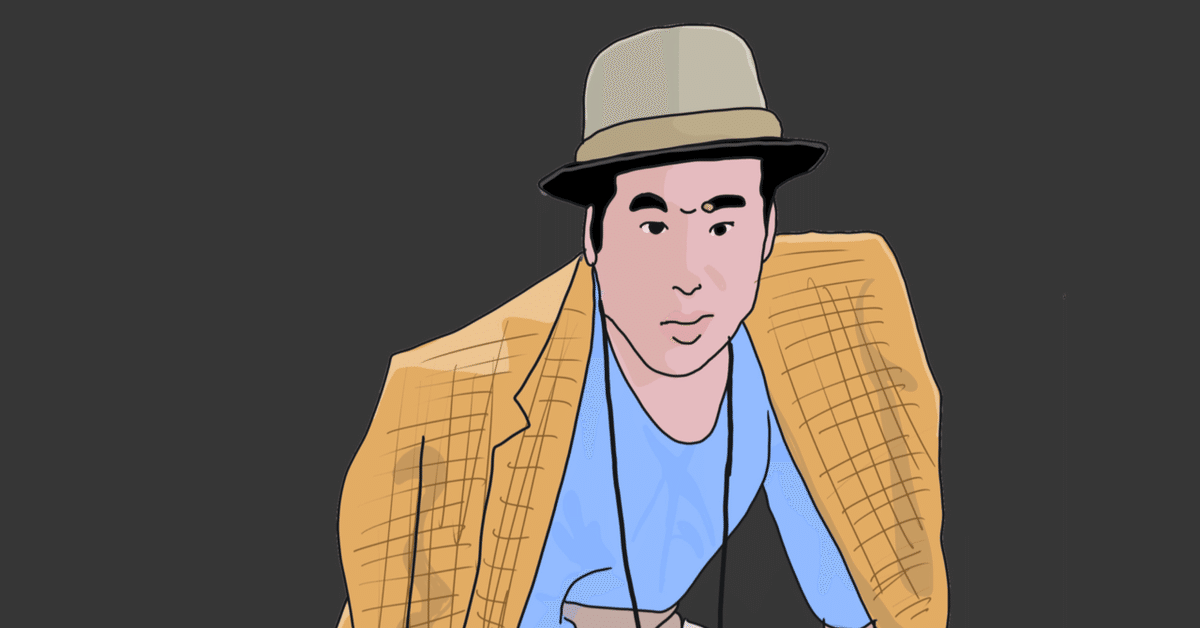
第2作「続・男はつらいよ」1969年松竹
「もし人違いだったらごめんなさいよ。もしや、あなたはお菊さんとは申しませんか。」
映画冒頭の寅のセリフですね。
「お菊さん」というのは、寅の実母の名前。
設定としては、寅の父親が、葛飾の芸者に産ませたのが寅ということになります。従って、妹さくらとは腹ちがい。
その母親と寅の再会が、この続編の重要なテーマとなります。
冒頭のシーンは、寅の旅先での夢なのですが、そこで、「あなたは38年前に、玉のような赤ん坊を産みませんでしたか❓」というセリフが出てきますので、前作で疑問だった寅の年齢が判明。
この続編の時点で、車寅次郎は、38歳ということになりますね。
寅はフラリと柴又に帰ってきます。
さくらは、前作のラストで生まれたばかりの満男を抱いています。
しかし、長居は出来ないという寅。
引き止めるおいちゃん、おばちゃんに首を横に振って、柴又を去ろうとします。
ここで出るのが、シリーズのキラーフレーズ。
「それが、渡世人のつれえところよ。」
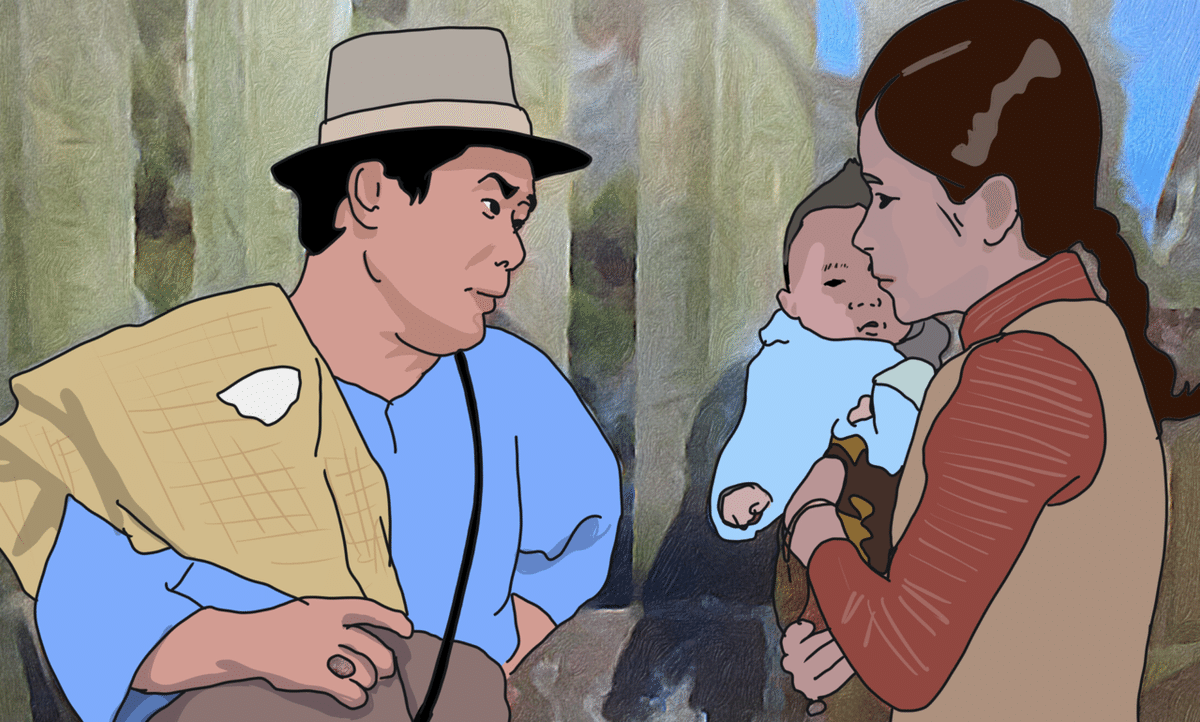
「行っちゃうの❓」というさくらをふり切って、昔懐かしい柴又を歩いていると、偶然にも小学校時代の恩師であった坪内散歩先生の家を発見。
懐かしさのあまり門をくぐり、恩師との再会を果たす寅次郎。
散歩先生を演じるのは、東野英治郎。
僕らの世代では、なんといってもテレビの「水戸黄門」で有名な人です。
この前年に放送されていたドラマ版のキャストをウィキしてみると、散歩先生は同じく東野英治郎が演じていますので、テレビ時代からのファンにはニンマリという設定なのでしょう。
そして、散歩先生の一人娘である夏子も、ドラマ版に引き続き佐藤オリエが演じています。
シリーズ2人目のマドンナですね。
あの主題歌で有名なドラマ「若者たち」の長女役の印象が強い方です。
ウィキによると、ドラマ「想い出にかわるまで」「愛という名のもとに」では主人公の母親を演じていると書いてありましたが、見ていたにもかかわらず、ちょっと印象には残っていません。
ドラマ版での役名は冬子でしたが、この名前は、前作の初代マドンナ光本幸子の役名とかぶるので、映画版では夏子という設定。
ちなみに、映画撮影時の東野の年齢が62歳。これは今の僕よりも年下ということになります。
還暦を超えても、こちらはなかなか、理想通りに老けられないので焦るばかり。
おいちゃんのセリフではありませんが、心の中で思うことは、「あーやだやだ。」
さて、散歩先生宅で、久しぶりご馳走を食べた寅は、胃痙攣を起こして病院へ。
ここで登場する医師藤村を演じるのが山崎努。
後に彼は、夏子と付き合うことになり、寅の恋敵となります。
ドラマ版の藤村は、バイオリニストという設定になっており、演じていたのは加藤剛。
ちなみに、本作での夏子の設定はチェロ奏者です。
病院に入院して、ここでもひと騒動起こしてしまう寅ですが、映画版では病院の院長である藤村に向かって放つのが、このシリーズ定番の寅の決め台詞。
「てめえ、さしずめインテリだな。」

山田監督によれば、これはもともと渥美清のアドリブだったとか。
脚本家が頭を捻っても、到底思いつけるフレーズではないと、監督は感心して、以降シリーズでは、大学での頭脳明晰キャラが登場するたびに、キラーフレーズとして頻繁に使われるようになります。
病院を抜け出して、舎弟の登といい調子で居酒屋でいっぱいやっていると、なんと2人の財布は空っぽ。
無銭飲食と暴力沙汰で警察にしょっ引かれてしまう寅の身柄を引き受けにくるのが妹さくら。
寅は、惨めさと恥ずかしさでいたたまれなくなって、旅に出てしまいます。
さて、一ヶ月後。
京都旅行中の散歩先生親娘と寅が、バッタリと遭遇するのが清水寺というのは、前作と同じ展開。(渡月橋だったかも)
宿泊先で、再び酒を酌み交わしますが、散歩先生は上機嫌。
「お前は人並み以上の体と、人並みに近い頭を持っておる。しかるに・・」
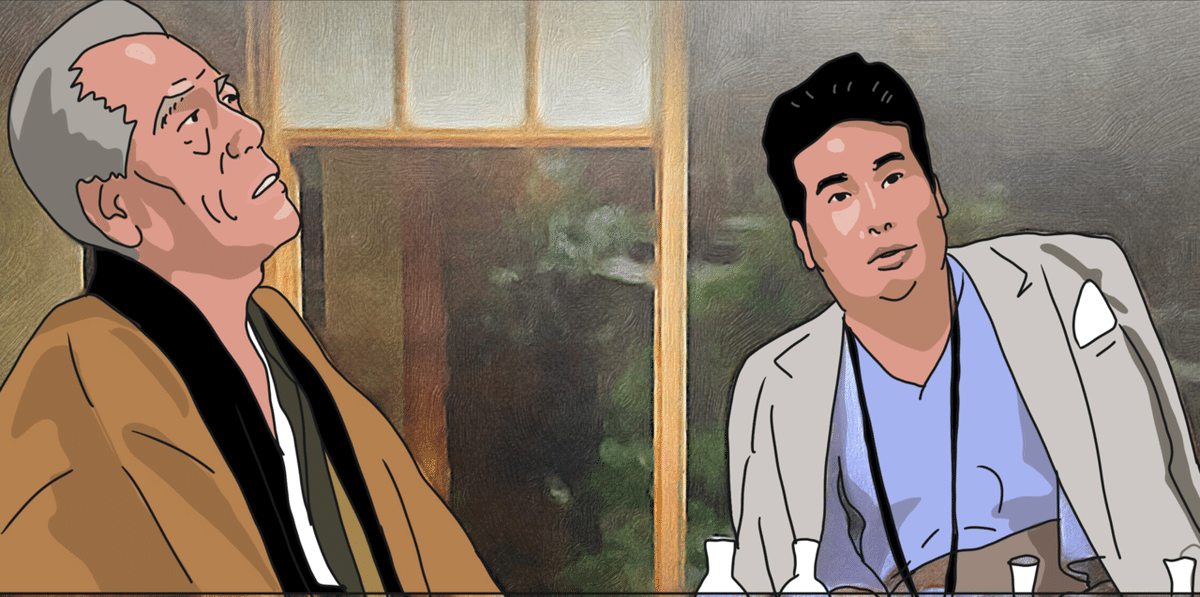
酔った勢いで、説教をされても、寅は嬉しくてしょうがない。
夏子もその様子を、嬉しそうに見守ります。
もちろん、寅はいつの間にか綺麗になっていた夏子に、とっくにホの字。
そのうち寅がポロリ。
「実は、京都には、おふくろがいるらしいんで・・」
それを聞いた散歩先生に尻を叩かれて、寅は夏子と一緒に、母親に会いに行くことになります。
寅の仲間が突き止めてくれた住所を頼りに、東山区の安井毘沙門町に向かうと、母親・菊は、女手一つで連れ込み旅館を経営していました。
菊を演じるのは、冒頭の夢で登場した風見章子かと思いきや、ケバケバしい衣装に身を包んだ関西喜劇界の大御所ミヤコ蝶々。
昔懐かしい大長寿番組「夫婦善哉」での関西弁全開の名司会ぶりは、僕の世代ではまだ記憶に鮮明です。
こういう大御所俳優が出てくると、どうしても撮影当時の年齢が気になってしまってウィキしてしまうのですが、1920年生まれのミヤコ蝶々は、このとき49歳。
これは逆に意外に若くてビックリです。
映画では、貫禄たっぷりでもっと年長に見えますが、渥美清との実年齢差は8歳しかありません。
しかし、映画の中で、並んで歩いても親子としてなんの違和感もありませんでしたね。
こういうあたりが、映画の面白いところです。
しかし、実際のミヤコ蝶々よろしく、寅の実母を演じる菊も、歯に衣を着せぬ辛口キャラ。
結局二人の心はすれ違い口論したまま決別。
傷心の寅は、夏子に連れられて、とら屋に戻ります。
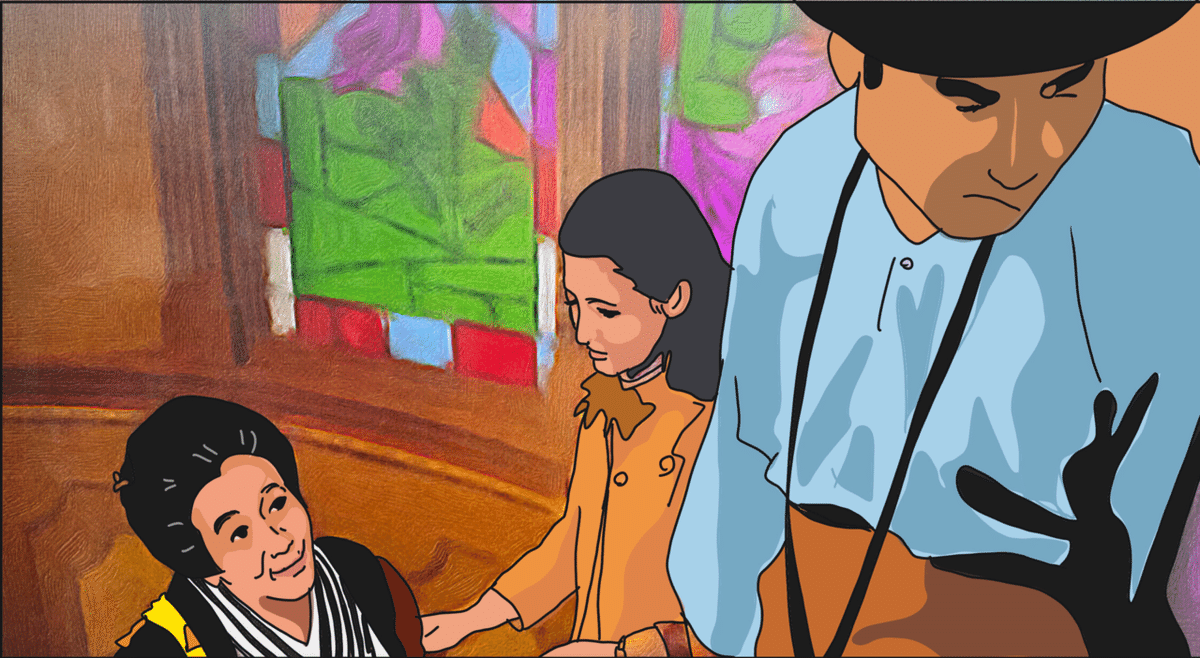
とら屋の面々は、絶対に母親の話題を出さないように相談して寅を迎えますが、テレビからは、あのコマーシャル。
「おかあさーん。」
これ、子供の頃はテレビっ子だったので、今でもよく覚えていたハナマルキ味噌のコマーシャルなのですが、やはり気になったのでググってみました。
商品名がその名の通り「おかあさん」。
昭和43年に、テレビコマーシャルとして全国のお茶の間に流れたモノクロのコマーシャルでした。
ですから、本作のタイミングとドンピシャリですね。
ずっと後になって、セルフオマージュ版として、芦田愛菜を起用したコマーシャルなども作られていましたから、根強い人気は今でも続いているようです。
寅さんシリーズは、時代の写し鏡という楽しみ方も出来るので、改めて見直すと結構いろいろな発見があります。
山田監督も、意識して、当時の風俗を積極的に画面に取り入れてくれているので、寅さんシリーズは昭和懐古映画としても大いに楽しめます。
ダイヤル式黒電話、チャンネル式のテレビ、五百円札、赤ポスト、さくらのミニスカート、参道のお菓子屋のお煎餅の入った瓶などなど。
昭和マニアには、この辺りはたまらないところです。
「ああ、あの頃はそうだったなあ。」という記憶を、昭和風俗変遷史としても追いかけて行けるのも、このシリーズの楽しみ方の一つでしょう。
夏子がある日とら屋に来て、散歩先生が寅に頼みたいことがあると言っていると伝えにきます。
散歩先生よりも、夏子に会えるのが嬉しい寅は、ルンルンと散歩邸に出向来ます。
そして、縁側で椅子に座りながら、散歩先生が寅次郎に依頼したのはなんと「江戸川の鰻」。
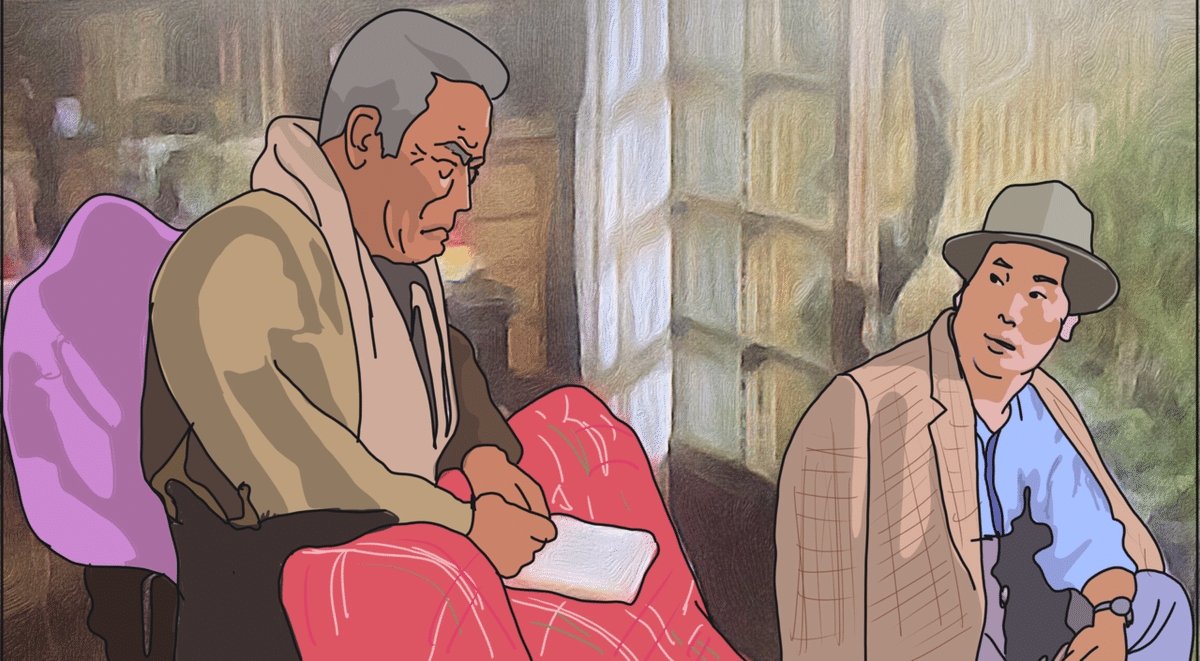
出前を頼めばいいじゃないかとブツブツ文句を言う寅ですが、お世話になった恩師の頼みをスルーするわけにもいきません。
汚れてしまった江戸川で、鰻がつけるわけがないとふてくされながらも、土手に座って釣り糸を垂れる寅。
様子を見に来たのが、とら屋の裏の印刷会社の社長。
ちょっと回りくどい言い方になりましたが、この時まで寅は、この社長に向かって、あのおなじみの「このタコっ❗️」という呼び方はまだ一度もしていません。
ただ、この時のやり取りの中で、「タコが釣れると思うかよ」なんてことを社長に向かって言っているという伏線がありましので、どこで「タコ社長」になるのかは、この後のお楽しみ。
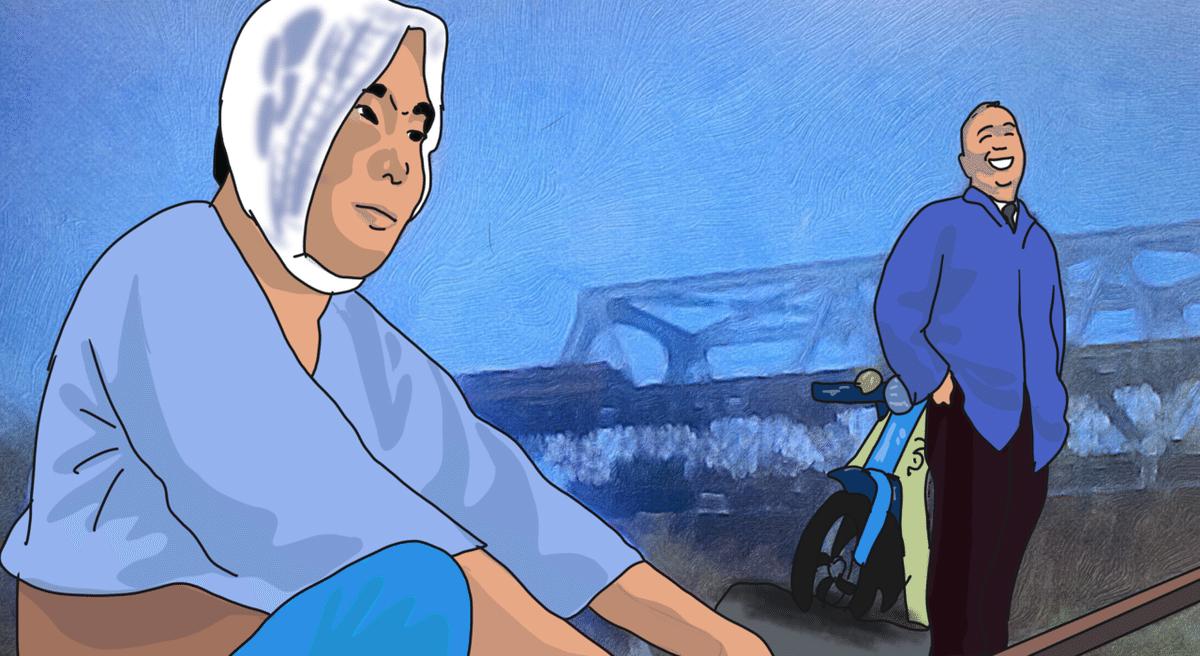
さて、釣れるわけがないと思っていた鰻を見事釣り上げた寅。
喜び勇んで、届けに行くと、散歩先生はなんと、頼んだ時と同じ姿で椅子に座ったまま息絶えています。思わず腰を抜かす寅次郎。
そのショックで、通夜の間も肩を落として悲しみに暮れる寅に、お経を上げにきた御前様が一喝。
これで目が覚めた寅は、翌日別人のように復活。朝の五時から、葬儀をテキパキと仕切り大奮闘。

そこに現れたのが、寅が胃痙攣で入院した時の病院の院長藤村。
実は、藤村と夏子は、あれ以降、しっかりと愛を育んでいたんですね。
しかし、そうとは知らない寅は、別室で藤村の胸に泣きながら顔を埋める夏子の姿を見てしまいます。
そして、出棺の葬列に遅れて乗り込んだ寅の霊柩車には、神妙に並んで座る夏子と藤村が・・・

かくして、寅のシリーズ二回目の失恋が、ここに悲しくも成立。
失意の寅は、また旅に出ます。
それから、しばらくして、とら屋にはカタギになった登が訪ねてきます。
そこにかぶさるのが、夏子のモノローグ。
結婚式を挙げた藤村と夏子は、新婚旅行で関西へ。
そして二人は、訪れた京都で意外な光景を見かけることになります。
それは、なんとあのとき喧嘩別れをしたはずの寅と実母菊が、三条大橋の上を楽しそうに並んで歩いて行く姿でした。
「声をかけなくてもいいのか❓」と夏子を促す藤村でしたが、夏子は黙って2人を見送ります。
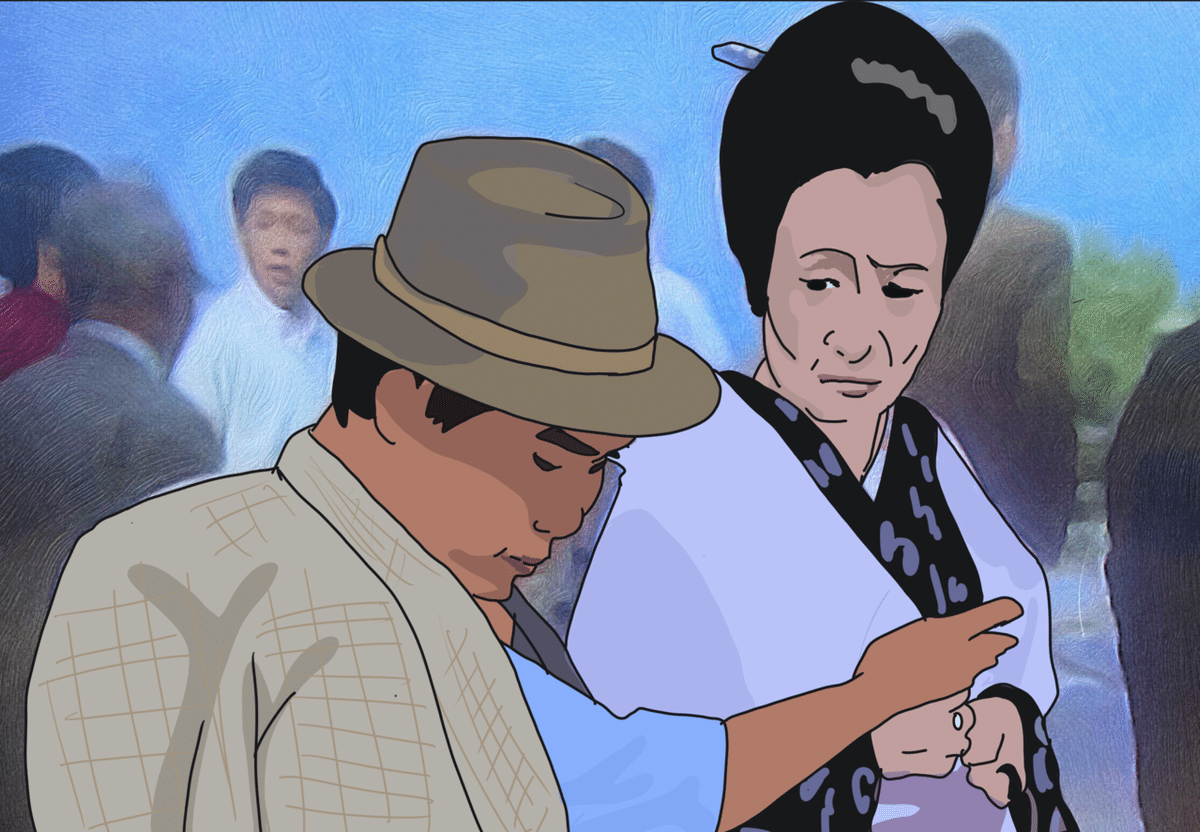
というわけで、第二作目は、「寅次郎瞼の母」編でした。
人気番組だったドラマ編の設定をまだかなり踏襲したシナリオですが、のちのシリーズの原型になる定番フォーマットは、ほぼ出揃った印象です。
「結構毛だらけ猫灰だらけ。お尻の周りはクソだらけ」
「見上げたもんだよ屋根屋のふんどし、たいしたもんだよ蛙の小便」
寅さんの常套句も何度か登場。
啖呵売も冴え渡ります。
本作でのバイは、主に占いの本が中心。
どのシーンでも、サクラ役で源公(佐藤蛾次郎)がアシスト。
帝釈天の寺男だったはずが、本作では登の代わりに、とら屋で働いていたりと登場シーンが激増していました。
本作では、ほぼ寅の舎弟になってしまっている設定でしたが、その辺りの説明は特になし。
寅に青あざを作られながらも、「あにき〜」と追いかけ回していました。
前作の大ヒットを受け、本作の監督も山田洋次が引き受けていますが、自分が監督をするのは、本作までと決めていたそうです。
さて、そんなわけで、
山田洋次が監督を下りることになる次回第3作目は「男はつらいよ フーテンの寅」❗️
監督変わったら、面白くなるかも❓
いやいや・・
「それを言っちゃあ、おしめえよ。」
(ちなみに、この台詞はまだ、登場していませんが)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
