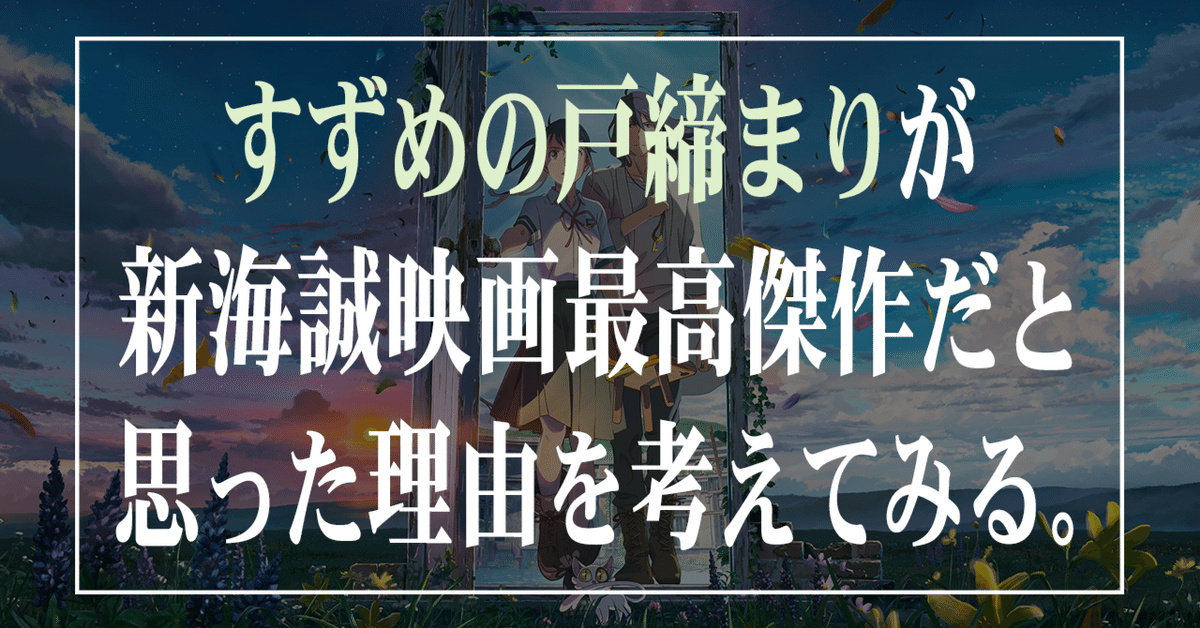
【ネタバレ注意】『すずめの戸締まり』が深海誠映画で最高傑作だと感じた理由を心を抉って(えぐって)考えてみる。
吾輩は猫を被ったニンゲンである。名前はぽん乃助という。
上映後すぐに見れなかった『すずめの戸締まり』を、2023年に入ってからやっと見ることができた。
結論、凄い作品だった。
すかさず、3回も映画館に観に行ってしまったくらい凄い。新海誠映画の中で、個人的には非の打ちどころのない最高傑作だと思った…が、ネットレビューは賛否両論だったので、とても意外に感じた。
その意味では、たぶん自分の感性が世間とズレている部分もあると思うので、自分の心を抉り(えぐり)ながら、最高傑作だと感じた理由を考えていくことにする。
私が好きな映画は、見終わった後に「誰かに話したくなる映画」「また観に行きたくなる映画」である。いわゆる、ニンゲンたちの中では『余韻』という言葉に集約される感覚なのであろう。
深海誠映画は、これまで、自分の中では「1回観ればいいや」という作品が多かった。でも、今回は違った。
多分それは、大衆のエンタメ映画で、「東日本大震災」を直接的かつリアルに描いたということが、理由として大きいのではないかと思う。これまで、国民の多くが観るエンタメ作品で、実際に起きた自然災害をメタファー(隠喩)として描くものは多かったものの、直接的表現で描くものは、ほぼ無かったのではないだろうか。

新海誠映画が爆発的に売れたきっかけとなった「君の名は」以降、「天気の子」「すずめの戸締まり」が制作されたわけだが、この3作は災害をテーマとしていることから、ディザスター3部作とも呼ばれている。
おそらく、新海誠も意識しているのだと思うが、この3部作を通じて、災害の心理的回復プロセスを彷彿した。
① 英雄期・・・災害当初、自分と家族、近隣の人々のために誰もが必死になる時期(災害直後)
②ハネムーン期・・・劇的な体験を生き延びた人々が助け合い、連帯のムードに包まれる時期(1週間〜6カ月)
③幻滅期・・・避難生活の疲れなどから不満が噴出し、怒りの感情などが表面化し、住民同士のトラブルなどが目立ち始める時期(2カ月〜1、2年)
④再建期・・・被災地に「日常」が戻り始め、生活の建て直しが進んでいく一方で、復興ムードから取り残される人々や、精神的な支えを失った人々の問題がくすぶり続ける(数年間)
『災害と心のケア ハンドブック』アスク・ヒューマン・ケア
「すずめの戸締まり」は、「君の名は」と「天気の子」と異なり、実際の大災害(東日本大震災)が既に起きた前提として、描かれる映画であった。
そして、「すずめの戸締まり」の主人公(すずめ)は、震災被害者で親を亡くしており、心の中に蓋で封じ込めていた過去のトラウマを、旅をしながら、向き合っていくことが一つのテーマであった。

これはまさに、上記の心理的回復プロセスでは、「再建期」にあたるものである。
リアルの世界で東日本大震災から10年が経ったこともあり、映画として、このテーマを選んだのだと考えられる。逆に言えば、これまでは被災者感情を踏まえてエンタメ作品では取り上げられなかったテーマであったが、10年経ってはじめて取り上げられるようになったと、言い換えたほうが良いかもしれない。
作中では、今後高い確率で発生すると予測されている首都直下地震が、実際に起きてしまったらどうなのだろう…と、身の毛がよだつほどに、恐怖心が煽られるシーンもあった。
地震調査研究推進本部地震調査委員会では、首都直下地震で想定されるマグニチュード7程度の地震の30年以内の発生確率は、70%程度(2020年1月24日時点)と予測している。
また、日本のどこにいようと、大地震が起きてもおかしくないというメッセージも、この映画では伝えたかったのではないかと思う。実際に、甚大な被害をもたらした2016年の熊本地震は、発生する確率が高いとは言われていない中で発生した。
そう考えると、私たちの誰もが、自然災害とは無縁でいられないはずだ。でも、この映画を見ていると、「あなたの心の中では、これまで発生した自然災害(東日本大震災など)が単なる過去の出来事になっていないか?」という問いを、真正面から突きつけられたように思えた。
「東日本大震災」は多くの人の命を奪った災害であった。それと同時に、原子力発電所の問題をはじめとして、「誰の責任なのか?」ということも強く問われたのが、この災害の特徴であった。
この災害を会話の中に触れるには、「被災者感情」が伴う。そして、「責任」が伴う。なので、当事者や専門家以外にとっては触れづらく、一種の禁忌のようなテーマになっていたのではないかと思う。
私だって、いつ被災してもおかしくない。でも、震災について会話の中で触れることを、どことなく恐れていたのかもしれない。心の奥底で「過去の出来事」として、整理してしまっていたのかもしれない。
そうした罪悪感にも自責感にも近いような気持ちが、この映画を見終わった後、泡のように頭に湧き上がる感覚もあった。
きっと、国民的なエンタメ映画で、東日本大震災を直接的にテーマにするのは、とても勇気が要ることであっただろう。そして、角が立たないような表現になるように、何度も作り直したシーンがあったに違いない。
「すずめの戸締まり」の上映後、映画館の中では「地震のこと、もっと考えなきゃね」という声もあった。私はこの声を聴いて、被災者でない人にとっても、この作品を通じ、過去の自然災害(東日本大震災など)やこれから発生しうる自然災害を、会話の中で触れやすくなったという意味で、社会的意義のある映画だと感じた。
また、全員が全員ではないと思うが、被災者であっても、この映画は見ることができる内容となっているという話を聞いた。この作品を作り上げるにあたって、取材を重ねた結果なのだろう。

こうした重いテーマが基軸なのにも関わらず、それを感じさせないエンタメ作品として成立しているのが、この「すずめの戸締まり」である。
上映中、笑ってしまうシーンもあり、泣いてしまうシーンもあった。深いことを考えすぎなくても、最後にはカタルシスがあり、見終わった後に心が澄んだ。そして、「誰かに話したくなる」「また観に行きたくなる」というような意味深なシーンも、随所に散りばめられていた。
この「すずめの戸締まり」には、震災をリアルに描くただならぬ覚悟と、とどまらないエンタメ性の進化を感じた。
これが、私が新海誠映画の中で最高傑作だと思った理由である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
