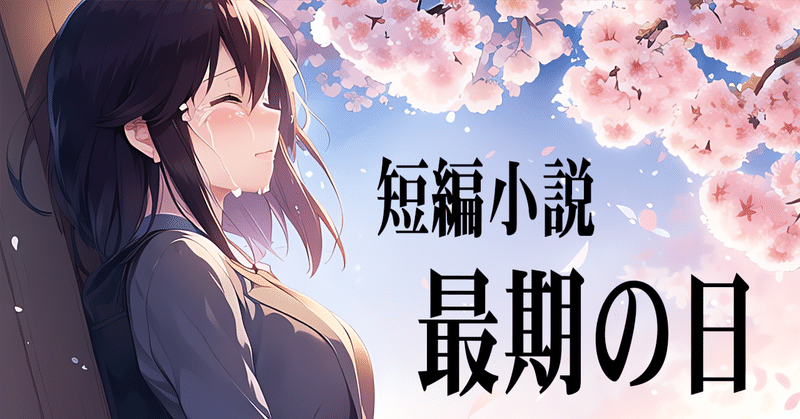
【短編小説】最期の日
僕は今日で、終わりを迎えることになる。
この街の桜は綺麗だけど、散り際がとても悲しい。
そんな言葉は、嫌になるほど、何回も聞いてきた。
でも、いざ自分が終わるとなって、やっと分かった。
散り際は、悲しいということを。
◇
僕が住む街は、かつては活気があった。
人の笑い声が聞こえたり、悲しむ声が聞こえたり、人々の喜怒哀楽を感じることができた。
人が集まる場所には、色んな声が集まる。
「今度、花火見に行こうよ!」
「一緒にあそこで飲んだコーヒーが懐かしいね。」
「お付き合いはここでやめたいと思ってる。」
そんな、男女関係のドラマの一端を味わえる台詞が聞こえることがある。
かと思えば…
「うちの生命保険に入ることであなたは一生分の安心が持てる。」
「この商品を広めたらあなたはとても儲かるわ。」
「信仰することであなたは幸せになれるの。」
そんな、相手を信じ込ませようとする台詞も聞こえることもある。
人の声だけじゃない。ハイヒールで床が響く音、フォークが皿にあたって響く音、ストローで氷を混ぜる音。
音だけじゃない。人の汗の匂いだって、タバコの煙の匂いだって、漂うこともある。
そんな些細な音や匂いに、嫌な顔をしたくなることもあったけど、今は思い出すだけで愛おしく感じる。
でも、都会に人が集まるようになり、この街は寂れていった。
僕は人の声や音、匂いを食べていくうちに、気づけば体がボロボロになっていた。
だけど、僕にはずっと、寄り添ってくれた女性がいた。
その人は、今日までずっと、僕の体を拭いてくれた。
意思疎通なんてできないのに、僕に話しかけてくれることもあった。
いまはただ、その人に感謝を伝えたい。
伝えられないけど、伝えたい。
もう、僕は最期だ。だから、心の中で叫ぼう。
(今までありがとう、さよなら!)
◇
私は喫茶店をずっと経営して、生きてきた。
私の父親が遺した喫茶店だ。
私に物心が宿った頃には、親という親は父しか知らなかった。
ずっと父のことは嫌いだった。でも、このお店はとても好きだった。
私は大学を卒業後、このお店を継ぐことを考えていた。
だけど、父は早くに死んでしまい、大学の卒業はかなわず、このお店を継いだ。
タイミングが悪すぎる。やっぱり父は嫌いだ。
でも、喫茶店を経営してまもなく、父はこの街の雰囲気を守りたかったのだとわかった。
父は嫌いだけど、父が大事にしてきたものは好きだし、守りたい。
その一心で、ずっと喫茶店を経営してきた。
だけど、喫茶店とともに生きていくには、もうこの街に人が居なさすぎる。
父も私も大事にしてきた、この街と決別する時がきたと思った。
そして、今日はこの喫茶店が最期の日。私はこの街から旅立つ日。
私は喫茶店のほうを向いて、一礼した。そして、喫茶店を背に歩き始めた。
この年になってから、新しい街で住むのは不安がいっぱいだ。
踏み慣れたこの街の地を、噛み締めるようにゆっくりと歩いていると、私の後ろから声が聞こえた気がした。
「今までありがとう、さよなら!」
後ろを振り向いても、寂れたこの街に不意に叫ぶ人なんているわけもなく、そこには壊れかけの喫茶店しかなかった。
私は郷愁を感じて、かつての賑わっていた街並みを思い出した。
ふふっ。
なぜだか、笑顔が溢れる。それと同時に、目から涙が溢れる。
「私こそ、ありがとう!」
誰に話しかけるわけでもなく、私はそう叫んだ。
風が吹き、この街に桜の花びらが舞い散った。
明日もまた、強く生きていこうと思った。

【あとがき】
私が住む近くのお気に入りの喫茶店が、閉店することになりました。
閉店になると聞き、私はその喫茶店のカウンター席に座りながら、複雑な気持ちを感じていました。
この複雑な気持ちはなんなのだろう…と考えつつ、筆を走らせたというのが、この短編小説となります。
終わりは悲しい。だけど、新たな始まりの予感もする。
そんな気持ちが、コーヒーの香ばしい匂いとともに、私の心を駆け巡っていったような気がします。
さて、最後に告知になりますが、「眠れない夜に寝ながら聴ける」ことをコンセプトとしたYouTubeラジオをはじめました。
先日、第5夜となるラジオをアップしましたので、気になる方はぜひ、ご視聴いただければと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
