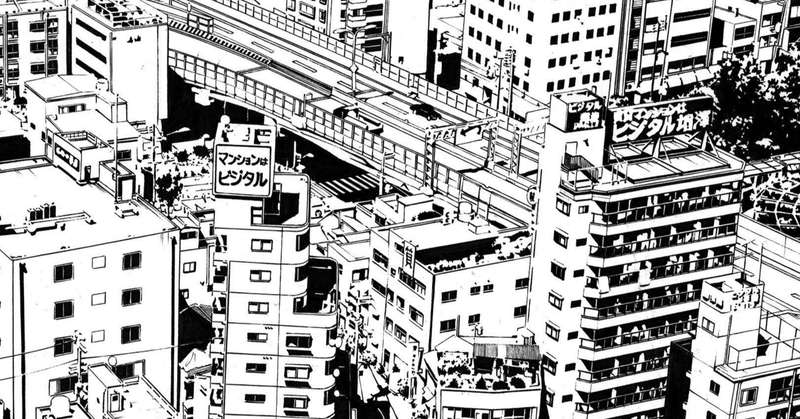
小説「青き獣を野に放て」最終章最終話
平成3年川崎警察署襲撃事件顛末
概要
随分前に大阪の西成区で、暴力団から警察署長が賄賂を受け取っていたとして、町の浮浪者や日雇労働者達か警察署を囲む暴動があった。
これを人に話すと大概の人は覚えていないと言う。
時に、残酷としか言い様のない事件も蓋を開けてみれば、偶発的な事で転がるように凄惨な結果になってしまったとい事がある。
そしてまた忘れられる。
ならばそんな事があったと昔話の様に都会の寓話を話してみよう。
平成3年に起きた川崎警察署襲撃事件をもとに川崎の若者の物語を了、勇、秋雪の3人の言葉で寓話的に描く。
登場人物
了(21才)
身長2mの大男、横浜から川崎に流れてきた。素手で人を殴り殺せる。
勇や秋雪は了の事を話す時、「あいつ」といい、名前で呼ばれない。
勇〈23才)
川崎で会長と言われる父親を持ち、その父親を殺す。
同時期に了と出会い、徐々に自分自身も会長と言われる存在になっていくが、本当は勇の中に作られた別人格で、本当の「勇」を引きずり出す為に、自分の胸に拳銃を当てて引き金を引いた。
秋雪(20才)
偶然、署長の息子に関わってしまい、街のクズの様なフリをする署長の息子のせいで、偶発的に南ちゃんという女の子を拉致してしまい。その後、人生が崩壊する。
ジヤン・ケン・ポン
母親が中国人の三つ子の兄弟、年齢は14.5歳だと思うが自分達ですらよくわかっていない。
夜光のクズだったが、了に拾われて行動を共にする。
先輩
若い暴力団の構成員
夜光のクズ達からそう呼ばれていて、そのまま了や勇もそう呼んでいる。
署長の息子
警察署長の息子
街のクズの真似事をし、出会ったばかりの秋雪を巻き込み、南ちゃんを拉致した張本人、
南ちゃんのお兄さん
南ちゃんのお兄さんで坊主
おじさん
勇がおじさんと呼ぶ養豚場の主、勇が父親の様に養豚場経営から始める事を見越して、自分の持つ養豚場を勇に譲る。
右手がC型の義手。
南ちゃん
署長の息子と秋雪に偶発的に拉致され、夜光のクズが集まるステージで殺される。
用語
会長
元々は勇の父親の事であった。暴力団すら恐れるその存在は川崎が昭和重工業都市となる上で必要な存在だった。勇の父親が死んだ今、それは亡霊の様に町の住人の脳裏にこびりつき、その亡霊を暴力団が利用しようとする。
クズ
街のチンピラや不良を川崎ではクズと言った。
その中でも夜光という町外れの団地に住むやつらを夜光のクズと呼び、どうしようもない奴らの集まりの代名詞の様に呼ばれる。
夜光の団地
団地に入るには線路の高架下を抜ける道一本しかなく、川崎の中でもより貧しかったり、行き場の無いものが住み、住人の半数は外国人労働者
ステージ
夜光の団地にあるスーパーマーケットの廃墟、
ここに夜光のクズはいつもたむろしている。
これまでのあらすじ
1章 勇と了と秋雪
昭和の終わり、重工業産業で発展した川崎はあふれる労働者とそれに群がる暴力団の街だった。
了は15才で川崎に流れてきた。
了はこの街の全てに君臨する「会長」の息子の勇に出会う。了に出会う事によって勇は会長である父親を殺す。しかしその事によって勇は「会長の息子」という身分も失い、着の身着のまま街に放り出される。了は勇を自らの手でこの街の会長にするために寝食を共にし、会長が最初にやった事業だという養豚場経営をはじめる。
2章 2年後
養豚場で生活をする勇と了、「おじさん」の手助けを受けながらも経営は順調だったが、勇にも了にもこのままでいいのかという疑問はあった。ある日、了は、週末にひとり街に戻るようになる。
同じころ秋雪という若者が「警察署長の息子」と出会い「南ちゃん」という中学生の女の子を車で拉致してしまうというトラブルに巻き込まれる。
「警察署長の息子」は南ちゃんの始末を「夜光のクズ」に頼もうとするが、そこに暴力団が関わろうとすることで秋雪の運命が変わる。
同じころ了も夜光のクズとトラブルを起こし、2つの出来事の運命がリンクしだす。
秋雪は夜行のクズと南ちゃんを集団レイプし、その事を勇に知られて、勇は了と共にレイプした夜行のクズの睾丸を抜き、街から放逐する。
そして暴力団や警察をも巻き込んで、勇は自分自身と決着をつけるために、全てを打ち壊す。
最終章 半年後
夜光のステージでクズや暴力団、警察をも巻き込んだ騒動の中、了と秋雪はジャンケンポン兄弟に連れられて、人工島の奥へ奥へと入り込み、製鉄所のコークス山でコークスを均す仕事をしていた。
こんな事をしていても埒があかないと、全てをあきらめ、もう、街に戻るという秋雪を連れ、了は夜光のステージに戻る。そこに先輩が現れ、よそ者は消えろと了に言い放つ。
最終話 「平成3年11月13日(土)」
◆ 了 21歳
〈親分〉は、川崎大師の竹林の向いの大きな一軒家に住んでいた。
切れ目の無い塀は高く、中は皆目、観えなかった。
大きなシャッターの横に、腰を屈めて入るような鉄のドアが一か所だけあった。
ドアは位置が低すぎて蹴破ろうにも、力が入らなそうだった。
「無理かあ…」と呟いたら、ジャンケンポン達が、「任せとけ」と、どこかへ消えた。
三兄弟は2度目の粉塵爆破で全員が眉と髪を燃やして、ますます見分けのつかない顏になった。
戻ってこない間、秋雪と待っていた。
親分の家から離れて、同じような壁の色の軒並みの間の、小さな公園に入った。
震える秋雪を、梢の隙間から零れる陽だまりの地面に座らせた。
特に話す事も無かったが、無言の時間も別に気にならなかった。
ふたり、黙って、30分を過ぎた頃、秋雪が紫色の唇を動かして、ボソボソと話し掛けてきた。
「あんた、名前」
「名前?」
「そうだよ。名前、知らないんだよ」
「お前もか…」
「ええ?」
「いや、俺が悪い。俺、こういうところあるから」
三兄弟の姉ちゃんが、あんたの周りは大変だ、と言った言葉が過った。
「名前は了だ」
「了、ああ、今覚えた。はは…」
秋雪は小さく笑った。
「なぜ笑ったんだ?」
「いや、あんたの名前を聞いて、それを、自分の口で言って、その名前の持ち主があんたなんだなって思ったら、急に、いろいろと特別の事のように思っていた事とか、ばかばかしくなって…いや、笑ったのは失礼だったね、ごめん」
「いや、いいんだ。気にするな。笑ったことが単純に不思議だったんだ」
「なあ、了、暴力団の親分の家の前で、何をしようとしてたんだい?」
秋雪の唇は青かった。
「署長の息子がどこにいるのかを、親分に聞いてみようと思って」
「それ、お前…もう直接、署長に聞けばいいじゃないか」
「馬鹿」
「馬鹿はお前だよ。お前が町をうろうろしていて警察に見つかれば、必ず捕まえようとするし、署長だって自分の息子が殺されると気付けば、どこかに隠すだろう?それに、もうこの街には居ないかもしれない」
秋雪の唇は青かった。
「秋雪、約束だよ」
「約束?」
秋雪は何かに気付いたように、俺を見上げてきた。
お前、やっと、気付いたのか。
「秋雪、約束を果たすのは、約束を受けた側だ、受けたのは会長だ」
秋雪はにじるように俺の体に張り付いてきた。
「そうだ、おお、そうだ。分るぞ、俺にも分るぞ」
秋雪の唇が赤く戻ってきた。座っていたのが良くなかったのかもしれない。
「署長の息子を殺すのは俺だ。そうだ。何故だ、何故、忘れていたのか。署長の息子は生きている。この街のどこかで、生きて待っているんだ、俺に殺されるのを!」
「そうだ、お前がやるんだ。今ある全てが、お前の為にあるんだ。いいじゃないか、お前はこの街の若者だ。その権利がある。いいじゃないか、それが会長とお前の繫がりだ」
「なぜ、今頃、俺は…」
ずっと同じ事を秋雪に俺は言ってきた。
「お前がこの街の若者の全てに伝えるんだ、約束は守られる」
俺の腕にもたれる秋雪を見ず、公園の前の道が途切れる先に目線を置いた。
霞む軒並を挟む道路に、重そうに何かをぶら下げた3つの人影が現れた。
ジャンケンポン。
三兄弟は持てるだけの炭酸ジュースのペットボトルを買って来た。
大きさは様々で、50本はあった。
「塀の中にどんどん投げて、爆発させるから、中の人が、コラーって、慌てて出てきたら、その時、中に入りなよ、ボス」
「そんな簡単に爆発するのかよ」
「しねえよ。これを入れるんだよ」
白い碁石の様なものを一つ、左掌に握らされ、訳が分らずそれを眺めていた。
三兄弟は、同じものを口に入れた後、笑いながら、眉の無い眉間をしかめて鼻の穴を広げた。
釣られて、掌のものを口に入れて、奥歯で挟んだ途端、辛い風が口の中に起こって、鼻から逆に抜けていった。
「ハッカだ」
秋雪に向いて言った。
秋雪はハッカを手に取り、一粒を口に入れ、一粒をペットボトルの中に入れた後、ボトルキャップを閉めた。
「ミントって言うんだよ」
そう言って公園の端にボトルを投げた。
ボトルは地面に着くとき、ボンボンボンと音を発てて丸く膨らんだ後、飛び散るように破裂した。
「お前ら、本当にクズだなあ」
秋雪は呆れていた。
「意外と、音が派手だろう?」
三兄弟は楽しそうだった。
「行こう」
秋雪を公園に置いて、また、同じ道を戻った。
ジャンケンポン達が言うように親分の家には簡単に入れた。
顏ばかりが厳しい大人が10人程居たが、どれも1発で斃した。
鉄の右手を試すのに丁度良かった。
静かになった広い家の中を、親分を探してあちこちを見て回った。
暗く広い駐車場には白い高級車が停まっていた。
ナンバーは〝1750〟となっていた。
居ないのかなと思ったころに、ジャンケンポン達が、こっち、こっちと親分が居る部屋に連れて行ってくれた。
ドアを開けると、縦横が分らない程の大きなベッドが真ん中に置いてあり、ベッドの中に若い女がひとり、座っていた。
開いたドアの前で、目線を左に動かした時、右から脇腹に固い物を押し付けられた。
拳銃だろうと思った。
「何なんだよ!おめえ!」
親分の声だった。
両手で拳銃を持った親分が銃口を脇腹に当てていた。
さすがに脇腹に弾丸を貰ったら、たまったもんじゃないと思ったが、中々撃たない。
そんなものを持っている事で、自分のほうが有利だと思っているのか。
1秒も満たない時間だが、馬鹿だなあと思った。
「すいません」
よく分らない事を言った。
親分も、よく分らないという顏をした。
言いながら真後ろに倒れ、倒れながら長めの右の鉄拳を、半円を描く様に振り下げた。
拳は親分の脳天に当り、くぐもった音を発てた。
重力に抗わず大の字に倒れた後、首を縦に振って上半身を起こした。
傍で、脳天を抑えた親分が悶絶して転がっている。
ジャンケンポン達が、座っている俺の横をすり抜け、一目散に女に向かっていった。
女は初めて悲鳴を上げた。
ベッドにはジャンケンポンの3人と女が沈んでいた。
飢えた犬の様に群がる三兄弟達に、女は「判った、判った、やらせるから」と言いながら押し退けていた。
肩越しにその情景を掴んだ後、目線を自分の正面に戻した。
左手で親分の胸倉を掴んで壁に押し付け、脚の爪先を宙に浮かせている。
「おおい!おいっ!おおおい!」
親分は誰かを呼ぼうとしたり、俺を見下げて怒鳴ったりしていた。
「誰も来ませんよ」
「何なんだよ!」
最初と同じ事を言った。
持ち上げられ、俺を見下げている眼は怯えたクズにソックリだった。
「署長の息子はどこですか?」
敬語なんか使わなくてもよかったが、さっき、「すいません」と言った流れで慇懃な言い回しになった。
「俺には関係無いだろう!」
「知っているんでしょう?教えてください」
「だから、関係ないだろう!」
敬語、やめた。
「おい、暴力団…」
こんな奴と6つも7つも、言葉を交わすのは煩わしい。
大人は本当に馬鹿だ。
何度見せ付ければ分るのか。
そうか、何度でも分るように教えなければならないのか。
俺が動く。
会長は分っていたんだ。
あの日、会長は、どうせお前が台無しにすると言った。
そう言われたら、何だか申し訳ないなあと思っていたが、そう言っただけで、そういう俺にも役割をくれていたんだ。
俺はただ動けばいい。
「会長はどこだ?」
「そんな事も知らないのか」
「ああ、知らない」
持ち上げる左手を軽く捻った。
親分は咽喉から変な音を鳴らしながら、「…北部病院」と言った。
試験場に行く途中にある病院だ。
きっと会長がいるところに署長の息子もいる。
親分を床に降ろした。
尻持ちをついて咳き込む眼の前の中年に、立つように促した。
目線も合わせずわざとらしく咳き込み、膝を庇って立ち上がった。
「脚が悪いんだよ」
言い終わらせて、鉄の拳を真正面から顔面にくれてやった。
親分は、紐で引かれる様に後頭部から壁にぶつかり、床に崩れた。
こいつは、さっきの会話で、俺が署長の息子の居場所に気付いた事に、気付いた。
生かしておいても後々、面倒だ。
代りの大人は幾らでも居る。
生死を確かめる為に、転がる親分の前でしゃがんだ。
鼻が潰れた平な顔面から血泡を吹いていた。
臭いと思い、匂いを辿ると、赤い小便を零していた。
気が変わった。
生かしておいたほうがいいかもしれない。
良い見せしめだ。
〝もうひとりの大人〟を殺そう。
ベッドに振り向くと、三兄弟のうち2人は終わって、最後のやつがいそいそと服を脱いでいた。
「行くぞ、署長の息子の居場所が分かった」
裸になった一匹ジャンケンポンは「もう!」と大きなため息を出して、また服を着た。
「車、お前が運転しろ」
そう言って、笑い掛けてやった。
◇ 秋雪 二十歳
公園で、する事も無くしゃがんでいた。
左足の痛みが抜けた訳じゃないが、痛いままでいる事に慣れた。
何も考えず、霞んだ晩秋の空を見ていた。
もう、考えるのは止めた。
路面を噛むタイヤの音に、空に向けていた顎を下した。
公園の入り口に、長く白い車が停まっていた。
触っただけでも汚れそうな純白の車体は誰がどう見ても暴力団の車だ。
フルスモークのドアウインドウがサイドドアに吸い込まれ、人の顏が現れた。
車内の顔ぶれに溜息を吐いた。
「秋雪!」
焦げた眉毛の三兄弟がニヤニヤとこっちを見ていた。
暴力団の車に、いつもの5人が乗っている。
ジャンケンポンは前に2匹、後ろに一匹、俺と了に挟まれてリアシートに深々と埋まっている。
前のシートで、右側の奴がダッシュボードを開けて、タバコを見つけた。
左で運転している奴と何本かむしり取り合った後に、リアシートの俺達に投げてきた。
全員で煙を吐いた。
あっという間に車中は白く濁った。
了は、今日、やる事を言った。
「署長の息子は北部病院にいる、秋雪、北部病院、分るか?」
「ああ、分るよ」
「そうか、お前をそこに連れて行く、丁度、怪我もしている。病院の前で降ろすから、手当てを受けたら、探して殺せ。俺達はやる事がある」
「やる事?」
「ああ、署長を殺す」
「そうか…了、お前を不器用だと思った事もあるが、そうじゃなかった。器用、不器用っていうのは、相対的な考えだ。お前には必要ない」
存在が絶対だからだ。絶対者が何を好んで器用に振る舞うか。
「ああ、必要ない」
了は優しく同意してくれた。
「警察署でも襲うのか?」
「ああ」
ああ、そうだろう。
俺を病院に送り届けた後のついでの様に言う。
争いは同じレベルの者同士でしか発生しない。
一対五十だろうと、百だろうと、お前には関係ない。
ああ、そうだろう、只、真直ぐに進めばいい。
「俺に出来る事はないかい?」
「無い。ただ車がもう一台必要なんだ。出来ればトラックがいい、うちの豚舎に行って借りてくる」
「ああ、あそこ、今は誰が居るんだい?」
「分らない。多分…知り合いが見てくれていると思う、元々、その人がやっていた仕事だから」
「そうか」
突然、ガリガリと擦る音が車中に響いた。
左折でサイドドアを擦ったようだ。
「お前、危ねえ!」
助手席の奴が、運転している奴の頭を叩いた。
「左ハンドルなんだよ!分んだろ!感覚取り辛いんだよ」
憤然とハンドルを両手で握っていた。
「なあ、了、俺にも手伝わせてくれよ。車の運転なら俺にも出来る。俺を送った後のついでなら、前のついででもいいだろう?」
了は何も言わない。
三兄弟に声を掛けた。
「よう、お前ら免許あるのかよ」
誰も答えない。
「こんな状況で、そんなものが必要と言っているんじゃないんだ。そんな危ない運転で、北に行ったり、南に行ったりして、無事に着けるのかって言っているんだよ」
「どうした?秋雪、急に」
了はまたタバコに火を点けた。
「どうもしなよ。手伝いたいんだ。それだけさ」
「そうか…じゃあ頼む。軽トラックはマニュアル車だからこいつらじゃ無理だ」
「無理な事無えよ!」
運転している奴がムキになって叫んだ。
「シフトチェンジ出来るのかよ」
「出来るよ!左足、怪我しているだろ!お前こそ出来るのかよ!」
「シフトレバーのRって何の事か言ってみろ」
「あーる?」
明らかに知らない復唱だった。
「あーる」
「あーる」
他の兄弟も同じ事を言った途端に、3人で馬鹿笑いを始めた。
「うるさいっ!」
了が声を荒げた。
突然、どうしたんだろう?
三兄弟もしおらしく黙った。
「お前ら3人、区別がつかない。今日はちょっと不便だ。おいお前、名前は?」
了が運転席に声を掛けた。
「ポン」
そのまま〈ポン〉の隣に声を掛けた。
「お前は?」
「ケン」
「じゃあ、お前はジャンだな」
了は、隣に声を掛け、〈ジャン〉の頭を軽く叩いた。
「豚舎に行ったら、バリカンがある。秋雪に頼んで、髪を切れ。ジャン、お前はモヒカンだ。ケン、お前は三角、ポン、お前は坊主頭だ、分ったな」
一方的な押し付けに、三人はおどけるように下唇を突き出して、「ういーす」と言った。
髪型については何も文句を言わなかった。
途中で運転を代り、了に道を聞きながら、丘の上の豚舎に向かった。
丘に上がる坂道を、左カーブを描いて昇り切った。
縦長の車体は坂の途中で慎重にハンドルを切らないと、フロントバンパーを擦りそうだった。ポンの運転だったら、バンパーはもげていたかもしれない。
昇り切ると、豚舎やプレハブの小屋は随分と狭く感じた。
豚舎の前には、軽トラックが止まっていた。
最初に了が車のドアを開けると、家畜の堆肥の臭いが車内に入ってきて、落ち着いた豚鼻の音が聞こえた。
ジャンケンポン達も車外に出た。
「待っていろ」
そう言って、了はプレハブに向かった。
10分程して、戻ってきた。
手には電動バリカンを持っていた。
「電源は豚舎にもある。外でも中でも、どこででもやれ」
眉間の苛立ちがより増していた。
「了、どうした?」
「いや…居ないから」
「居ない?」
「豚が生きている。オジさんが居る筈なんだ」
「豚舎に居るんじゃないのか?」
「それなら、直ぐに出て来るだろう?」
「どうした?急に、そんなイライラして」
「ここをな、投げ出したのに、誰かがちゃんと見ていた。あんな無責任に突然消えたのに」
了は豚のざわめく音がするほうを見た。
「中に居るんじゃなのか?」
特に考えも無く、俺はそう言った。
「バリカン、プレハブの中でやるよ、来いよ」
三兄弟を連れて、プレハブに入った。
プレハブの中は雑然と物が散らかっていて、さっきまで誰かが使っていたといった風だった。
他人の家に勝手に入るような気まずさで思わず、「すいません」と声を掛けた。
返事は無かった。
「早くやろうぜ、ボスの機嫌が悪い」
確かに。
「ジャン、ケン、ポンで縦に並べ。髪型を間違えたら、俺までとばちりを貰いそうだ」
机の横にコンセントがあった。
スイッチがオンのままだったのか、プラグを刺した途端にボワンと音を発てて刃が動き出した。
3人を刈り上げるのに30分程掛った。
了は戻って来なかった。
「まだ、外に居るのかな。行こう」
3人を連れて外に出た。
了はまだ、豚舎の中に居るのか?
離れたところに立っていたから、豚舎の中は暗く見えなかった。
横に立っているモヒカン頭に声を掛けた。
「ジャン、見て来いよ」
「俺、ポンだぜ」
は?
「はあっ!?」
頭が真っ白になった。
モヒカンは笑った。
「嘘、ジャンだよ」
三兄弟は意地悪く哂った。
「馬鹿!そういう冗談はよせ。ああ、もういいや、ポン、お前も行ってこい」
こいつらはどんな状況でもこういう奴等だ。溜息しか出ない。
モヒカンと坊主頭が豚舎の中に消えた。
ケンは、自分の三角の髪形を触っている。
「嫌か?」
俺もケンの頭を触ってみた。素直に触らせてくれる。
「別に」
それ以上は言わない。本当に気にしていないんだろう。
「なあ、お前ら、了に付いていくのか?」
「ああ、俺達のボスだからな」
「お前らだってこの街で生まれたんだろう?」
「んん?」
「いや…街が嫌いか?」
「別に考えた事もない。街を出ちゃ駄目なのか?」
「駄目じゃないさ、いや、もうやめよう」
何の事だと言わんばかりにケンは首を傾げた。
もう、考えるのは止めよう、公園でそう決めたじゃないか。
俺のやっている事が矛盾だらけなのは分っていた事だ。
矛盾の出口はそこに無い。
在るのは事が起こり、終わる。
それだけだ。
「羯帝羯帝波羅羯帝波羅僧羯帝菩提僧莎訶 」
脈絡も無く呟いた。
なぜ声にしたのかも、自分で分らなかった。
ただ、呟いた事で南ちゃんの顔が、脳裏に浮かんだ。
南ちゃんは制服姿で笑っていた。
見た事も無いのにそんな姿を思い浮かべた。
もう一度、呟いた。
「ぎゃあていぎゃあていはらぎゃていはらそうぎゃていぼしそわか」
聞こえたのか、ケンが俺を見た。
「なんだそれ?」
「経だよ」
「きょう?」
「お経」
両手を合わせて見せた。
「ああ、おきょう、で、どういう意味だ?」
「意味?」
「ああ、意味あるんだろう?」
経の括りの言葉に意味はない。
意味を求めてはならない。
世界中でこの菩薩の言葉がどんなに訳されようと、ただ音で憶えなさい。
俺ですらそう習っただけだ。
「意味なんかないさ」
「そうか…」
素直だな、
「ぎゃあてーぎゃあて―はらぎゃあてーはらそうぎゃあて―ぼしそわかあ」
ケンも同じ音を呟きだした。
「ぎゃあていぎゃあていはらぎゃあてい…」
気に入ったのか繰り返し呟き出した。
「ぎゃあてい ぎゃあてい…」
〝往き往きて〟
「はらぎゃてい…」
〝彼岸に往き〟
「はらそうぎゃあてい」
〝彼岸に完全に着きし者こそ〟
「ぼしそわか」
〝悟りである、めでたし〟
意味なんか、俺にも解らない。
暗い豚舎の入口まで、モヒカンのジャンが、中から出てきた。
珍しく神妙な顔でこっちに来いと顎を振っている。
どうせまた、悪い冗談でも考えているんだろう。
ケンを促して、豚舎に向かった。
歩きながら、ケンが、「変な匂いがする」と言った。
言われて、無意識に鼻腔を広げたが豚の臭いしかしなかった。
俺は杖を前に出したが、出てきたジャンは中には来なかった。
歩みは暗がりに差し掛かった。
軽く視界を失いかけたが、数歩で持ち直した。
両端に並ぶ小部屋には、色白の巨体が寝たり立ったりしていた。
歩く通路の幅は大人の肩より一回り大きい程で、暗がりの一番奥に了は立っていた。
了の傍にポンが立っている。
俺達を見て、ポンが了を見上げた。
了はこっちを見た。
その眼は俺だけを見ていると確信させた。
何か俺に言いたい事があるのか。
杖を前に前に進めた。
了は又、自分の正面に顔を戻した。
促されもせず、俺もその視線の先を見た。
黒く大きな豚が居た。
豚は前足の肩口のうねる様な筋肉を動かし、無心に床に転がる〝それ〟を食べていた。
それは、了と変わらないほど大きな〝人の形〟をしていて、両手を投げ出して床に寝ていた。
人の形としか認識出来ないのは、顔と思える部分がえぐるように無くなっていたからだ。
眼も、鼻も、唇も、顔を形成する突起が何も無かった。
えぐれた穴からは血が湧き溢れていた。
ただそれだけで、「人だろうか?」と、分り切った事に思考がたどり着かない。
上着をはぎ取られ、床に転がるそれの腹の辺りに豚は、口元を血まみれにして、鼻を動かしていた。
「さっきまで顏を食べていた」
と、了が言った後、豚は、重重しく首を振り上げた、口には青白く長い腸を咥えていた。
何腸かは判らないけど、首を振って、器用に中空で咥え直して、ドンドン腹の中から引きずり出していた。
腹の横で溜まっていた黒い血だまりが、関が切れた様に柵の外へと流れてきた。
流れる血は、床の豚の塊糞を取り囲むように避け、足元の溝に流れこんだ。
家畜臭に紛れて、微かに匂う温い血の臭いが、喉の奥を刺激した。
声も出せず、その場に吐しゃした。
眼の前の異様な光景に感情はそれ程動かなかったが、臭いが嫌だった。痛い脚を引き摺って、外まで出て吐くのが億劫なだけだった。
了が豚小屋の鉄格子を開け、中に入った。
豚は無心に食べていた。
了が、その背中を鉄の右腕で軽く叩いた。
豚は驚いて、背中をはねさせたが、それだけで食べるのを止めようとしなかった。
もう一度叩くと、首を振ってひと声鳴いて、また鼻を床に転がるそれの腹の中に突っ込んだ。
了は右膝を上げ、押すように豚の顏を蹴った。
豚はごうと鳴いて、顔を振りながら了を見た後、水を飲みだした。
了が格子の中から振り向いた。
「他の豚達も腹をすかしているだろう」
それだけでポンは分ったのか、黙って外へ出た。
「秋雪、トラックで待っていてくれ」
そう言って、了は〈それ〉の脚を片手で持って引きずり出した。
豚の領域から出ると〝それ〟が、やっと誰かの死体だと腑に落ちた。
俺は死体を引き摺る了の後ろを、杖をついて歩いた。
両手を広げて通路に出された死体の左手には義手が付いていた。
その開いていたC型の義手が何かの拍子でカチンと閉じた。
その音を切欠に、俺は口を開けた。
「それ、誰?」
「ああ、知り合いだ」
「豚が殺したのかな?」
「さあ」
「あれ、雄だろう?大きいし、牙もすごかった」
「無残な事をすれば、無残な死に方をするだけさ」
「悪い人だったのか?」
「いいや、でも昔、会長のお父さんと二人で、10人近く仲間を焼き殺したそうだ」
「仲間?」
「大学生の時に、山で殺したそうだ。ここの土地は会長のお父さんがその見返りにおじさんから貰ったものだ」
ところどころ情報が抜けた話に戸惑いながらも、その話をそこまで判りたいとも思わなかった。
「会長のお父さんは自分の息子に背中を押されて川で溺れ死に、おじさんは豚に食い殺された。起きるべくして起きた報いだ」
「じゃあ、了、お前もそうだな」
「ああ」
「俺も」
「ああ」
了は一度も後ろに振り向かなかった。
なんて悲しい背中だ。
「なあ、了、お前のその人間離れした力を、誰かの為とか思わず振り回してみろ」
獣よ。
「お前のは度量が広いんじゃない。馬鹿なだけだ」
青い獣よ。
「馬鹿は馬鹿なりに自分を好きになれよ。ジャンケンポンを見ろ」
自らを慈せよ。
「秋雪、会長に約束させたのは俺なんだよ」
「ああ、ありがとう」
「行こう、俺も行く」
「ああ、行こう」
暗く狭い通路を出た。
沈む夕日が、俺の正面を照らす。
前を歩く〈あいつ〉の顏にも当っていることだろう。
もうトップリと日が落ちた。
荷台に了と黒い豚を乗せた軽トラックを運転して、ゆっくりと警察署の敷地に入ってきた。
建物の玄関に立っている制服の男はただ、こっちを見ていた。
玄関は地面から、三段ほどの階段があった。
その階段を、リヤタイアの正面に捉える為に、サイドミラーで車幅を確認した。
鉄格子で枠組みされた荷台には、雄豚と了が乗っている。
ヘッドレスト横の小窓の視界は、豚の巨尻でパンパンだった。
このまま下れば、玄関に突っ込める体制を慎重に作った。
制服の男はそれでもこっちを見ていただけだった。
ギアを〝R〟に入れ替えると同時にアクセルを踏んだ。
折れていない右足で、底が抜ける程にアクセルを踏んだ。
600㏄そこそこのエンジンは絶叫しながら、車体を後ろへ後ろへと運ぼうとする。
その時、
踏ん張る右足に、視界がおかしくなるほどの衝撃が突き上げてきた。
俺は両手でハンドルを握っていたが、乗り上げ切ったと同時にフロントが浮き、勢いよく着地すると、無軌道な回転がシャフトに流れ込み、ハンドルを握る腕を狂った回転に巻き込んだ。
もう何も出来ない。
車体は傾き、リアから玄関に突っ込んで動かなくなった時には左側を真横にし、倒れていた。
運転席で視界が逆さになったが、意識は飛ばなかった。
真っ白に砕けたフロントガラスを蹴破り、這う様に外に出た。
目の前に、暴力団の車が止まると、バタバタと幾つもの脚が俺の前を駆け抜けた。
「秋雪、じゃあな、そいつに乗って行け!」
三角頭が斜めの視界の向こうで叫んでいた。
横倒しの車で玄関を塞いだ建物の中ではすでに、雄豚の絶叫と、訳も判らず慌てふためく人々の叫び声で充満していた。
脚を引き摺って立ち上がり、転がる車体の隙間から中を見た。
首の辺りを擦りながら、了が立ち上がろうとしていた。
立ち上がる背中は、豚舎でのあの悲しい背中じゃなかった。
濛々と豪気を背負った獣の背中だった。
その背中を、ケンが消火器を振り回しながら掻き消し、ジャンとポンが、例のボトル爆弾をドンドン投げ込んでいる。
ボトルはキャップを叩くと〝碁石〟が落ち、破裂する仕掛けになっていて、中には画鋲が底にたまる程に沈めてある。
怒号の中、ボトルが破裂すると、短い悲鳴が混じる。
脅かす程度の、何一つ傷付けられないものだが、人はその程度で戦意を失い、動けなくなる。
その程度だ。
プラスチックボトルの破裂音、三兄弟の奇声、暴れ狂う豚の絶叫、訳のわからない礫に逃げ惑う人々の悲鳴、
その中を構わず了が歩く。
まあ、そのうち収まるだろう。
目の前の車のドアを開け、肘で這い乗り、シートに座った。
座ったシートの目の前にはハンドルがあった。そのままアクセルを踏んだ。
ゆっくりとハンドルを回して、建物から出た。
敷地を囲む壁の後ろに人影が見えた。
警察の制服を着ていた。
嫌な予感で、壁伝いに車を徐行させた。
〈署長〉が4、5人の制服に囲まれて、裏の道路を歩いていた。
溜息が無意識に出て、その溜息に舌打ちした。
◆ 了 21歳
白煙の中で、バスバスと破裂するボトルと、暴れまわる雄豚のおかげで、誰も頭を上げられない。
俺はどんどん階段を上がれる。
螺旋の階段を何度回ったか分らない。
小走りのまま、もう一段上がろうとした時、ジャンに引かれてフロアの廊下に出た。
「四階の奥だ」
と、はっきりとポンが言って、ジャンと共に俺の前を歩く。
ケンは後ろで白煙を巻き散らかす。
フロアは暗かったが、非常灯が足元に並ぶ廊下は、それほど不便じゃなかった。
前を歩くジャンの脚が止まった。
「誰か、居る」
そう言われて、廊下の先に眼を凝らすと、非常灯の薄明りに、廊下を埋め尽くすような人影がひとつ、立っていた。
影から突然、火花が散った。
咄嗟に後ろのケンに覆いかぶさって床に伏せたが、火花は、4つ、5つと構わず放たれる。
火花から放たれたものは壁や床で跳ね、天井の暗い蛍光灯を割った。
拳銃を撃って来た。
なるほど、本気だ。
立ち上がらずに影を見ていると、握っていた拳銃を捨て、真直ぐにこっちへ歩いてきた。
「カクホスル!」
影が甲高く叫んだ。
が、
悠々と歩く足並みのおかげで、落ち着いて立ち上がる事が出来た。
「アックホッズル!」
言葉の最初がかすれて、ますます甲高い声になっていた。
暗い中でも、随分大きな影だと分かった。
「ボスよりデカいぜ」
ケンが耳打ちしてきた。
顏色がはっきりと見えるくらいの距離になったころ、様子がおかしい理由が解かった。
狂っていた。
制服を着た狂った大人が唇を紫色にし、口角に干からびた唾泡を溜めて立っていた。
「ッホスルウッ!」
自分の中の獣を放つ為に狂っていた。
大人は不便だなあ。
「ボス、ありゃあ、俺達じゃ無理だ」
言いながら、ケンが空になった消火器を正面の暗闇に投げ付けた。
狂人は手に持つスチールの警棒で軽々しく退けた。
ガンガンガンと床で跳ねた赤い鉄筒は、足元へ転がり戻ってきた。
「あれは俺に任せろ、署長を頼む。どうせお前らのほうが詳しいんだろう?」
少し投げやりに言ったら、ポンが慌てて「だって」と言って、戸惑う顏をした。
「ああ、会長の言う事も聞けと言ったもんな」
そう言って笑ってやった。
怒っちゃいないさ。
埠頭の廃屋からは、走れば2時間程で団地に着く。
会長が、こいつらの姉ちゃんとでも連絡していたんだろう。
外国船に乗れと軽々しく言えるくらいだ、それくらいは出来るだろう。
「上に行けよ、窓から上がれ」
そう言って、ズンと右足を出した。
目の前の大人は随分と強そうだ。
挙句に最初から狂っている。
やれるか?
廊下の真ん中で、巨人が二人、両手を下げて睨み合う。
埒もあかないそんな時間が俺は苦手だ。
先に手を出した。
膝を下げ、眼の前の狂人に右の鉄腕を下から振り上げた。
同時に振り下ろしてきた警棒が鉄の腕に当たり、甲高い金属音が耳を劈いた。
その音がきっかけのように、轟々と互いに鉄の凶器を振り回し、時にぶつからせ、火花を散らせた。
何度も何度も、同じように撲りあった。
10分もした頃、この拮抗した撲り合いに痺れを切らした狂人が、地面に着くほど尻を落とし、タックルしてきた。
猪凸猛進。
膝で蹴りあげようかと思ったが、嫌な予感がした。
〝脚〟は辞めとこう。
と、踏み出した左脚をそのまま伸ばして右膝を地面に着けた。
目線は狂人の脳天と並行になり、眼の前に鉄の右腕を水平に振り抜いた。
鉄の腕と狂人の頭の衝突音が、ごおうんと重く響いて、狂人はピタリと止まった。
狂人は掴み損ねた蟹の様に両手を広げ、数秒、動かなかったと思ったら、突然、海老のように後ずさりした。
暗闇に消えた狂人が、次に、何をするかなんて判っていた。
地響きを起てて、脳天を再び突進させてきた。
獣の戦いは勝つか死ぬかだ、死ぬまで付き合ってやるさ。
お前がな!
構わず、右の鉄拳を正面に振り抜いた。
鈍重な音と共に、突進する脳天が再び止まった後、丸見えの後頭部がカサカサと後退した。
また来るのか。
2回目で、もう煩わしいと思った。
次は丸出しの後頭部を打ち下してやろうと思った時、咽喉元に嫌な唾が出た。
ゴロゴロと口元に込み上てきた唾を吐き出すと、どこかで声がした。
〝なにをいっているんだ?〟
獣だ。
おお、分っているさ。
獣と意見が一致した。
吹っ切れた意識は背骨を伝って、背筋をビリビリと刺激する。
右の拳を引いた。
より股を広げ、衝突点を想像し、宙空に線を引く。
この線を超えた時、真直ぐに鉄拳を叩きつけて頭蓋骨を粉砕してやる。
何かの合図のように「おおう」と叫んで、狂人は暗い空気を蹴散らしながら迫り来る。
突進する狂頭が〝線〟を超える寸前、肩が引き千切れるほどに肘から先を振り抜き、鉄拳を迫る脳天に衝突させた。
猛烈な鈍衝が、肘を伝って首筋まで痺れさせた。
視界が暗くなり掛けたが、心臓に激痛が走り、正気に戻った。
狂った脳天はまだ押してくる。
鉄拳はじり貧に押し戻される。
押し返される鉄拳は、脳天との間に高熱をおこし、腕と鉄の隙間の筒革を、しりしりと焼き出し、狂人の触れ合う脳天から煙をだした。
もう一段、腰を下げ、脚の親指を丸めた。
そこから起きた小さな螺旋が脹脛から背筋へと伝わった時には、全身を竜巻の様なバネにする。
ぷっと息を吐いて、力を右腕に流し込むと、ぶつかり合う頭との圧迫は、装着する鉄拳のくびれを消し去る程に膨張させ、膨張は留まらず、鉄腕全体を濛々と膨らませ、肘の付け根で短く裂けるような音をさせた。
「狂わなければ何もできないウスノロが!」
右肘を押し出した。
伸びきる肘の先で起きた破裂の衝撃は、鉄拳を右腕から噴射した。
ロケットパンチ。
腕から離れた鉄拳の突撃に、狂人は渦を巻いて吹き飛んだ。
伸ばし切った右腕の先には、何もない。
床に転がる狂人はうんとも言わない。
死んだか。
そう思ったとき、鼻をかむ様な音をさせ、狂人が噴血を巻き散らかして立ち上がった。
眼の中には生きているものの光がなかったが、それでも腰を落とし、脳天を突き向けてきた。
正直、参ったなと思った。
右腕は吹き飛んだ。
という事は、左の拳を使う為のバランスも失った。
参ったなとは思うが、むこうには関係無い。
狂人の脳天は突進してきた。
鉄のロケットパンチにも絶えた脳天の進撃だ。
狂死の進撃だ。
それを、自分の顔面の真正面で受けるべく膝をついた。
どうせ、立っていられない。
立膝で弓を引く様に左拳を後退させた。
これしかない。
間違えば、こっちの頭が粉砕する。
もとより相手はもう死んでいる。
この一撃の為に心臓が最後の爆発をしている事だろう。
憶えがある。
右の拳を失ったあの戦いを思い出した。
思い出すと、気分が急に冷めた。
そんなものに付き合っていられるか。
利き腕は左だ、獣なんか要らない。
立膝を広げ、背中を丸め、水平な左の肘を直角に立てた。
その狂弾を眼の前でえぐり上げてやる。
それでも、危険な賭けである事には変わりない。
山の様な圧力がぐんぐん迫って来る。
ここだと思う瞬間を誤ればそれまでだ。
鼻先の10センチ手前、
背骨の動きには1寸の狂いもない。
その狂いのない動きは、肘先の拳へと叫ぶような信号を送る。
突き上げろ!
驀進する狂人の顔面を、鼻先に触れる寸前で、えぐり上げ、宙へと撥ね退けた。
狂人の巨体は円を描いて地面に落ち、首が捻れ、動かなくなった。
覗き込んで確かめた顔面からは血が溢れていた。
「ごめんね」
微塵にも動かない死体を見て、ちょっと悪い気がした。
が、
かまっていられない。
よろよろと起ち上がり、死体を跨いで、向こうへと歩いた。
換わりの〝右手〟を見つけなければ、そう思いながら歩いた。
壁伝いに手をついて歩いた。
廊下の突き当りの部屋に三兄弟が立っていた。
俺を見ると、全員、口元を歪め、バツの悪そうな、苦い顔をしていた。
理由は言わなくても判った。
もうここに〝居ない〟のなら用は無い。
「港へ行こう」
ケンが、俺の脇に手を廻して支えてくれた。
階段を下りて玄関から出た。
誰にも止められなかった。
声すら掛けて来なかった。
何処かで、ぼうと雄豚が哭いた。
敷地を歩いて出て直ぐ、
「乗れよ」
後ろから声を掛けられた。
左脇に見覚えのある傷がある高級車だった。
秋雪が、
開いたドアウインドウに肘を掛けていた。
随分顔色が悪い。
「どうした?病院に行かなかったのか?」
「徒労だったな」
「とろう?」
秋雪の言葉をケンが繰り返した。
「無駄足ってことさ」
誰も喋らなくなった。
秋雪の顔がみるみる紫色になる。
車の中を覗きこんだ。
秋雪の膝にすくえるほどの血が溜まっていた。
慌てて車に乗り込み、秋雪を助手席に押し込めた。
座った途端に、温い血だまりがズボンに吸い込まれ、尻を濡らした。
ハンドルをにぎって正面を向くと、フロントガラスに丸く開いた穴が3つあった。
「お前、撃たれたのか?」
「署長を…見かけたからな…轢き殺せとアクセルを開けたけど、かすりもしなかった。その時に、銃声もしたからそのまま逃げた」
「逃げたって、お前、撃たれているじゃねえか!」
ポンが傷口を覗き込んだ。
「了、悪いが…運転してくれ。病院へ行こう…丁度いい」
「ああそうだな、丁度いい」
秋雪は眼を瞑った。
「ありがとう、了」
それきり、秋雪は喋らなくなった。
左手だけでハンドルを握って、静かにアクセルを踏んだ。
◆ 勇 23歳
空想だった。
父親は会長と呼ばれ、尊敬され、恐れられていた。そして、その重圧に耐えかねて、俺は父親を殺した。
その為に、この身体の中に生み出された。
された筈なのに、
何故か今も俺のままだ。
それは、全てが俺の空想だった。
そんなものは在りもしない想像だったんだ。
瞑ったままの瞼の奥の意識は、俺一人だった。
〝本当の勇〟なんて居やしなかった。
誰かに押し付けられた人生を投げ返す為に、自分の胸に銃口を当てた。
撃鉄を引いて撃ちだされた弾は肺を打ち抜き、これ以上ない衝撃で心臓を揺さぶってやる。
いや、死んでやる。
主人格を守るための副人格が自らを殺す。
心臓。
頭の中に居ないのなら、お前はそこに居るのだろう?
案の定、打ち抜く寸前に意識が滑落した。
が、居なかった。
俺だった。
居るのは俺だけだった。
つくられたという空想だった。
みっともない。
俺は唯の軟弱者だ。
きっと、ありありと残るこの二年間の記憶すら、俺が作ったものだ。
名前も知らない獣のようなあいつも、大人達と渡り合う俺も、そんなものは存在しない。そんな都合のいいものはない。
胸を銃で撃ち抜くなんてやっていない。
ただどこかのベッドに横たわる豚だ。
耳に入る物音、鼻先に臭う部屋の空気、肌に触れるその空気の湿りもありありと感じているのに、俺は眼を開けない。
何の〝振り〟なのかも分らない。
分らな過ぎて起きる事すら出来ない。
存在しない〝本当の勇〟をまだ怨むのか。
最悪だ。最悪にみっともない人生だ。
これは空想だ。
ならば、最後の仕上げだ。
暗闇の中で、眠るように意識を消す。
暗闇の中の身体は足元から、砂を溢すように崩れいく。
この砂が崩れ去った時、このみっともない人生も本当にさよならだ。
と、
ドアの開く音が鼓膜を揺らした。
別にいつもの事だ。開いて、閉まる。
ただ、その開いたドアから懐かしい匂いがした。
血の臭いだ。暑苦しい人の体温と共に血の匂いがした。
「会長、秋雪死んだよ」
聞き覚えのある若者の声だった。
「秋雪、死んだよ」
若者は、もう一度言った。
声は、静かに落ち着いていた俺の心臓の鼓動を刺激した。
首元の動脈にゴクゴクと血液が流れるのを感じる。
喋る若者の声、秋雪という名前、血の匂い。
暗闇に無理やり照らされるトーチのように、無神経で刺激的だ。
瞼が熱くなった。
このまま起きれば、もう一生、俺でいるしかない。
分かっているのか?
それでも皮一枚挟んだ室内の光を浴びようと、眼球は急く様に瞼を擽る。
しょうがねえなあ。
「そうか」
俺は瞼を開けた。
開けた眼を、臭いのする方に向けた。
南ちゃんのお兄さんと、ジャンケンポンのどれかが一匹立っていた。
ジャンケンポンのどれかは、頭からつま先まで、血と埃で黒く汚れていた。
「なんだ、お前、その頭」
短く髪を切った頭は真ん中に変な突起を乗せていた。
「ボスが三角にしろって言ったんだよ」
その言葉で、大体分った。
「他の二人はどんな髪型だ?」
「ジャンがモヒカンで、ポンが坊主だよ」
「じゃあ、お前はケンか」
起きたいなんて言って無いのに、南ちゃんのお兄さんが俺の背中を持ち上げた。
「やっと眼を覚ましたね」
いつからの〝やっと〟なのか。
「先輩を呼んで下さい」
「外に…」
そう返された後、ドアが開いた。
先輩が入ってきた。
先輩は少しだけ笑って、自分で閉めたドアの前に立った。
俺はベッドに座って、言わなければならない事をまず言った。
「秋雪は今、どこに?」
俺が言う言葉はそのまま町の人間の耳に入る。
「下に車で来ている」
ケンが答えた。
「そうか、約束だったのにな、残念だった」
俺の言葉はそのまま俺の考えだと、街の人間に伝わる。
「署長の息子は死なない。受けた約束は果たした」
南ちゃんのお兄さんは何も言わない。
「その為に全てを先輩に任せた」
南ちゃんのお兄さんが、何も言わず俺を起こしたように、そこには否も応もない。
さあ、もう起きよう、空想は終わりだ。
目の前に現実がる。呆れた現実だ。
眼の前の、血と埃でどろどろのケンを見れば、何が起きたか大体、想像がつく。
あいつの事だ、街は滅茶苦茶だろう。
「秋雪も覚悟の上だった筈だ。死体は置いて行け」
「わかった」
ケンは、俺を見て顎を引いた。
「じゃあ、行くよ。ボスと街を出るんだ」
心臓の鼓動が早くなった。
「先輩に送って貰え、その方がいい」
「ああ、いいよ」
三角頭が、まるでこっちが頼んでいるように返事をする。
「会長、豚小屋で、手伝いのおじさんが死んでいたよ。ボスがその方がいいって言うから、肥貯めに捨てたけど、2、3日したら浮いてくると思う。豚も今日の夜の餌はあげたけど、明日はもう誰も見ないぜ」
「ああ、こっちでやっとく。悪かったな」
「うん、わかった。じゃあ」
「あいつによろしく。元気でな」
「ああ、言っとくよ」
ケンは何か言いたげな眼で俺を見たが、俺は口元で「もういいんだ」と呟いて、外に出した。
〈あいつ〉は街を出る。
名も知れぬ獣が川崎を去る。
悪かったな、ありがとう。
エピローグ
永遠かと思えるほどの暗い海を、了を乗せたバンカーは進む。
了は、船の舳先に立ち、向かってくる海風を身体に受けて、左右に流す。
月は無い。
黒幕に散開する星の瞬きに、右手に着けたオジさんの義手を天に突き刺す。
何をどうしても〝C〟は丸くなったまま開かない。
どうやったら開くんだろう?
了は力の加減を変えるが、義手はビクとも動かない。
了とジャンケンポンは、3兄弟の姉ちゃんに言われた〝バンカー〟に乗り込んで、港を出てた。
朝日が昇る頃、了は必ずこの舳先に来る。
視界の限界の暗い青海をぐるりと見渡す線を見ると、自分の住むこの世界の果てが丸い事を悟らされる。
バンカーはジャンケンポンの母親の故郷へ向かう。
彼らに船の中で出来る仕事なんか何もない。
夜中の見回りくらいだ。
大陸に近付くと、「物騒な奴ら」が海から船に上がって来る。
了達が、夜中に「それ」をやれば、全ての船員が夜、寝むれる。
と、ものすごく色の黒いキャプテンに頼まれた。
了は、快く引き受けた。
果てしない甲板を、順番もなく了は、三兄弟とウロウロする。
持っているハンドトーチには、抜きピン式のサイレンが付いている。
何かあればこれを抜く。
真夜中の見回りの途中で、了は舳先に立つ。
左手に持つハンドトーチの明りを消し、闇風に身を任せる。
下を向いても20メートル下の波は見えな。
空の船は喫水が高く、波の音すら聞こえない。
艦橋の明滅する警告灯以外は何もない。
甲板には、蓋をされた巨大な奈落の口が四つある。
それを回るだけで、30分掛る。
巨大、という言葉だけで表現するには足りないほどのサイズだ。
自分がちっぽけに感じる、悪い気分じゃない、と了は思う。
風を受け、暗い水平線を眺めていると、けたたましくサイレンが了の耳をつんざいた。
たまらず了がサイレンの方に顏を向けると、サイレンと一緒に、円い薄光が忙しなく回転している。
回転は無軌道に上下して、こっちに向かってくる。
途中で光は二つに分かれ、闇の中に何かを叫んでいる。
叫んでいるが、サイレンの音で聞こえない。
叫び声が聞こえる頃には、二人の顏もまともに見えたが、すぐ後ろにドタドタと人が数人付いてくるのも見えた。
「やっかいな奴ら」が本当に来た。
手前の二人はジャンとポンだった。
零れる涎も拭かずポンが言った。
「ボス、海賊だ」
「そうだな」
ジャンとポンを挟んで、眼の前に5人の海賊が立っている。
了は勇に遭った日にクズに囲まれた事を思い出した。
が、
ぞろぞろと眼の前に並ぶ男達は皆、了と目線が一緒だった。
という事は2メートルの男達が、了を合わせて6人居る。
海賊の3人は手ぶらだったが、2人はおもちゃの様な拳銃を持っている。
トーチのサイレンは鳴りつづける。
「トーチを捨てろ」
言いながら、自分の分を海に捨てた。
合わせる様に残りの二本も投げ捨てられ、やっと静かになった。
自分の掌すら見えない暗闇の中に海賊が何か言った。
ジャンが小声で了に耳打ちした。
「お前、デカいな、だとよ」
了は少し笑うと、多分、海賊は拳銃を使わないだろうと思った。
仲間が多いし、暗いし、近い。
「ケンは?」
「ブリッジに行った」
艦橋のテッペンの警告灯の瞬きが変わった。
この船が襲われている事を航空機や他の船舶に教えている。
ケンがキャプテンに知らせた証拠だ。
SOSが宇宙の衛星信号を使って世界中にばら撒かれているだろう。
仕事を果たしたと思う安堵感が了の緊張を解いた。
「ボス、頼んだぜ」
ポンとジャンの気配が消えたが、まだそこらに居るだろう。
下手には動けない。と了は暗闇に数をかぞえた。
「…18、19、20…やるか」
合図のように呟いて、了は暗闇にに拳を振った。
何処にも当らなかった。
拳風に、燥ぐような笑い声が起きた。
同時に前後左右から、からかう様に拳が飛んできた。
軽々しい罵り声とはうらはらに、降ってくる拳は刺青おじさんの拳のように重かった。
その拳が、10本ある。久しぶりだ、思いっ切りやろう。
了はどっしりと踵を踏みしめ拳を胸元に置いた。
刹那
互いの何本もの拳で、どっと撲り合ったが、了は海賊2、3人に群がられて、持ち上げられた。
しまった!
了は、あっという間に船の外に投げ落とされた。
上も下も無い暗闇の中空に身体を放り出し、20メートル下の海面に背中を打ち付け、固いゴムで叩かれたような衝撃と共に、身体は波下に沈んだ。
海中で、前後無く身を回転させ、2、3度と、進む舷側に身体をぶつけたが、もがく指先に掴まるモノは無く、転がるように海中の舷側を滑った。
船から離れれば、死ぬしかない。
溺れて死ぬ。
見知らぬ海獣に食われて死ぬ。
永遠に広いこの海原で、力尽きて死ぬ。
嫌だ!
了は、両手を伸ばし、仰ぐ様に櫂いだ。
時々、身体が船にぶつかる。
もう何十メートルと流された。
船から離れてはならない。
その一点に気持ちを集中させ、了は、両手を漕いだ。
何度も漕いだ。
息がもたない。
でも漕いだ。
突然、ぼおと全身に竜巻のような泡波を受け、船尾のスクリューの起こす旋流に巻き込まれ、より深い海中に投げ出された。
最期だと思った。
息も出来ない暗海の中、空気を求めて海面を探す。
手足を動かし、何とか海面に出たが、外洋の荒波は空気を吸う度に、口の中に海水を投げ込んでくる。
船から離れてしまったという焦燥感しか頭にない。
顏を振ると、右に点の様な明りが見える。
放り出されたバンカーの明りだと思った。
もう終わったと思った。
泳いでたどり着ける距離じゃない。
船は離れていく。
光から眼を放し、上を見た。
星空の瞬きは変わらない。
「ありがとう」
突然、秋雪の最期の言葉が、了の頭を過った。
なんて事だ。
誰にも言った事がない。
俺はそんな言葉を誰にも言った事がない。
一緒に居る三兄弟にも、昔の会社の同僚にも、母さんにも、死んだオジさんにも、会長にも言った事がない。
しらじらと世間を眺めていた。
周りを巻き込み、引きずり回しながら、自分の身の回りの人々を馬鹿にしていた。
それを悟られるのが嫌で、当たり前の事をさぼってきた。
助かりたい。
了は、心からそう思った。
もう一度、波間の光を見た。
光の点は動かない。
心臓の鼓動が早くなった。
光を見つめながら、口の中でゆっくりと数をかぞえた。
60をかぞえても、光は動かない。
泊まっている。
海面に停泊している船だ。
海賊の船か?
そうか、何隻かの船で来ていたのか。
泳げば、辿り着ける。
了は、自分の身長程の波に、平泳ぎで進もうとしたが、右手の所為で上手くいかない。
しょうがなく左肩を海に沈めて、顔の右側を空に向けて泳いだ。
どこに隠れていたのか、丸い月が波面にはねるほど、黄色い光を放っていた。
いつかあの町に帰ろう。帰って会長に会おう。
それでも、そう意気込むことじゃない。
了は、月明かりのおかげで、気分が楽になっていた。
船の姿がハッキリと見え出した頃、辿り着いたのは船の後ろ側だった。
古ぼけた漁船の後ろの赤錆びた梯子に手を掛け、了は、一気に上半身を海面に揚げた。
と、
同時に、黒々とした海面が飛び上がるように破れ、赤い口を開けた怪物が鼻先を月明かりに照らして、覆いかぶさるように襲ってきた。
鮫だ。
月が出たときくらいから後ろに居た気配を感じていた。
待ち構えたように撲ってやろうと思ったが、了の左手は手すりを握っている。
仕方なく、空いている義手の丸く閉じた〝C〟で、鮫の尖った鼻先を力任せに横殴った。
鮫は口を開けたまま海面に叩きつけられ、尾びれを振り回して海中に沈んだ。
鮫が起こした騒々しい波音の所為で、船尾へと誰かが来る足音がした。
頭を出そうかと思った時、短い銃声が2発した。
また何か叫んで、足音が近付いて来た。
了は、海面に身体を胸まで沈めた。
目線が海面と同じになった時、月に照らされた鮫の背びれが、海面に浮いてきた。
また来た。
正面を向いた背びれを月明かりで光らせ突進してくる。
今度は左拳で撲ってやろう。
鮫ぐらい、一発で殺す。
どうにかCが開かないか。
梯子に捕まるだけならそれでもできる。
だが、丸く閉じて開かない。
鮫は、切り裂く波を月明かりに光らせ、突進してくる。
変なのに懐かれたもんだ。
ふふ、会長も、俺にそう思っていたのかな。
と、苦笑いで溜息を吐いたその時、右腕のCが、カチンと開いた。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
