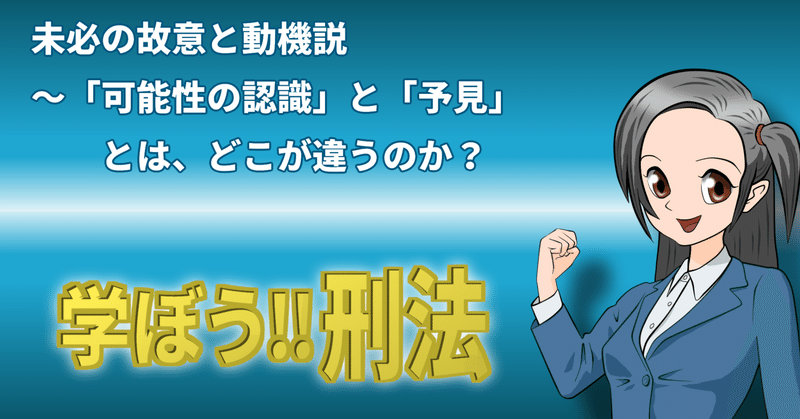
【学ぼう‼刑法】未必の故意と動機説~「可能性の認識」と「予見」とはどこが違うのか?
第1 はじめに
「未必の故意と認識ある過失との区別」という論点があります。
「未必の故意」は、手元の『法律学小辞典』によれば、次のように説明されています(ちょっとばかし古いのはご容赦を)。
未必の故意 1 意義 故意の認められる場合のうち、行為者が犯罪事実、特に結果発生を可能なものと認識している場合を指す。結果発生を確実なものと認識している場合および結果発生を意図している場合である確定的故意と区別される。……(以下略)
この「未必の故意と認識ある過失の区別」という論点をめぐっては、故意に意思的要素は必要か否かという問題と絡んで、蓋然性説、認容説、動機説が対立しています。
問題となるのは次のような事例の場合です

この事例において、AはVを死亡させているところ、Aに殺人罪(刑法199条)が成立するのか、過失運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)が成立するのか問題となります。
殺人罪は故意犯ですから、Aに故意が認められればAは殺人罪となりますし、故意が認められなければAは過失運転致死罪の罪に問われることになります。
そこで「未必の故意」と「認識ある過失」とを区別する基準が問題となりますが、冒頭に述べたように、ここには蓋然性説、認容説、動機説が対立しています。本稿では、これらについて簡単に解説しながら、「可能性の認識」と「予見」とがどう違うのかということについてお話ししようと思います。
第2 故意と実現意思
1 まずは条文から
刑法上の故意については刑法38条1項が規定しています。
(故意)
第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
(2項、3項略)
ここにいう「罪を犯す意思」が故意です。
これは「犯罪を実現する意思」と言い換えることができます。
そこで、故意の内容を明らかにするうえで問題となるのは、
ここにいう「犯罪」とは何か?
「実現する意思」とは何か?
という2つですが、本稿のテーマと関係するのは「2」の「実現する意思」とは何かという点です。
2 実現する意思(実現意思)とは?
「実現する意思」の内容をめぐっては3つの説が対立しています。
【意欲説】犯罪事実の認識(予見)および意欲とする
【認容説】犯罪事実の認識(予見)および認容とする
【認識説】犯罪事実の認識(予見)とする
ここに「認識」(広義)とは、事実を知っていることを意味します。
狭義では「認識」は、現在までの事実について知っていることを意味し、将来の事実について知っていることを「予見」と言います。
そして、狭義の認識と予見をと併せて、広義で「認識」または「表象」と言ったりします。
「意欲」とは、その事実の実現を望む心理状態を言います。
「認容」とは、その事実を「よい」または「構わない」と受け入れる心理状態を言います。
意欲説は、故意が認められるためには、犯罪事実を認識・予見しただけでは足りず、その実現を望む意欲があることが必要だとする説ですが、これでは故意の認められる範囲が極めて狭くなってしまい妥当でないため、この説は現在では採られていません。現在有力な見解は、認容説と認識説です。
第3 未必の故意と認識ある過失の区別
1 認容説
認容説は、未必の故意と認識ある過失の区別の基準は、まさに認容の有無にあると考えます。つまり、いずれも結果が発生する可能性を認識していたという意味では、両者は同じですが、認容があるのが「未必の故意」、認容がないのが「認識ある過失」であるとします。従来からの通説であり、現在でも通説でしょうか?
認容説によると、先の事例の場合、Aが「仮にVにぶつかってVを死亡させてしまうかもしれないが、それでも構わない」と思っていたのであれば、Aには殺人罪の未必の故意があったということになります。
2 蓋然性説
実現意思に関する認識説を前提に、古く主張されていたのが蓋然性説です。
この説は、行為者が、単に結果発生の可能性を認識していたにとどまる場合は「認識ある過失」だが、結果発生の高度の蓋然性を認識していた場合は「未必の故意」であるとします。
蓋然性説によると、先の事例の場合、Aが自車がVにぶつかり、Vが死亡してしまうことについての高度の蓋然税を認識していたか否かにより結論が変わることになります。高度の蓋然性の認識があったのであれば、殺人罪の未必の故意が認められることになります。
3 動機説
実現意思に関する認識説を前提に、もう1つ主張されている見解が動機説です。この見解がどのような区別の基準を用いるのかは、いまひとつ解りにくいところがあります。
そこで、動機説の論者である平野龍一先生の本の説明を見てみることにしましょう。
自己の行為の結果として人が死ぬであろうことを予見したときは、これを、行為を思いとどまる動機にしなければならない。それにもかかわらず、思いとどまる動機とせず、その行為をしたことを非難するのである。認識説は動機説だといわれるのもそのためである。動機説というと、うらみをはらすためであったとかいうような他の動機の有無又は種類によって、故意の有無を決する見解であるかのようにとられるおそれがあるが、そうではないことに注意する必要がある。
まず、ここで言われている「動機」とは、行為を思いとどまる動機、つまり「反対動機」のことであるということが説明されています。
そして、人が死ぬであろう、というような結果の「予見」をしたときは、行為者には「そのような行為には出ない」という反対動機を形成することが求められる。それにもかかわらず、行為者が、そのような反対動機を形成せずに行為に出た場合に、そこに法的な非難が加えられる。
平野先生はそう説明されているようです。
ということは、動機説によれば、「未必の故意」と「認識ある過失」とは結局のところ「予見」があるかないかで分けられ、予見があれば「未必の故意」、予見がなければ「認識ある過失」とされるということのようです。
そうだとすると、この説は、わかりにくいどころか、極めて単純な説だということになります。
では、この説によると先の事例では、Aは、Vの死亡という結果を予見していたというべきなのでしょうか?
先の事例では「Aは、このまま自車を進行させればVに衝突し、死亡させてしまうかもしれない」と思っていました。しかし、同時に「自分の運転の腕前ならばVの前方をすり抜けることができるだろう」と思っていたのです。
確かに、Aは、Vを死亡させえてしまう可能性は認識していたのです。しかし、そうはならないだろう、と思っていたのです。
この場合「予見」はあるというべきなのか、ないというべきなのか?
4 可能性の認識と予見との違い
平野龍一先生の本からもう少しだけ引用してみましょう。
……このように、認識説が、実際的にも理論的にも妥当だと思われるのであるが、しかし古い認識説のように、蓋然的であると思ったか、単に可能だと思ったかで区別するのは、適当でない。故意と過失とは、単なる程度の差ではなく、質的な差があるべきだからである。蓋然的であるか可能であるかという判断は、一般的な判断であるが、具体的な当該事件では、結果は発生するかしないかのどちらかであって、その中間は存在しない。したがって行為者も、一応は、結果発生の蓋然性がある、あるいは可能性があると考えたとしても、「結局においては」、結果が発生するであろうという判断か、結果は発生しないであろうという判断かのどちらかに達しているものと考えることができる。このような意味での犯罪事実の認識の有無が、故意と過失との限界をなすのである。
まず、ここで述べられているのは、蓋然的とか可能とかいう判断と、結果が発生するであろうという判断は質的に異なるということです。
そして、一般的な判断として、結果の発生が蓋然的であるにせよ、可能的であるにせよ、行為者自身は「結果が発生するだろう」あるいは「結果は発生しないだろう」かのいずれかの判断に達しているハズであり、これを基準として故意・過失を区別すべきだと言っているワケです。
5 実行行為の認識と結果の予見
この問題をもう少し具体的に、殺人罪(刑法199条)の構成要件的故意を使って考えてみましょう。

殺人罪は、結果犯の最も簡素な構成要件の形をしています。
客観的構成要件要素は、①実行行為、②結果(構成要件的結果)、③因果関係の3つです。他方、主観的構成要件要素は、④構成要件的故意だけです。
①実行行為は、結果犯における実行行為の公式どおり、構成要件的結果を発生させる現実的危険のある行為です。つまり、この場合は、構成要件的結果が「人の死亡」ですから、「実行行為」は、人を死亡させる現実的危険のある行為ということになります。
また、②結果は「人の死亡」、③因果関係は「実行行為と人の死亡との原因・結果の関係」ということになります。
主観的構成要件要素である、④構成要件的故意は、構成要件に該当する客観的事実を認識・予見することですから、①について認識し、②および③について予見すること、となります。
さて、さらに、「実行行為を認識する」とはどういうことなのかについて分析してみましょう。
「実行行為」は、実行行為性のある行為ですから、これを認識するとは、
「行為」を認識すること
「実行行為性」を認識すること
の2つに分解できます。
1は、意思による支配可能な自己の身体の動静について認識することと言えます。では、2はどうでしょう?
「実行行為性」とは、その構成要件における実行行為の特徴・特質のことですから、殺人罪の場合であれば「人の死亡を発生させる現実的危険がある」ということを意味します。そして「現実的危険がある」とは「現実的な可能性がある」と言い換えてもよいでしょう。
そうすると「結果の発生する可能性」を認識するとは、実行行為の「実行行為性」を認識するということを意味していることになります。
では、構成要件的故意の内容としての「結果の予見」とは、どういう内容でしょうか。
これは「結果が発生すると思っていた」ことを意味しています。殺人罪の場合であれば「人が死亡すると思っていた」ということです。
そして、行為者が「人が死亡すると思った」のであれば、法は行為者に対してその行為に出ないように要求します。つまり、法は行為者に対して直ちに反対動機を形成することを要求し、行為者もそうすべきだと言えます。
6 故意責任と過失責任の差
しかし、行為者が「人が死亡する現実的危険」を認識していたとしても、「人が死ぬとは思っていなかった」(=予見していなかった)場合は事情が異なるでしょう。
この場合、行為者は、内心では「結果を発生させないままやり遂げることができる」と考えているからです。
この場合も、もちろん、法は、最終的には反対動機の形成を求めるでしょうが、その場合、まずは予見が可能であることを前提に、行為者に対して注意深く振る舞うことを要求し、それによって結果を予見して行為を思いとどまる、ということを要求することになるでしょう。
しかも、こうした場合、反対動機形成への道のりは、予見のある場合よりは遥かに遠いため、これによる刑事責任の程度も、故意責任よりは遥かに軽くなると考えられます。予見のある場合、反対動機の形成は容易ですが、予見のない場合はこれに比べて困難だからです。
もっとも、実際問題として「人が死亡する現実的危険性」について、行為者がその高度の蓋然性を認識しながら、その一方で「人が死ぬとは思っていなかった」というのは、かなり不自然であることは否定できず、なかなか想定し難い事態だと思います。
そうすると、動機説と蓋然性説との差は、むしろ、動機説では、結果の発生する可能性はそれほど大きくはないが、行為者は結果が発生するだろいうと思っていた場合に「未必の故意」が認められるという点になるでしょう。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
