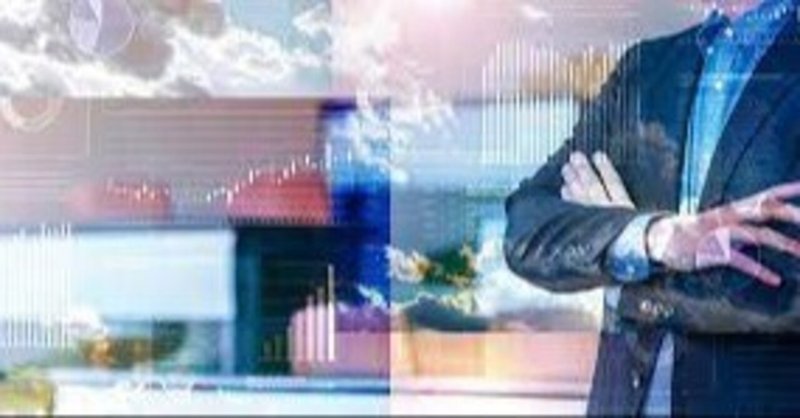
判断できない下請け根性
受託開発によくある問題には「下請け」とセットで扱われることが多く、これを
「下請け根性」
とも椰楡されることがあります。
確かにIT業界の多くの会社は下請けを生業としています。

43,000社ほど存在するIT企業のうち、42,500社ほどがいわゆる中小企業です。もちろんプライムで活動している企業もありますが、2次請け以降の開発を生業としているところが圧倒的に多いのではないでしょうか。
もちろん経営の判断として「あえて」選択し、きちんと成功している会社もあります。下請け根性に起こりがちな問題はまさしく悪しき『根性』の問題なのです。
下請けという仕事の請け方が問題なのではなく、下請けに「甘んじている」という根性が問題となっていることが多いといわれています。判断や管理を元請け企業にゆだねることでリスクを回避しているつもりの
「認識の甘さ」
「主体性のなさ」
「思考しない不誠実さ」
が真の問題なのです。
このような甘えが文化として根付いてしまうと非常に危険です。
甘えを持った組織の例として、山一證券が挙げられます。

ひとことでいえばそれは「判断停止」であった。なにも判断しなかったのである。その結果、山一證券はつぶれてしまったのだが、この「判断停止」になった理由は「自らの判断を決める基準がなかったからだ」と石井氏はいう。
ここで引用したことはどのような組織・チームにもありえることです。ただ言いなりになればいいものと勘違いすることを諫め
「判断停止」
「思考停止」
を防がないとプロジェクトのみならず、組織の存続すら危ういのです。
受託開発というビジネスの現状は厳しいと言わざるを得ません。ライバルは多く、予算の圧縮/納期短縮のプレッシャーは今後も続きます。ソフトウェアが提供する機能はコモディディ化しており、完全にフルスクラッチのカスタムメイドシステムの需要は今後もどんどん減っていくでしょう。
また、次から次へと登場する新しい技術に対応し続けなくてはいけません。
技術を「早く」「正しく」使いこなすことは競争であり、手を緩めると負けてしまう厳しいレースです。厳しい環境のなか生き残っていくためには確たる技術でもなく、見事な交渉力でもなく、変化に主体的に対応できる柔軟な思考力が必要です。
どのような仕事をしていてもそうですが「下請け根性」からは脱却しなくてはいけません。どのような立場であってもプロフェッショナルとしての自覚を持たなければなりません。
「判断停止」はマネージャーだけでなく開発者の問題でもあります。
「判断停止」から脱却するにはまず明確な判断基準を持ち、そして同じ価値観を持つ仲間を増やすことで、自身を取り巻く環境の文化を変えていく必要があります。
また、経営者や管理職のなかには契約というものをロクに理解していない人も多々存在します。
準委任契約であっても
— Takashi Suda / かんた (@kanta0526) March 17, 2022
善管注意義務を果たさなければ
「偽装請負」
になる。
これを知らないでビジネスしてる人が多い。
契約類型の問題じゃなくて
労働者派遣法
職業安定法
の違反なんだよね。
IT企業でプロジェクトマネージャーや
管理職、経営者を経験すれば
知ってるものだと思ってた。 pic.twitter.com/itTALWQHcr
安易に「やったらやっただけ請求できる」なんてのは妄想です。それは善管注意義務を正しく運用した場合にのみ与えられる資格です。
そんなことも理解しないままに元受けのIT企業に人工を提供すれば請求できると盲目的に信じている人が多すぎます。そしてそうした誤った考え方が次の世代に継承されているのがとても悲しく感じます。
「思考停止」して上の立場の人が言うことをただただ鵜吞みにしていると、むしろロクでもない大人になりかねないということは知っておいたほうがいいと思います。人の認識から発言された言葉は鵜呑みせずに、裏をしっかりととったほうがいいでしょう。
いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。
