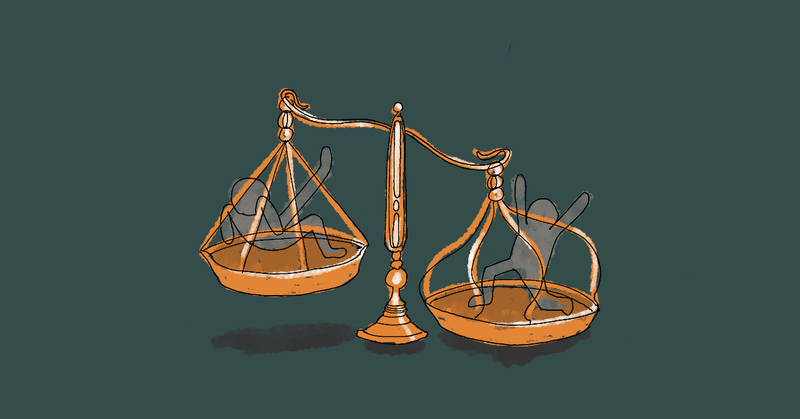
「中国式民主」ってどんなものか、中国人の視点からまとめてみる
「中国式民主」というワードが(僕の中で)話題です。
中国がアメリカを代表とする欧米諸国からのその「民主的でない」体制に関する批判を浴びた際に、「中国には中国の民主主義がある」「民主の形は一つではなく、それぞれの国にあった民主の形があるべきだ」という反論としてよく用いられます。
一方で、この「中国式民主主義」というワードが登場する時、同時に語られる「中国がどのようにして「民主」を達成しているのか」「中国における「民主」とはどのようなものなのか」というロジックについては、さまざまなものが見られます。その内容を見ていくと、今の中国が「民主」をどのようにとらえ、それを達成しようとしているのかが垣間見えてきて、非常に興味深いです。
このnoteでは中国の側から「中国式民主」が語られる際に、どのようなロジックによってそれが説明・支持されるのかという例をいくつか紹介しながら、「中国式民主」の姿を学んで見たいと思います。
代表の選び方
先ごろTwitterでは、中国の大阪総領事館のアカウントによるこんなツイートが話題になっていました。
中国に民主主義はない?答はちゃんと有るとのこと。貴方が思うのと形が異なる民主主義なのだ!
— 中華人民共和国駐大阪総領事館 (@ChnConsul_osaka) October 13, 2021
このスレッドは中国式民主主義をわかり易く解説してくれた。本人の了承を得た上、日本語に訳して紹介する。是非ご覧ください!https://t.co/7OUkF3SSaQ
この一連のツイートは、ある中国人ユーザーが英語で投稿したものを日本語訳したもので、主に現在の習近平国家主席がどのような道程を辿って国家主席の座に就いたのかが紹介されています。
要約すると「中国では血筋や出身に関係なく、試験で公務員を選抜している」「公務員になっても厳しい考課制度がある」「厳しい選抜の中、部署や区県長を経て経験を積みながら着実にステップを踏んでいかなければ国のトップにはなれない」ということが例を挙げて語られています。
以上が中国の最高指導者になるための険しい道。私はそれを「中国式民主主義」と読んでいる。それは厳格な選抜と各級人民代表大会の表決によってできた政治体制で、中国ではそれが良い体制だ。(16/N)https://t.co/SEz9ddrZsc
— 中華人民共和国駐大阪総領事館 (@ChnConsul_osaka) October 13, 2021
つまり、いわゆる西欧的な民主制度下の選挙ではなくとも、このような険しい道を乗り越えてその能力を認められた者が代表となる中国は、西欧とは違った意味で代表を選ぶにあたっての「民主」を達成しているでしょ? ということです。確かに「民主主義≒選挙」とされがちな西欧式の民主とは大きく違ったロジックであり、非常に興味深いと思います。
(ちなみに中国には国民による選挙制度が存在していないわけではなく、県以下の人民代表大会の代表選出の際には住民による直接選挙が行われていまが、その内実は非常に形式的なものにとどまっているというのが現状のようです)
どのように国民の意見を吸い上げるのか
代表選出の方法以外にも、どのように国民の意見を政治に反映させるのかという部分に答えたものもあります。
人民日報の「中国式民主の生き生きとした実践」(中国語原文はこちら)と題されたコラムには、第14次五カ年計画など国の方針を決めるにあたって、政府がいかに民意を汲み上げてきたかということが具体的な数字とともに語られています。
計画提言の起草期間、習総書記は地方視察を重ね、踏み込んで民意を聞くと共に、自ら特別座談会を7回開いて各分野・各階層の人の意見や提案を聴取した。今年の全国両会期間、習総書記は代表・委員らと共に計画綱要草案の審査や議論を重ねた。(中略)最終的に、各方面の意見や提案を吸い上げた上で計画綱要草案の55か所を修正した。一連のデータと事実は、いずれも「全過程にわたる民主」を示すものであり、計19篇・65章・192節のこの計画綱要が全党・全国各民族の人々の知恵と願いを集めたものであることを十分に物語っている。
つまり国民の意見を広く集め、それを政治に反映するシステムは中国において十全に機能しているでしょう、ということです。
ちなみにこのようなロジックは、そのまま西欧式民主を攻撃する際のロジックとして用いられます。言い方はさまざまですが、「選挙の時だけ国民が呼び起こされ、あとは政治も国民も何もしないのであれば、それは民主と言えるのか」というのがその際の主張です。
国民を守り、そして国民に支持されているか
この「中国式民主」がもっともよく用いられるのは、やはり新型コロナウイルスの抑え込みに一定程度成功した中国と、対応に苦戦したいわゆる「民主的」な国々を対比する場面です。ウイルス対応で遅れをとった「民主的」な国々に対して、「国民に大きな被害を出しておいて何が「民主」なのか」というような主張がよくみられます。
そして、このような見方は政府だけでなく国民にも浸透しつつあります。国民による中国政府のコロナウイルス禍における対応への評価は非常に高く、それと同時に各国の「惨状」が報じられたことから、「民主的な」国々に対する疑念のようなものがいまの中国には大きく広がっています。
さらに言えばコロナというきっかけがなくとも、多くの混乱があった前世紀や今世紀初頭の中国と比べて、いまの中国は経済的にも文化的にも大きく発展しています。今の中国人はどんどん自国に誇りを持ち、「民主的」な国々にも我が国は負けないんだ、と考えるようになっています。
この番組の中で、ある中国人の学生さんはインタビューにこう答えています。
「コロナ対策を見て、中国政府の指導力が唯一無二で最強だと思いました。(アメリカは)想像していたほど、よくはありませんでした」
(街中に仕掛けられている監視カメラや言論統制をどう見ているかという質問に対して)「この質問、答えなきゃだめですか?普通の人には大きな影響はないと思います。中国では制限が多く、民主的でない生活を強いられていると言われますが、そんなことはありません。今の生活に満足しています。法が許す範囲であれば、何だってできます」
このように国民の支持を広く集める今の中国の体制は、国民の望みに沿ったものであり、国民のために尽くしているという点で「民主的」ではないかという見方も、「中国式民主」の正当性を支える重要なロジックになっているように思います。
これまでの民主主義に対する問いかけではある
これらが真に「民主的」と言えるのかどうか、また政府や国民がいうようにこれらが中国の国情に適したものであるのかどうかという評価は、浅学な僕にはわかりません。違和感を感じることも多い一方で、それなりの筋が通っているように見える部分もあります。
何にせよこれらの「中国式民主」は、これまで世界で支配的だった西欧的な民主主義に対する問い直しを提示するものであるように思います。
政治学者・宇野重規さんは著書「民主主義とは何か」の中で、民主主義を論じる際につきまとう「〜ではあるが、それだけではない」という命題について述べています。
「民主主義は多数決の原理だが、少数者を保護することでもある」
「民主主義は選挙のことだが、選挙だけではない」
「民主主義は具体的な制度だが、終わることのない理念でもある」
このような軸で上にあげた「中国式民主」を見ると、確かにいまの「中国式民主」はこれまでの民主主義に対する挑戦、あるいは挑発のようにも見えてきます。
コロナ以降は特に、民主主義のあり方が世界的に問われています。そのカウンターパートの大きな一つとして「中国式民主」を知ることは、これからの世の中を見ていく上で大きな手がかりになると思います。
これからも「中国式民主」に注目していきたいと思います。
いただいたサポートは貴重な日本円収入として、日本経済に還元する所存です。
