
過去アニメから読み解く時代描写の変遷
①YAWARA!(1990年前後)
連載時期やアニメ放映期間から考察するに、本作品は1990年前後の若者を描いた作品となっている。猪熊柔のモデルとされた田村亮子(谷亮子)が1975年生まれであり、作中の猪熊柔よりも少し下の年齢だが、本作はアニメ化にあたって1992年のバルセロナオリンピックを意識した作品となったため、当時の世相が色濃く表れた作品となっている。
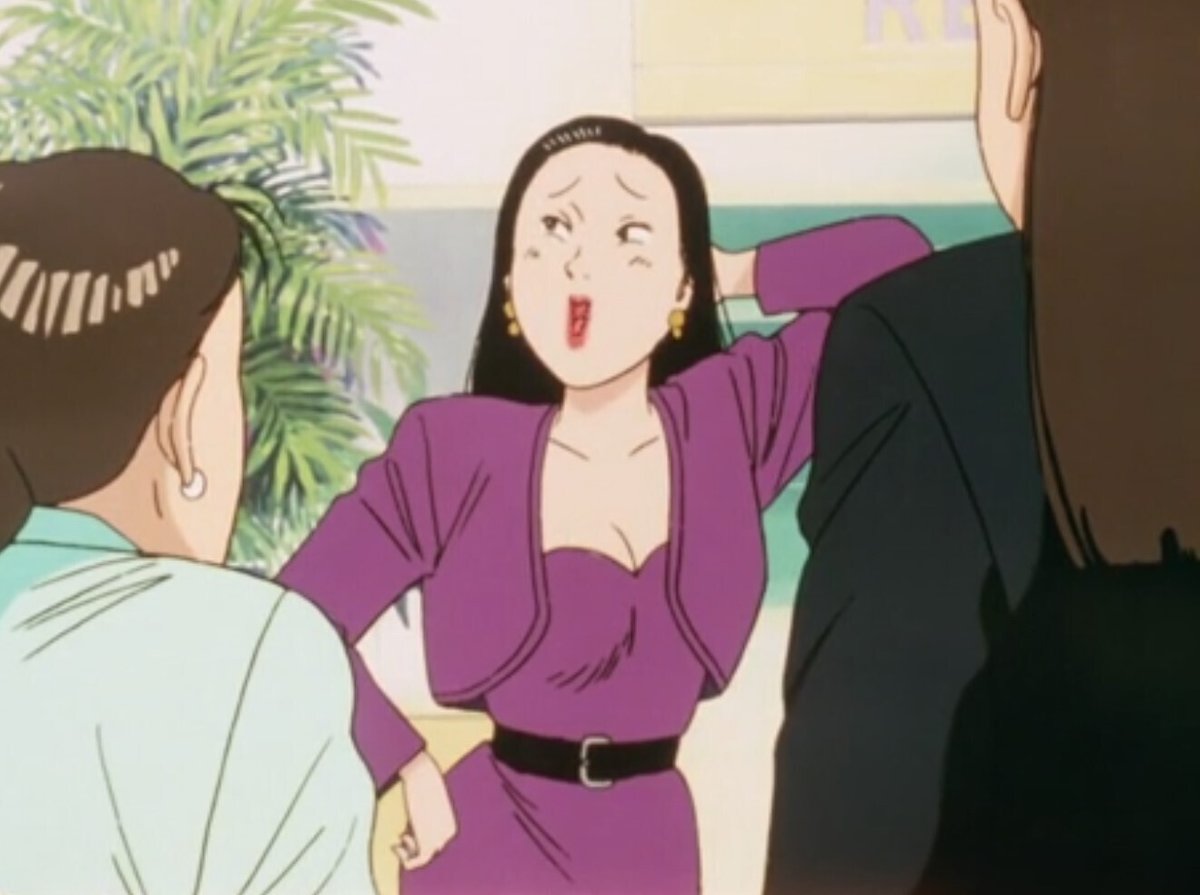
この時代、連載開始が1986年という事もあってか、まだバブルは崩壊しておらず、大金持ちの描写はあっても、金銭に困る様は殆ど描写されていない。お金はマジで無限にあった時代なのだ。ライバルの本阿弥さやかは、本阿弥グループのお嬢様でありで、正しく時代を象徴するキャラの一人となっている。

今だとマジで考えられんが、女子は社内結婚するために就職してたような時代である。

髪型もトレンディドラマの影響で吉田栄作みたいな真ん中分けの青年がイケメン描写されており、この辺もちょっと前の韓国感が漂っている。この辺からも、中国、韓国のファッション関連は間違いなく日本からちょっと遅れたトレンドを歩んでいるような気がするんだよなぁ。
まぁ、でもこの時代の若者達は今よりは結婚・出産こそしていたが、90年代の不倫や離婚ブームで、色々紆余曲折あった世代なんですよね。(1994年出産と仮定して、子世代は今だと30歳位か?)
ちなみに、彼女等の5〜10歳下はバブル崩壊の影響を受けまくった氷河期世代。逃げ切れなかった男子は非正規雇用・引きこもりのボリューム層となり、女子はコギャルや援助交際といった社会問題を数多く起こした混沌とした世代となっています。
控えめに言って地獄が待っていたんやな。
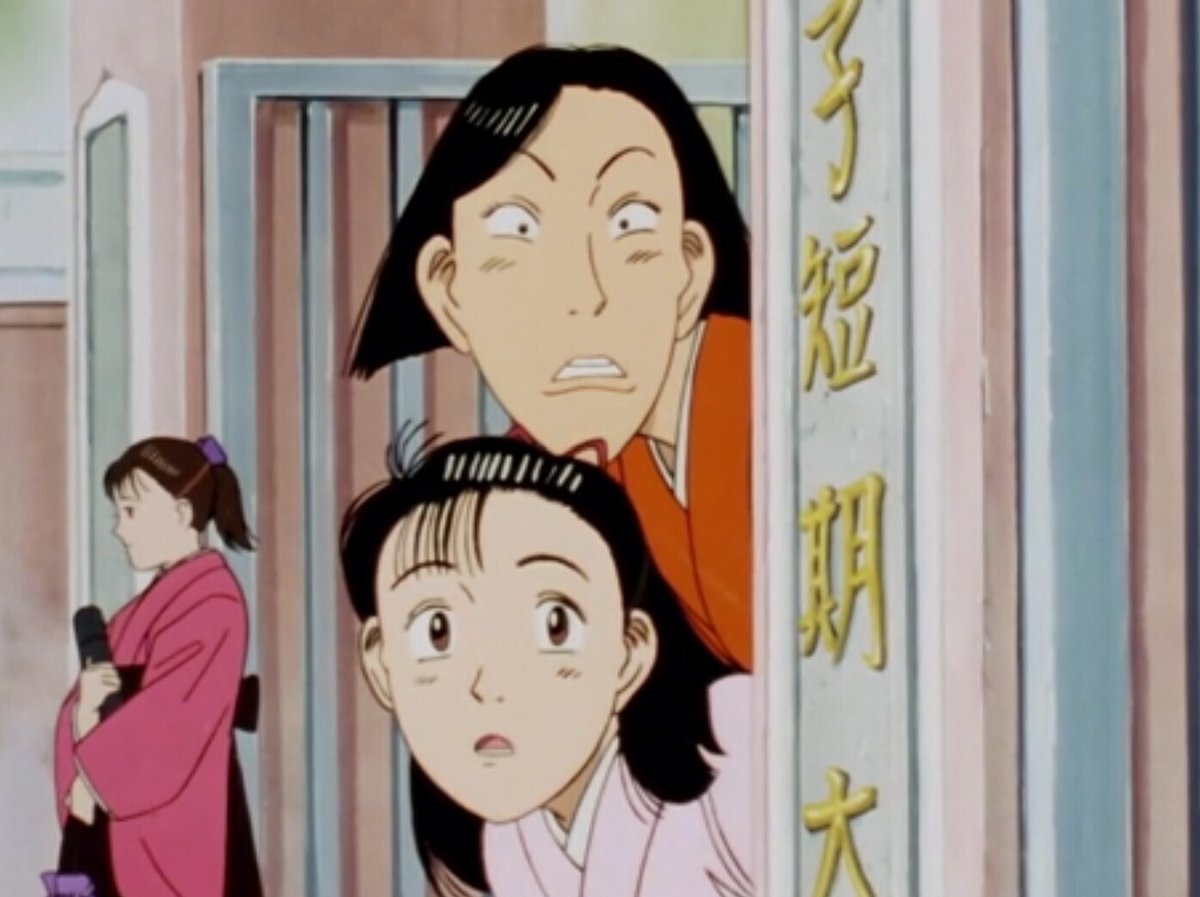
地方出身の自分にはこの光景がマジだったのかどうか知る由もないが、当時の都内の大学ではよくある光景だったのかもしれない。
ちなみにこのあと柔が就職した会社は鶴亀トラベルという旅行代理店で、今では絶滅しかけている社員旅行を主力商品としていた模様。当時の社員旅行といえば観光バスを何台も貸切ってデカい温泉地に行き、宴会場でクッソ寒い宴会芸披露させられたり、翌日ゴルフしたりといったクソみたいな文化だった事は言うまでも無いが、そうした文化はこの頃に醸成されたといっても過言ではないだろう。令和の世になってもあるところにはまだ残存してるから末恐ろしい。
確かこの世代は団塊ジュニアにあたるかと思うので、同年代の数だけはマジで多かった筈だ。1学年20クラス近くあった高校も存在したと聞く。
ちなみに氷河期世代である自分の高校時代から既に少しずつ少子化は始まっており、兄世代で1学年12クラス(480人)、自分世代で10クラス(400人)、私の卒業直後には1学年8クラス(360人)と、急速に子供が数を減らしていたのを記憶している。
圧倒的な人口数の中、同調圧力でこんなイカれた団体旅行文化が当たり前だったんだから、そこに馴染めなかった層もそりゃオウム真理教みたいな危険カルト教団に囲い込まれるわな、って。

これはブルスクではない。当時はまだWindowsがなかったのである。
当時のパソコンはまだ自動計算機の延長線上にあったに過ぎず、手打ちで数字を入れて数字を出したり記録したりといったものが主な機能で、テキスト(ワープロ機能)も今のように豊富な漢字まで充分にカバーされていなかった。
OSは多分、MS-DOSかな・・・。
求められたパソコン技能も今と比べると格段に低い。とりあえずキーボードさえ打てれば熟練者として胸を張れた時代である。
これからはAIの時代であるため、今後の若者はさらに高い知識と技術を要求される事になるだろう。これで給料がこの当時よりも低く、物価もクッソ上がってんだから、そりゃやってらんないよね・・・。
②のだめカンタービレ(2000年代)
連載期は2001年~。アニメは2008~2010年なので、大体2000年代の描写があると思っていいかもしれない。

福岡から上京して音大に通っているのだめであるが、都内で防音の一人部屋に練習用のピアノ、今の一般家庭にここまでの環境を用意してやれる家庭が一体どれほど果たしてあるだろうか・・・?
音大という環境上、あくまで想像する事しかできないが、今も昔も音大はマジのガチで金持ちの子しか行く事はできないのではなかろうか?特に東京藝大クラスになると、それこそ選ばれた富裕層の子しかその門を叩く事は出来ないものと思われる。
作中では中華料理屋の一人息子がバイオリニストで登場しているが、いや、流石にフィクションや・・・と言いたくなる。まぁ漫画だから別にそういう設定の子がいてもいいけどさ。

この頃では大学生がノートパソコンを所持するのも一般化してきている。
パソコンの形から判断するに、初期のセレロンかなんか積んだ14型辺りのTFT液晶モデルと思われる。Windowsは98かMeくらい?ここには線は描写されてないが、まだ今のようにWi-Fi無線環境は難しかったと思われるので、LANケーブル繋いで使うタイプのネット環境(ADSL?)だったのではなかろうか。
ちなみに、まだスタバは一号店の出店が1996年らしく、2000年代はまだ今のように広域での出店はされていなかったらしいので、スタバでMac開いてドヤ顔って文化は無かったものと思われる。
そもそも、この頃のノートパソコンってまだまだ重かったし、持ち歩いてるだけでオタク呼ばわりされていたのではないか。
ソニーのVAIOが一生懸命お洒落路線追及していたような気がするが、バブル崩壊からの不景気はまだまだ続いており、時代が悪かった。
そんな時代だったからこそ、音大で出会った千秋とのだめとその仲間達が才能を磨き、社会や世界に羽ばたいていくという本作のストーリーは、今にして思うと異質だったように感じる。そもそも音大行く人ってお金持ちですからね・・・実家が太い勝ち組ですよ、勝ち組。
しかも当時はインターネットの普及と音源の電子化が急速に進んでおり、CDはどんどん売れなくなっていってる時代で、こんなうまい話があるかい!と、当時見ながら思った記憶がある。
でも、良いんです。これもまた創作なのだから。
③げんしけん(2000年代)
同じく2000年代を描いたオタクの青春物語である。
のだめと違って学生のタイプが全然違うので、同じ時代の作品に見えない。物語の舞台は中央大学がモデルとなっており、全国から若者を吸い尽くしている多摩地区に位置する。

こっちはのだめと違ってかなり若者の解像度が高い。よくある文系大学陰キャのキャンパスライフというものをリアルに描いており、まだそんな昔って感じがしないですけど、もう20年前の世界観です。(絶望)

中央大学って結構規模のデカい大学なので、地方とは大きく描写が異なっている筈である。私が行っていた大学も部活動はあったが、勧誘が旺盛だったのでアメフト部だけで、あとは空気みたいな印象だった。試験の過去問貰う為だけに存在した部活もある。
この作品ではよく分からんサークルが無数にあって、それこそ涼宮ハルヒのSOS団とか、はがないの隣人部、みたいなノリに近い。私は東京の大学は行っていないのでよく判らんが、通常はそういう活動内容がよく分からんサークルは大学が許可しないと思うんだよね。しかし、こういう作品を見ていると、都内の多くの大学ではこういう趣味団体みたいなサークルは割と自由に作れたのかもしれない。
今ではそもそも多くの一般家庭が貧しくなっている為、大学に行く事自体のハードルがクソ高くなっており、学費は親持ちでも生活費はバイトという子も珍しくない。こんな風にサークル活動を楽しめている若者はもうあまりいないのではなかろうか・・・?

たまり場然としたこの作品のサークル棟は、ちょっと自分の大学像とも重なる部分がある。自分らの場合は研究室が割とたまり場になっていたケースが多いのだが、大体陽キャが占拠してしまうので、自分は大学の後半は出席を友人に任せて、ほぼ自宅に引きこもって国家試験の勉強してましたね・・・。

バブル崩壊後の就職戦線を描いた描写は、実に解像度が高い。
主人公の笹原がメンタル的に病んでいく就活編、ここもコロナ禍明けの令和の世と大きく異なる事に注目したい。自分は就職氷河期世代なので、笹原の代よりも更に厳しい時代であったが、2000年前半はマジで100社受けて1社受かるかどうかの時代があった事は事実である。
リクルートが調子に乗って学生を食い物にし、靴下の色は何色がダメだの、お辞儀の角度はどうだの、しょうもない文化を広めまくっていったのである。滅びろや人転がしが。

YAWARA!と比べると学生達の空気にも大らかさがなくなり、将来何になりたい、とか夢を生き生きと語る描写は皆無となる。働くとは何か?という厳しい現実を突きつけたような物語展開ではあったが、望む仕事に携わるには、薄給でも非正規雇用でも我慢・・・みたいな空気があったのは事実である。
そして、この薄給文化は2020年代の今でもまだ続いている。
今年になってようやく昇給の流れが出てきたが、特に社会保険税は20年前と比べても驚くほど上昇している。
ちなみにYAWARA!の時代はまだ賞与への課税は所得税だけで、今みたいにごっそりと社会保険税や住民税は課税されていなかった。
思うこと…
こうしてみると、1990年~2020年代・・・僅か30年で、若者を取り巻く環境はめちゃくちゃ変わっている。こうなると今後は大学生活を描いた漫画やアニメって、かなり描写が難しくなるのではなかろうか?
そもそも、修学旅行すらバスの運転手の確保が難しくてキャンセルになったりする時代。当たり前のように行われていた学生の行事は様々な事情で行われなくなり、林間学校や修学旅行、キャンパスライフ、サークル活動といった定番の表現は、今後急速に描かれにくくなるような気がする。というより、もうこれらが過去のモノになりつつあるのである。
事実、近年のJKモノ・青春をテーマにした作品の主題はオッサンの趣味をJKにやらせる系に移行しつつあり、趣味を通じた少数の仲間達での温泉旅行や海水浴等の水着回は残しつつ、大人数での学校行事を描く作品は年々少なくなっているような気がする。
少なくとも、クリエイター側にもそういう経験が乏しい層が今後は増えてくるはずなので、多くのアニメが描写してきた若者の姿というのは、やはり少しずつではあるが、確実に過去の遺物(文化的遺産)になりつつあるのである。
ファックユーな時代・令和を生きるキッズ達、タフに生きていこうや。

