
【2022.09.15 イベントレポート】異職種が協働してプロダクト開発するカルチャーの作り方 / PharmaX
皆さん、組織やカルチャーづくりにおいては非常に悩みも多く、手探りなこともあるのではないでしょうか?
特に、スタートアップフェーズにおいての組織やカルチャーは非常に大きなissueです。そこで今回はスタートアップの中でも既存産業DXをリードしている5社によるLT形式で様々な事例をご紹介するイベントを開催しました。
こちらではイベントで紹介した内容を各社のレポート形式でご紹介させていただきます。様々な企業の取り組みをぜひ参考にしてみてください。
今回は、PharmaX株式会社 上野氏のLTをご紹介いたします。
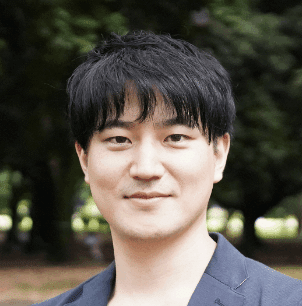
【LT概要】 PharmaXの強みは、薬剤師とPdM ・エンジニア・デザイナーが高度に協働して取り組むプロダクト開発カルチャーです。 ドメインエキスパート(薬剤師)をどのようにプロダクト開発に巻き込むとよいのか、逆に開発者がどのようにユーザー目線・ドメイン知識を獲得していくとよいのかをお話します。
PharmaX 上野彰大氏(以下、上野):よろしくお願いします。PharmaXの上野と申します。私自身は共同創業者で、開発チームの責任者をやっております。開発組織としては、現在7-8名の組織で、今後さらに急成長していきます。
私たちは新しい薬局の形、オンライン薬局を自分たちで作っています。薬剤師、エンジニア等の色々なメンバーが活躍しています。
このように色々な職種の人が恊働してプロダクトを開発するカルチャーの作り方をテーマに発表します。

PharmaXについて〜会社紹介・事業紹介〜
「世界で最も患者/生活者主体の医療体験を創造する〜Design the world’s most poeple-centrered healthcare experience〜」というミッションを掲げています。

我々の事業ドメインは薬局です。薬局は皆さん行ったことがあると思いますが、すごく身近な医療機関であり、日々の中に深く根ざしている存在だと思います。一方で、これまでの薬局は、「薬剤師の仕事のメインは薬の管理」というような対物中心の業務がメインと言われていました。
それをテクノロジーの力を使ってDXをすることで、患者中心、対人中心というような、人に向き合う仕事にもっとシフトしていくべきだと思っています。そして近年その流れが加速しているとも思ってます。
我々の事業としては2つあります。1つ目はセルフメディケーション事業(処方箋を必要としないもの)、2つ目は調剤事業です。
セルフメディケーション事業の方は、例えばCRMツールを開発したり、薬剤師さんが個人にあった薬を提案するようなアルゴリズムを作ったりと、徹底的に患者さんに寄り添った体験を作ってます。
もう一つが、調剤事業です。
こちらについてはDX推進に伴い、法改正が行われている市場であり様々な新しい体験を生み出すことに注力しています。
例えば、処方箋が必要な薬であっても、オンライン服薬指導と言い自宅にいながら薬の説明や受け取りまでできるようになりました。
そして、薬剤師さんと簡単に話してもらうだけで、処方箋が必要な薬に関しても「すぐに受けること」「LINEで気軽に相談できること」ができるようになりました。
そして、我々の強みとしては自分たちで薬局を構えていることです。
SaaSだけに閉じるのではなく、薬剤師さんのオペレーションも自分たちで考え、患者さんの体験を完全に一新していくことを目指しています。
異業種が協働してプロダクトを開発するカルチャーの作り方
ープロダクト開発者が患者・ドメインに対して肌感覚を持つ
今回お伝えしたいことのメインになります。私たちは様々なバックグラウンドを持つメンバーが活躍しています。そのためどのように恊働してプロダクト開発をしているのかお伝えできたらと思います。
(弊社以外にも様々なバックグラウンドを持つ方が恊働する必要がある会社さんも多いと思います。少しでもお役に立てたら嬉しいです)
まず一番重要なことは、プロダクト開発者が患者さんやドメインに対して肌感覚を持つことだと思っています。
弊社のエンジニアは患者さんにインタビューすることも多々あります。定性的・定量的両方の面から、ミクロ・マクロの面からディープダイブします。薬剤師さんと一緒に患者さんの課題を抽出することからエンジニアも含めて第一線でやる体制を築いています。

また非常に特徴的だと思いますが、薬剤師エンジニアが所属しています。彼らは、全体のエンジニア向けに薬剤師の知識勉強会を開催してくれており、ドメイン知識を底上げしていくことに力を入れています。
ードメインエキスパートを中心としたプロダクト開発をする
先程はエンジニアの角度からお話しましたが、今度は薬剤師メンバーの角度からのお話をします。
全員がプロダクト開発に参加できるような体制にしたいと思っており、透明性の高いスクラム開発体制を構築しています。例えばフローは当然可視化したり、タスクの管理においても全員がタスクの優先度が分かるように可視化したりしています。
スクラムのイベントや、試作共有会(今着手しているものの共有会)を開催する等非常に透明性が高く、誰でも意見が言えるような体制を作っています。
プラスして、異職種のメンバー同士が自分たちの課題を抽出してディスカッションしています。薬剤師さんのオペレーション上の課題を吸い上げることができるからこそ適切な優先順位に落とし込むことができています。
また、薬剤師のメンバーに対してITスキルをインプットしていくためのIT勉強会をしています。例えば、エンジニアチームが主導しSQL勉強会を薬剤師さんやロジスティックスのチーム向けに開催しています。実際、弊社の薬剤師さんは簡単なSQLであれば自ら実装できます。
薬剤師さんがオペレーションを進める上で、エンジニアが全て絡まないとPDCAが回らないのは現実的ではないので、自分たちのオペレーションやマニュアルであれば自分たちで変えることができる、いわば薬剤師チームだけで完結できるような体制を築いています。

協働を可能にする仕組みをプロダクト開発に盛り込む
最後になりますが、一番重要なことは、共通の目標や明確な優先順位付けを設定することです。
その上でデータを収集できるような仕組みを作りあげることが必要だと思います。
患者さんの声やアンケート等、薬剤師さんのレスポンスのスピード等が収集ができていなければ可視化や優先順位付けはできないので、収集できるような設計を作る必要があります。
透明性の高い開発サイクルでデリバリし、データ分析を民主化することによって結果を可視化して共有する、サイクルをぐるぐる回していくことによって、皆がどの方向を目指しているのか。今、自分たちがやったことがどういった結果に繋がったのか。
全てのメンバーがわかるような仕組みを作っています。

Q&A
Tebiki 渋谷和暁氏(以下、渋谷):ありがとうございました。非エンジニアがSQLをかけるようにする仕組み作りと、それを体現してくれるメンバーがいることは素晴らしいですね。
上野:そうですね。やっぱり勉強会をしっかり開催するのは大事だと思います。でも正直弊社にジョインしてくれる薬剤師メンバーは、ITリテラシーが結構高いので意外にもスムーズだったなという印象はあります。
渋谷:非エンジニア向けの勉強会の頻度ってどれくらいの頻度で開催しているんですか?
上野:ITパスポート取るために集中して数ヵ月でやりきるのは半年〜一年おきぐらいです。SQL勉強会も集中して2・3ヵ月で詰め込みでインプットしてもらいました。
かなり力を入れていかないといけないですが、やった甲斐があったかなと思っています。その後は、非常にワークするので良かったですね。
渋谷:絶対そうですよね。視聴者の方からの質問を拾いますね。
「プロダクトチームの中でエンジニアサイドとドメインサイドで優先順位が食い違った時はどう解決されていますか?」
上野:優先順位を最後に決める人は明確にしています。弊社の場合はPdMです。我々のミッションとしては患者満足度(患者中心)を大切にしているので、各自に多少の負荷がかかったとしても「患者さんが喜ぶことで優先順位を付けましょう」という行動指針が明確にある会社なので、優先順位は案外揉めないですね。
渋谷:みんなが顧客に向いているということですね。
上野:そうですね。医療業界、医療のドメインの中でも弊社はtoCを主軸にしますよ。ということを謳っています。
渋谷:最後にチャットでたくさん意見がきているのが、「薬剤師エンジニアってすごい!」です。確かにパワーワードですよね。
上野:確かに(笑)最初の仲間集めの時とかもすごくこだわったわけではないですが、今までとは異なる可能性を生み出したいと思っていました。薬剤師エンジニアだけでなく、キャリアチェンジについては個人的にも会社的にもすごく応援しているので最近多方面に増えてきたのは非常に嬉しいです。
上野:ご清聴いただきありがとうございました!
是非また次回のイベントでお会いできることを楽しみにしています。
ここまでご覧いただきまして誠にありがとうございます!
異職種のメンバー同士が恊働しプロダクト開発を加速させているPharmaX。みなさんもなにかお持ち帰りいただけるトピックスがあれば嬉しいです。
PharmaXにご興味をお持ちの方はこちらをご覧ください。
Startup Tech Live
Startup Tech Liveのテーマは「エンジニア組織のグロースに必要な知見の流通」です。
運営元であるGlobis Capital Partnersは、国内巨大産業のアップデート(DX)や日本発グローバル展開を志すスタートアップへの投資を行うベンチャーキャピタルです。我々は、国内産業の更なる発展の可能性や、それを強力に推進するテクノロジーの力を信じています。
Twittter: https://twitter.com/gcp_byvc
connpass: https://gcp-tech.connpass.com/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
