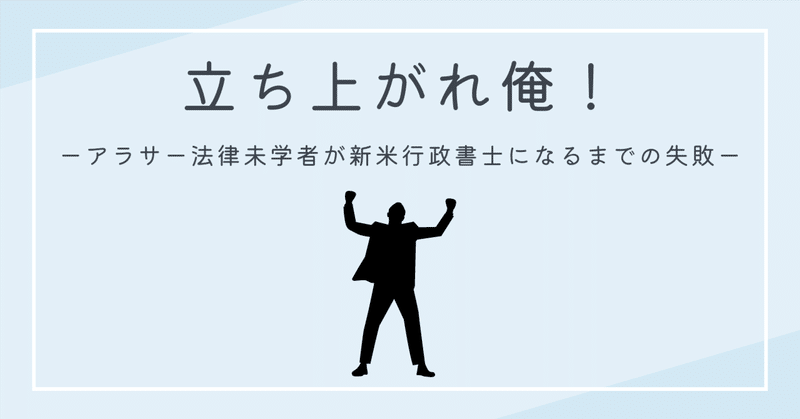
【行政書士試験失敗記】2話 隣の芝生は青く見える
今回から、早速私の失敗をご紹介していこうかと思う。
現在、思い浮かぶだけでしばらくネタに困ることが無さそうなのがなんとも情けないのだが、少しでも、ほんの少しでも誰かの役に立てばと思う。こんな失敗を誰かに繰り返して欲しくない。
私の失敗の1つと言えば、隣の芝生を見過ぎたということだろうか。
隣の芝生は青く見える。そのままの意味のことが私には起きていた。どういうことか。
私は行政書士試験を受ける人間が、自分と同じような人生を歩んできたと勘違いしていた。
ここで行政書士試験におけるスタートラインについて話しておきたい。
スタートラインについて分かりやすいのは高校受験だろうか。
高校受験というものは、ほぼ似たような年齢層の人間が受験する。その背景については差などはあまりなく、程度の差はあれど、一応義務教育を受けた若者が受けるものとして存在している。
私はそれと同様の感覚で行政書士試験というものを見ていた。しかし、それが間違いだった。どういうことか。
ここでどんな人間が行政書士試験を受けるのかを解説しよう。どんな学力の人間が目指すものなのか。
ここで余談ではあるが、学力の話題が出たので、私の学力について改めて。
と言っても、私の学力など別に人様に自慢できるものでもない。平凡。これに尽きる。普通の偏差値の普通科の高校を卒業し、ちょっと変わったカリキュラムの専門学校に4年通いながら、声優になるべく芝居の稽古をしていた。それくらいなものだ。
ここで超有名私立大学卒、国立大学卒! とか言えたならエリートが陥る失敗記! みたいな感じでこの失敗記も面白い方向に言っただろうし、不良漫画に出てくるような高校に通っていて、そこからの合格劇であれば「ヤンキー行政書士」と名乗れたり、それについての成功記を書けたり、ブランディングできたりしたのだろうなと妄想が捗ったりしたのだが、残念ながらそうはならない。
こういう時に改めて、もっと勉強しとけばよかったなんて思ってしまう。この場合、もっとヤンチャしておけばよかった、とも思う。なぜ私はこうまで平凡なのだ。
話を戻す。
結論から言うと、行政書士試験は誰でも受験できる国家試験である。受験資格が存在しない。
記録的なもので言うと、令和4年度の最年少申込者は8歳。最年長申込者は98歳。老若男女誰でもがこの試験を受けることができる。8歳で国家試験に挑戦しようという方がいること自体驚きだし、そのチャレンジ精神には敬意を表したい。
誰でも挑戦できる。これは国家試験の中でも珍しい。
例えば弁護士になろうとする場合、司法試験予備試験に合格するか、法科大学院を修了する必要がある。
社労士になろうとする場合は、学歴要件があったりする。誰でも受けられるものではない。
私はというと、最終学歴が少々特殊な専門学校卒だったので受けられるか受けられないか微妙なラインではあったが、行政書士試験を合格しているのであれば受験できるとのこと。すごいな行政書士試験。
ここで誰でも受けられるということを文字通り受け取ると危ない。
どういうことか。受験生の中には弁護士を志し、ロースクールに通いながら行政書士試験を受ける人がいる一方で、今まで一度も法律の勉強をしてこなかった人もいるということだ。
独身の人もいれば、子供の面倒を見ながら勉強して受験する人もいる。
誰でも受けられるということは、つまり学習のスタートラインは千差万別なのだ。
かく言う私も、法律未学者としてこの文章を書いてはいるが、突っ込んだ話をすれば、前職は不動産業の業界団体で働いていた。業界団体は行政庁と比較的近い関係であったので、行政法の理解は人よりも良かったと思う。行政庁と言われて「ああ、こんな場所ね」と想像することができた。また、これも仕事の関係ではあるが、株式会社の設立に立ち会ったことから会社法の理解も早かったと思う。
逆に私は常識があまり無かったのか、民法と一般知識には最後まで苦戦した。お陰で試験を通して少しはマシな人間に成長できたと思う。ありがたいことだ。
何が言いたいかと言うと、たとえ法律未学者であっても、歩んできた人生で理解しやすかったり、その逆もまた言えるということである。
「あの人ができて、私にはできない……どうして?」なんてことは当然に起こりうる。しかもその責任を自分の努力不足だと錯覚してしまうことが大いにある。
だがそれは間違いだと私は思っている。なぜならば、今まで述べてきた通り、行政書士試験のスタートラインというものは絶対的に平等ではないからだ。
そこを理解していないと、合格するまで、他人と自分との差にずっと苦しむことになる。
自分はどうしてSNSやネットのみんなとは違うのだろう。書いてある通りに努力しているはずなのに模試の点数が上がらない。なぜだ?
疑念はいつか怒りに変わり、怒りは自責に変わり、そしていつかあきらめに変わってしまう。
ただ、そこで一度落ち着いてみて欲しい。
あなたが読んでいる成功記は果たして、あなたと同じ経歴の人物が綴ったものだろうか? 成功記を参考に努力することは必要だが、成功記を真に受けて落ち込む必要はない。
そこに書かれている人物はあなたではないからだ。
私も、受験生時代、色々な人の成功記を読んで悩んだ。
行政書士試験は一発で合格するのが当たり前だと思い込み、二回受験するのなんてありえないと思っていた。
そして、二回目の試験も不合格だった時、結果に対して烈火の如く怒り、それが終わると自分の不甲斐なさを責め、最後には考えることをやめてしまった。
あきらめる、あきらめないの話ではなく、そのままのそのそと生きるだけの物体にまで成り下がっていたと思う。それほど徹底的に折れた。
振り返ってみると、あの時、あきらめるの選択肢が頭に出ないくらい折れてくれたのがよかったのかもとは思ってしまうが。
行政書士試験を受けていると、外から様々な情報が入ってくる。
その情報の全てが、自分に当てはまっている気がして、本来自分がやらなければならないことが疎かになる。
特に独学で進めている時には注意が必要だ。誰もあなたの勉強が正しいのか、間違っているのかを判断してくれる人がいない。そんな時、ネットの海に泳ぐ情報に飛びつき、それを繰り返しているうちに遭難……なんてことが起こる。
隣の芝生は青く見える。情報が溢れた現代において、青く見えるのは物理的に存在するお隣さんだけではない。SNSが発達した昨今、いわば、目の前に何千、何万の隣の芝生があると思っていい。
例えば、あなたがとある模試を受けたとしよう。あなたにとってその模試はとても難しく、自己採点をしても100点を超えるか超えないか……そんな結果だったとする。
そんな時、SNSを覗くと同じ模試を受けている人が何人も結果報告をしている。そこにはこんなことが書いてあったりする。
「今回の模試、簡単だった? 200点超えてた。この調子で頑張ろう!」
その前向きな言葉はあなたを傷つけるだろう。
だが、それを誰も責められない。その人にとってのただの事実を投稿しているだけであるからだ。
我々はその人の背景を知ることなく、勝手に後ろ向きになっているだけなのだ。その時、我々は実質、隣の芝生を見ている。
このように情報ということであれば、我々にとっての隣の芝生は無数に存在するし、その芝生は青く見えるだけでなく、虹色や金色に見えることもある(そう見えるように加工している場合もあるが)。
私自身、情報の濁流に飲まれて自分を見失ってしまった。
優秀な人を見て勝手に落ち込み、別の芝生が紹介しているものに飛びつき、ついに自分がどこに立っているのかわからなくなってしまったのである。これが私の失敗だ。この失敗に気が付くのは3回目の試験に挑み始めるころだったと思うのでかなり根深いものだったと思う。
行政書士試験を受験するあなたに言いたい。
あなたが立っている場所は周りの受験生と横並びでは決してない。あなたはあなたのスピードで合格に向かって走っていくしかない。その差が埋まるか埋まらないか。後ろから追い越されてしまうのかどうかについては全て自己責任だというしかない。
この試験において平等は無い。
無いが、
行政書士試験において、受験生が唯一平等になる日があるにはある。
それは行政書士試験当日である。
この日だけは180点以上を取ったものが合格者であり、それ以外は不合格者だ。
どれだけ努力していようと、努力していないとしてもその日だけは180点取れたものが合格者なのだ。そこだけは揺るがない。
その日までは、自分で自分のことをうまく舵取りしながら進んでいくしかない。
私はできなかった。だから失敗したんだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
