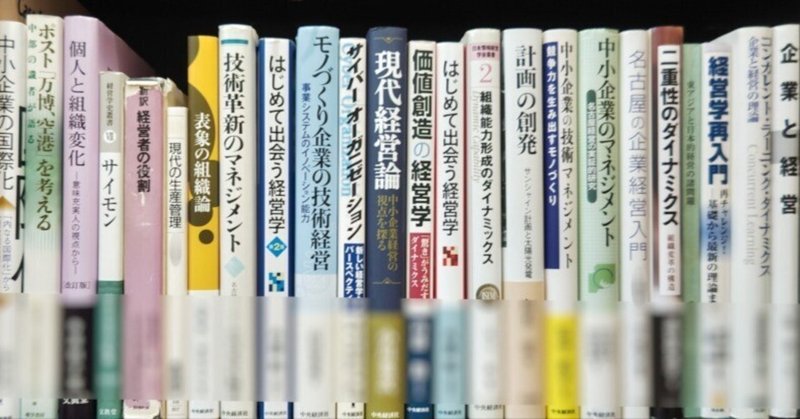
社会科学研究の将来 #1 ~組織論・イノベーション論分野を中核として~
大学を退職して、研究の一線からは身を引いた研究者として、最近の組織論やイノベーション論の研究の在り方について危惧を抱いています。いつの頃からかは判然としませんが、経営学会や組織学会などの組織論やイノベーション論の研究が発表される主要学会では実証が重視されるようになってきました。実証は重要ですが、重要視しすぎる風潮、実証しておけば良いという風潮は社会科学分野の研究や学問をゆがめるような気がします。
理論と実証
例えば組織現象やイノベーションの発生・進行などを説明する理論が存在する場合、その理論で現実の組織現象やイノベーションを説明できることを科学的根拠に基づいて立証することが「実証」でしょう。したがって、実証のためには科学的根拠となり得るデータの収集が必須となります。もちろん、データを収集して、その分析結果から新たな理論を構築したり既存理論を修正することもあるでしょう。しかし、これはデータ収集の後に形成された理論を事前に実証しているに過ぎませんから、実証とは理論が現象を説明することをデータに基づいて立証することと言って良いでしょう。
自然科学は理論と実証の相互作用で発展してきました。例えば、惑星の運動に関するケプラーの法則は他者の観測記録に基づいて太陽を巡る惑星の動きを定式化したものです。先行するデータがケプラーの法則を実証しています。
また、相対性理論はほとんどの科学者が正しいだろうと信じていますが、完全には実証されていません。100年以上にわたって、相対性理論を実証するために様々な観測方法が考案され、観測がなされ続けています。例えば、一般相対性理論が説明する重力場での光の波長のシフトを実証するデータが東京スカイツリーでの実験により観測されています。
同時に自然科学での実証は、実証をした研究者とは異なる研究者による実験の再現や同様のデータの収集によって立証されています。再現性のない実験や観測だけでは実証と認められないわけです。
社会科学ではどうでしょうか。私は組織論やイノベーション論分野の研究者ですからこれらの分野での事情になりますが、自然科学のような理論と実証の関係は形成できていないように思います。
社会科学におけるデータの収集
実証に不可欠なデータの収集は、自然科学では客観性が重要となり、基本的に数量データで収集されます。しかし、社会科学でのデータ収集は自然科学と次のような違いがあります。
社会科学ではおおよそ実験することができません。小さな集団などでの実験を行うことはできるかもしれませんが、条件を同一にした実験の再現は不可能でしょう。
社会科学のミクロ現象の場合、観測することが被観測対象の行動に影響を与えるため観測の再現性が低くなります。
社会科学のマクロ現象の場合、研究とは異なる目的で収集されたデータしか使用できない場合が多く、それらが実証に使えるデータとは限りません。
量的計測ができない場合には、事例研究などの質的データが収集されますが、質的データの収集は収集者の属人的データとなり、客観性が低くなります。
自然科学でも属人性を伴う観察は重要ですが、そのような属人性を取り除く観察・観測手法を探索し、属人性を排除してきました。また、観測が観測結果に影響を及ぼすようなミクロな現象についても、観測手法の探索が行われ、観測結果で議論が進みます。
社会科学の分野、少なくとも組織論やイノベーション論の分野において、収集データの客観性と再現性について特別に触れることはほとんどありません。データ収集の方法は述べたとしても、上記のような特性からの脱却についてはあまり触れられません。「半構造化インタビューによってデータを収集しました」という逃げ口上でごまかすことはあっても、データ収集についての属人性の排除については語られることはありません。
データの特性を無視した実証偏重の結果
再現性のない実験や観測で入手したデータに基づく実証は何を実証しているのでしょう。極端なことを言えば、実験対象群に限られた、観測対象群に限られた「理論」を実証しているに過ぎません。研究者はそれぞれに私の観測データに限定された「理論」を構築できるだけになります。これでは広範な状況で利用できる理論の構築はできません。
もちろん、実証すること、実証しようとすることは重要です。私は実証することを否定するつもりはありません。しかし、データ収集や収集されたデータの性質について何の問題もないことにして、「統計的な分析をしておけば実証できているでしょう」という姿勢や「半構造化インタビューだから実証的事例研究でしょう」というような姿勢の「実証研究」は「実証」だけを目的とした研究に堕していると思います。
最近の若い研究者の実証研究には、ある程度広範な状況において成立する理論を実証しよう、あるいはそのような理論を形成するためにデータを処理しようという姿勢がなくなってしまっているように思います。実証を重視しすぎて論文を評価する社会では実証のための実証がはびこり、社会についての理解を深めたり、社会的な問題を解決したりすることに役立つ理論を形成することに資する実証研究が駆逐されていくような気がします。
理論との関係を持たない実証は「事実の記述」であっても研究ではないと思います。局所的・局時的な理論(もどき)を提示したとしても、それはやはり「事実の記述」にとどまります。いかなる研究もそれは何らかの形で理論形成に資するものでなければいけないと私は考えています。したがって、実証のための実証がはびこる学会では理論の形成が阻害されるのではないかと危惧しています。
ここで述べたことは「実証」できるものではありませんが、自然科学とは異なる社会科学における実証偏重は社会にとって役立つ理論を形成することには繋がらないように思います。最後にくり返しますが、実証しようとすること、実証することは大変重要です。
2024年5月22日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
