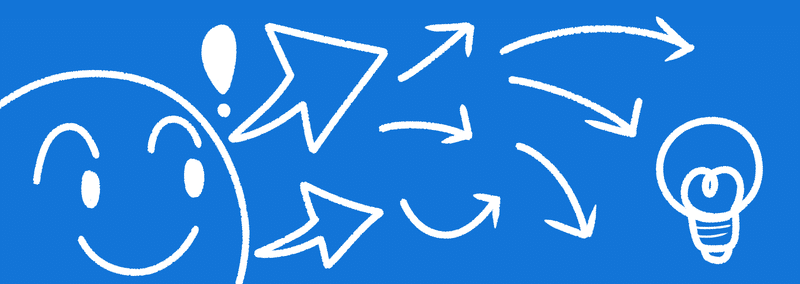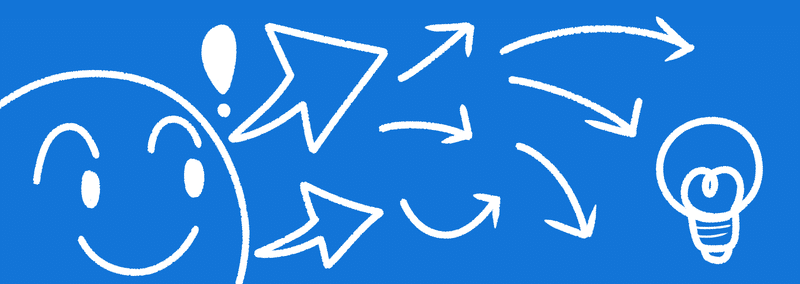【第2回】アウトライナーに向いた人
前回の記事はこちら▼
「アウトライナーに向いた人」とはどんな人かやままさんはアウトライナーに向いた人だという感覚がありました。もっというと、アウトライナーを必要としている人だという感覚がありました。やままさんとは数回しか会ったことがなかったのですが、その数回の会話の結果として勝手にそう思っていました。もちろんこれは私がアウトライナーフリークだからという面が大きいのですが、とにかくそう思っていました。
アウトライナーは「2,000字ならなんとか書けるけれど20,000字は書