浅倉透と言葉について +感想を語るということ
※当記事には浅倉透のTrueEndイベントなどのネタバレがあります
1.はじめに
この記事の主題は、浅倉透を通して”言葉”について語るということをしたいというというところにあります。
あくまで後者が主題です。だから、『アイドルマスター シャイニーカラーズ(以下『シャニマス』)』において、浅倉透がシナリオ上どういうキャラクターとして描かれているかという考察は必然的に少なくなっています。というかほぼ無いに等しいです。ごめんなさい。
それでもなぜわざわざ浅倉透というフィルターを通して、言葉について語りたいかと思ったかといえば、下記ツイートがその動機の一つにあたります。
浅倉透、語彙力がないと言われがちだけれど、言葉に表す意義を見出せていないっていった方が適切だと思う。野暮。
— 国家理性ちゃん (@pacopaco_pa) May 7, 2020
本記事の内容は当該ツイートの肉付けにあたるといって差し支えありません。語彙力がないと称される浅倉透のフォロー(的ななにか)ができればいいなと思っています。
言葉そのものを語ることによって、「語彙力がない」と形容される浅倉透のキャラクター性に何らかの示唆が与えることができるのであれば幸いです。
2.浅倉透と言語
浅倉透は口数が少ないキャラクターだ。語彙力が少ないと俗に言われる。しかし、「無口キャラ」と単純にカテゴライズできるようなキャラクターでないことは、彼女のプロデュースイベントを一度でも読めば明らかにわかる。
浅倉透の口数の少なさ、言葉にすることの忌避にはある種の思想がある。浅倉透は「言語化」という作業を嫌っている。というより、くどくどとした言葉で育まれるコミュニケーションよりも、無言の空気感で通じ合える関係性の方に惹かれると表現した方が適切だろうか。プロデュースイベントの「ていうか、思い込んでた」において、その傾向は特に顕著にあらわれている。
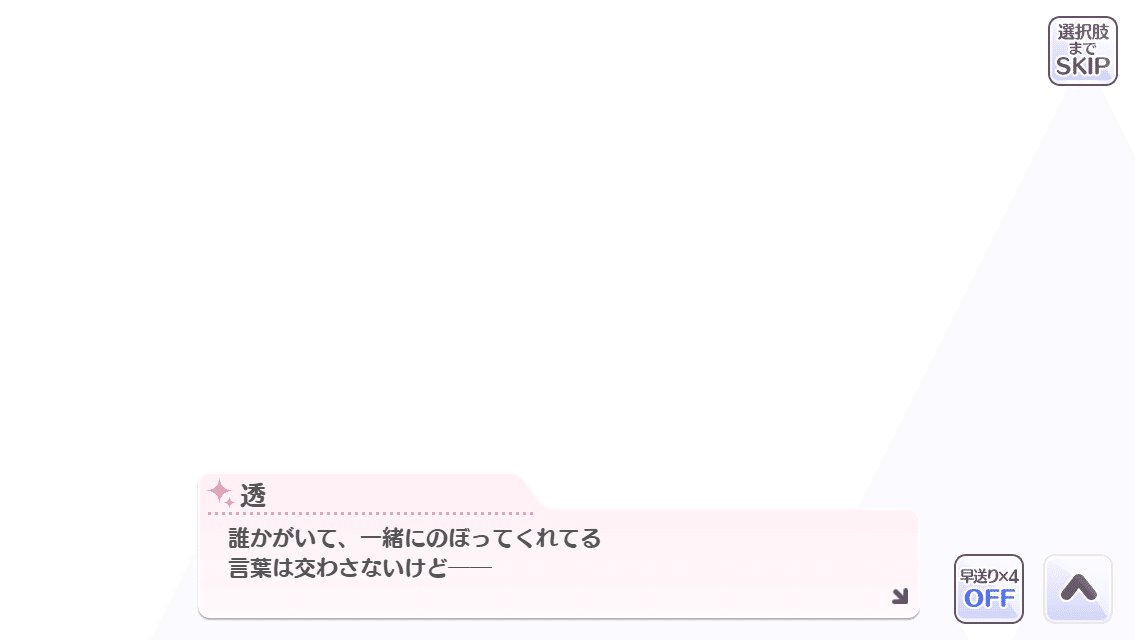

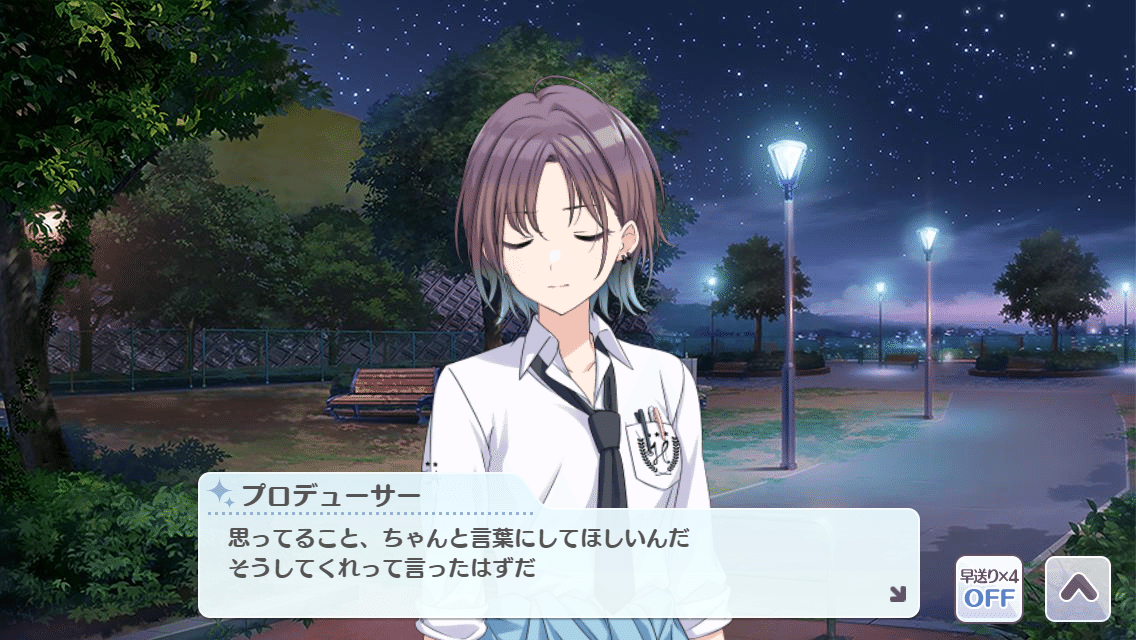
言葉によるコミュニケーションを求めるPとそれに辟易とする浅倉透の表情。かわいい。
とはいえ、後のプロデュースにおいて、浅倉透は映画の「感想」を語ることによって言葉による歩み寄りを果たすのだから、必ずしもそれ(言葉にしないこと)に固執しているわけではない。

しかし、浅倉透の日常的コミュニケーションに無自覚にしろ自覚的にしろ、言葉にすることへの敬遠があることは明らかだろう(とはいえ、この傾向は一般的に私達が少なからず持っているものであるように思われる)。


上記浅倉透と樋口円香のサポートイベントの会話の意味するところは、一見する限り、わかりやすいものではない(少なくとも私には彼女らの台詞が意図するものについて、つかみきれなかった部分が多かった)。この2人の間のコミュニケーションは言葉をほとんど必要としない。ちょっとしたしぐさが一文以上の意味で伝達される。
だからこそ、この2人の中で通じるような幼馴染的言語ゲームを共有していないプロデューサーにとっては、浅倉透の中の普通のコミュニケーションは不安を煽るものにほかならなかった。浅倉透にとって普通の言語はプロデューサーに共有された言語ではなかったのである。
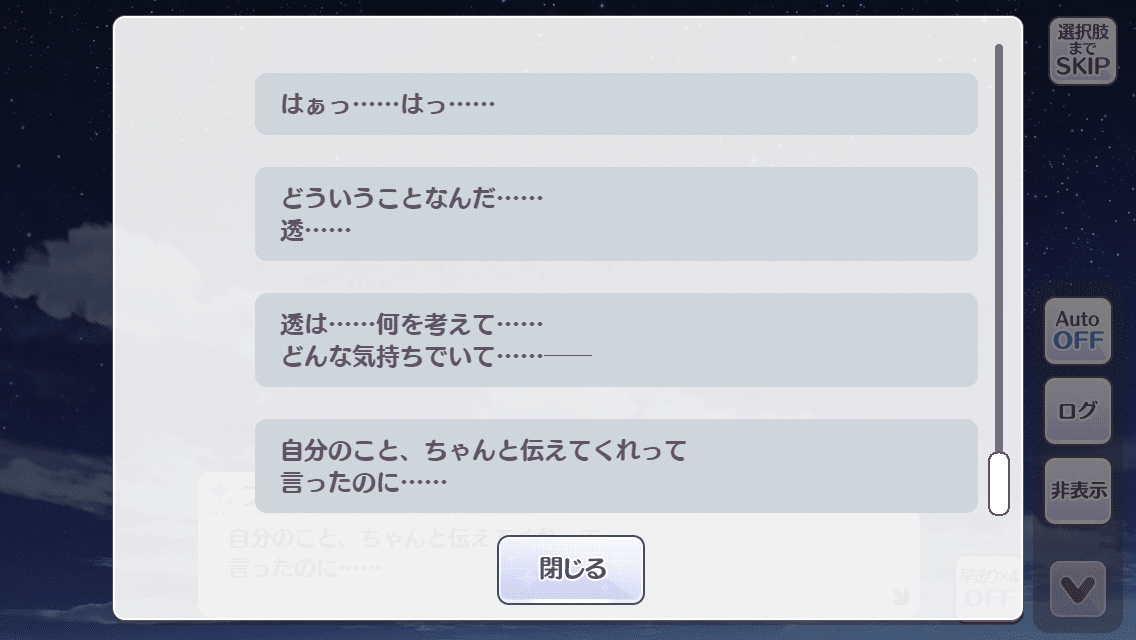
浅倉透の短い台詞で見せる心理描写の機微として特徴的なものに、市川雛菜Nのサポートイベント【StringTEL】を挙げることができるだろう。

![]()

上記画像のサポートイベントでは「部屋が狭い」という浅倉透の台詞が2回続けられており、1回目と2回目では明らかにその意味するところが異なる。1度目の「部屋が狭い」は1人用の部屋に3人が集まることの窮屈さを示す意味で用いられている(ように思えるが、雛菜と円香のギスギスとした空気感という共通の文脈からすると、後述する二度目の部屋が狭いに連なる精神的負担がここに現れているようにも解釈できるかもしれない。ここでは深く立ち入らないが)。
対してこの2度目の「……部屋、狭いなー」には、物理的窮屈さのみならず、浅倉透の精神的閉塞感が色濃く反映されている。脱線を恐れながら、この記事の結論を一部先取りして述べると、同じ言葉は同じ意味をもたないという典型的な例がまさしくこれにあたる。
よく引き合いに出される反転図形――あひるのくちばしの絵がアスペクトを変えるとうさぎの耳に見えるようなだまし絵をひとつ例にとろう(下図は『哲学探究』でウィトゲンシュタインがジャストロウ(Fact and Fable in Psychology)から借用した絵を私が真似たもの。絵が下手でよくわからないって人は「あひる うさぎ だまし絵」とかでググってください)。

上のような反転図形は、一般に「見るということには解釈が前提されている」という類の知覚に関する理論を正当化する典型的事例といえる(上図を借用したウィトゲンシュタインの見解が必ずしもそうでないことは強調したいが、ここでは深く立ち入らないことにする)。
いずれにしろ、見る対象が同じものであっても、その受け取り方が一様でないだろうということを想像することは困難ではないように思える。
同様のことは言葉のレベルでも起こりうる。
3.言葉という虚像
言葉の意味は、たとえそれが同じ文字列であっても、状況に応じた変化が生じる。たとえば私が「石が欲しい」と述べたとき、その「石」はシャニマスないし他のソシャゲをプレイする文脈であれば、主にガチャで消費されるデータになるだろうし、河原で遊んでいる時には、その辺に落ちている手で掴み取れるサイズの硬くてつるつるとざらざらが入り混じったものを指すだろう(この河原における文脈で発せられる「石」は一般的な使用法だろうが、そのような状況であっても、私は石の正確な定義を考えながら「石」が欲しいなどといっているわけではない!)。
ロマンチックなたとえに変えるならば、有名な「月が綺麗ですね」という言葉は、夏目漱石の例のエピソード(これが創作かそうでないかはここでは関係がない)を知っているかどうかで意味が様変わりするだろう。
私達が何かを見て、何かを感じて、何かを発するとき、そこには物語性、劇性が前提される。言葉や振る舞いは、共同体において、生活という反復練習をすることによって獲得され、そして生活という劇のなかで行使することができる公共的なスキルだろう。「わたし」がある感情を発話する際、それは私個人の感情の直接的記述といえるのだろうか。
言葉というフィルターを通して物事を考え、感じるとき、果たしてそこに私秘性をこめることなどできるのだろうか。。
私達の現実には語りえないもの、あるがままが存在するとしよう。このあるがままは、言葉でろ過しようとするとたちまち神秘から外れたものへと変容してしまう。だから、ある人々にとっては言葉は「知性に暴力を加えてすべてを混乱させ、そして人々を空虚で数知れぬ論争や虚構へと連れ去る(ベーコン,F『ノヴムオルガヌム』p85)」ような虚像として捉えられる。
公園に散歩にでて、適当な樹を眺めたとしよう。今私がいる地点には木の葉がパラパラと落ちてくる。私は、自分の目の前に落ちてくる緑色がかった楕円形の物体それぞれを全て木の葉と呼んでいる。しかし、この木の葉一枚一枚が全く同じであることは決してないだろう。重さなり形なり何らかの差異が私の目の前に落ちて一緒くたにされる無数の木の葉それぞれにあるはずである。しかし、私が木の葉を「木の葉」と呼ぶとき、その差異は捨象される。こういった考えに則ると、世界そのものを語るツールとしての言葉には限界を感じざるを得なくなる。
現実を表わす手段としての言葉はまがいものにすぎない。とはいえ、私達の経験は大体が何かしらの模倣、贋物の上になりたっている。小林秀雄が述べたような例でいえば、私達は音楽をレコードで聞き、文学を翻訳で読み、絵を複製で見るような「翻訳文化」と蔑視される生活の中で生きている。そこにあるのは、偽物と本物という二元論ではなくグラデーションである。度合いでしかない。本物というものがあったとして、そこにより近いか遠いかだろう。
だから、開き直って偽物の言葉を紡ぎ続ければいいのだろうか。いま、このあるがままを言葉で表現しようとしても、なかなか難しい、なんとも言いようのない感覚につつまれるということがある。言語化ができない。いま体験しているこのありのままを適切な言語としてすくいだすことができない。
ナンセンスな言葉、言葉としておかしい言葉、本当でなく偽物としか思えない表現がむしろその状況を表わすのにより適切に感じてしまうような場合がある。
ナンセンスな言葉を多く生み出す代表的なキャラクター(表現が不適切に感じるようであれば「ナンセンス」を「詩的」と読みかえてもいい)として幽谷霧子を挙げることができる。
彼女が発する「恋鐘ちゃんは……春に似てる……」や「お魚さんたち……タンスから……出たいって……」といった言葉は、言葉の意味を世界との関係において把握する限り、意味を持てない。それでもなんとなく私達はその意味を感じることができるだろう。


世界を表わす像としてその言葉がまるでふさわしいものでなくても、私達はその意味をコミュニケーションにおいて感じることができる。それをナンセンスと一笑にふすことは、それこそ野暮というやつにほかならない。
このような詩的表現のキモは、その文が真であるかどうかといったつまらない問題ではなく、聞き手としての私達に感ずるところがあるかどうかにあるだろう。その意味で、詩的表現をナンセンスとしながらも、コミュニケーションとしてのその役割は尊重するといった立ち位置を取ることは可能である。比喩や詩的表現を愛する人にとってみても、そういった言明にはそれほど違和感を感じられないように思える。
それでは、逆に、詩は世界そのものを表わすことはできないのだろうか。
そんなことはないだろう、ナンセンスな比喩はむしろこのあるがままの世界を映し出す度合い、グラデーションをより濃くするための第一歩であるように私には思える。
明らかに恋鐘ちゃんは春そのものに似ているわけではないし、着物に描かれた魚がタンスから出たいと思うことなどない。しかし、恋鐘ちゃんが春に似ているという言葉から私たちは恋鐘ちゃんの明るさに関する新たな表現を獲得することができる。それはさながら前述した、うさぎとあひるのだまし絵のようなものである。詩的表現はナンセンスかもしれないが、世界に対する異なったアスペクトを提供することができる。
とはいえ、「恋鐘ちゃんが春に似ている」という言葉それ自体から、恋鐘の陽気さあたたかさを引き出すことができるだろうか。いま私がその文にその意味をくみ取っているのは、その台詞が発せられた【綿毛ノ想】のサポートイベントの文脈を知っているからであるし、「春」という語の表情を今までの人生の経験から季節それ以上の意味として反復されて扱われることを知っているからである。
言葉の意味は、その文脈によって生み出され、また、その反復使用によって定着させることができると言うことが可能かもしれない。ただし、付言すれば、単独の一文それ自体が無意味であるとは必ずしもいえないような気もする。文脈によって文の意味を形作ることが可能であれば、文から文脈を作成することもできるからである。
「わたしは、この文の文脈をつくりだすこともできるかもしれない。」
とウィトゲンシュタインがいう通りである。
文は可能性を生み出すことができる。
4.語るということ
浅倉透に戻ろう。浅倉透と言葉に関する、私の元々の問題意識はどこにあっただろうか。記事の冒頭では、言葉足らずの浅倉透のフォローがしたいといった、もっともらしい建前を立てている。今、浅倉透に立ち戻って言葉について考えている自分の感情を踏まえると、口数が少ないことをもって「あいつ何も考えてないよ」と(悪気はないにしろ)くさす、一定層のプレイヤーにいいようのない不満を抱えていて、その発露がしたかった、と述べた方がより正直で適切だったような気もする。
私自身は浅倉透の語彙力の多寡についてはコミュの少ない現段階では判別ができないと考えているが、いずれにしろ、何も考えていない(極端な物言いを引き合いに出すのはあまりよろしくはないが)ということはないように思われる。
上述した「部屋が狭いな」に現れているように、浅倉透の短い言葉からは彼女の言葉にしない感情の機微を見て取ることができるし、【10個、光】の4つめにおけるプロデューサーとのある種意固地なやりとりを読む限り、彼女なりの生活形式、ルールがあることがわかる。
浅倉透は会話の中で、かなり思考を張り巡らせているように私には思える。はじめに、浅倉透は言いようのない感覚を言葉にすること、言語化することへの忌避感があるのではないかと述べた。私はここに、浅倉透と幽谷霧子の対立軸をどうしても見出してしまう。
霧子はその独特の感性からナンセンスな言葉――詩を生み出すことに長けている。世界そのものをすくいとり、童話的世界としてそれを言葉に描くことができる。言葉を通す限り、世界そのものをあらわすことはできない。一文でナンセンスな言葉は、文脈を生み、反覆し続けることで新たな意味を獲得することができる。世界の有りようは無限だが、限界的な変化で近づくことはできる。ただし、その「言い表せない」世界の事象を言葉にするという作業(いわゆる言語化)は、普通の人間にとって苦痛この上ないように思われるが。
透の場合は逆だ。ジャングルジムに登る2人という童話的体験をプロデューサーに対し、言葉で共有するということはしない。ジャングルジムに登るという「実践」を通してプロデューサーに訴えかける。

再三、述べたように、このあるがままの世界の奇蹟を言語でそのまま映し出すことはできない。せいぜいその本物に近づける度合いを高めることができるにすぎない。しかし、その度合いを高めることは容易ではない。
本物――ここまでくると「物自体」というありていの単語を用いた方が適切なのかもしれないが――に言葉で近づこうと思うなら、霧子のように既成の言語では捉えられない、ナンセンスな詩を紡ぐほかない。
しかし、私達には「行為」という手段が残されている。言葉など用いずとも、言語ゲームという劇場において、私達はあるがままを「身体」によって伝達することができる。スラッファが示した寓話のように、ナポリ人の慣習では「指先でアゴの下を外に向けて、掻くのと反対の方向にこする」ような身体の仕草で侮蔑を表わすこともある。
原初の楽器として、私達の身体は音楽を奏でることもできる。なぜ変ロ短調の楽曲を聴くと、教えられたわけでもないのに、原初的な恐ろしさを感じてしまうのか。なぜ和音の進行がドミナンドコードで停止すると、いいようのない気持ち悪さ、不安定感を感じてしまうのか。
それこそ、浅倉透という人間の身体美は、言いようのない神秘が示されている。とまれ、浅倉透は言葉ではなく、ジャングルジムを登るという行為によって、プロデューサーに浅倉透にとって忘れられない脳裏に焼きついたあの過去を呼び起こそうとしたのである。追憶は言葉でなく体験によって想起されるほかなかった。
最後に、浅倉透SSR【10個、光】のTrueEndについて語りたいと思う。
浅倉透は町中ではなく世界中が見渡せる丘の上で、いま・ここの世界が誰のものなのかプロデューサーに問いかける。プロデューサーは決まり文句的な返答をするが、浅倉透はうまくそれを言語化することができない。


ここにおいて、浅倉透の語彙力がないといえるだろうか。
「私の」世界の所在を浅倉透は語ることができない。「世界は私の世界」であることが語りえないのは、その命題が無意味であるからである。
しかし、それを示すことはできる。プロデューサーとのコミュニケーションを通して、浅倉透は自らのありかを確認することができる。
プロデューサーの隣人として立っている「いま・ここ」を。
5.結論的覚え書き
シャニマスの深い考察やら感想に対するお気持ち的な文章を最近たまに見かける。「長文で言語化できないからシャニマスのシナリオに関する深い感想がどんどん生み出されるこの風潮に気後れしてしまう」だとかそういった内容だ。この記事についていえば、シャニマスに関して深く語っているわけではないので、シャニマス自体の考察ないし感想としては、恥ずかしい浅い内容だと本当に思う。
ただ、この恥ずかしい本記事に関連してそのような風潮に対しコメントするとすれば、語りえない感情を無理に言語化する必要はないということになるだろう。WING優勝後コミュの浅倉透がジャングルジムを踏みしめる音、TrueEndで浅倉透が見つめた世界の景色、星の美しさについて、そのままの(「いかに」あるか、ではなく「ある」ということの)感動を言葉にすることは不可能この上ない。語りえないことを胸のうちにしまっておくことは、祈りと等しく神聖な行為だと思う。
それでも、そのあるがままを自分のものとして掴み取ろうとしたとき、僕は言葉に頼らざるをえない。世界の存在という奇蹟を手に取るには、おなじ言葉という奇蹟を使用するほかない。言語のなかに、世界の存在を表わす表現はないが、言語そのものの存在は世界そのものと同様に奇蹟的なものだとみなすことができるから。
だからこそ、語りえないものについて沈黙できずに、ナンセンスを語ってしまうのである。
#シャニマス #アイドルマスターシャイニーカラーズ #浅倉透
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
