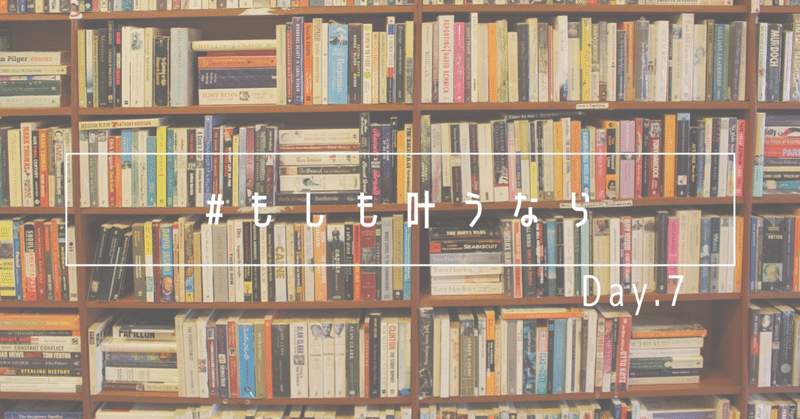
現実を生きたい。
障子のすき間を吹き抜けていく風のような人間に会った。留まることを知らず、孤独も愛も同じ味がすると言うような雰囲気だ。その人の、霧の中をぬって歩く声が私の耳に届くたび、メガネの額縁が黒光りしている。
その人は言う。誰にも見せていない原稿が山ほどあると。生きるために書いている側の人間の言葉だ。他人からの評価も、言葉をお金に変えることも、生きることに比べたらどうだっていいのだ。
見せてはくれないその人の世界は、混沌としてるのだろうか。その人は「あのときに死んでもよかった話」をしてくれた。日本海の黒くうねる色、思いとどまった気持ち、一本の電話。
生きるも死ぬも人間の気まぐれだ。他人の命の話を聞いているのもただの偶然にすぎない。偶然今もその人は生きていて、私も生きていた。特別なことは何もなく、ただ現実が秒針と共に流れていくような時間だった。
その人はその人でしかなく、私は私でしかない。お互いに「自分」であり続けなければいけない時間を一緒に過ごしていた。見せない世界でその人は、幸せに生きているのだろか。
見せない世界で人間は、人間でいる必要はない。私たちは雲にも虫にもなれる。普段は喋らない植物が歌い、三日月が綺麗な夜空の中を自由に飛び回る。欲も悲しみもなく、柔らかい羽根に包まれてる感覚の世界だ。
私を捨てられる世界と言い換えてもいい。穴の開いたバケツに自信を注ぎ込んでいる性格も、満たされない寂しさも、無知で暴力的な人間性も、私から剥がれ落ちて大きな音を立てる。
孤独な時間だけが私を全て許してくれるのだ。右の崖に夕日が沈んでいく海辺も、近くて遠い新宿の夜景も言葉なしに私を軽くしてくれた。隣の席で談笑する人たちを見て、私の孤独は深まっていく。
持っていなくても生きていけるもので世界はあふれているのに、幸せそうに他人が何かを持っていると同じように欲しがってしまう。羨ましくて、惨めで、寂しくてたまらない。
孤独は寂しさと紙一重である。孤独が無ければ生きられないのに、見せない世界は寂しさで歪む。寂しさが弱点な矛盾した孤独世界なのだ。私は現実も生きる必要があると感じる瞬間だ。
紙とペンを取り出して、見せない世界を現実に落とし込んでいく。文字の中で孤独が色づき、香りが漂う。目を閉じて、羽根に包まれた感触を思い出しながら書き続けた。私は現実を生きている。
満たされい寂しさは、夢中がかき消していく。他人が持っているモノも見えなくなり、幸せそうな笑顔のおこぼれをもらう。笑っている人間ほど生命力に満ち溢れている。温かいのだ。
私の孤独世界が作品になるまで、幾度と惨めになり寂しさと戦うだろう。それでも私は生きる選択をする。生きるも死ぬもできない現実は苦しかったが、物語はいつもそばにあった。
何冊も本をつめ込んだ重い鞄をさげて電車に乗った。苦しくなったときに逃げ込める世界はたくさんあるほど安心できる。腕にのめり込むフォークの幻影も、非常階段から落ちていく妄想も物語が止めてくれた。
部屋に積みあがった物語を見つめ、私の生きられる世界はたくさんあるのだと安心する。私が人生を一休みできる物語たちだ。物語は孤独の世界にねじ込んでくれる。
何度でも言い聞かせよう。私は現実も生きたい。現実を生きなければならない。だから今日も書こう。書き続けよう。エッセイでも小説でもいい。私は、書いて生きている。
**
その人は立ち入らなかったが、無名の作家が書いた物語を積み上げた店と出会った。私が何年も通っている雑貨屋の隣にある店なのだが、初めてその店に気が付いたのも奇妙な話だ。
調べると何年も前からその店はあった。物語が詰まりすぎて、現実との境目がぼやけるような空間だった。作家の見せない世界が作品として並んでいる。夢が詰まっていた。
私の作品もいつかはきれいに装丁されてここに並ぶだろう。そう強く感じると、拍手が響きカラフルな紙吹雪が舞った。私は現実を生きたい。書いて、書いて、本を作りたい。
もしも叶うなら、本を作りたい。書き続けよう。私は現実を生きたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
