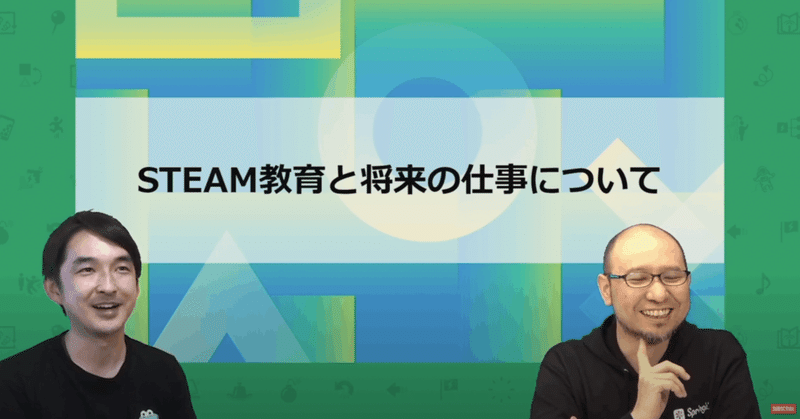
STEAM教育と将来の仕事について【後編】 開発者対談レポートvol.5
2021年10月29日に開催された、しくみデザインのオンラインセミナー「未来の可能性を拡げるSTEAM教育―「できた!」原体験は創造の原動力―」。
今回は、ソニー・インタラクティブエンタテインメント、「toio」の開発者、田中章愛(たなか・あきちか)さんをお迎えして、「できた!」という成功体験の重要性と、STEAM教育と将来の仕事について、お話を伺いました。
聞き手は、創造的プログラミングアプリ「スプリンギン」の開発者である株式会社しくみデザイン代表の中村俊介。
vol.5の今回は、前回に引き続きSTEAM教育と将来の仕事についてお送りします。
動画本編はこちらをご覧ください。
STEAM教育と将来の仕事について
今はない仕事を創り出す
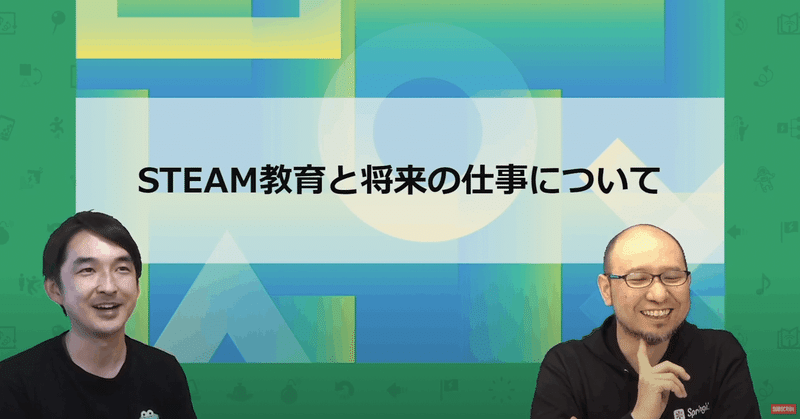
中村:僕は結局、就職活動をほとんどしてないです。それで、ドクターまで行き、芸術工学という博士号を取りました。なんでドクターまでいったかというと、就職したくなかったから。それに、こちらからお願いして会社に入るってなんでなのと。
今となれば、当然そうでないとはわかりますが、当時は「就職活動しなければいけない」みたいな同調圧力的なものを感じたし。就職とは、いろんなサイトに登録して、エントリーシートをいっぱい書いて、そこから面接を進んでというものだった。僕には最初から無理だと思っちゃったんですよね。
それで、研究よりはメディアアーティスト活動の方が途中からメインになり作品を作っていたら、九州工業大学で産学連携センターを作るときに、若くて、「工業じゃないけど工業っぽいことをやってる人」、「アートっぽいというかデザイン寄りだけど、ちょっと工学もかじってるような人」を探してるっていう、すごいピンポイントで引っかかったんですよ。
それだったら面白いかなと思って。大学の講義は年に1、2回しかなくて、研究メインと産学連携だったので、先生方の研究をどうやって世の中に出して、実際のものとして使えるようにしていくかみたいな部署に立ち上げから関わることができた。
そこで、僕は一人産学連携みたいなことをやり始めて。研究者でもあるし、自分の作った会社もあるし、自分のやっている研究を利益相反にならないように、そこは大変だったんですけど。会社のメンバーが作ろうとしている新しいことと、元々僕がやっている研究を組み合わせることで、新しい産業を生み出すことを始めたんですよね。
それって結局、今ある仕事のこれをしたいとかではなくて、今やってることって世の中にどうやって出したら面白いだろうねというところから始まっている。仕事を創り出したとも言えるかなと。
だから、田中さんとすごく近いと思うところがいっぱいあります。いいと思ってやってたら、それがいろんなつながりによって、仕事につながっていったとか。
結局やりたいことって、僕もそうですが、自分が欲しいものを作るというよりは、自分が作ったものでどれだけ多くの人が笑うか、喜ぶかということが楽しくなってくる。
そうなると、作ること自体が楽しいし、世の中の役に立っているかどうかは分からないけど、世の中の人に少なくとも影響は与えてるということがだんだん面白くなってきて。
それを、どんどん規模を大きくしていこうと思ったら、ビジネスを大きくするか、ツールの利用の幅を大きくするかとかですね、アートとして作っていたものをアートではなく道具にしようという感じで、どんどん変わっていくのが今の状態なんですよね。
田中:なるほど。お話しされたように、しくみデザインさんは、メディアアート作品を大商業施設に入れるところも、もともとの事業としてやられている。
なぜそこからスプリンギンにつながったのかなと。
メディアアートって、まだ多分「仕事」にはなっていなかった時代。職業がなかったか、ほんの一部の人だったところから、商業施設にたくさん入れている。そういうところになるまでに実は興味があったので、起業家として聞けて良かったです。
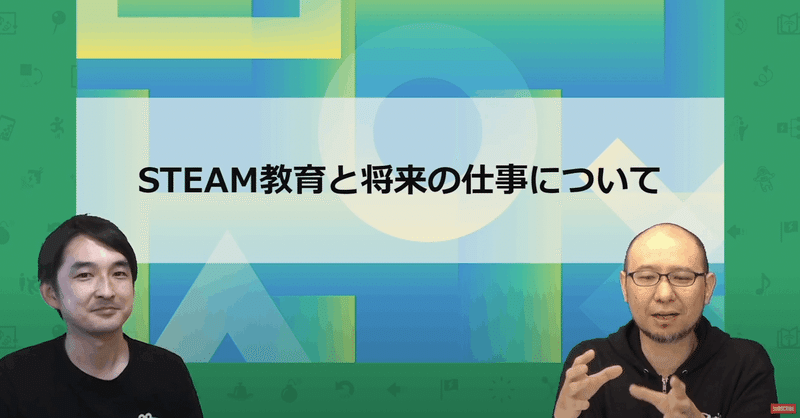
中村:より多くの人に楽しんでもらいたいと思ったら、「これはアートなのでこの場に来てやってください」っていうと限界があるんですよね。
「メディアアート」という表現も、最近特にNFTとか出てくるのでいろいろ変わってきてますが、アートってやっぱり「希少性」は大事。
だから簡単にコピーできるということ自体が価値が下がるものなので、メディアアーティストとしてどうやって価値を上げて、ビジネスとして成立させようかなって思うと、大きく二つに分かれるんですよ。
一つは、本当にメディアアーティスト。アートとしてやって、知名度を上げて、「あそこに行くとあって、それが体験できる」っていう状態にして、一応コピーはするけど、その期間はかぶらないようにするとか、場所を変えるとか、時間を区切るとか、いろんなことをして価値を上げていく。「この人が作った、この会社が作ったからすごく価値があるんだ」という醸成をしていくのがひとつの方法ですね。僕にはあまり向いてなかったので、選択しなかった。
もう一つが、道具としてより多くの人に使ってもらおうと、「コピーすることに価値が生まれる方に持っていこう」という方法。
最初は「KAGURA」という、身体を動かして演奏する楽器を作っていました。初めはメディアアートとして作っていたので、いろんな場所に置いて体験してもらうところからスタートして。
けど、やっぱりこれ楽器にしたいなと。より多くの人に使ってもらうためにはソフトにした方がいいので、アプリケーション・ソフトウェアとして開発し直して、今度はそのままインターネットで買えるようにした。ただ、ユーザーを選ぶというか、どうしても狭くなってしまった。
スプリンギンなら、子どもでも大人でも、気軽に何か作ろうと思ったら、サッとスタートして、5分ぐらいでなんとなく動いちゃう。めちゃくちゃ時間をかけて作り込んだら、めちゃくちゃすごいもの作れるんだけど。
「道具」として浸透させてしまう方が、僕がやりたいことにつながっていると思ったので、そういう選択肢をとったということが、大きいかなと思いますね。
田中:僕も研究として、役に立つかわからないようなすごいロボットはできたけど、みんなにはまだ使ってもらえないというよりも、たくさんの人が使いこなして遊べるようなロボットを作りたいし、まさに5分ぐらいで、ぱっと遊べて、すぐに体験できるものを作りたいですね。
中村:そういう思想とか近いですよね。
------------------------------------------------
toioとスプリンギンはお二人の「やりたいこと」が仕事になった結果、誕生したプロダクトだったのですね。
次回は最終回、お互いへの質問コーナーの様子をお届けします。
次回の更新もお楽しみに!
