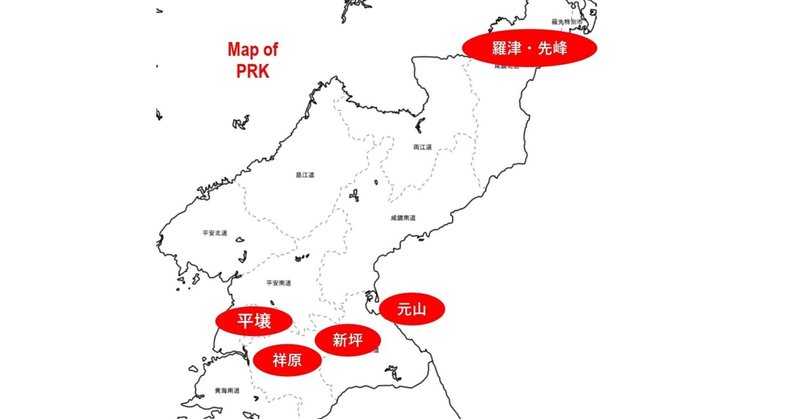
長編小説「平壌へ至る道」(27)
高い給与と除隊後のキャリア保証を餌に、国内の主に貧困層に属する若者がスカウトされ、幾つかの特殊部隊が結成された。国際法に抵触するテロ行為がその目的となり、手段となる以上、それらの部隊は韓国正規軍の一部として見做されることはなく、当然そこに所属する若者たちにも、正式な軍籍が与えられることはなかった。彼らのことごとくは「失踪者」扱いとなり、戸籍から抹消される者までいた。
厳しい訓練で死者も出た、後遺障害に苦しむ者も出た、そして脱走者も出た。命からがら故郷に戻り、自分の葬式が出されていたことを知った、という例も枚挙に暇がなく、部隊そのものが解散となった後でも、国家ぐるみの違法行為に関わった者として、彼らには徹底した緘口令が敷かれ、それを破った者ー破らなかった者にもーには社会的な制裁が容赦なく与えられた。常に見張りに追われ、どの職場でも噂が立ち、最終的に無職に追い込まれた者も多数いた。徴兵通知が届き、自分は特殊部隊で二年勤めた、と役所に抗議に行っても、その期間自分の職歴は真っ白になっていた、という例も報告されている。高賃金という口約束など守られるはずもなかった。
今なお数十万人単位で残る韓国国内失踪者。その最大の原因は朝鮮戦争だが、当時そうした特殊部隊に徴集され、そのまま何処かで命を奪われ遺体を秘密裏に処理され、死亡通知すら発行されなかった者もまた少なからず潜在している。
そうした問題が顕在化した最大の出来事が、「実尾島事件」だ。
韓国西部、仁川沖にある実尾島に、まさに朴大統領を襲撃した朝鮮人民軍一二四部隊と同じ員数の三十一名が集められたのは、青瓦台事件発生三ヵ月後のことだった。
訓練のさなか一名が溺死し、一名が隊員間のいざこざにより撲殺され、二名が逃走を図った際に殺害された、とされている。正確な経緯が不明なのは、証人となるべき部隊の全員がその四年以内にこの世を去ったからだ。そうでなくとも狭い無人島で若い男三十名以上が寝食を共にし、いつ実行命令が下るかを知らされないまま果てのない殺人稽古を昼夜問わず余儀なくされるのだ。その他三名が途中で脱走、本土に渡って強姦事件を起こし、仲間と教官に追われ二名が自殺、残る一名が逃走時の負傷が元で間もなく死亡したと言われている。
二年が経ち、残った二十四名がいよいよ海を越え、軍事境界線を越えようとした時、世界の潮流は彼らに背を向けた。青瓦台事件のあった一九六八年にアメリカ大統領に就任したニクソンは、長期化するベトナム戦争による国防費の国家予算への圧迫、世界の基軸通貨たる米ドルへの信用失墜、国内の厭戦感の蔓延と戦火の拡大を進める政府への不支持率の上昇を背景に、米ドルの金本位制度からの脱却を図るとともに、対外的には鉄のカーテンの向こう側にあった共産主義陣営との対話の道を模索し始めたのである。
戦後のデタント、緊張緩和の第一歩であった。
ベトナムで湯水のようにカネを捨て続けた西側陣営のトップランナーにかつての余裕はなく、デタントの一環として、七十年代に入ってアメリカは在韓米軍の大幅な規模縮小を決めた。
歴戦の闘士、朴正煕といえども、メンツだけで戦争はできない。ハシゴを外される形となった韓国政府は、自らの最大のスポンサーに追従するように、北朝鮮との対話チャンネルをこの頃から増やすようになっていった。
その必然の結果として、実尾島の特殊部隊は厄介なお荷物へと変質し、しかし解散とはならなかった。残った二十四人に徹底した秘匿を死ぬまで要求することは可能か?困難であるならば、いっそ全員をー。
答えのないまま、彼らはアンタッチャブル存在のまま捨て置かれ、最早その意味を失った訓練だけが、日常的に繰り返された。
そして一九七一年八月、実質的囚人たちは決起した。
島でまず教育係兼監視役であった正規軍属者を殺害した彼らは、仁川に上陸しバスを乗っ取り、まさに青瓦台へと向かい、俺たちに金日成を殺させろと叫びながら大統領への直訴を求めた。いみじくもかつての朝鮮人民軍一二四部隊がそうしたように、彼らもまたソウル市内に入って銃撃戦を展開せざるを得ない状況へと追い込まれた。仲間であるはずの者たちが向けてくる銃口に、二十四人は自分たちの立場を悟った。手榴弾による自爆で二十名が即死、残った四人は上告の機会を与えられることなく翌年、全員が銃殺刑となった。
事件は当初、「北朝鮮のゲリラ部隊によるもの」と発表され、その後「空軍が管理していた犯罪人による暴動」という報道に代わった。事件から一ヶ月経て、国会の場でようやく「特殊部隊の反乱」と答弁がなされたが、その後当件に関する質疑応答は打ち切られ、その一切が国家機密とされた。
実尾島事件が映画化され、韓国国内で大ヒットを記録したことにより、首謀者二十四人の背景、葛藤、悲哀、本名、そして事件の真相そのものが明らかにされたのは、実に三十二年後のことだった。
「そう。金日成の暗殺にはアメリカが失敗し、韓国も成功できなかった。そもそも奴の住居の場所も数も、完璧には掌握していないだろう。KCIAの調査能力をもってしても、あのコブ親父が今日は何処で誰と寝るのか、追いきれてはいないのではないか」
「じゃあ、あんたもうあの国への復讐は諦めんのか」
「そうは言ってない」
「まあ、俺は単なる駒やから、皆さんの指示に従うだけやけどね」
鄭は立ち上がり、部屋を出ようとした。
「どこに行く?」
「この家の周辺には県警の監察官が張り込んでんねやろ」
「俺の生家が県内にある、とさっき言ったが」
「山奥に、とも言った。どうせ集落の全員が顔見知りで、異邦人が現れたら音速よりも早くその情報が共有されるような場所とちゃうんか」
議長は苦笑した。今後、君へのコンタクトはどうすればいい?
「連絡先を教えてや。最初に大阪の伝道所地下室で会った時、俺は自分の生命与奪権を議長さんに預けると伝えた。その台詞に嘘はないし、このまま逃げたりもせん」
まさにその最初の出会いの場で、議長はこの小柄な若者にだけは自らの本名、職業、現況を包み隠さず打ち明けたのだが、しかし連絡先は口にしなかった。
今、議長はためらいもなく、自宅の電話番号を目の前の男に告げた。
朴や伊勢に対しては、仮に敵の手に落ちた場合、何もかも簡単に歌ってしまうだろうと考えていたが、鄭相慶はそんなタマではないと確信していた。どのみちこの男が結局ゲロする相手なら、遅かれ早かれ俺の所まで辿り着くだろう。
彼らはそのまま別れた。
その四週間後、メンバーの有事により、再び地方紙に新聞広告が掲載されることになる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
